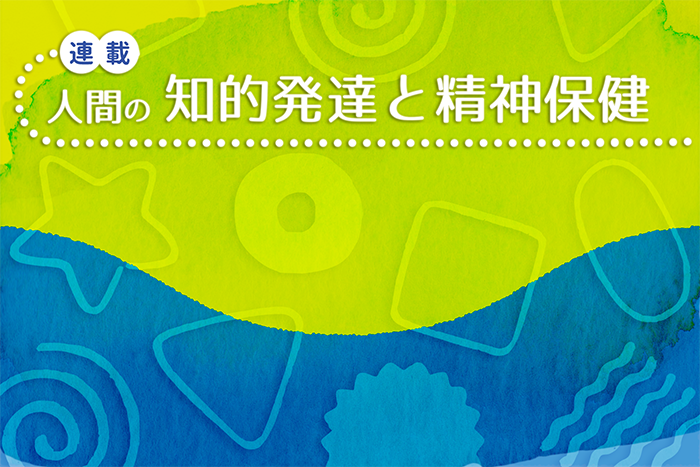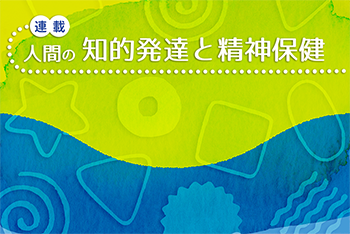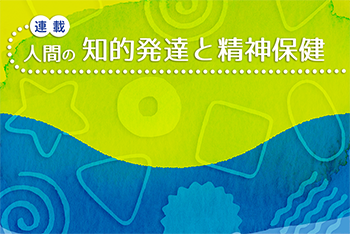この連載では、人間の知的発達を身体的要因や社会的要因の視点から紹介してきています。第12回では脳は情報の誤り等を補正する機能があること、脳も疲労や負担によって機能低下を起こすことがあることを紹介しました。第13回から第14回では、感情認知と衝動性に焦点を当てて、気晴らしとストレス対処は別に持った方がいいことなどを紹介してきました。
さて、人間がほかの種族に比べて知的に成熟しているものの1つに、社会性や協調関係とよばれたりするものがあります。狩猟や農耕の時代から、人は一人では達成できないさまざまなことを、集団によって解決するという方法をとってきました。
そこで今回は、人間の社会性の獲得の歴史をふまえながら、現代社会における「依存」などの精神健康上の特徴を紹介していきたいと思います。
言語を用いない協調関係
いくつかの歴史的知見から、人は文字による言語を獲得する前から、協調関係や上下関係があったと考えられています。というのは、縄文時代のいくつかの遺跡には、文字をまだ持っていないと思われる時代の遺跡が残されているのですが、個人や家族単位の人数では到底作れない規模の建物があったことが示されています。「建物を作る」という行為を実現するには、設計や材料収集、実際の建築行為などのいくつかの工程が必要です。これらの工程を計画して遂行するリーダーシップのような能力と、そのリーダーシップをもつ人に協力する複数の人たちがいる、というような協調関係のある集団が必要です。
縄文時代の人々が音声による意思伝達方法を有していたのかどうかはわかりませんが、もしも音声による意思伝達ができたとしても、他者の行動を観察して推察するメタ認知能力(→第6回、第11回などを参照)が必要であったことでしょう。