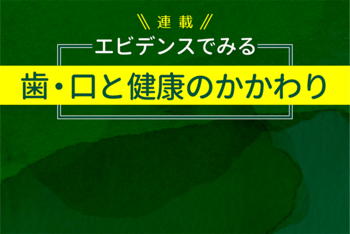看護学や医学に関係するみなさまにおいて、お手元にある「微生物学」の教科書に載っている微生物はだいたい、ヒトに病気を起こす「病原微生物」ですね。この手の教科書ばかりを見ていると、なんだか微生物に「悪者」みたいなイメージがつきまとうのですが、実は微生物のなかには、ヒトに有益なものもあるんです。とくに農学部では「発酵学」「醸造学」の研究が昔から盛んに行われていて、発酵食品を作ったり、お酒(アルコール飲料)を作ったりするところで微生物を利用することが研究され、実際に活用されてきました。このコラム、たまには趣向を変えまして、今回はこのような「有用微生物」の一例について、お話しさせていただこうと思います。
酒造りにかかせない酵母菌
さて、お酒の造り方について・・・

図1はお酒を造るための2段階の反応について説明した図です。順番は逆になりますが、まずは後の方の反応、①についてお話ししますね。
おそらく人類が最初に作って試した「お酒」は、①の反応だけでできたものではないかと想像します。造り方が単純だからです。たとえば、ブドウを材料にした「ブドウ酒」、いわゆるワインがそうなんですが、これ、基本的にはブドウの果実を搾った果汁を置いておくだけでできてしまいます。と言いますのも、ブドウの果実にはもともと、その名の通りブドウ糖が含まれていますので、②の反応が必要ないわけです。さらにブドウの皮についている白い粉、あの中に酵母菌が含まれていることが多く、おそらく偶然ブドウ果汁を放置していたところブドウ酒ができあがったものが、原始的なお酒だったのではないかと想像します。
ただ、このブドウの果皮に付着している菌には酵母菌だけではなく、ものを腐らせる腐生菌がある場合ももちろんあって、その場合には果汁が腐ってしまうだけです。まさにラッキーな場合だけお酒ができることになるんだと思います。現在のワインの造り方もこの原始的なお酒と大きく変わりません。自然酵母(野生酵母、土着酵母)といって、ブドウの果皮についている酵母菌をそのまま使ってワインを造る場合もあるんですが、品質を安定化させるため、タンクに入れたブドウ果汁の中に純粋培養した酵母(培養酵母)を入れる場合も少なくありません。
“アルコール発酵をさせるため”の菌
この①の反応、アルコール発酵といわれますが、基本的にはどのお酒も共通の菌種によって行われます。サッカロミセス・セレヴィジエ(Saccharomyces cerevisiae)という酵母菌です。微生物の分類でいうと「真菌」の仲間ですね。連載第7回でお話しした微生物の学名の由来で言いますと、「saccharo」というのがラテン語で「糖」を意味し、「myces」というところはラテン語で「真菌」を意味します。種名のcerevisiaeはどうも、ラテン語で「ビール」を意味するようです。しかしビールの醸造だけでなく、日本酒もワインも、基本的にはこのサッカロミセス・セレヴィジエが行っているのがなかなか不思議なことです。ただし種としては同じとしても、菌株としてはかなりいろんな特徴があって、さきほど出てきました「培養酵母」として使う場合は、かなり工夫して酵母を選んで使っているようです。このお話もあとでまたしますね。
この酵母菌によってアルコール発酵が生じるための材料(基質)は基本的に単糖であるブドウ糖だけなのですが、例外的に二糖類であるショ糖(砂糖ですね)も基質として用いることができます。酵母は自分が持っている酵素(インベルターゼ)でショ糖をブドウ糖と果糖に分解できるんです。さらに酵母はブドウ糖だけでなく果糖も基質として利用できるので、結果的にショ糖もアルコールの材料にできるのでした。
世界にはサトウキビの汁を材料としたお酒もあります。有名なのはラム酒です。ただこちらはサトウキビを発酵させた「醸造酒」をさらに蒸留した「蒸留酒」でして、アルコール度数が40%以上にもなります。有名なラム酒の「ロンリコ151」(図2)ってのはその名のとおり151 proof、つまり度数は75.5%なんですよ。悪酔いに注意です。しっかり薄めて飲んでくださいね。ちなみに、沖縄の「黒糖焼酎」というのもサトウキビを原料とした蒸留酒ですね。

⦿日本酒の度数が高いわけは…
前述のように、酵母菌は基本的に1種ですが、同じ種であっても特徴が異なるたくさんの菌株が存在します。たとえば、日本酒のアルコール度数は普通16%程度なのですが、実は原酒は18%を超えることもあります。こんなにアルコール度数が高くなると、普通の酵母は自分が作ったアルコールで「消毒」されてしまうというか、耐えられずに死んでしまうのですが、日本酒の酵母はこれくらいのアルコール度数でも死なないのです。その結果、日本酒は世界のお酒の中でも、おそらくもっともアルコール度数が高い「醸造酒」と言えるかと思います。
穀物類からブドウ糖を作るには?
ご覧いただいたように、果実やサトウキビなど、単糖や二糖類が豊富な原料を用いた場合は、酵母だけでお酒が造れます。それならもっと炭水化物がたくさん含まれている穀物類を材料にすれば、ずっとたくさんのお酒を造ることができるのではないでしょうか。その通りなんですが、図1の②の過程、つまりデンプンを分解して酵母が基質として使うことができるブドウ糖をどうやって作るのかが問題なんです。私が知っている限り、この方法は4種類くらいしかありません。
本当に大昔の時代、「噛み酒(はみしゅ)」あるいは「口噛み酒」と呼ばれるお酒があったようです。お米を口に入れてくちゅくちゅと噛んで、それをペッと吐き出したものを貯めて、これを発酵させて作ったお酒ですね。唾液にはアミラーゼという酵素が含まれており、デンプンをマルトース(麦芽糖)まで分解することができるんですね。このマルトースもなんとか酵母は分解できるので、アルコールを造ることができるというわけです。しかし、現代の世の中で、他人が吐き出したモノでできたお酒って、いやあ、さすがに飲めないですよね・・・。うむう・・・。
物理的に熱をかけてデンプンを分解する
そうなると実際にお酒造りに応用できる②の方法は3つになります。
まずは物理的に「熱」をかけることでデンプンを分解する方法です。有名なのは、竜舌蘭(リュウゼツラン)の地下茎である「ピニャ」(図3)を原料としているテキーラです。

このピニャにはデンプンに似た多糖類であるイヌリンが多量に含まれています。このイヌリンを分解するのに、「マンボステラ(マンボステイラ)」という、一種の石窯を使ってじっくりと行う伝統的な方法と、いわゆるオートクレーブ(「アウトクラベ」と呼ばれます)で高温・高圧で短時間に行う方法があるようです。
私、「物理的に熱をかける」方法と言いましたが、実際にはこの過程で、素材が持っている酵素を用いて多糖類を加水分解しているんでしょう。すみません、これは私の想像なのですが、たとえばサツマイモを「石焼きイモ」にするときに、焼き石を使って60℃~70℃程度の絶妙な温度にすると、サツマイモ自身が持っている酵素がもっとも活性化されて、蜜のような甘い成分が出てきます(これはNHK「チコちゃんに叱られる!」の受け売りなんですが)。化学の先生に聞きますと、多糖類を純粋に熱だけで加水分解しようと思うと、200℃以上まで加熱しないといけないということですので、やはり生物学的な力を借りているんだと思います。
麦芽を用いてデンプンを分解する
多糖類を単糖・二糖類にする方法、2つ目は「麦芽」を使う方法です。麦の粒が芽を出したものが麦芽ですが、これにはデンプンを分解する酵素が多量に含まれています。種(たね)である麦の粒にはデンプンがたくさん含まれていますが、芽を出すときに貯蔵型のデンプンを分解して栄養分として使う必要があります。そのときに働く酵素をちゃっかり利用するわけなんです。麦芽を利用しているお酒としては、醸造酒であるビールや、蒸留酒であるウイスキーなどが有名ですね。バーボンウイスキーの原料はトウモロコシが半分以上と規定されているんですが、原料が麦以外であっても、デンプンを分解するのには麦芽の助けを借りています。ビールにおいても、「麦100%」と謳っていないものでは、原材料名をよくみると、お米やトウモロコシが含まれていることが多いのですが、この場合でもデンプンを糖に変えるところでは麦芽の力を使っているんです。
コウジカビを使う
そして3つ目の方法が、「コウジカビ」を使う方法です。これは日本酒の造り方ですね。そうなんです。日本酒は①と②の過程で、おのおの別々の、2種類の微生物を巧みに組み合わせてお酒を造っているわけなんです。
蒸したお米の表面にコウジカビを生やしたものが「米麹」なんですが、もともとは「麹室(こうじむろ)」という湿った土壁の蔵のような中で、蒸したお米を台の上に敷いて、壁や天井から自然に落下してくるコウジカビの胞子をもとに米の表面にカビを生やしていました。ただ現在ではそんな作り方はしていなくて、純粋培養したコウジカビの胞子を蒸し米の上から振りかけています。
コウジカビ属はAspergillusといいますが、日本酒を造るのに用いられるのはAspergillus oryzae(黄麹菌)です。漫画「もやしもん」で「オリゼー」と呼ばれて有名になりましたよね。実はこのコウジカビ、日本酒や焼酎だけでなく、味噌やしょう油、かつお節、いずしなどの「なれ鮨」などの製造にも関与しています。そうそう、病棟の建て替えなどで古い建物を壊すような場合、Aspergillus属による日和見感染に注意しなければならないというのは有名な話ですが、麹室の話を聞くとよく分かりますよね。古い建物の壁や天井にはAspergillus属の菌が生えている場合があるのですね。これをうまく使ったのが昔の麹室だったというわけなんです。
乳酸菌も日本酒造りに貢献していた!
すごいですね。日本酒は2種類の微生物を巧みに組み合わせて造られたお酒だというわけです。ところがところが、実は2種類だけではなかったんです。私、よく行く居酒屋さんで、大将に日本酒のおすすめを聞くんです。私の嗜好をよくご存じなので、おすすめのお酒は絶対おいしいんですよね。そのときによく「これは山廃仕込みなんです」とおっしゃっていました。この「山廃」というのが何なのかよくわからなくて、調べたことがあります。
日本酒の伝統的な作り方として、生酛(きもと)造りという方法があります。昔は大きな樽、いまではステンレスタンクで「もろみ(醪)」を発酵させるのが日本酒のアルコール発酵なんですが、このもろみに酵母菌を入れるところで、あらかじめ酵母を培養して大量に増殖させた「酒母(しゅぼ)」と呼ばれるものを作る必要があります。この過程で、できるだけ純粋な酵母菌をたくさん含んだ酒母を作るために、乳酸菌の助けを借りているんです。木でできた櫂を使ってお米をすり潰してドロドロの液体にする(これを「山卸し」とか「酛摺り(もとすり)」(図4)といいます)ことで乳酸菌が生えやすいようにし、自然界にある乳酸菌を取り込んで酸性環境にすることで、酵母が繁殖しやすく、そして雑菌が生えにくくしているんです。この作業が「生酛造り」です。

いやあ、すごい発明ですね。コウジカビ、酵母菌だけでなく、乳酸菌という「第3の微生物」が登場しました。日本酒はたいへん手間のかかった発酵手段を取っているんですね。ただ、最近では乳酸菌の助けを借りて酒母を酸性環境にするのではなく、てっとり早く乳酸を入れることで済ませてしまう「速醸酛」という方法が主流で、生酛造りであったり、それとよく似た方法ですがお米をすり潰す「山卸し」を行わないもののやはり乳酸菌の助けを借りる方法、これを生酛造りに山卸しを廃止した、という意味で「山廃仕込み」というものも徐々に増えてきています。生酛造りや山廃仕込みのような、いわゆる速醸酛を使わない、伝統的な方法でつくる日本酒はおそらく、全体の1割もないんじゃないでしょうか。
ふうう・・・。ここまで調べないと、私も「山廃仕込み」の意味は分かりませんでした。大将がお店で一から教えてくれなかったのが、今となってよく分かりました。この長いお話、居酒屋で聞いたら、酔いが一気に醒めてしまいそうです・・・。
乳酸菌は諸刃の剣?
さてさて、日本酒を造るための「第3の微生物」として乳酸菌を取り上げましたが、実はこの菌、諸刃の剣なんですよ・・・。というのも、酒蔵のお酒が一気にすべて変質してしまう「火落ち」という現象が昔から知られており、酒造りの専門家である杜氏がもっとも恐れる現象なのですが、実はこの現象は一種の乳酸菌が原因であることが明らかになっています。火落菌Lactobacillus hiochiiと名付けられています(のちにホモ火落菌L. homohiochiiとヘテロ火落菌L. heterohiochiiの2種に分かれています)。
というわけで乳酸菌、実は日本酒造りの助けにもなりますし、致命的な事故を起こす可能性もあるわけなんですね。衛生状態がよくなかった昔、酒蔵に女性が入れなかった時代があったのですが、これは私の勝手な想像ですが、膣の常在菌としてLactobacillus属の菌がいますので、そのような菌のコンタミネーションを経験的に恐れていたのではないかなと思っています。いまでは優秀な女性の杜氏さんがたくさんおられます。
ちなみに1990年代初頭、パーキン・エルマー社がPCRの特許を持っていたのですが、臨床検査についてはロシュ社がその権利を買い上げました。日本では、臨床検査以外のPCR使用に関しては宝酒造(現タカラバイオ)が権利をもっていた時期がありましたが、私、その当時に同社のカタログを見ていたら「火落菌検出PCRキット」というのが売られていて、おおぉさすが、酒造りがルーツの会社だなあと感激した次第。

今回はお酒、とくに日本酒について詳しくお話ししました。最後に私おすすめの日本酒に関する岩波新書を1冊。坂口謹一郎著『日本の酒』です。この本、1950年代に初版が発刊され、永らく絶版になっていましたが、ありがたいことに今では「岩波文庫」として再版されています。でも私には、縦長の新書版の方がしっくり来るんですよねえ・・・。残念ながら類書の『世界の酒』は絶版のままです。
坂口先生は東大農学部の教授。ビアホールの泡が多すぎて中身のビールが少ないと、客がお店を訴えた裁判があったそうですが、そのとき坂口先生は証人として出廷したとか。先生の『日本の酒』では、いきなりの第1章で、日本酒の味を表す形容詞が延々と数ページに渡って書かれているんです。いやあ、圧倒されました。私、いまでも「甘口」「辛口」くらいしか日本酒を形容するコトバが思いつきません・・・。ぜひご一読を。