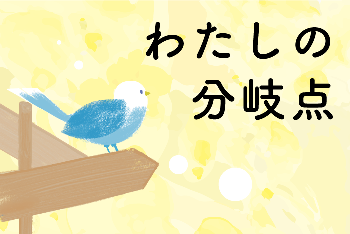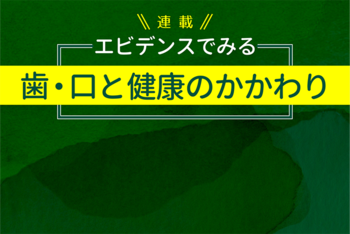今回はどこの業界にもある専門用語、とくに隠語のようなものについてお話ししたいと思います。
■さまざまな業界用語
私がテレビ番組などで見聞きした中では、たとえばデパートに万引き犯がいる場合は館内放送で「川中様」と言ってスタッフだけにわかるように周知するのだとか。万引き犯は「買わない」から「川中」だというのを聞いたことがあります。鉄道業界では「さつまのかみ」というと不正乗車の客のことを指すんだそうです。これ、語源がなかなか由緒正しくて、平清盛の弟の名前が「平薩摩守忠度(たいらのさつまのかみただのり)というわけで、「忠度(ただのり)」、つまり「タダ乗り」で、不正乗車の客が「さつまのかみ」になったといいます。なるほど。
万引きやキセル乗車の犯人を見つけた場合、本人や周りの人に気づかれないようにスタッフ間で情報を共有しないといけないので、こういう業界用語=隠語が生まれたのだと思います。デパートでは「トイレ」や「食事」にも隠語がありますが、たしかにお客さんには知られたくないでしょうね。テレビ番組では、高島屋や松坂屋、伊勢丹や三越など、会社によってこの手の隠語は全部違うんだと言っていました(図1)。おそらく独自の進化を遂げたのだと思いますが、他の会社の人がお客さんとして来ていた場合にも知られたくないから? なんて勘ぐってしまいますね。

私が医者になったのはもう30年以上前なので、当時はまだドイツ語の医学用語がちょろっと残っていたように思います。テレビドラマでは「クランケのオペが・・・」なんてやっていましたが、さすがにその時代でも、患者さんのことを「クランケ(Kranke)」と呼んでいる医者はもういませんでしたねえ・・・。でも先輩の先生から「先生、もうエッセン行ったの?」と言われたことはありました。私、最初は、シャウエッセン? ソーセージ? と思ったのですが、そういえばドイツ語でエッセン(Essen)は「食事」のことだと思い出しました。患者さんのいるところで「食事はもう食べたの?」とはなかなか聞きにくいですね。デパートの隠語と同じような感じかと思います。
同じように、面と向かって言いにくい言葉は隠語になりやすいのでしょう。「あの病院はゲルがいい」というのも聞いたことがあります。ゲルはドイツ語のGeld、「おかね」のこと。つまり給料がいいか悪いかを言っているんですね。最近では「あそこの当直はコストが悪いなあ」ってのを聞いたことがあるので、英語のcostに変わっちゃったのかもしれません。いえいえ、私は報酬で仕事を選ぶことはいたしませんので。
ポリクリ、クリクラ、ムンテラ、IC・・・略語の違い今昔
当時、ドイツ語の用語で残っていたものとしてはそのほか、パーセントが「プロ(Prozent)」、水は英語でwaterですが「ワッサー(Wasser)」、ブドウ糖はsugarから「ツッカー(Zucker)」なんてのもありました。「50プロツッカー取って!」と言われたら大急ぎで「50%ブドウ糖液」を持って行かないといけません。医学生の臨床実習は、昔は「ポリクリ」っていいました。おそらくこれは、外来診療科を指すPoliklinikが由来なんでしょうが、今では「診療参加型臨床実習」になっちゃったのでclinical clerkshipって言います。ところがこれもどうやらポリクリと同じ「4文字」に略したいということで「クリクラ」になっちゃいました。ミネラルウォーター屋さんではありませんよ。
4文字といえば「ムンテラ」なんてのもありました。Muntが「口」、それに「治療」のTherapieがくっついて略しているので、「言葉での治療」というような意味でしょうか。患者さんや家族に病状などを説明することなんですが、今では「アイシー(IC)」っていうんですね。私、父が入院したときに「患者の家族」としての立場で看護師さんから聞いたのが初めてでした。おそらく私のことを「同じ業界人」だから通じると思って「来週あたりに主治医からアイシーがあると思いますよ」と言われて面食らいました。それまでほんとに知らなかったんです・・・。これ、インフォームド・コンセントの略なんですね。それを聞いて、なるほど、I see、でした。
ステる? マンマとは? 略語と若きとろろの壁
当直明けに先生方が「昨晩1人ステってねえ」って言っているのを聞いたことがあります。よくよく聞くと患者さんがお亡くなりになったことを話していたわけですが、人が死ぬことを「捨てる」はないだろうと、ちょっと義憤に駆られたのですが、実は全然違って、ドイツ語で「死ぬ」を意味する動詞sterbenからきてるんだと知りました。たしかに、これは究極の隠語ではあります。今はなんて言うのかな。
そうそう、看護師の方はご存じだと思いますが、お亡くなりになった方の処置をするための器具や消耗品類を集めたものを「エンゼルセット(エンジェルセット)」と言いますよね。あれがなにを指すのかわからなかったことがあります。私は「ショートーダイ」もドイツ語か何かだと思ってましたよ。床頭台、つまりベッドの横のテーブルのことなんですよね。「ひょうちん」もわからなかったなあ・・・。こおりまくら(氷枕)ですよね。このような「看護業界用語」は、若い医者にとっては大きな壁でした。
昔は「がん」を本人に告知しないことがありましたので、隠語で話していたこともありましたね。胃がんはMagen Krebsで「エムケー(MK)」ですが、同じ外科で扱う乳がんも「マンマ・クレブス」だから「MK」になっちゃいます。そこで乳がんの方は「MMK」といってたんじゃなかったっけ。マンマ だからMMなんでしょうか。
微生物・感染症に関する隠語や略語
あわわ、ここで思い出しました。このコラム、微生物・感染症に関する話題を扱うものなのでした。ここから始めてもいいですか?
私が現場で聞いたのは「マーサ」が最初でした。ちょっとビックリで、何これ?と思いました。お父さんが時代劇の大御所であるフジテレビの局アナさん(当時)??? いえいえ、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)のことなんでした。いやいや、MRSAはちゃんと「エム・アール・エス・エー」っていってくださいよぅ。
耐性菌やあまり検出されないでほしい菌ってのは隠語になりやすいんでしょうか。私、緑膿菌のことを「ピオ」って言っているのを聞いたことがあります。緑膿菌が出す緑色の色素は「ピオシアニン」といいますが、もともとピオは「膿(うみ)」のことなので、由来はしっかりしています。最近では学名のPseudomonas aeruginosaから「シュード」っていう人が多いように思います。同じような菌の略称? としては、Aspergillus属の真菌を「アスペル」って言ったり、Acinetobacter baumanniiを代表とするアシネトバクター属の細菌を「アシネト」って言ったりします。このあたりは原形が残ってるので理解しやすいですね。
感染症の名前でSARS(重症急性呼吸器症候群)は「サーズ」でいいと思います。しかしSIRS=全身性炎症反応症候群のことを「サーズ」って言ってる人がいましたが、これはできたらやめてほしいです。同じ感染症の領域で同じ「音」の用語が乱立するのは混乱のもとだと思います。
こういうことは実は前例がありました。心筋梗塞は今でもMI(myocardial infarction)と言いますよね。だいたいが急性発症(acute)なので「AMI」っていうことが多いと思います。ところが私が学生の頃は、僧帽弁閉鎖不全のこともmitral insufficiencyでMIって呼んでいたんですよ。しかし、さすがに同じ循環器領域で「MI」が2つあるのはまずいだろうということになり、僧帽弁閉鎖不全のほうをmitral regurgitation(regurgitationは「逆流」の意)にして、「MR」と呼ぶようになり、現在に至る、なんです。
略語がたくさん! 多剤耐性菌
MRSAの話はしましたが、こちら、もともとは「methicillin resistant Staphylococcus aureus」の略です。正式名称が長い多剤耐性菌は略号の嵐です。以下に列挙してみましょう。
多剤耐性○○菌の多くは冒頭に「multi-drug resistant」が付くので、略称がMDxxになりますね。たとえば、
MDRP:多剤耐性緑膿菌(multi-drug resistant P. aeruginosa)
MDRAB:多剤耐性アシネトバクター・バウマニ(multi-drug resistant A. baumannii)
などです。結核菌の場合は「MDRTB:多剤耐性結核菌(multi-drug resistant Mycobacterium tuberculosis、頭文字を合わせるならtubercle bacilliかな?)」ですが、標準治療に用いられる4剤すべてに耐性を持つものを「超多剤耐性結核菌(XDR-TB)」と呼ぶことがあります。Xって何の略なんだろ? と思って調べたところ、どうやらExtensivelyの略みたいです。
さて、そのほかの耐性菌としては・・・。
PRSP:ペニシリン耐性肺炎球菌(penicillin resistant Streptococcus pneumoniae)
VRE:バンコマイシン耐性腸球菌(vancomycin resistant enterococci)
PPNG:ペニシリナーゼ産生淋菌(penicillinase producing Neisseria gonorrhoeae)
ESBL:基質拡張型ベータラクタマーゼ産生菌(extended-spectrum β-lactamase (producing bacteria))
BLNAR:ベータラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性ヘモフィルス属菌(β-lactamase non-producing ampicillin resistant Haemophilus spp.)
などなど。この手の「多剤耐性菌の略号」のなかでも、ちょっとややこしいのが「CRE」です。これ、もともとは「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌」carbapenem-resistant enterobacteriaceaeだったのです。しかし細菌の分類が変わりまして、それまで腸内細菌科であった、セラチアやプロテウス、エルシニア属などに含まれる細菌が腸内細菌科から外れて、新設された複数の別の科の中に入っちゃいました。しかしこれらの菌もカルバペネム系に耐性を持つとCREと呼びたいので、科より上の分類である「腸内細菌目enterobacterales」であればまとめて呼べるだろうということで、略号は同じCREなんですが、「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌」(carbapenem-resistant enterobacterales)と呼ぶことになりました。なんともややこしい・・・。
感染対策の現場で飛び交う言葉
感染症の名前、あるいは感染の病態なども略号はいっぱいあって、感染対策ラウンド(回診)のときに現場で飛び交っています。私、CRBSIというのを知らなくて、ICU(intensive care unit:集中治療室、さすがに一般用語ですね・・・)にラウンドに行ったときにどうしても意味がわからず、「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」だと自分に言い聞かせて、現場のスタッフにおそるおそる聞きました。catheter-related blood stream infection、つまり「カテーテル関連血流感染」のことだと教えてもらいましたが、微生物の先生なのにそんなことも知らないの? というような白い目で見られた(ような気がしました)。やっぱり聞かずに自分で調べたほうがよかったのかなあ、と・・・。いえいえ、やはり恥ずかしがらず、現場の疑問は現場で解決するようにしましょう。

さて、私が不思議に思っているのは、よく業界では役職や地位の略称というのがあるんですが、医療業界ではほとんど聞かないなあということです。私、産業医としてある工場に行ってるんですが、そこではたとえば製造部長のことを「セゾチ」と呼んでます。「鉄ヲタ」の方には有名でしょうが、カレチといえば「客扱い専務車掌」のことで、今でも雑誌「鉄道ファン」の巻末にある、いわゆる編集後記に相当するコラムは「カレチ」というタイトルです。「レチ」は車掌のこと。「列車長」が語源みたいです。客車の車掌長がカレチなら、貨物列車の車掌長は「ニレチ」で、これら合わせた車掌長の総称は「レチチ」。
しかしこういうの、医療業界では全然聞かないんですよねえ。もちろん医療界でも病院長とか看護部長とか医事課長とか役職はいろいろあるんですが、それをたとえば、「ビレチ」とか「カブチ」とかいう病院は聞いたことがありません。やっぱり現場では「インチョー」「シチョー」が飛び交っていますよねえ・・・。もし、うちはこんなコトバを使ってる、というのがあれば是非教えていただきたいです。
もともと隠語っていうのは、その業界の人たちだけが理解できるもの、逆に言うと患者さんやご家族にはできれば知られたくないと思って使っているふしがあります。つまりこれをバラしてしまうのは業界人としてタブーなのかもしれません。そこで今回のタイトルは「禁断の回」としました。私、明日になったら抹殺されているかもしれません。夜道を歩くときには気をつけますので、このコラムを読んだ皆様も抹殺されないようくれぐれも気をつけてくださいね。