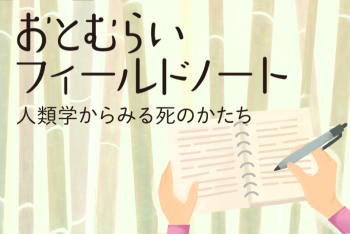みなさまは疥癬(かいせん)という病気をご存じでしょうか。今回は、この疥癬のお話をしたいと思います。
私、介護老人保健施設(老健)での感染対策のアドバイスも行っています。もちろんつい最近は新型コロナウイルス感染症対策が大変でした。しかしそれ以前は、疥癬の集団発症がしばしば起こり、その対策に難渋した経験があります。そのときのお話をしたいのです。
疥癬の原因となるヒゼンダニ
まずは疥癬という病気がどんなものかお話ししますね。疥癬はヒゼンダニというダニ(図1)が原因の皮膚疾患です。

ダニは節足動物ですが、クモと似て足が8本(4対)あります。この写真は顕微鏡で拡大したものですから、ヒゼンダニは肉眼では見えない、非常に小さなダニです。形態をよく見ると、その足はかなり短いことがわかります。つまり自分で動ける距離は極めて短いことが想像できます。実際、疥癬の感染経路は接触感染なのですが、ヒトからヒトへ感染する場合は、「体温を感じるくらいの濃厚な接触」が必要です。つまり、性感染症のひとつでもあります。
感染症ではないのに「性感染症」?
少し脱線しますが、「性感染症」という言葉については注意が必要です。もともとはSTD = sexually transmitted diseaseを訳したものでした。しかし英語をよく見ると、どこにも「感染症」という言葉は入っていないんです。STDを直訳すると、性行為で“うつる”(伝播する)病気、というだけです。ですので、たとえば今回のヒゼンダニというダニ、すなわち節足動物が原因で起こる「医動物疾患」もSTDに入ります。しかしこれ、「微生物が原因で起こる感染症」(狭義の感染症)ではないんです。感染症でない病気が「性感染症」に含まれている、というのはなんとも不思議な話ですが、許容されています。疥癬以外でも、たとえば・・・(図2)

ケジラミ(頭髪に巣くうアタマジラミとは異なります)の学名はPhthirus pubisといいますが、英語では陰毛(恥毛、pubic hair)に巣くうということでpubic louse、あるいは形がカニに似てるのでcrab louseと呼ばれます。louseはシラミの単数形ですが、複数形はliceです。中学校の英語の先生に、レストランで「ごはん(rice)」を頼むときにLとRの発音を間違えるとシラミがお皿に山盛りになって出てくるぞー、って脅されたことがある方もいるのではないでしょうか。それです。
このケジラミ、主に陰毛の毛根近くにがちっとくっついているので、性行為で伝播することになります。病気の名前は「ケジラミ症」で、こちらも典型的な「医動物疾患」です。どう考えても「感染症」ではないのですが、性行為で「伝播」しますのでSTDなわけです。なので、日本語では性感染症のひとつになってしまいます。
よくご存じの方は、最近では性感染症のことをSTDではなくSTIっていうんだぞー、っていうツッコミをされるかと思います。その通りで、たとえばHIV感染症やB型肝炎など、性感染症ではあるんですが、無症候性キャリアーの時期が長いものがあり、キャリアーの時期は「病気(disease)」ではないためsexually transmitted diseaseとはいえないという理由で、STDではなくSTI = sexually transmitted infectionということになりました。こうなると直訳しても「性感染症」となりますね。はて、だったら結局、疥癬やケジラミ症などの医動物疾患は、STIに入るんでしょうか・・・。今までの歴史的な経緯もありますし、感染対策を考えても、私はSTIに入れてよいと思いますが、いかがでしょう。「感染症」ではないんですけどね・・・。あくまでも「transmit」する、ということで・・・*。
疥癬の症状
すみません、かなり脱線してしまいました。疥癬の話に戻りますね。まずは疥癬の症状についてお話しします。これがなかなか診断が難しいのです。
2つの病型「通常疥癬」「角化型疥癬」
病型から見て、通常疥癬と角化型疥癬の2つに分けます。免疫が正常な方にヒゼンダニが巣くいますと、通常疥癬を発症します。ダニが体に付着してから症状が出るまでの潜伏期は1~2ヵ月程度と言われています。ただこれを「潜伏期」というのは私、違和感があります。おそらく「かゆみ」や「発赤」という症状が出るためにはヒゼンダニの成分に対するアレルギー反応が成立することが必要で、その期間を指しているんだと思いますが、普通に病原体が増殖して閾値を超えたところで症状が出るという感染症の潜伏期とは明らかに異なっています。
通常疥癬では、赤いプツッとした紅斑、あるいは小丘疹が皮膚にできます。これは幼虫や若虫が一時的に皮膚に潜ったあとの穴なので、ここからダニが見つかることはほとんどありません。しかしダニが残した糞や脱皮した皮に対するアレルギー反応によって、非常に強いかゆみが起こることが特徴です。
一方、ダニが皮膚の中に潜っているところは結節になります。よく見るとダニが横方向に進んでいくことによる「疥癬トンネル(図3a、図4)」が見つかることがあります。紅斑や結節は、頭皮以外どこにできても不思議ではないですが、胸やお腹や太ももの皮膚、腋窩や腕の内側などによく見られます。割と特徴的なのは、男性の場合、結節が陰嚢に好発することです。

b:角化型疥癬。灰白色の角質増殖と痂皮に覆われ、亀裂も生じる。
c:ヒゼンダニのメスは人の皮膚の表面の産卵に適した場所に穴を掘り、オスを待ち、交尾が終わるとメスは皮膚の角質層に特徴的なトンネル(疥癬トンネル)の横穴を開ける。

一方、高齢者や免疫力が低下している宿主にヒゼンダニが寄生しますと、皮膚の角化が特徴的な角化型疥癬(図3b)を発症します。あるいは通常疥癬の診断を誤り、ステロイド軟膏を使用することで角化型疥癬を発生させてしまうこともあります。この角化型疥癬、昔は「ノルウェー疥癬」と呼ばれていたものです。図3bでも分かりますが、角化した皮膚からポロポロと落屑(らくせつ)が発生します。この落屑に多量のヒゼンダニが含まれています。
かつては困難だった、疥癬の治療と対策
性感染症でもある疥癬が、なぜ老健などで集団発症するのかといいますと、ひとつはこの、角化型疥癬の患者さんが一人いると、落屑が原因で伝播するためです。もうひとつの理由は、ベッドシーツや枕カバーなどのリネンを介した感染が起こることです。認知症の方の場合、自分の居室からトイレに行って、帰ってくるときに別の居室のベッドに間違って寝るような事例もしばしば見られますし、シーツ交換のときにヒゼンダニを広げる可能性もあります。スタッフが感染することもしばしば見られましたし、老健施設での疥癬の感染対策は非常に難しかったのです。
画期的な治療薬「イベルメクチン」
治療も大変でした。20年ほど前までは、イオウ(硫黄)の臭いが強い「六一〇(ムトー)ハップ(図5)」 という薬剤をお風呂に溶かして患者さんに入ってもらい、そのあとクロタミトン製剤(オイラックスなど)を頭から下の全身に塗っていました。これを根気強く続けないと治りませんでした。ところがこれらの「涙ぐましい努力」なしに一瞬で解決できる治療薬が導入されました。イベルメクチン(図6)です。
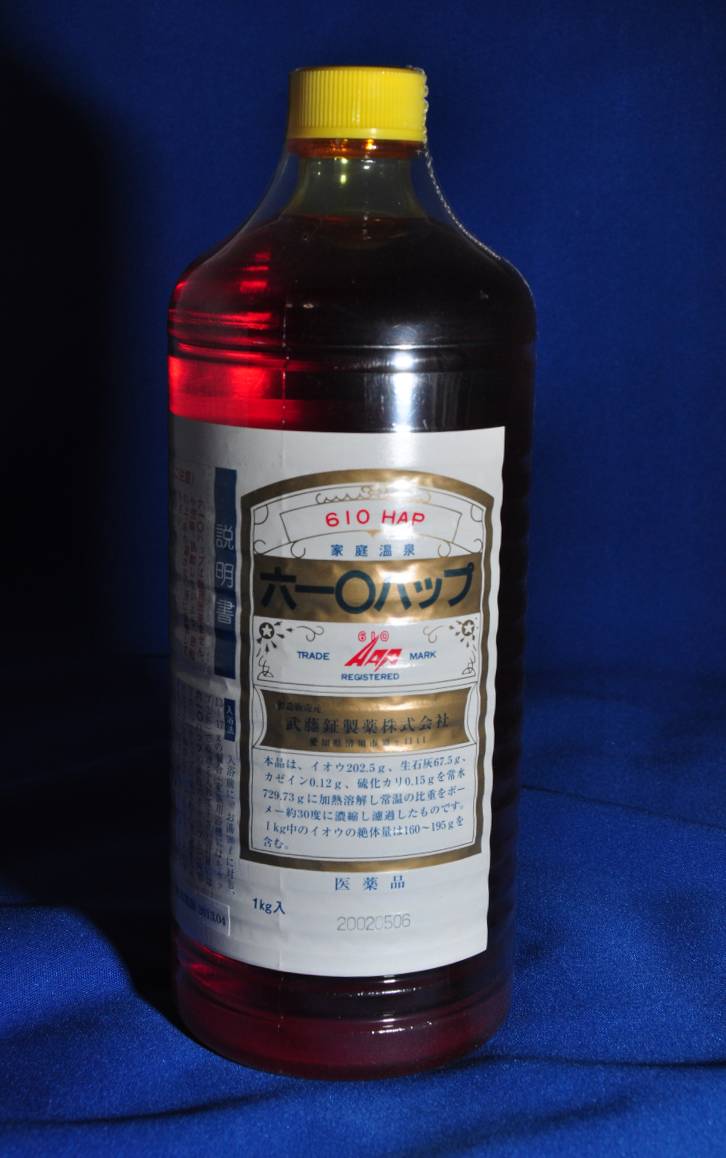

イベルメクチンは、静岡県の川奈ホテルゴルフコースの土壌で採取された放線菌が産生する物質、エバーメクチンから誘導された薬剤です。この物質を発見したのが、2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智博士であることは有名です。
私、感染症学会地方会の特別講演で大村先生のお話をうかがいましたが、後にも先にも、エバーメクチンを産生する放線菌は見つかっていないんだそうで、まさに奇跡の発見だと思います。
このイベルメクチン、もともとは寄生虫疾患であるオンコセルカ症(河川盲目症)の治療薬なんですが、沖縄地方に多い糞線虫症にも有効であることが示され、2002年から輸入薬としての治療が開始され、2006年よりマルホがストロメクトール®として国内発売しています(そういう経緯があったので、私が大村先生の特別講演を聴いたのは、2016年に沖縄コンベンションセンターで開催された感染症学会 中日本・西日本、化学療法学会西日本の合同地方会だったわけです)。つまり、寄生虫の薬であるイベルメクチンが、医動物疾患である疥癬にも有効であることが後でわかったのです。
私の経験をお話ししたとおり、当時老健などでの疥癬の集団発症は深刻な問題となっていたことから、新たに臨床試験を実施することをせず、きわめて迅速な経過で2006年に疥癬への適応追加が行われたのです。このあたり、ストロメクトール®のインタビューフォームから記述を抜粋します。
外国においても本薬の疥癬への適応追加を目的とした臨床開発試験が実施されていないこと、疥癬は皮膚感染症であり、高齢者介護施設等で突発的に流行するため、臨床試験を実施することが極めて困難であること、国際的に信頼できる学術雑誌に掲載された科学的な根拠となり得る論文、又は国際的に評価された総説等がある等の理由から、新たに臨床試験を実施することなく本剤の疥癬への適応追加申請を行い、2006年8月に適応追加が承認された。
当時、疥癬に有効な治療薬が導入されたのはたいへんありがたいことでした。実際、患者さんには3~5錠(体重による)を1回飲んでもらうだけで、ほぼ100%の割合で疥癬が完治しましたので、その劇的な効果に驚きました。そして施設内の感染対策に関しても、シーツやタオルを熱湯で消毒したり、イオウのお風呂に入ってもらったり、全身にクリームを塗ったりという、まさに涙ぐましい努力をすることもなくなりました。本当に、治療薬の開発というのはきわめてインパクトが大きいことなんだと感じました。
大村智先生のお人柄
大村先生はノーベル賞を受賞されましたので、その人となりは広く知られていることと思います。本学と同じ高槻市にあって、医学部・薬学部の授業でもご協力いただいているJT生命誌研究館が発行している季刊誌にも大村先生の記事が掲載されています1)ので、ぜひお読みいただきたいです。
私は感染症学会で先生のお話を一度、拝聴しただけなのですが、とても強い印象が残っています。ひとつは「厳しい先生」だなあ、ということ。海外の製薬会社と対等に渡り合って、特許に関する収益に関しては頑として譲らず、その収益を北里大学のため、そして研究助成のために活用されたそうです。大村先生が得た特許料で建てられた北里大学メディカルセンター(埼玉県北本市)の廊下に展示されている絵画はすべてホンモノなんだそうですね。そしてもうひとつは、特別講演の際、先生の最後のスライドで研究室から育った研究者の一覧が示されたのですが、学位を取った方が100人以上、そして全国で教授になっている方が数十人も列挙されていて、先生の「人を育てる力」に感銘を受けたことです。
でも実際の先生はガチガチの科学者という感じではなく、絵画の趣味をお持ちですし、自宅の敷地内に温泉を掘り当て、温泉施設まで作っておられます。さらにゴルフも大好きなんだそうです。そんな先生に、神様が川奈ゴルフコースの土から放線菌を発見するチャンスをお与えになったのかもしれませんね。
1)JT生命誌研究館:新しい微生物創薬の世界を切り開く.サイエンティスト・ライブラリー No.84.生命誌ジャーナル,〔http://brh.co.jp/s_library/interview/84/〕(最終確認:2024年12月10日)



」サムネイル2(画像小)_1645683211002.png)