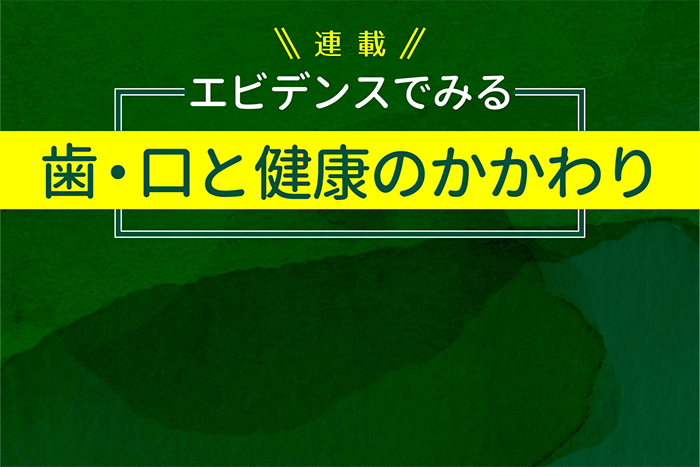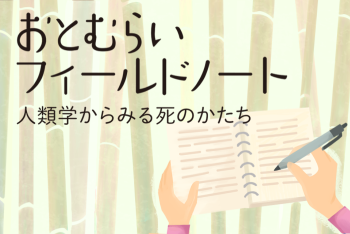子どもの虫歯は親次第―社会的側面から
現在の日本において、経済的な事情などにより十分な医療を受けることができない家庭が少なくないことが社会問題になっています。当然ながら、歯科も含まれています。図1に示すように、家庭状況で貧困層に虫歯の罹患率が高くなるという統計があります。
さらに、世帯収入が低いほど歯科診療代の支出が低い(図2)ことから、貧困層ほど歯科医院に行かないと考えられます。医科と比べて診療代の支出が世帯収入に相関するところも歯科の顕著な特徴です。
虫歯予防などの口の健康に対する知識や意識(デンタルIQ)の低さも貧困層には認められ、子どもだけでなく親も虫歯が多い傾向があると言われています。
経済的に余裕のない家庭では安価な菓子類で子どもの空腹を紛らわせ、おやつの「だらだら食べ」が常態化する結果として口腔内が酸性環境になる時間が長くなり 、虫歯が増加するリスクも上がってしまいます。中には歯ブラシや歯磨剤すら与えられない子どももおり、経済的な背景が虫歯罹患率に影響するのは明らかです。
乳歯が健全な形を保つことで、永久歯の正しい位置への萌出が誘導されます。虫歯等で早期に乳歯を失ってしまうと噛み合わせや歯並びが悪化することになり、歯磨きに悪影響が及びます。その結果として、将来的に虫歯や歯周病になりやすくなってしまいます。
歯や歯ぐきの不健康は食生活によくない影響を与えますから、大人になってから高血圧症や糖尿病などの生活習慣病になるリスクが上がる可能性もあります(過去の連載参照 )。
このように、経済的な貧困による口腔管理の問題は口の中だけの問題にとどまらず、全身的な健康にも暗い影を落とすものなのです。
歯科未受診と医療費助成・扶助の関係
学校検診で虫歯を指摘されても受診しない「未受診率」について2019年に報告された全国保険医団体連合会の調査では、全国の5000を超える小・中学校、高校の統計データをまとめています。その結果によると、図3のように未受診率は学年が上がっていくごとに上昇していく傾向が認められましたが、その背景として医療費の助成が小学6年や中学3年の節目で打ち切られてしまうことも要因の一つであると言われています。
子どもの医療費助成制度は自治体によって金額や期間が異なっていますが、特に生活保護を受けていない「相対的貧困」(世帯の所得がその国の等価可処分所得の中央値の半分に満たない状態)の家庭が歯科受診を渋る傾向にあります。生活保護を受けている家庭の子どもは医療費が扶助される仕組みがありますが、生活保護を受けていない「相対的貧困」の家庭では医療費が扶助されないことが要因と考えられます。
そのほかの歯科未受診の要因
また、受診を妨げる要素として「自己負担金が払えない」という経済的な理由に加えて、「多忙」つまり、シングルの親が働き詰めで子どもを歯科医院に連れていく時間を作ることができないことも挙げられます。
経済的な事情を抱える家庭では時間的な余裕もなく、虫歯の予防に対する正しい知識を得る機会も失われてしまっています。子どもの口の中を注意深く観察することもできないまま、虫歯になっても放置状態になることが懸念されます。
歯や口腔ケアに関する正しい知識や方法を普及・啓蒙する講演会や講習会は歯科医師会などの主導により各地で開催されていますが、「もともと意識が高めの人しか来ない」というのが実情であり、本当に知ってほしい親たちに必要な情報が行き届かない状況があると言われています。都市圏では、土・日・祝日や夜間に診療や口腔衛生指導をしている歯科医院も少なくないため、うまく活用して定期的に通院できる時間を作り出してほしいものです。
学校における歯科保健指導の問題
以上のように家庭での保健指導には限界があるため、学校歯科医や養護教諭が中心となって学校で改善プログラムを作り実行する必要があります。しかし、現状としてはどのようなものなのか、兵庫県を例に挙げて見てみましょう。
2017年に兵庫県保険医協会の歯科部会が兵庫県内の小中高等学校・特別支援学校を対象に実施した学校歯科治療調査1)では、調査に回答のあった274校において歯科受診が必要な子どものうち65%が未治療の状態でした。しかも、口腔崩壊(一人で虫歯が10本以上ある、もしくは歯の根しか残っていないような未処置の虫歯が何本もあるなど、咀嚼が困難な状態)の子どもがいる学校は35.4%にも及ぶことが判明しました。
このように子どもたちの歯科の健康状態が不十分である一方で、274校のうちの46校、約16.8%の学校において歯科保健指導が実施されていませんでした。
都道府県によって対応の違いがあるとは言え、家庭でも学校においても十分に歯の健康を守ってもらえない子どもがいる現状は、非常に遺憾なことです。
* * *
虫歯治療で通院しているM君(11歳、男子)は、虫歯ができたら500円玉を持って一人で来院します。本来なら、小学生の子どもが歯科治療に来る時は親などの保護者も一緒に来院して、X線写真を見ながら虫歯の詳細な説明や治療方針などを伝え、同意の上で治療を進めていくものです。
しかし、彼の場合は母子家庭で、しかもお母さんは休日返上で働いているとのこと。M君が来院するたび、お母さんの携帯に電話して連絡し、虫歯の状況や治療方針をお伝えしますが、いつも「任せますから。いいようにしてやって下さい」という素っ気ない返事です。
保険証や医療券の提示が必要なため、お母さんが来院されることもあるのですが、見るからにご自身も歯が悪い印象で、歯の自己管理も不十分なことがうかがえます。
家庭の事情なので仕方がありませんが、このように子どもが放置される家庭が少しでも減るような国の政策が充実されることを望みます。
【引用文献】
1)兵庫保険医新聞:学校歯科治療調査 結果詳細.2017年5月25日(1846号)ピックアップニュース,〔http://www.hhk.jp/hyogo-hokeni-shinbun/backnumber/2017/0525/070002.php〕(最終確認:2024年3月15日)