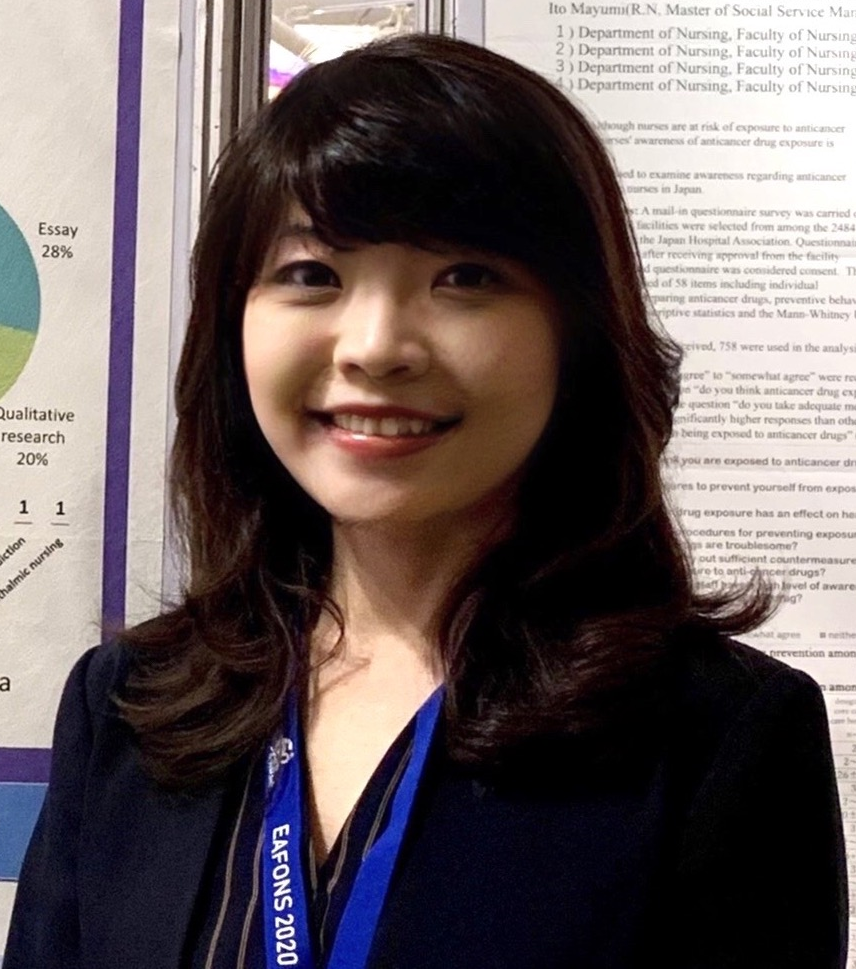こんにちは。今回は、質的研究の質評価に関心を抱いて、質的研究のクリティークとサブストラクションの開発に取り組んだお話です。
研究の質を測るもの
突然ですが、皆さんはどんな研究論文が良い論文だって思いますか? 自分の関心に近いテーマを扱った論文や、自分が得意とする方法を用いた研究には、より興味が湧くし、内容も理解しやすいと思いますが、それでも「良い」と思えない研究もありますよね。いったい研究論文の良し悪しって、何を基準に、どのようにして評価されるんでしょう。
逆に、あなたの論文が評価される場合、どのような視点で評価されたいと思いますか? 単に「好き・嫌い」という好みの問題で判断されたいとは思わないでしょう。良い点はなぜ良いか、良くない点はなぜ良くないかを、根拠とともに明確に指摘されたとき、その指摘に納得が得られ、ぜひ再考して論文や研究の内容を改善したいと思えるのではないでしょうか。
私が大学院で学んで良かったと思うことの1つは、こうした「研究の質とは何か、それをどのように判断するのか」について学べたことです。大学院では、自分が取り組む研究の研究疑問を導き出したり、理論的前提を見定めたり、研究結果を意味付けたりする際に、先行研究を適切に評価することの大切さを学びました。知識を開発し、次なる研究領域を明らかにするためには、先行研究の徹底的で批判的な吟味が必要となるのです。
この、先行研究に対する徹底的で批判的な吟味とは、そう、「クリティーク」とも呼ばれるものですよね。クリティークは、研究の単なるレビューや要約とは違って、個々の研究の長所と限界をよく考えた上での批判的な評価1)であり、研究の強み、限界、信頼性、意味、そして実践への適用可能性を判断するために、研究のあらゆる側面に対して系統的なバイアスのない注意深い調査を行うこと2)です。すべての研究には弱み(短所)がありますが、強み(長所)もあるのです。
私は、クリティークに慣れない頃、論文の内容に「なるほど」と納得するだけで、批判的な視点はなかなか持てませんでした。が、研究方法を学び、論文をたくさん読み、クリティークの視点が内在化されるに従い、「あれ? これはおかしいな」「論理的に飛躍しているな」と気づいたり、「この点は本当に素晴らしいな!」と感心したりするようになりました。クリティークすればするほどポイントを押さえて読むことができるようになるので、今でも大学院生には「最初は思うようにできなくて当然。とにかくクリティークの経験を積むように」と伝えています。
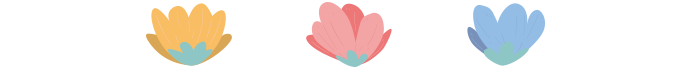
クリティークの意義
GrayとGroveは、「ある研究の長所が、他の複数の研究の長所に加わることで、実践のためのしっかりとした研究エビデンスが徐々に構築されていく」と指摘しています2)。この指摘は真実だと、私は考えています。
私が論文査読を行い始めた2000年代前半には、かなり低いと言わざるを得なかった日本の質的研究論文の質が、今ではだいぶレベルアップしていると感じます。この変化の背景には、もちろん看護学教育の向上があるでしょうが、それだけでなく、査読を受けて修正を経た論文が公開されることで、その論文を読んだ別の研究者が質的研究に求められる観点を学びとり、その観点を自分の研究に取り入れたことも大きいでしょう。そうして論文の質が高まり、より良い論文がより多く公開されることによって、この20年間に相当なレベルアップが図れたのだと思います。
このように、研究クリティークは個々の研究や論文に対して効果をもたらすだけでなく、看護学全体のレベルアップにも貢献するという点でも、重要な意義を持つといえるでしょう。
質的研究のクリティークのためのサブストラクション
私が大学院で学んで良かったと思うことの1つは、研究の質を見分ける方法を学んだことだと述べましたが、この「方法」には、クリティークの視点だけでなく「サブストラクション」も含まれています。サブストラクションとは、研究における理論、研究デザイン、分析モデルの一貫性をアセスメントするための1つのテクニックです3)。
研究の枠組みをいったん解体して組み立て直すことによって遂行されるサブストラクションのプロセスを、私は大学院で学び、なんて合理的で効率的な方法なの! と感激しました。と同時に、サブストラクションは基本的に、質的なフィールド研究を基本とする探索的記述研究ではなく、仮説検証型の実証研究や調査研究に適用する方法とされていることも知りました。質的研究のように、全く仮説を持たないで臨む研究や、研究のプロセスの中で仮説生成と検証を繰り返していくようなアプローチの研究には適さないとされていたのです。
え……それって本当かな? むしろ、質的研究の方が、研究方法までの内容と結果・考察の内容に一貫性がなく、何を言っているのか良くわからない論文が多いって気がするから、サブストラクションを使って、研究の論理的一貫性を吟味したほうがいいと思うけど。生意気にも大学院時代の私にはそんな風に感じられ、「サブストラクションは質的研究に適さない」との言説に違和感を覚えました。
そう思っていたのは、私だけではありませんでした。2005年頃だったと思いますが、大学院時代の同級生だった北 素子先生(現・東京慈恵会医科大学医学部看護学科教授)とそのような話になり、すぐに意気投合して勉強会を始めることにしました。その後、質的研究におけるサブストラクションの必要性について論文を書き学術誌に投稿したり、開発中の質的研究のサブストラクションの枠組みを学会の交流集会で発表したりと、数年間にわたりアクティブに活動を続けました。その成果を集め、書籍としてまとめたものが『質的研究の実践と評価のためのサブストラクション』4)です。
サブストラクションワークシートの意図するもの
この本の中で、私たちはサブストラクションを行うためのワークシート(図1)を考案しました。そして、出版社にお願いし、ウェブサイトからワークシートのファイルをダウンロードできる仕組みを作っていただきました。このワークシートは、私たちの本を購入しない方でもダウンロードし、開発者に許可なく使用することができます(図1のキャプション参照)。
北先生と私は、学問的知識は誰にでも開かれたものであるべきだと考えています。少しでも多くの方にサブストラクションワークシートを提供し、より系統的で徹底したクリティークを行なっていただきたい。そのことが看護学全体の底上げにつながれば、私たちにクリティークの大切さを教えてくださった看護の先達に対する、私たちなりの恩返しになることでしょう。

https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/63018#tab3
引用文献
1)Polit, D. F., & Beck, C. T. (2004)/近藤潤子(監訳):看護研究—原理と方法,第2版,p.674,医学書院,2010
2)Gray, J. R., & Grove, S. K. (2021)/黒田裕子,逸見功,佐藤冨美子(監訳)::バーンズ&グローブ看護研究入門,原著第9版,p.427,エルゼビア・ジャパン,2023
3)Dulock, M. L., & Holzemer, W. L. (1991)/操華子, 近藤潤子(訳):サブストラクション—理論から方法をよりよく導くために.看護研究 26(5):59-65,1993
4)北素子,谷津裕子:質的研究の実践と評価のためのサブストラクション,医学書院,2009

_1695266438427.png)