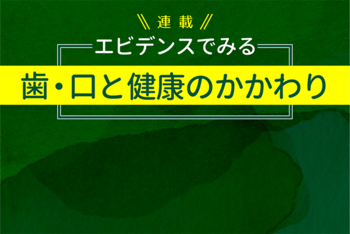今回は、現実主義の哲学について考えたい。私の専門ゆえに、国家や社会に関わる表現が多くなるが、全く同じ議論が、医療従事者の日々の仕事への取り組み方についても当てはまるので、ぜひ参考にしていただきたい。
ポパーの漸進主義
哲学者カール・ポパーは、哲学史上最大の悪人を三人挙げている1。プラトン、ヘーゲル、マルクスである。ヘーゲルとマルクスはそれぞれ、人間の精神と経済の構造の発展のプロセスを説いた。そのプロセスのゴールは、各々、人倫国家2と共産主義社会ということで異なっているのだが、この違いはここでは重要ではなく、重要なのは、両者が共に、人間や社会の変転を、一本道の必然的な進歩のプロセスと捉え、そのすごろくのあがりを最初から設定しているという点にある。つまり彼らは、ユートピア主義者・理想主義者なのである。
そのような発想になる大元の原因に、プラトンによる、あらゆる物事には理想型・理念型(これをイデアと言う)があり、私たちは、それを認識し、接近できるという考え方がある。ポパーによれば、この前提に基づくユートピア主義が、自由民主主義よりも全体主義を志向し、世界を破滅に導くのである。哲学は、机上の空論にすぎず、毒にも薬にもならないと思われるかもしれないが、直接ではないにせよ、ヘーゲルやマルクスのために、何人の人間が死んだだろうか。
ユートピア主義に対して、ポパーが好むのは、漸進主義である。ユートピア主義のように最終目的地を最初から設定するのではなく、実際にやってみてうまくいかなかった点を反省し、次回に生かす、終わりなき微修正を続けるのである。このような漸進主義は、遥か彼方の星を見るのではなく、ゆっくりとボートを漕ぐように、直近の過去を見ながら進む。
この漸進主義の根本にあるのは、私たちは、最終目的地・ユートピアはもちろん、少し離れた将来のことや、少し大規模な社会全体のことを、把握し・設計し・改善するための、自身の能力を過信してはならないという考え方である。ポパーはこれを、ソクラテスの「無知の知」というスローガンに見る。自身の知性の限界を知ることが、知への第一歩なのであるが、残念ながらソクラテスからプラトンに至って、この前提が完全に転覆してしまった。
ハイエクの下意上達主義
同じ考え方は、経済学者フリードリヒ・ハイエクにも見られる。彼は、計画経済よりも自由市場経済のほうが社会をより良くするとして、社会主義陣営に共感する知識人も多かった20世紀、首尾一貫して自由主義の旗を掲げ続けた。
社会主義の理想は、労働者の搾取や疎外を止めさせるという、その「内容」自体は非常に真っ当なものであるのだが、その「手段」が社会全体の経済を集権的に設計することである点をハイエクは問題視する。人々が有する需要や選好と供給能力に関する情報は、社会全体に散在し、時々刻々変化するので、それを一元的に管理し、正義の政策を計画・設計することなど人間の理性の能力の限界を超えている。もちろん、個人の文脈では、計画は、立てられるし立てるべきことが多い。試験に向けて学習の計画は、立てるべきである。しかし、それを社会全体で実施することはできないし、無理にそれを押し通そうとすると、かえって破滅的な帰結をもたらすことがある。
経済に限らず、多様なアクターが行動する場面では、内容が正しいからといってトップダウン(上意下達)で計画を実施するのではなく、各アクターが局所的に取引する中で自然に形成されてきたボトムアップ(下意上達)型の秩序を利用したほうが、うまくいく。それは、自由市場であり、民主主義であり、伝統文化である。これらは、時に緩慢で不合理だが、長い目で見れば、賢慮にかなっている。
これら、ポパーやハイエクに見られる現実主義・保守主義の特徴は、人間の持つ知性・理性の能力を過信しないという謙虚さにある。もちろん、啓蒙を完全に否定し、オカルトや陰謀論に溺れるのは危険だが、理性の暴走もまた危険である。ソクラテスやポパーの戒めは、私たちが常に誤りうる存在であることを忘れないという、可謬(かびゅう)主義にある。
夢想家のワーク・ライフ・バランス
ここまで、理想主義的な功利主義やプラトンと、現実主義的なポパーやハイエクとを比較してきた。皆さんの人生において、理想は、専ら仕事で追求するということもあるかもしれないが、より成熟した個人や社会では、余暇も含めた包括的な生活の充実・全人格的な発達が重要だろう。とりわけ多忙な医療従事者にとって、それはどのようにして可能になるだろうか。
戦中戦後の女子ミッション・スクールが舞台の皆川博子によるサスペンス・ファンタジー『倒立する塔の殺人』では、誰しも大切な人たちが毎日、戦禍でいわれなく殺されていく。卑賎さが跋扈する、唾棄すべき日常世界で、少女たちは、いかにして美しい夢の世界を作り上げ、守ることができたのか。皆川の答えは、美の想像と創造ということになろうが、私たちも現実に魂が食い尽くされないように理想を想像する力を維持しつつ、現実と折り合っていきたいところである。
同じ華美絢爛の作風でも、前回も紹介した須永朝彦は、三橋鷹女の「嫌ひなものは嫌ひなり」を愛唱し、したいことしかせず、見たいものしか見ず、最近、極貧のうちに死んだ。他方、幅広い仕事を着実にこなした皆川は、文化功労者である。私はどちらも好きだし、勲章などは世俗の飾りにすぎない。しかし、理想と現実の間に、成熟した大人のバランスを実現することの意義を思わざるを得ない。
***
さて次回は、ハイエクの議論を続け、リバタリアニズムの思想に話を広げたい。ハイエクは、国家による計画より市場で自然に発生する秩序こそ、望ましい分配を実現すると考えたが、分配的正義を実現する際に、国家が果たすべき役割は、どのようなものだろうか。国家・社会・家族の役割分担の観点から見ていきたい。