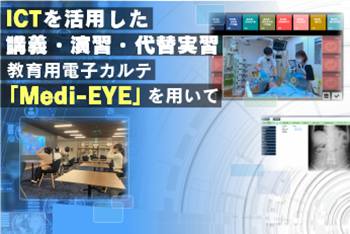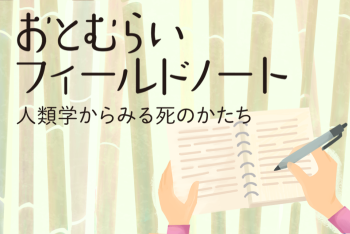「肉体『われわれは同じ名を頒け持つてゐる。王よ。俺はおまへの肉体なのだ。』
精神『それなら私は?』」
三島由紀夫『癩王のテラス』より
今回は、人間の身体の価値について考えたい。多くの臨床研究では、人体由来のサンプルが用いられるが、そのような研究では他にはない特別な倫理的配慮は必要になるだろうか。あるいは、献体1の手続きにおいて、特に注意すべき倫理的問題は何だろうか。医療は人間の身体に最も接近する実践であるので、これらの倫理的問題を考える手がかりを、以下で示してみたい。
身体とは何か、それを所有するとはどういう意味か
生命倫理では、これを「自己所有権」の問題として考えることがある。これは、「自分の身体は自分が所有権を有しているので、自分がコントロールできるべきだ」という考えである。この命題は、単純なように見えて、実は多くの複雑な問題を含んでいる。
まず、所有とはどのような意味だろうか。法律学では、それは、物を、自由に使用・収益・処分できるという意味で全面的に、私的に支配することである。この定義は、法律学のみならず、生命倫理学でも参考にしてよいだろう。自分の身体を自由に収益・処分するという意味で、臓器を売り渡すことについては、自分の身体を「所有」していると認識しているにもかかわらず多くの者が、倫理的に許されないと考えていると思われる。この意味で、身体の全部または一部を、土地や資本のような、通常の意味での所有権の客体とはせず、倫理的配慮の必要性から特別視し、その扱いに様々な法律上の規制をかけようとするのは、自然なことかもしれない。
次に、身体とは何だろうか。明白に身体であるもの、明白に身体ではないものは問題ないとして、その境界線上にあるものは、興味深い問題である。たとえば、義足・眼鏡・乳歯・血液 ・髪は、どうだろうか。倫理的な特別扱いの必要性の観点から適切と思われる、身体の定義を考えてみよう。
第一に、生物の個体に有機体的に統合されている部分を身体と見るものである。この場合は、義足も心臓ペースメーカーも身体ではないので、定義として少し狭すぎるかもしれない。第二に、生活に必須な機能を担っている部分を身体と見る定義である。これだと、スマートフォンも手と同じくらいの身体性を有することになるかもしれず、少し広すぎる。第三に、主体と精神的に統合されている部分、つまり主体が強い愛着を感じ、それを失う場合、人格に重要な変化が生じると考える部分を身体と見る定義である。切った後の爪に情が移る者はまずいないだろうが、盲導犬に対する暴力が器物損壊ではなく傷害の構成要件に該当する(つまり、それへの愛着ゆえに、当該盲導犬は、物ではなく身体である)という主張がなされたことがある。この定義はフレキシブルに私たちの身体観にフィットさせられるが、それゆえに曖昧で厳格さに欠ける。
結局、私たちが持つ身体観念の複雑さゆえに、どのような単一の定義を採用しても、帯に短し襷に長しとなるので、他の多くの概念と同様に、身体概念も、多くの要素(そのどれもが「必要」条件でも「十分」条件でもない)の複合と見るのがよいだろう。とはいえ、上記の3つの条件は、少なくとも、「重要な」条件であるということは、確実に言えるだろう。ちなみに、第二(機能)と第三(愛着)の条件は、精神と身体の密接な関連2を主張するものである点で、興味深い。
身体は本当に倫理的に特別な地位にあるのか
では、上記のような意味で、「個人が身体を所有、つまり支配する権利を有するべきである」という自己所有権の主張を理解するとして、その主張の規範的な妥当性について考えてみよう。
第一に、私的な所有権は、そもそもなぜ妥当なものなのだろうか。所有の規範的妥当性の説明として、思想史上、最も有力な説の1つが、ジョン・ロックによるものである。ロックによれば、神が世界を創造したとき、世界は誰の所有物でもなかった。ただ1つ例外があり、人間の身体は、その身体に宿っている人格・魂・主体に固有のものとされた。そして、人間が身体を用いて、つまり労働によって、たとえば無主物である荒地を耕作すれば、固有の所有権が、その土地にも浸透していくと主張されたのである。身体の所有が、身体の動作=労働を通して、土地などの身体以外の財物の私的所有へと拡張されるという理屈である。労働は、身体の働きであると同時に、精神の働きでもあるので、土地を耕すことは、耕す人の精神がその土地に浸み渡っていくことだというイメージである。
この説明では、身体の所有と、土地やその他の資源の所有が、一続きになっているのだが、現実の多くの諸制度では、両者の間には大きな違いがある。たとえば、第29回でも述べたように、平等主義者は、土地や資本を多く持つ者に課税し、それを持たざる者に再分配すべきことを、さも当然のこととして主張する一方で、仮に身長が人間にとって重要だったとして、高身長の者から低身長の者へ身長を再分配せよとは通常言わない。身体は、人格や精神と不可分に結びつき、その人そのものを構成するものであるから、外部の権力がむやみに介入するのは人道に反すると考えるからである。この意味で、身体は、その他の物体とは異なり、神聖不可侵なものであり、倫理的にも法的にも、その扱いに強い規制が課される。
この身体の神聖視・特別視は、私も直観的に認めざるを得ないのだが、前述の身体概念の曖昧さに鑑み、もう少し掘り下げて考えてみたい。ロック、そしてその思想的子孫であるリバタリアン(自由至上主義者)によれば、身体の所有が神聖であることはもちろん、身体そして労働の延長物としての土地その他の財産の所有も、同等に神聖なのであり、国家権力が課税したり処分の仕方を規制したりするのは許しがたいことになる。そこまでリバタリアンに肩入れしないとしても、身体を倫理的に特別視することを無条件に自明の理としたり、「①身体は倫理・法で厳しく規制、②その他の財産は規制緩和で自由な活動に委ねる」という単純な二分法で考えたりすることを止めて、身体が大切と思われている背景的な理由や根拠にまで遡って考えるべきである。
そもそもなぜ身体は重要なのか
では、そもそも身体は私たちにとってなぜ重要・必要なのだろう。その根拠は、色々と考えうるが、精神的活動としての自律(つまり、自分の人生を自分の価値観に沿って制御すること)のためには、身体が担うことを期待される能力や機能が必須の条件になっているということは、明らかに重要な根拠の1つだろう。身体の健全性は、自律能力を高める。健康であってこそ、やりたいことができる。自律を尊重するという倫理的立場を採るのであれば、①自律にとって重要な機能を担い、②それを失えば一貫した自律が失われるという意味で自律主体に統合され、③それゆえに主体が強く愛着を持つものを、それを身体と呼ぶか・みなすかに関わりなく、倫理的・法的に重視し、その取り扱いに対して、その他の財産・対象よりも厳しい規制を設けるべきではないだろうか。
このように考えると、機能の重要性・統合の密接さ・愛着の強さが、全か無かではなく、程度問題であるように、身体とそれ以外もまた、截然(せつぜん)とした内外の境界線はなく、グラデーションの概念ということになる。だとすると、それに応じて、法的・倫理的規制も、単純な二元論ではなく、よりきめ細かなものであるべきだろう。
***
次回は、生命倫理にとって、いや哲学史上、最も古く重要な問題の1つである、死について考えたい。
2 心身問題(心と体の関係の問題)は、非常に古くからの哲学的問題であり、デカルトの心身二元論などが特に有名である。同時に、この問題は、埋葬の仕方など、宗教的、社会・文化的にも大きな含意を有する。