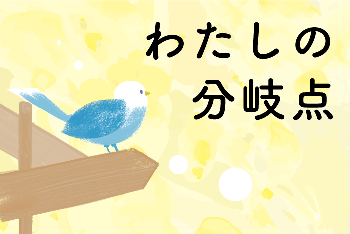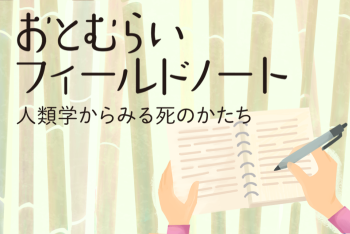“Til death overtake me in the chase Still will my hopes pursue thee”
My Dying Bride ‘Black God’より1
今回から、2回にわたって死の意味について取り上げてみたい。私自身、魂が揺さぶられるような死の場面を直に経験2したことがないので、議論が上滑りしないように注意しながら考えていきたい。
死にどう立ち向かうか
個人が、死に完全に勝利することが不可能であることは、疑いない。しかしまた、部分的に勝利を収めることが可能であることも間違いない。ここで「勝利」と言ったのは、個人が死を支配・制御するという意味である。人間の理性が築いてきた近代文明は、多くの自然を人間の支配に服さしめることに成功してきたが、依然として死は巨大な未踏峰である。死ほど思うに任せられないものはない。
この点を強調するのが、実存主義である。実存とは、さしあたり「かけがえのない個人としての存在」と考えよう。その重要性を唱えるのが、実存主義である。私たちの生活におけるおおよそのことは代理・代表が利くが、中にはそのような代理可能性のないものもある。死はその代表格であり、誰かの代わりに死んであげたり、代わりに死んでもらったりすることはできない。このどうしようもなさが、死の支配困難性の大きな原因の1つである。また、当然、誰も自身の死を経験したことがないので、死の一人称的経験のエビデンス・知識の蓄積は、これまでも今後もゼロである。
支配や制御ができない、知識や経験がなくその正体が皆目不明であることは、大きな恐怖を生み出す。死の恐怖を異常に強く感じるタナトフォビアは、勁強で偉大な精神の持ち主でも、そこから自由ではなかった。濃厚に死を匂わせる作品を多く遺したグスタフ・マーラーは、第九の呪い3を強く恐れていたと言われる。死の恐怖を前に、我々の精神が敗北することも、時にある。
しかし、実存主義は、恐れずに死に立ち向かう、つまり自身が死すべき運命にあることを常に意識することが、私たちの生活を緊張感と充実に富むものにすると言う。死を忘れた弛緩した精神は、私たちの生き方をだらしないものにするが、それに対し、死の運命への意識は、うまく利用すれば、人生を豊かにする恩寵にもなるのである。
この観点から、死に対してせめて部分的に勝利するための戦略を練ってみよう。死に抗う1つの方法として、この世界の記録と記憶に、一時的とはいえ強固な爪痕を残すことが、よく挙げられる。しかしもう1つ、ここで考えたいのは自律である。つまり、どう生きるか・どう死ぬか(両者は全く同じことである)を、自分自身の価値観に基づいて差配することである。死んででもなすべきことを見出だして、それに打ち込む。そうすることで、生死を超えた価値を示せたことになる。実際、マーラーは、第九を完成させ、その呪いを一身に受けてか、第十番を未完に病に倒れた。もちろん、死に克つためには、何もそこまでの偉業を成し遂げる必要はない。業績は結果論にすぎず、偉人たちは自分らしい生き方を追求しただけである。またそれは、多くの人に知られる必要もない。名誉や承認は、しょせん自律ではなく他律に基づく価値である。
自律のためには、エンディングノートをコツコツ書くだけでも良いかもしれない。多くの者は、高齢になってから様々な終活を始めるが、生まれた瞬間から終活は始まっているという気概さえあれば、期待以上に素晴らしい境地に到達するかもしれない。そのための具体的な行動の内容は、それこそ実存、すなわちユニークな個人の問題なので、他人がとやかく言うべきものではない。ただそれは、自身の真摯な価値観に基づいている必要がある。それが自律の定義だからである。
自律は、内発的な何らかの欲求や希望に駆られてのものであり、死の瞬間まで屈せず自律的に追い求めるものがある人生は、何と幸福なことではないか。
死ぬとはどういうことか
以上は、死にどう立ち向かうべきかという、態度や心構えのような議論であったが、ここから次回にかけて、より細かい理論的な話をしたい。例によって、まずは諸々の定義を明らかにする作業が必要である。人間の死は、その存在の消滅と捉えられることがある。この存在という概念は、相当に厄介で、ある存在者(つまり「もの」)が本当に存在していると言えるためには、どのような条件を満たす必要があるかという問題が、存在論という哲学の一大分野をなしている。他の概念もそうであるように、存在の概念も、伸縮自在の性質があり、広義から狭義まで様々な概念が、「存在」という言葉と結びつけられる。たとえば、「個物として指示(指し示し)可能であること」や「他の存在者と関係性を持つことができること」、「知覚できること」などを、存在の条件とすることが考えうる。第2回でも少し触れたが、規約主義の考え方によれば、「論理的には」どんな定義を採用するのも自由である。しかし、人間の死を、うまく説明するための適切さという「実践的な」理由からして、これらの定義は、少し広すぎる。なぜなら、これらの定義だと、たとえばフィクション内の登場人物も存在しているし、死者も私たちの心の中で存在し続けていることになってしまうからである。したがって、ここではもう少し狭い定義を採用するのが好ましい。
このような観点からして、人間の死、すなわち存在消失の定義・説明として適切なのは、それを主体性の不可逆的な喪失と捉えるものだろう。主体性とは、意識・欲求・目的を持ち、世界を経験し、それに反応する能力と定義してみよう。これは、すなわち自律の行使のために必須となる能力である。これが、回復不可能な形で失われることを、人間の実存・存在の消滅、つまり死と考えよう。
死の害悪を減らす
死は、ほとんどの場合、悪いものと評価される。もちろん、例外的には死んだほうがましだという主張がされる場合もあり、これが安楽死や尊厳死の許容可能条件をめぐる議論につながるのだが、基本的には、個人が死によって失うものは、得るものより大きい。
死の害悪には、死の接近に伴う心身の苦痛もあるが、そのような派生的なものはさておき4、死そのもの、つまり単純に存在が消滅することの害悪に焦点を当てたい。死そのものの害悪とは、死ぬ本人が、死によって得られるものから失うものを差し引いた分である。遺された人々や社会に引き継がれるものは除いて、死ぬ本人が、死んで得られるものはゼロであるから、これは要するに、死によって、生きていればできたはずのこと、すべきだったことを達成する機会が失われることである。
こう考えると、個人にとっての死の害悪をできるだけ少なくすることとは、死による機会喪失をできるだけ少なくすることに他ならない。こう言ってしまえば凡庸であるが、心残りをできるだけ少なくすることである。ただ、ここで注意すべきは、この心残りは、個人の主観によって定義されるべきではない。仮にそう定義すれば、一方で、生きる意欲や希望を失くした者は、今すぐに死んでも、主観的に失われるものがないのだから、何ら害悪はないが、他方で、不死を願う独裁者はそれが叶えられるべきであるということになってしまい、これは望ましくないだろう。そうではなく、死の害悪は、間主観的に、つまり社会的に定義されるべきであり、死による心残りとは、ある時代のある社会の構成員として、個人が正当に享受を期待できる人生の経験5と、実際に死んでしまうことでそれが実現できないことの差額と考えるべきである。
この方法で定義された死の害悪をできるだけ減らしていくように日頃から自律的な生活を心掛けることは、死を恐るに足りないものにするための、十分条件ではないだろうが、少なくとも必要条件の1つと言えるのではないだろうか。
***
次回は、死にゆく人と、どう向き合うかという問題について考えたい。
2荼毘・屠殺・処刑・戦死など生々しい死の場面を、日常の経験からできるだけ排除することを、我々は文明と呼んできた。
3ベートーヴェンが、交響曲第九番の完成の後に死去したことから、交響曲を九番まで書くと死ぬと言われている。
4派生的な害悪が重要ではないと言っているわけではない。医療・看護が焦点を当てているのは、これら派生的な害悪をいかに減らすかという問題であろう。ただ、今回は、存在消滅そのも のの害悪を考えたいということである。
5これについて、悲しく美しい情感のこもった風習が日本の東北地方にあった。ムカサリ絵馬による冥婚である。たとえば、未婚で出征し戦死した若い兵士の、泉下の幸福を願って、温かく豊かな色彩の婚礼の場面を描いた絵馬が奉納された。