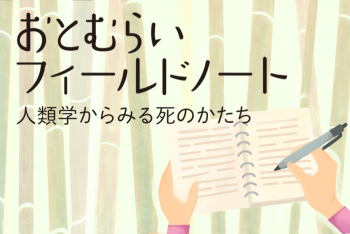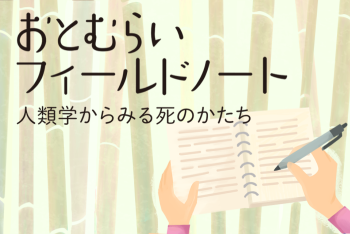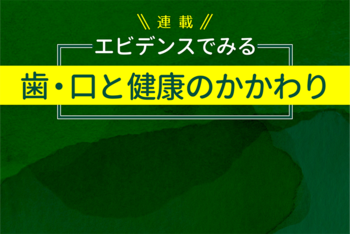「私は闇の息子なのです1。」ジャン・ジュネ『ヘリオガバルス』より
「惣三郎め、美男すぎた。・・・化物が住み着いたのだろう2。」大島渚『御法度』より
今回は、命の分配的正義においてくじ引き、つまりランダムな抽選を用いることの是非、そしてその背景にある問題としての理性・合理性の意義について考えよう。
生き残りのくじ引き(サバイバル・ロッタリー:survival lottery)
生命倫理において悪名高い(?)、ジョン・ハリスの生き残りのくじ引き論(臓器くじ/サバイバル・ロッタリー)というものがある3。それによれば、我々は例外なく、生き残りの無作為抽選に参加しなくてはならず、運悪く当選となれば、その身体は五臓六腑から髪の一本に至るまで、全て安全に摘出され、それを必要とする人々に完璧に安全に分配される。
罪なくして死なねばならぬ身となれば、たまったものではないが、重篤な疾患になっても移植によって助かる見込みが改善する。1人の身体から多くの臓器が収穫可能だから、運悪く当選する確率はかなり低いのに対し、この制度のおかげで、より長生きできるようになる可能性は相当にある。一般的に言えば、この制度によって、全ての者の余命の期待値は大きく改善するというのである。
この提案をめぐる論点は、社会全体の福利を向上させるハリス流の功利主義と、それに反対し自己の身体の処し方に対する個人の拒否権を重んじるリバタリアニズム(これは、次回のテーマである自己所有権にかかわる)との争いという文脈で扱われがちだが、忘れてはいけない論点がもう1つある。この論争では、功利主義よりもリバタリアニズムに直観的に分がありそうだが、それは功利主義よりリバタリアニズムのほうに説得力があるからではなく、生き死にのような重大事をくじ引きという偶然に委ねることに我々が強い拒否感を持つからである。
くじ引きは、あらゆる理由づけを拒否して、全くの偶然を利用するものである。どんな決定にも理由や根拠・合理性を求める、知性主義・理性主義・啓蒙主義の立場は、くじ引きを嫌うだろう。熱湯に手をつけてできる偶然の傷跡に基づいて裁判で判決を下したり、神託で征夷大将軍を選んだりするのは、暗愚である、と。確かに、それも一理ある。しかし、あえて理由を用いないことが、適切な場面もあるのではないだろうか。
2人のうちどちらかが死ななくてはならないギリギリの場面において、AのほうがBより知能指数が1高いとか、Bのほうが子供の年齢が1歳若いとか、厳格で合理的な根拠を示すことにあくまでもこだわれば、救われなかった者は、厳格かつ合理的に、生きる価値が劣っていると宣告されたことになる。それに対して、くじ引きを用いれば、救われなかった者は、合理的に何かが劣っていたわけではなく、単に運が悪かっただけである。彼の利益は守られなかったが、せめてその尊厳は守られたのである。
このように、倫理とくじ引きの関係は、一筋縄ではいかないのだが、これは結局、倫理や正義は、理性をどこまで重んじるべきかという問題である。
アポロンとデュオニソスの決闘(デュエル)
ニーチェは、太陽神アポロンと酒神デュオニソスに、それぞれ理性・知性と、感情・欲動を象徴させている4。両者の対立は、古今の哲学における一大論争軸である5と同時に、私たちの日常における実践的対立でもある。たとえば、私たちは、科学をどこまで信用しているだろうか。医薬品、たとえばコロナワクチンの安全性と有効性について、啓蒙主義的知性主義と、懐疑主義的な反知性主義の間の対立は、激しい政治的罵り合いにまで発展した。
ニーチェ同様、私も、理性と感情、両者のバランスが肝要と考えているが、世間一般から見れば、私も相当に理屈っぽく、頭でっかちな方だろう。たとえば、私は、反ワクチン運動の多くが掲げる反科学主義の主張に概して否定的であり、科学研究に基づく医薬品の認可の制度を基本的に信用している。この制度がなければ、世にまじないや流言が容易に蔓延るだろう。やはり科学と理性の力は偉大である。
しかし、こと自身の論文やそれに類する文章では、私は、自分を反知性万能主義に位置づけている。それは、私が普段、学術的な文脈で、自分をはるかに超える知の巨人に囲まれて、極度の理知主義に飲み込まれてしまいそうだからである。空疎な綺麗事や、議論のための議論に終始することなく、現実に人々を動かしている力の所在を見定めるバランスを失わないように努めたいと思っている。
知性主義者は、信頼・信用を生みだす権威やブランドの多様性を、もっと顧みるべきである。残念ながら人間は、自らの行動や信念を決定する際に、理屈やエビデンスをそれほど重視しない。医薬品の認可に権威があるのも、科学のブランドへの信頼と同時に、国家のブランドへの信頼にも依存する。(海外旅行には、母国から大量の医薬品を持参するだろう。)
このような意味で、私は決して完全な反理性・反科学ではなく、むしろ理性や理由を社会においてより良く用いたいとする立場である。そのためには、人間の非理性的な本質をよく理解しなくてはならない。
***
次回は、自己所有権、すなわち自分の身体が自分に固有の所有物であることの意味について考えたい。
2 理性と秩序を体現する土方歳三が、新選組の綱紀粛正のため、妖気漂う桜の木を一刀で斬り倒す。
3Harris, John(1975). “The Survival Lottery”, Philosophy, 50, pp.81-87.
4ニーチェ『悲劇の誕生』一~四節
5この構図は、「主知主義」と「主意主義」の対立という用語でも表現される。