ここまで数回の議論は、分配的正義に関するものであった。つまり、社会に存在する利益や負担を、どのようにして公平に分かち合うかをめぐる議論であった。医療や看護の文脈では、有事におけるトリアージや、医療機関内外あるいは地域間での人的・物的な資源の分配という実践的問題に適用可能な議論である。公平な分配とは何かという問いに対する答えは、「社会の効用が最大化するように」とか「平等に」とか、いろいろありうるが、それは「どのように分配するか」という観点からの答えである。これはこれで重要なのだが、それとは別に、「誰が分配するか」という、分配の責任主体の観点も忘れてはならない。重要な問題なので、少し長くなるが、今回はこれに取り組みたい。
家族・市民社会・国家、そして特に後二者の競合
ヘーゲルは、人間のつながりの形を、家族・市民社会・国家という三分法1で考えた。それぞれに、情緒的な紐帯、欲望の合理的追求、法による統治を理想に掲げているが、これらはどれも分配的正義の責任主体になりうる。これらの中でも特に、国家と市民社会は、特定の分配について、どちらがその任に適しているかについて、しばしば競合している。たとえば、呼吸器感染症のパンデミック時において、マスクの生産と分配は、国家が主導すべきか、民間企業の自由な活動に委ねるべきか。
大きな対立軸で言えば、国家主導・大きな政府による、法律に基づいて強制的に実施される財の再分配に肯定的な立場と、自由市場の民間企業主導で、小さな政府は市場にできるだけ介入しないという立場がある。前者は、経済的左派、後者は経済的右派とも言われる。分配の主体として、集権的国家を信じる左派・社会主義者と、分権的な市場と企業を信じる右派・リバタリアン(自由至上主義者)が、対立しているのである。
ハイエクの帰結論的リバタリアニズム
左派の考え方は、次回以降の平等主義の際に考えるとして、今回はリバタリアンの思想を見てみよう。彼らは、国家・政府・法律による、個人や個々の企業の社会経済活動への介入は、できるだけ少ないほうが良いと見る。代表格は、やはりハイエクである。彼は、トップダウン的命令より、ボトムアップ的な自生的秩序を好む。計画経済より自由市場、設計主義的な成文法より判例法や慣習法、独裁制や寡頭制より民主制、押しつけの啓蒙的教育より自然に培われた伝統文化が、優れていると考えるのである。国家は、設計図に基づいて人工的に自動車を組み立てる工業モデルより、自然が本来持っている力が最大限に花開くように環境を整える農業モデルで考えるべきである。つまり、国家・政府・法律は、民間・市民社会が本来持っている草の根の創意工夫の力が発揮されるためのサポート役に徹するのが良い。
このようなハイエクのリバタリアニズムの根拠は、「そのほうがうまくいくから」というものである。つまり、彼は帰結論に基づいている。小さな政府、「それ自体が良い」という、義務論ではない。
トップダウン型がうまくいかないのは、個人が何を欲し・何ができるのかに関する情報が複雑で散在しており、集権的なやり方ではそれを収集・管理できないからである。逆に、人々の欲求や生産能力がシンプルで、分かりやすい財が重要性を持つ時、すなわち有事においては、トップダウン型のほうがうまくいく場合もある。たとえば、トップダウン型組織の代表格である自衛隊が、ワクチン接種のロジスティクスを担当したのは良いアイデアである。ボトムアップ型それ自体が良いわけではないので、トップダウン型のほうがうまくいく場合は、帰結の良さに応じて、柔軟にそれを採用すべきである。
ノージックの義務論的リバタリアニズム
それに対して、もう1人の重要なリバタリアンである、ロバート・ノージックは、義務論的である。つまり、個人の独立・財産権の保障・結社の自由は、その帰結の良し悪しと関係なく、神聖不可侵である。ノージックは、防衛(軍)・治安維持(警察)・紛争解決(裁判所)の三つだけは、国家が集権的に実施すべきだが、医療・年金・保険・教育などその他の社会事業は、すべて分権的な民間の結社の自由に委ねるべきと考える。
これは、社会福祉の軽視、弱者切り捨てと言われるかもしれないが、リバタリアンに言わせれば、むしろその逆である。サービスの提供は、単一に統合されたほうがそれを享受する個人の自由がより大きくなるものと、バラバラであるほうがより自由に資するものがある。一つの領域の内部に、治安維持機関が並立すれば、縄張りをめぐって抗争が始まり、かえって平和が脅かされるかもしれないし、紛争解決機関が複数あれば、セキュリティソフトを複数インストールしたパソコンのように、社会経済活動の安定性と流動性が損なわれるだろう。それに対し、それ以外の、医療・年金・保険・教育・食・ファッション・芸術などは、多様な個人や企業が切磋琢磨したほうが、より多くの質の良い選択肢が提示される。このように考えて、ノージックは、国家の役割を、上記の三つに限定するのである。医療や福祉を、より良くしたいからこそ、国家ではなく民間にやらせるのである。
多様な責任主体のハーモニーを模索する
さて、このようなリバタリアニズムの考え方に対して、私は必ずしも諸手を挙げて賛成しているわけではない。この問題は、政治的な思想信条にも密接に関わるので、ぜひご自身の価値観に合わせて考えていただきたいのだが、いちおう私自身の考えも述べておこう。
一般論として言えば、分配的正義の実現に責任を負うべき主体として、家族・市民社会・国家のうち、特定のどれかが無条件に優れている、あるいは劣っているということはない。古今の芸術家の題材となってきた三美神カリステ2は、互いにその美貌を競ってはいるが、それぞれに良さがあるのであって、どれが一番ということはない。分配的正義についても、どれか一つが、専ら責を負うのではなく、役割のベスト・ミックスを模索すべきである。
というのも、家族・市民社会・国家のそれぞれに、扱う財の種類による、得意分野というものがある。「どのように分配するか」と「誰が分配するか」と並んで、「何を分配するか」も重要なのである。では、医療はどうか。医療が扱っているのは、消費者が財のクオリティをすぐに理解し、より良いものを求めて取捨選択できる探索財ではなく、専門家に対する信用が重要になる信頼財である。ファストフードのような探索財であれば、市場・市民社会による分配が適切だろうが、信頼財としての医療は、国家によるクオリティ・コントロールが、強く要求されるのではないだろうか。
また、医療分野でも、特に高齢者や小児の看護やケアについては、特に日本社会においては、家族の負担が重すぎるので、市民社会、またより強く国家が、その責任の一部を肩代わりすべきではないかと思う。三美神のハーモニーは、華麗なダンスのように、社会の文脈に応じて、柔軟に変容していくべきである。
***
次回は、分配的正義の有力な立場の一つである、平等主義を取り上げたい。



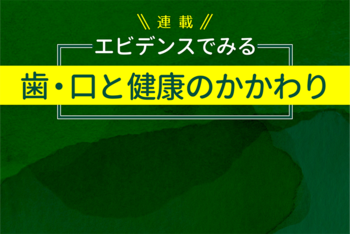
」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)

