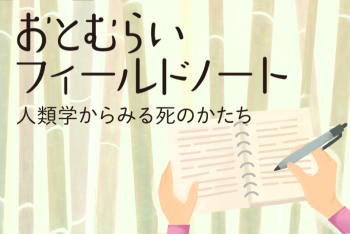今回で、ついに自律・福利・正義という、看護の倫理の三部門の解説が、ひと通り終わりになります。こまごまとした、しかし興味深い各論がまだいくつか残っているので、それらは次回以降に説明しますが、ひとまず正義論の締めくくりとして、正義をめぐるここまでの議論を使って、看護の実践に かかわる思考訓練をしてみましょう。
数年前の、ある鮮明な記憶について
全世界を恐怖と混乱に陥れた、2020年に始まる感染症の世界的流行との最初の直面は、日本においては豪華客船の来航でしたが、欧州では、ヴェネツィアのカーニバルに、『赤き死の仮面 』1 さながらに、不穏な影が迫るように訪れたことであったのは、読者の多くもまだ鮮明に記憶されていると思います。極彩色の祝祭は、徐々にニュース速報と清潔な防護服に置き換わり、マリア祭2の華は咲いたばかりで摘み取られ、アドリア海の女王は都市封鎖されました。
しかし、そこからの逆転劇は、まさに心震えるような人間性の勝利でした。例外なくすべての者が、多かれ少なかれ重大な犠牲を払ったにもかかわらず、どんな絶望にも決して屈しない、私たちがこれまで幾度の危機に対してそうしてきたように、何度でも立ち上がる姿は、鬼神をも哭(な)かしむるという表現でも大袈裟ではないでしょう。その英雄的主役は、間違いなく医療従事者でしたが、正義と法律もまた重要な脇役を演じたと思います。そこで、以下では、有事における希少財の分配的正義の問題を列挙するので、ぜひ自分なりの解答を考えていただきたいと思います。
緊急事態における分配をめぐる、いくつもの問いについて
まずは、ワクチンの分配の公平性です。とりわけ、普及の初期の段階では、その希少性が際立っていました。
【問い】
・日本では、まずは医療従事者、次いで高齢者という順に分配がなされました。前者は、事態に対処して多くの他者を救助する「能力」に着目した基準、後者は重症化リスクなどの「必要性・ニーズ」に着目した基準と言えますが、これは公平・公正な基準だったと言えるでしょうか?
・ワクチンの分配は、COVAX3のような国際的な枠組みが、統一的な基準で主導する傾向を、より強めていくべきでしょうか?それとも逆に、各国や各自治体が、それぞれの取り組みに広い裁量を有する分権にかじを切るべきでしょうか?
・今回のパンデミックでは、製薬企業の動きが相当に機敏であったと思われます。法が、特許等、企業の知的財産権を強く保護することは、イノベーション・発明のインセンティブになるという指摘もありますが、そのような法制度は、ワクチンの迅速あるいは公平な分配に、どのような影響があるでしょうか? より一般的には、国家・法は、製薬企業の活動に、どこまで介入すべきでしょうか?
・上記の回答は、パンデミックの初期・拡大期・収束期で、どのように異なるでしょうか?
・国家は、次のパンデミックに備えた研究支援を、どこまですべきでしょうか?
また、ワクチン以外でも、パンデミック時の分配的正義には、多様な問題があります。たとえば、人的資源の分配の公平性は、重要です。
【問い】
・医療従事者の、たとえばあなたの職場の負担の分配は、公平だったでしょうか?それを、より公平にするには、どのようにすればよかったでしょうか?
・国際・国内の地域間で、病床やその他の医療サービスの質の極端な偏在をなくすには、どうすればよいでしょうか?
さらには、分配的正義ではなく、自由・自律にかかわる問題になりますが、ワクチンの接種において、個人の選択の自由をどこまで認めるべきでしょうか。
【問い】
・国家は、ワクチン接種を、禁止すべき? 罰金などで抑制すべき? 全く放任すべき?補助金などで推奨すべき? 望む者全員への無償化などで保障すべき? 望まない者も含めて義務化すべき? これらのうち、どのような対応が望ましいでしょうか?
緊急事態だからこそ大切なこと
次に、分配的正義というより、正義一般、そしてその背景にある問題を考えたいと思います。パンデミックに限らず、緊急事態においては、法の支配の価値が軽視されがちです。特に初期のパニック期においては、いわゆる「○○警察」が多数出現しました。たとえば、マスクをしていない、あるいはしている人間を全員逮捕してしまえという乱暴な主張が、冗談ではなく、真顔でなされました。国家は、それを可能にする実力を保持しているのだから、正しいことをするのに躊躇している暇はない、という意図なのでしょう。正しさはさておき、確かに国家はそのような実力を有しています。しかし、その実力を制御するための法が、それを許していないということが、あまり意識されていなかったのではないでしょうか。あるいは、法の支配の価値は十分に理解しつつも、緊急事態だから超法規的措置もやむなしと考えたのかもしれません。
確かに法を守って社会が滅んでは元も子もないので、法の支配も絶対の価値ではありません。しかし、法は、私たちが何度も危機を乗り越えてきた歴史の上に築かれているものなので、危機に対応できないほど硬いものでも、危機に瀕して機能停止するほど脆いものでもありません。もう少し法を信頼して冷静になれるよう、平時からの心の鍛練に努めたいものです。そこで問いたいのは、次の点です。
【問い】
・緊急事態においては、どこまで例外的措置・原則からの逸脱が許されるでしょうか?
これらの問いに対し、功利主義者・リバタリアン・平等主義者は、全然違う答えを提示すると思います。いずれにせよ、答えは、一般理論ではなく現場や事例の中にあるので、ここで言えることには限界があります。ぜひ自分の周囲の具体的な文脈に当てはめながら、答えを探してみてください。
***
さて、次回からは、ここまでに登場しなかったテーマを取り上げます。初回は、人生における時間についてです。年齢・余命など、時間に関わる事柄が、生命倫理において、どのような意味を持ちうるか考えます。