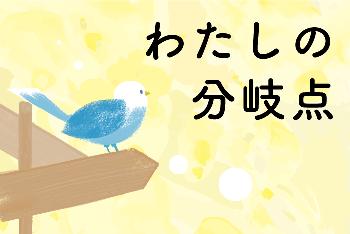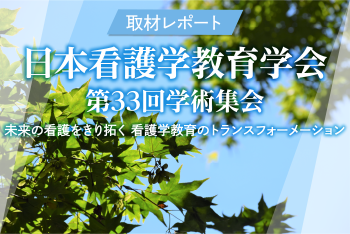NurSHAREは2024年11月23日をもってサイトオープンから丸3年を迎えます。この間、コロナ禍において看護教育の発展に寄与すべく、様々な情報の発信、イベント開催等に取り組んできました。何か利用者のみなさまのお役に立てたことがあったでしょうか。
さてこのたび3周年を記念して、サイトオープン時に本サイトへの期待を寄稿していただいた聖路加国際大学の林 直子先生に、いま現在の地点から、看護教育に携わるみなさまへのメッセージを頂戴しました。さらに多くの種が蒔かれ芽吹くことを願いお届けします。(NurSHARE編集部)
[サムネイル写真:聖路加国際大学横の築地川公園にて(2021年11月14日撮影)]
いつ頃からだろう。自分の思い描く将来像は、“看護婦さん” だった。
ありがたいことに、健康に恵まれた私は入院経験なく幼少期を過ごしたため、かかりつけのクリニックで患者の呼び出しをしている人や、診察室の医師の背後で医療器具らしきものを煮沸消毒している人(今のようにディスポ製品が主流ではない時代である)、乳鉢で粉薬を調合し、一包ずつに分けて薬袋に入れ窓口で患者に薬の説明をして渡す人が “看護婦さん” だと思っていた。大きくなるにつれ、テレビドラマやドキュメンタリー番組を通じて、実際の看護婦さん(臨床看護師)のイメージが少しずつ具体化され、どうやら入院患者の心身のケアをしたり(療養上の世話)、医師の治療の介助(診療の補助)をしたりする人らしい、というイメージを持つに至った。これほどまでに仕事内容を知らない私が、漠然と「看護婦になる」と思った背景には、気づかぬうちに耕され、種が蒔かれていたことに尽きる。
物心ついたころから、事あるごとに母親に「看護婦さんになったら?向いていると思うわよ」と言われて育った。なぜ? と問うと、だって強いものには歯向かうけど、弱いもの、傷ついている者には絶対優しいから、と笑って答えた。(前半部分は看護師の資質とは関係のない、単なる私の性格であるが、なぜか必ずワンフレーズの如く言われた。)他の職業をあまり知らない幼少期の私は、そうかそうかと鵜呑みにし、何ら疑うこともなく将来像を思い描いた。
時は流れて中学、高校と具体的に進路を考え始めると、幼少期からの “刷り込み” 効果か、自ずと医療分野に関心が向いた。いざ職種を考えると、「治療」を行う医師、「治療薬」を調合あるいは開発する薬剤師、そして幼い頃から言われ続けた看護婦、どの方向に行こうかと迷った。しかし、この時の母の助言(方向づけ)も明快だった。「これからの日本は高齢化がどんどん進んで老人が増える。またコンピューター化が進んで、一層ストレスの多い社会になるから、メンタルケアが必要な人が増える。そういう時に最も力を発揮するのは看護婦だと思う」「医師はこの先余る時代が来るかもしれないけれど、看護婦はますます足りなくなる」「看護婦は医療職の中でとても重要な役割を担っているのに、社会的地位が低い。これを少しでも改善するためには教育の強化が重要でそのような役割を担える人が必要」と。ここでも一貫して “看護婦推し” だった。今から40年余りも前のことである。なぜ医療職でもない、専業主婦の母がそこまで看護について語るのか、当時はあまりの説得力に圧倒されるばかりで疑問を持たなかったが、後年その理由を聞いて合点がいった。
チエコさんが運んできたアメリカの風
父の従姉妹に日系アメリカ人(日系二世)のチエコさんという人がいた。彼女は父よりひと回り以上も年上の従姉妹だった。チエコさんは2、3年に一度チエコさんの夫のヒデオさん(同じく日系二世)と実母(日系一世)とともに来日し、アメリカのお菓子を沢山携えて我が家に遊びにきてくれた。1970年代後半から80年代にかけてのことである。私たち子どもにとっては、チエコさんたち一団がお菓子を持ってアメリカの風を運んできてくれる楽しい時間という印象であった。この時私はまだ知らなかったのだが、チエコさんは米国イリノイ大学シカゴ校看護学部の教員であり注1、看護婦がいかに社会的に重要であるか、米国の看護教育がどのように行われているのかを母たちに語っていたという。日本の看護は米国と比べて30年ほど遅れている、このギャップを埋めるためにも、日本の看護教育の水準を上げねばならない、と力説していたそうだ。
チエコさんの看護に対する熱い想いと看護教育への揺るぎない信念に感銘を受けた母は、チエコさんから聞いた話をそのまま私に吹き込んだ。1980年代当時、日本に看護系の大学院が殆どなく注2、より高いレベルの教育課程で学ぶことを望んだ看護学生は、米国の大学院に留学した。その留学先の一つが、イリノイ大学であった。当時の留学生で、現在は本邦の看護界の重鎮のおひとりから、イリノイ大学で学んだ看護の大学院生でチエコさんのお世話にならなかった人はいない、と後年聞いたことがある。太平洋戦争を挟んで日系アメリカ人は過酷な状況下に置かれ、チエコさんたちも一時は日本への強制帰国を余儀なくされたと聞いた。それでも戦後再び米国に戻り、看護師になる道を選び、スクールナース、米国における小児のナース・プラクティショナー第1号を経て大学教員として後進の指導を行ったチエコさんの看護教育にかける思いは、果てしないエネルギーに満ちていたことと思う。さらに、日本からの留学生の指導に携わり、その修了生たちが帰国後本邦の看護教育を牽引してきたことを思うと、日本の看護教育にも貢献したことになる。そしてまた偶然にもチエコさんのパッションが、医療とは無縁の母を介して私へと伝わったのである。
それは “仕方ない” ことなのか
同じく高校生の頃、認知症の祖母(母の実母)が誤嚥性肺炎で入院した。定年退職するまで高校の古文の教員として勤めていた祖母は、いつも長い髪をきれいなお団子に束ねてピンで留めていた。そのキリッとした姿が好きだった。晩年は認知症の症状がかなり強かったが、それでも長い髪は一つにまとめていた。祖母の入院先は、少々遠方の病院だった。母は平日に一人で見舞いに行っていたが、ある週末、私にも一緒にいこうと声をかけた。面会に行くと、祖母の髪は無造作にバッサリと切られていた。ベッドでほぼ寝たきりの祖母に私と母が声を掛けると、目を開けて二人の顔をじっくりと見比べて、しばしの沈黙の後、「どっちが若いんですか?」と聞いた。「あらやだ、娘と孫でしょ」と母が言うと、さらにじっくり見比べて、「こっちのほうがよくできています」と私の方を指さした。それだけ言うとまた閉眼して寝てしまった。母は、せっかくきたのに失礼しちゃうわね、と怒りつつも笑っていた。相変わらずの祖母の自由な言動を嬉しく思う一方で、私は短髪の祖母の姿、手に抑制帯がつけられた寝たきりの他の高齢患者の姿(今から40年以上前のことである)に衝撃を受け、この状況は果たして “仕方ない” ことなのか、とショックを受けて帰路についた。「尊厳」や「患者の権利の擁護」という言葉に全く馴染みのない時分であったが、人としてとても大切なものが侵害されていることへの驚きと悲しみを体で感じた。
また、こんなこともあった。身内に入院加療が必要となり、医師から治療方針と今後の見通しについて説明があるから一緒に聞きに行こう、と母に連れて行かれた。医療者がどのように患者家族に説明するのかを知る良い機会だ、と。この時の医師の説明はとても丁寧で、平易な言葉で説明してくれていたように記憶している。それでも診断名と治療について、おそらく想定より厳しい内容を伝えられた両親の深く沈んだ表情は、子どもからみてもとてもつらいものだった。臨床看護師になると、日常的に “ムンテラ”(治療方針の説明)に同席したが、患者家族の様子がいつも気がかりだったのは、この時の経験があったからだと思う。
現職場である “聖路加” の名前を知ったのも、高校の時だった。高校の養護教諭の先生が聖路加(当時の興健女子専門学校)出身で、先生のユニークな保健の授業が毎回楽しみだった(先生のユニークな授業については他誌注3に譲る)。その授業の中で、しばしば聖路加で受けた独特な教育のこと、看護の奥深さについてとても熱く語っていた。先生をこれほど魅了するのだから、きっと看護とは深遠でやりがいのある仕事なのだろうと思った。その先生が語っていたことの一つに、女性の生き方と妊孕性のことがあった。この先の世の中では、女性も男性と同じようにどんどん社会で仕事をしていくようになる。ただ女性の場合、将来出産することを希望する可能性があるなら、女性の体を考えると子どもを産める年齢というものがある。そのことも一方で意識しておくことが大切、ということだった。今でいうところの、妊孕性についての話である。この10年余り、乳がん患者の妊孕性温存に関する研究に携わっているが、乳がん患者の中には、妊孕性について考えたことがなかった、知らなかった、と語る人も多い。高校の時から妊孕性について意識していた者として、女性が自身の体について知り、意識する(awareness)ためにどうしたら良いか、と考えることにつながっている。
蒔かれた種は芽を出し、根を張っていく
こうした多方面からの “導き” により、私は看護師になった。さらに思いがけず看護教員となった。仕事を始めた頃、母から「将来、色々な事情で仕事のペースを落としたり、時に中断したりせねばならない時もあるかもしれないけれど、そういう時はその時一番大事なことを優先すること。そしてそれが落ち着いた時に、また一緒に仕事をしたい、と言ってもらえるように、仕事ができる時は存分にするようにね」と言われた。将来の仕事と子育てとの両立を見据えていたのだろう。また、なぜか「いつか教科書の仕事ができるといいね」とも言っていた。なぜそのようなことを言ったのかは不明であるが、教員だった祖母の姿を、母もまた追っていたのかもしれない。看護学テキストNiCEシリーズのお話をいただいた時、ためらわずに引き受けたのも母の言葉がどこかに残っていたことによる自然な反応だった。
母が還暦を過ぎた頃、まだ健康状態に全く問題のない時であったが「将来は聖路加(のホスピス)で死にたい」と言っていた。聖路加の看護は素晴らしい、とチエコさんから聞いていたことも理由の一つだったようだ。思いがけず聖路加看護大学にご縁をいただいた時、聖路加の地へと踏み出すことを迷わず選んだ。
母は晩年認知症を患い、介護者として大変なことも多かったが、いつか母を聖路加国際病院で看取ることを目標に、認知症介護に励んだ。しかし思いがけず自宅で突然他界したため、最後のミッションは未完了なままの幕引きとなった。
現在、私は看護の教育に携わり、教科書の仕事もしつつ、米国との30年のギャップを埋めるべく、高度実践看護師であるCNS、DNPの教育に携わっている。蒔かれた内なる種は、すっかり根を下ろして、“抜け(られ)ない” 状態になった。「ほらもうやめられないでしょ」、と種を蒔いた人たちが、どこからか言っている気がする。
果たして、私は本当に看護に向いていたのか、母にあったらぜひ聞いてみたい。そんな問いかけに、母はこう問い返すかもしれない。「それよりあなたはどんな種を蒔いたの?」
残りの教員人生、まだまだやることはありそうだ。
注1 Chieko Onoda (小野田千枝子):元イリノイ大学シカゴ校(以下、UIC)看護学部教授、ナース・プラクティショナー(小児)。UIC看護学部にて1974-2000年にかけて教育に従事。日本でも1997-2007年の間、看護教育に携わった(文献a)。イリノイ大学シカゴ校のホームページには、「UICグローバルヘルスにおける伝説」として、戦後GHQの看護課に赴任し日本の看護教育・看護制度の再構築と発展に寄与した故バージニア・オールソンらと並び、紹介されている(文献b)。日本でもフィジカル・アセスメントを教授する第一人者として知られ、著書も残している(文献c)。1990年代以降、日本の全国の大学で教員を対象にイリノイ式フィジカルアセスメントトレーニングコースを開講していたこともあり、筆者も受講した。
a)Ganbare! The Life and Times of Chieko Onoda | UIC Nursing,https://www.youtube.com/watch?v=-3u_Opq-mz8
b) Legends in UIC Global Health,https://nursing.uic.edu/about/global-health/legends-in-uic-global-health/#chieko-onoda
c)小野田千枝子監:実践!フィジカル・アセスメント,改訂第3版,金原出版,2008
注2 2021年NurSHAREサイトオープン特別寄稿「分かちあい高めあう、新たな “知の共有基地” への期待」に掲載のグラフ(図2,3)参照
注3 雑誌『保健の科学』62巻2号(2020年発行)の巻頭言「恩師の教え」(p.73)に記した。