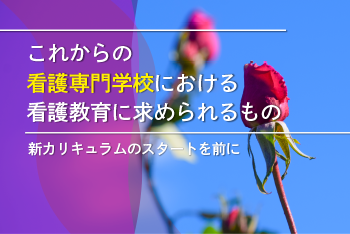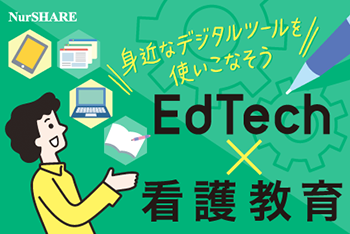前回は既存の医師・介護職向けVRコンテンツの活用事例についてお話ししてきましたが、今回は看護教育の場で使用することを想定したVRコンテンツの制作について、筆者らの取り組みをご報告します。
VR看護教育コンテンツ制作への発展
大田 博(福岡大学医学部看護学科 講師)、坂梨左織(同講師)
筆者らは、看護教育へのVRの導入を行い、様々な学生の反応を得ました。その反応に遭遇し、教育者として、看護職者として「VRは看護教育に有効かもしれない」と感じました。それは感覚的、直観的な印象だったと思います。
VRの教育効果については、先行研究などで様々に公表されていましたので、それらからも、筆者らは多くの示唆を得ました。以下は、実際の教育展開を行って得た、学生の反応と教員間のディスカッションでのテーマです。いずれも、先行研究の結果を踏まえ、実際の教育展開において確認できたものです。
| アンケートで高評価を得た学生の反応 |
| ・実践への関心の深まり:全体の平均 5.7点(6 件法) ・VR 体験の満足度:全体の平均 5.6点(6件法) |
| 教員が感じているVRの教育効果 |
| ・自分がその世界に入り込んでいる感覚(没入感) ・自分はこの世界に存在していると感じる感覚(Sense of Presence、実在感) ・臨床の状況や登場人物の行動意図を伝えられる(ストーリーテリング) ・いろいろな状況の体験が可能 ・学生によって視線や関心領域が異なることがわかる ・視覚や聴覚が互いに影響を及ぼし合い(クロスモーダル現象)、学生の感情に強く働きかける例がみられる ・感情や情動の誘起 ・学生自身が見たいところを見ることができる ・臨場感の中で当事者に近い感覚になれる ・コンテンツ内の登場人物の主観的な理解の促進(観念的追体験)ができる ・現状の客観視がより可能になる(マクロ視点とミクロ視点の行き来ができる) ・危険な状況でも安心して体験ができる(心理的安全性) ・シミュレーショントレーニングとして有効かもしれない |
| 教員が感じているVRの改善点と課題 |
| ・リアルの世界と非同期である ・VR体験そのものの個人差 ・VR体験前の経験(主に生活体験やコミュニケーション体験)の個人差 ・体験者のリテラシーが学習に影響を及ぼす ・非体験者への配慮(体験機会の不平等性) ・身体的負担(VR酔い) ・1回のVR体験では状況理解が困難 ・VR体験中はメモをとれない(集中力、疲労感) ・VR体験の記述が重要(デブリーフィングで言語化) ・学習目標との整合(目標・デザインの柔軟な解釈) ・既存コンテンツにどう組み込むか(コンテンツの体系化) ・楽しそうだったが、理解度ははっきりしない(評価) |
筆者らはVRの効果を実感し、期待をもって、看護教育で有効活用できるVR看護教育コンテンツ(以下、コンテンツ)の制作を医療用VRのプラットフォームを開発・運営する株式会社ジョリーグッドに提案し、同社との共同制作へつなげました。これは、医療研究開発革新基盤創成事業(国立研究開発法人日本医療研究開発機構・株式会社ジョリーグッド)への実証施設参画によるプロジェクトとして始動しています。
プロジェクトの展開にあたっては、外部企業との綿密な調整のほか、学内向けにも様々なタスクがあります。医学部長、コンテンツのための撮影を行う福岡大学病院病院長・看護部への趣旨説明や協力要請をはじめ、関連部局との調整、権利関係の確認調整、撮影にあたっては模擬患者の調整や撮影病棟の確保、当日の調整があります。また、今後も実症例を用いる場合の倫理審査など、多くのタスクがありますが、それらに対応をする必要があります。
ここからは、筆者らが制作したコンテンツ「療養環境(3シナリオ)」の制作過程と今後の展望について、プロジェクトに参画した教員より紹介します。
コンテンツの制作過程と今後の展望
映像撮影までの準備(コンテンツの決定を中心に)
春田京子(福岡大学医学部看護学科 助教)、藤 理絵(同助教)、松村友紀子(同助教)
当プロジェクトメンバーは様々な領域の教員で構成されており、コンテンツのコンセプトと事例の決定においては領域ごとに演習や実習上の課題を出し合い、それらの課題を解決するためにどのようなコンセプトや事例がよいか、また、VRの特長をどのように取り入れるかについてディスカッションを行いました。
その中で各領域に共通する課題が2つ明らかになりました。1つ目は、演習では臨床のようなリアリティのある場面づくりに限界があり、演習で実施したことが実習に活かされていないこと、2つ目は「気づき」という感性を磨くトレーニングが不足していることでした。そのため、2つの課題を解決できるようなコンテンツを制作する方針が決定しました。
筆者らには、コンテンツを制作したら終了ではなく、制作したコンテンツをベースとして各領域に展開していきたいという構想がありました。そのため、最初に制作するコンテンツで取り上げる場面は各領域に特化したものではなく、どの領域にも共通する場面がよいと考えました。
そこで、コンテンツのコンセプトは看護の基礎として学ぶ内容である「環境整備」としました。「環境整備」には患者の状況と今後を見通したアセスメント能力、患者の個別性への配慮、患者の快適性や安全性への認識などの感性が求められ、さらに360度観察できるというVR映像の特長を最大限に活かすことができるのではないかと考えました。「環境整備」の事例は人工膝関節置換術を受ける患者の「入院時」「術後2日目」「術後5日目」の回復過程に応じた療養環境を整えるというものに決定し、学習者の気づきにつながる場面づくりを行いました。
様々な領域の教員が集まり、準備を行う中で互いの専門性に気づくとともに、ディスカッションを重ね、共通認識のもと取り組むことの重要性を実感しました。
撮影当日について(プロジェクトメンバー教員の役割を中心に)
鮫島由紀子(福岡大学医学部看護学科 助教)、松村友紀子(同助教)、藤原悠香(同助教)
明確な意図をもつ教育用コンテンツの制作であるため、あらかじめVRの中で注目してほしい気づきのポイントを設定し、撮影当日を迎えました。当日は、外部の制作スタッフのほかに、模擬患者1名とコーディネータとしてプロジェクトメンバーの教員6名がかかわりました。
本コンテンツは看護師目線のVR教材であるため、看護師役の前に定点カメラを設置し撮影が行われました。この看護師の視点を軸として、学習者は前後左右に顔を向けることで360度の視野が体験でき、VRの特長である臨場感や没入感が得られることになります。
コンテンツには、同一患者の「入院時」「術後2日目」「術後5日目」の3つのシナリオがあります。それぞれに「環境整備前」と「環境整備後」の映像が必要でしたので、合計6場面を撮影しました。コンテンツの視聴時間にすれば数分程度ですが、撮影は、前日からの機材準備のほか、当日は機材搬入や準備も含め1日がかりとなりました。撮影という緊張状態の中で、集中力を維持しなければならなかった模擬患者さんには、負担が大きかったと感じています。
撮影時には、設定した気づきのポイントに忠実に、患者の私物や医療機器などを配置しました。雑然とした療養環境であっても、学習者に、視界に映ったそれは何か、どういう状況なのかを認識してもらえなければ、問題箇所への「気づき」につながりません。本コンテンツの場合は、視覚からの情報が重要ですので、とくに見え方にこだわりました。
リハーサル後にはプロジェクトメンバーもVR体験をしながら、学習者の目線で患者の私物や医療機器の配置、映像の明るさなどを確認しました。また、できるだけ臨床との差異がないことも、教育用コンテンツとしては欠かせません。そのため、撮影の合間にもプロジェクトメンバーでディスカッションを重ね、“リアル”を追求しました。
撮影自体は外部の制作スタッフのサポートで乗り切ることができましたが、何はともあれ、プロジェクトメンバーの意思統一をはじめとした事前準備の重要性を改めて実感した1日でした。
撮影後からコンテンツ完成まで(編集過程におけるプロジェクトメンバー教員の役割を中心に)
掛田 遥(福岡大学医学部看護学科 助手)、蘭 美彩(同助手)、松本祐佳里(同講師)
VR映像の撮影後、外部の制作スタッフによりプレビュー映像が作成されました。映像に対し、プロジェクトメンバーからのフィードバックを行い、業者により映像を修正してもらう工程を数回繰り返し、コンテンツの1つのシナリオが完成しました。以下、VR映像の編集過程において、本プロジェクトメンバーで吟味したポイントを振り返ります。
学習者が患者の状況を推測しながら、療養環境の問題点を思考するため、映像の序盤に患者・看護師間の短い対話を組み込み、一定の映像停止時間を設けました。その後、術後に使用する医療機器の管理状況、食後のベッド周囲の整理状況など療養環境としての問題箇所を表示し、最後に整えられた病室を映します。
この構成の要は、VR映像の一時停止時間です。ここで想定する学習者は、看護学生や新人看護師であり、様々な療養環境を見慣れていない初学者のレベルを想定しています。映像の停止時間が、より広い範囲に目を向けることや、今後の患者の行動を予測して潜在するリスクを捉えること、また、患者にとっての環境の安全性や快適性を検討することなど、自由に思考する時間になることを期待しています。この映像停止の尺が短いと期待する効果を与えられず、長すぎると間延びするため、撮影に携わった者だけでなく、プロジェクトメンバーの初見者の意見を取り入れて映像停止時間を決めました。
映像全体としては、注釈の適切性やエフェクトの視認性、場面と効果音の調和がとれているか、療養環境の問題箇所の表示方法などの検討をしました。映像内の様々なしかけが視聴者の認識や思考に影響する要素となるので、映像の確認も重要な工程だと感じながら確認作業を行いました。
このように、多角的な視点からVR映像をブラッシュアップしたつもりですが、実際にこのコンテンツを教材として活用し、学習者の反応を省察するプロセスが必要となります。そこから得られた知見を発信したり、新たなコンテンツ制作へ活かしたりすることが今後の課題になると考えています。
VR看護教育コンテンツ制作の今後の展望
蘭 美彩(福岡大学医学部看護学科 助手)、藤原悠香(同助教)、松村友紀子(同助教)、松本祐佳里(同講師)
今後は今回のコンテンツ制作の経験をもとに、コンテンツ数を増やしていきたいと考えています。そこで、具体的にどのようにコンテンツ制作に取り組んでいくか、今後の展望についてお話ししたいと思います。
プロジェクトメンバーが様々な領域の教員で構成されているという強みを活かして、まずは多様な視点を取り入れたコンテンツを制作したいと考えています。核家族化が進んで様々な発達課題の人々と接する機会が減っている中、学生が実際の看護場面で相手の気持ちを想像することが難しいという社会的背景があります。小児、高齢者、妊産婦、外国人など、看護の各分野で対象となる人々の視点を体験することで「気づき」という感性を磨くようなトレーニングにつながればと期待しています。
たとえば、小児では低い視線から見た風景、家族が視界にいない不安感、「“てんてき(点滴)”ってなんだろう?」といった難解な言葉が理解できない小児の思いを吹き込んでもおもしろいかもしれません。高齢者では、円背で足元を見ている世界、渡された資料の字がぼやけている、看護師の声が遠くで聞こえるなど、加齢に伴う身体的変化を高齢者の思いと共に体験できればと思います。このコンテンツでは、まずは対象者視点からの場面観察(①)、その後は①に対象者の思いを吹き込んだ状態での場面観察(②)、さらに対象者視点から、看護者にしてほしいことなどを呼びかけたが、その対応が対象者の想定と違ったケースの場面観察(③)、といった3部構成にする工夫もできると考えています。
ほかにも取り組みたいことは、病院以外の多様な場所でのコンテンツ制作です。看護師が活躍する場は多岐にわたります。病院だけではなく、保育所、高齢者施設、避難所など、とくに日常で経験できない場所に関しては、VRから得られる学びが多いと考えています。学生がVRを体験して終わりではなく、演習や実習につなげていけるようなコンテンツをつくっていくことも今後の課題です。
これまでは、学生を対象としたコンテンツ制作についてお話ししましたが、今後は臨床の継続教育における看護師を対象としたコンテンツ制作も考えています。福岡大学医学部看護学科棟は、福岡大学病院と同じ敷地内にあり、今回の撮影でも実際の病室をお借りしました。今後は、さらに病院と連携してコンテンツを制作していきたいと考えています。
看護師は日々の病棟業務を行いながら治療や検査の実際を見学する機会はほとんどありません。治療や検査の実際をVRで体験することができれば、病棟に戻ってくる患者に対し、根拠を持って看護を展開していくことができるのではないでしょうか。
たとえば、内視鏡室での上部消化管内視鏡検査など狭い空間で行われる検査や、造影室での嚥下評価撮影など被曝リスクがある検査は見学の機会が少ない現状があり、VR学習の効果が期待できます。さらに、救急の現場など実症例を用いたコンテンツを制作することが可能であれば、より高度な専門医療の学習にも活用することができると考えています。看護師向けに制作したコンテンツを、学生向けに活用することも効果的な学習へとつながるかもしれません。
|
NurSHAREでは、みなさまからの実践報告をお待ちしております。ご興味をお持ちの方は、こちらのフォームをご覧ください。 |

_1671416277801.png)