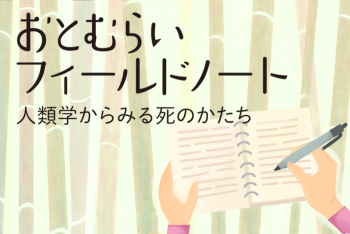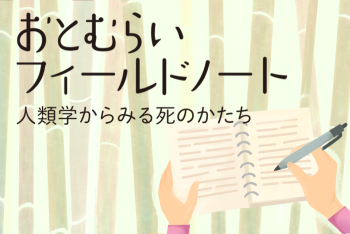臨床看護師を18年、ケアマネジャーを1年経験した後、地元へのUターンを決めた。過去の看護教育に関する学びから学校での教育に興味があったことと、そのころから拡大してきていた在宅療養支援に関する経験を活かして看護師を育てる分野にかかわりたいと考え、お誘いをいただいた現在の勤務校にお世話になることを決めた。退院支援業務やケアマネジャーとしての仕事を通して看護職以外の職種から学ぶことは多く、視野が広がったことで得られた経験を学生たちに伝えたいと思っていた。
「彼は看護師として働いていけるか」と問われ……
看護教員としての勤務がスタートして1~2年目の頃、ある男子学生の実習を担当した。実習態度の課題や学習不足が多く、実習での不合格が続き留年していた学生だった。周囲の先輩教員による評価は低かったし、私から見ても勉強に身が入らないようすであった。実習後の評価に迷っていたある日、当時の上司から「この学生が看護師として働いていけるか、経験者としてどう思うか」と問われた。
上司のこの問いに、冷静になって考えてみた。彼は社会人経験者で、教員や実習指導者に対して「納得いかないことはできない、やりたくない」という姿勢を強く示す、癖のある学生だった。その反面、患者とのかかわりに関して言えば、とても相手を思いやった態度が取れる学生でもあった。結果的に、私は「臨床の場に出て成長できる力をもっている学生だと思います」と答えた。直感的に「彼は大丈夫だろう」と感じたことを、そのまま上司に伝えたのだ。
なぜ臨床に出ることができると判断したか、何がその時の自分の直感の根拠だったのか、折に触れ考えることがある。今にして思えば、決め手は学生の誤魔化しのない正直さ、実直さにあったのだろう。患者の状況について率直にやりとりしケアを考えることができる実習中のようすから、臨床での基本的な思考が踏めることは感じていた。あとは、知識・技術の習得方法、指導側への態度・言動面を段階的に改善できれば何とかなると考えたのである。
それからは、課題への具体的指導に力を注いだ。とくに態度面の改善には苦戦したが、彼のうまくできている面、評価している面を認めるようなかかわり方をすると、彼はすごく素直にやり取りをしてくれるようになってくれた。一緒に行動を振り返り、課題を共有し、何を解決すべきか具体化することで、少しずつ成果を上げ、日々の過ごし方や学びへの姿勢も目に見えて変わっていった。以前は他人と距離を置きがちだったが、留年して同じクラスになった1学年下のクラスメイトともたわいのない雑談ができるようになっていた。次第に教員からの評価も上がり、「通常通りの支援の範囲内で、4年間で卒業できそうだ」という共通認識に変わっていった。彼はその通りに卒業を迎え、今でも臨床で看護師として活躍している。
あれこれと手をかけすぎず、それでいて課題にはともに向き合う
彼のように、指導者や教員との関係性にやりにくさを抱えている学生は多い。指導側の求めているレベルが高すぎたり多すぎたりすることで、それ以前に多くの自己課題を抱えたままの学生は何から取り組めば良いのかわからなくなり、追い込まれていくようだ。解決策が見えなくなったまま休み始めたり、感情のコントロールができなくなるなど、実習に支障をきたすこともよくある。
看護教員になりたての頃の私は、どうしても患者を見るように学生を捉えてしまったり、「この学生になんとか学んでもらわなければ」と思うあまり、あれをしてみたら、これはどうか、違う角度から見てみたら、こんな課題に取り組んでみたらどうか、とたくさんのものを学生に投げかけてしまっていたように思う。学生にとって、その投げかけは一つ一つが自分の欠点や足りていないことを投げかけられるような、辛い経験ともなりかねない。受け止めた学生が「先生に言われた10のうち、今の自分は3までやってみよう」というように上手に選択できればよいが、そうはいかずにどんどん追い込まれてしまい、キャパオーバーになってしまうこともある。
多くの先生方が言っていることであるが、学生と向き合う時、私はまずよく話を聞くようにしている。すぐに手を出さず、「学生が今何を理解していて、何が分かっていないか」の確認から出発するために、学生の姿をよく見つめて話を聞く。ともに課題と向き合い、絡みあってしまっている事実や感情を整理しながら「正確に現実を見つめること」「誰にどう働きかければ前進できるか、とるべき具体的コミュニケーションは何かを考えること」を意識して傾聴する。そして、それぞれの自主性や学んで感じたことをふまえて、学生自身の力で解決に向けた答えを導くことができるよう手助けをする。臨床で培った自分の看護をそのまま伝えるのではなく、学生と一緒に考える。これならできそうだ、という学生にとっての目の前のステップが見えたら、そこからは持てる力を信じて待っていれば、学生は前に進める状況になることが多いと感じている。
もちろん、葛藤の末に看護師への道から進路を変更する学生もゼロではない。残念なことだがそれも一つの決断であり、彼らの将来の糧となる大切な経験だと考えている。しかし、伸び悩む学生でも、実習経験を重ねて見えてくることが増え、何をどのように見ればよいのか、何を感じとり、どのように伝えればよいのか、感覚的につかんだことを機に、知識や技術については自ら磨く行動をし、いくらでも伸びるようになると感じている。
経験を積み重ねる中で、どんな学生にも成長への転換点があるのだということを知った。そして、正確に現実を見つめる力と実直にコミュニケーションをとる力がある学生は、自己の課題を見極め、必ず成長していけるのだということも分かった。逆に言えば、学生が自分の力で歩ける人・看護師になれるよう導くために、これらの基本的な力を伸ばしていくことこそが、看護の教育者が力を注ぐべき点なのではないかと感じている。
.png)
還暦の歳まで教育にかかわってこられたことは、本当にありがたいことだと感謝している。私自身、まだまだ知識も技量も足りていないと日々感じつつ、若い先生方が看護教育に喜びを見出せるよう、もうしばらく力を注がせていただきたい。
嬉しいことに当校では今年(2024年)の4月になって、教員として一緒に働く仲間が4名も増えた。看護教員の経験がなくても、実習指導者として学生に教えたり、プリセプターとして新人看護師に教えたりする経験の中で、「次の世代に自分の経験を伝えたい、学びにかかわりたい」と強く感じ、教員としてのキャリアを歩む決断をしている。
学生や新人看護師が、経験を重ねて見えることが増えるように、看護教員もまた経験を重ねてようやく見えてくるものがある。学生の成長と共に自分の成長を楽しむのもまた、この分野の面白さなのではないだろうか。