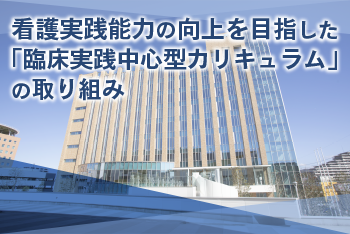事務職から看護学校へ、力ある看護師を目指して
前職の事務職で仕事も覚え、周囲からの信頼も徐々に得られた頃に、退職を申し出るとともに、憧れていた看護師を目指して看護学校への入学意思を伝えました。仕事を継続してほしいとの上司の願いを背中に感じながら、確かな技術と思いやりを持った看護師になりたいと意気揚々と看護学校に入学しました。専門領域の学習に入った頃には、同級生との年齢差も気にならず、仲間と支えあいながらつらい日々も乗り切りました。卒業後、かねて家族で決めていた国家試験合格の合図「サクラサク」を、看護師になることを反対していた父親に伝えたところ、心から喜んでくれました。
生死を深く考えたICU
卒業後は都立病院に入職し、脳神経外科病棟に配属され、日常生活援助に追われる日々でした。援助では、患者の安全の確保とケアの基本を確実に実施しなければならないことから、看護基礎教育がいかに重要であったか身をもって体験しました。この頃から「教える」あるいは「教え方」に興味を持つようになりました。
3年目には、師長から呼ばれ、「推薦をするので病棟からICUに異動してほしい」と言われました。私は助産師になるための進学を考えていたのですが、「第三次救急医療を学ぶ機会は貴重で、ICUを経験すれば何でもできる看護師になれるよ」と言われ、救急医療の場で働くことを決めました。今振り返ると、退職者を出さず人事異動を推進するための師長の策略だったのではと思いますが、異動を促してくれたことに感謝しています。
ICUでは細やかな観察や蘇生のための知識・技術が必要であり、脳神経外科での経験も役立ちました。一方、モニタリングのための動脈ラインの準備、多発外傷に伴う骨折部の固定、挿管の介助から人工呼吸器の管理など初めて行うこともあり、日々学習の連続でした。即戦力となれない自分に力不足を感じながらも、ICUでは速やかな判断と行動ができる人に囲まれ、彼らを目標に自己研鑽していきました。
しかし、生命の危機的状況にある患者は、ほどなくして命を落とすことも多く、残念な思いも経験しました。朝、元気に家を出た人が変わり果てた姿を見たときの、その家族の衝撃や悲しみに、言葉も見つかりません。脳死と診断されたお子さんに対して、現実を受け入れられず面会を拒否していたお母さんに、スタッフで協力し対話を重ね、お母さんの腕に抱かれて最期の時間を過ごせた子もいました。看護師としてどのような対応が望ましいのか、仲間とともに研究にも取り組みました。家族から得られたそのときの思いや、行動の観察から分析を行いました。また、研究メンバーとともにアルフォンス・デーケン氏の「死の準備教育」の講演を聴講し、キュープラー・ロスの「死ぬ瞬間」なども読み、「脳死と宣告された患者家族の一考察」としてまとめ、院内で発表した後に看護部から推薦され、ある医学学会のシンポジウムで発表する機会を得ることができました。
「教える」と「教え方」への追求
ICU勤務に慣れてきた頃には、異動してきたスタッフなどに「教える」役割を担うようになりました。知識・技術だけではなく、生命の危機的状況の中にある患者と家族に接するうえでも、看護師として重要な役割があると感じました。
しかし、その重要なことについての「教え方」には常に課題を感じていました。「教え方」に幅を持ち、個々にあったアプローチについて学んでみたいと考えるようになり、都立病院では小児科病棟を最後に、11年間の臨床現場を離れ、看護教員養成講習を受講しました。そして、10年間は看護学校で「教え方」を学び、再び臨床にもどり新人教育などに携わりたいと考え、看護学校への異動希望を出しました。母校である都立松沢看護専門学校に専任教員として勤務し、5校の都立看護専門学校の転勤を経て、2020年3月に退職しました。2020年4月から、11学科がある医療の総合専門学校へ入職しました。
キャリアを重ねる中で、かつてのように一生懸命な自分の姿を見せる時代から、ドナルド・ショーン『専門家の知恵』にある、「行為の中の省察1)」と実践による「教え方」に共感するようになりました。多様な学生へ、瞬時に適切な指導が求められる場面が多い中「教え方」を追究し続け、今も看護専門学校で勤務しています。
卒業生からのフィードバック
長く勤務していた東京都の看護専門学校で受け持った卒業生が多くいます。彼らが看護部長や師長となり、業務の中核となって活躍している姿をみることは私にとって大きな喜びです。また、どの卒業生をみても存在を尊く感じます。教育を続けられた要因は、関わった卒業生の成長がモチベーションとなっていたからだと感じます。
嬉しいこともありました。卒業記念パーティで、ある卒業生が「看護師になれると信じてくれた先生の言葉があったから、学校を辞めずに卒業ができました。最後にお礼を言いたかった」と駆け寄ってくれました。できないことがあっても、他者に信じてもらうことで心が強くなり、学生が前に進む勇気につながったのだと感じました。
現在も「教え方」を模索中ですが、「あなたの成長は、私が信じている」「私が責任を持つ」という姿勢が鍵になるのではないかと考えています。簡単なようで難しく、私自身の成長や学生の良さに気づく感性が必要です。
しばらく救急医療から離れていましたが、今は救急医療を再度学ぶためICLSのインストラクターを取得し、他施設でも指導をしています。今までの経験を次世代に伝えながら、目の前の一人を守るために必要な多職種連携のスキルや知識・技術とともに人を支えられる感性を持った、臨床で活躍できる学生を育てられるよう、これからもともに学び、成長していきたいと思います。
1)ドナルド・ショーン著,佐藤学,秋田喜代美訳:専門家の知恵: 反省的実践家は行為しながら考える,ゆみる出版,2001