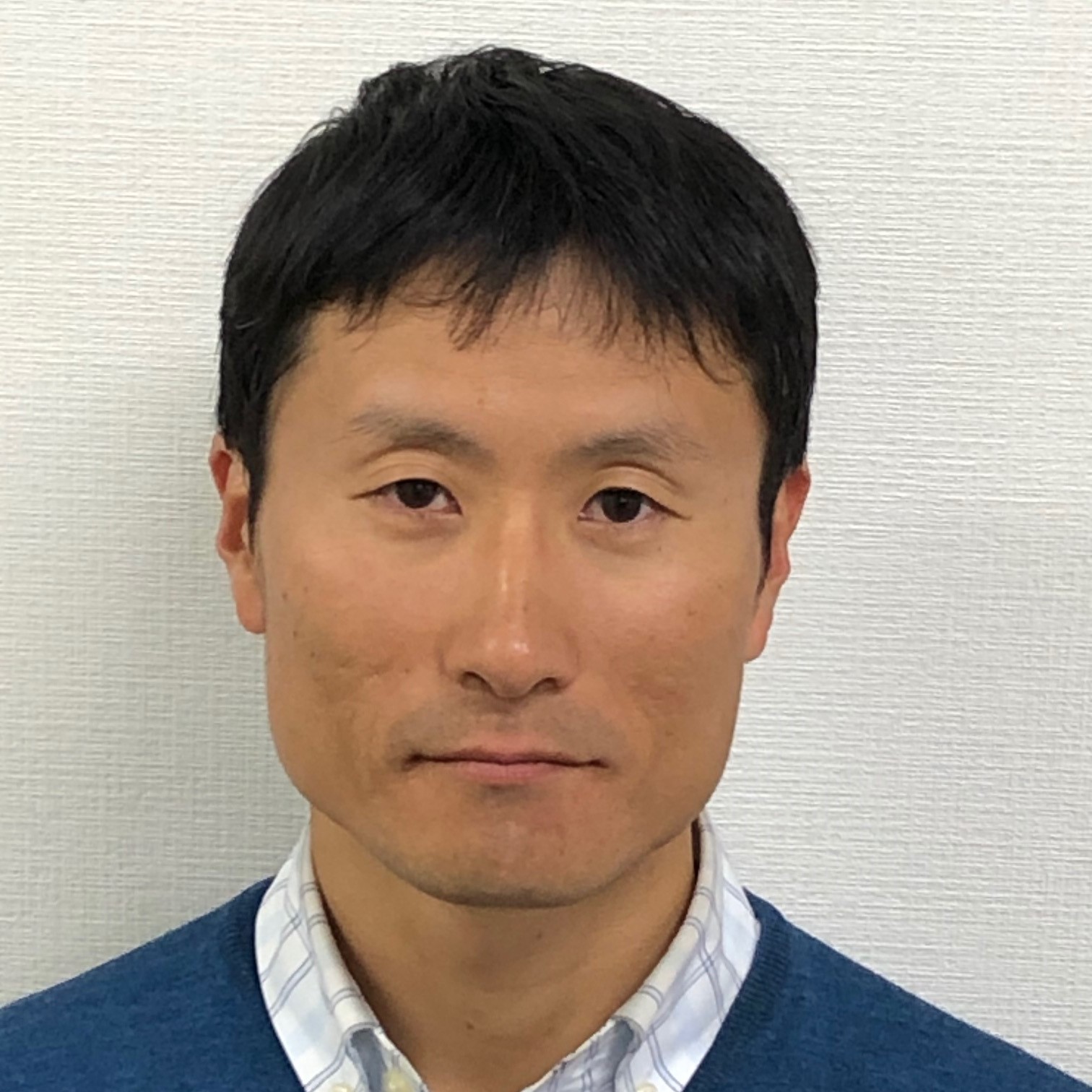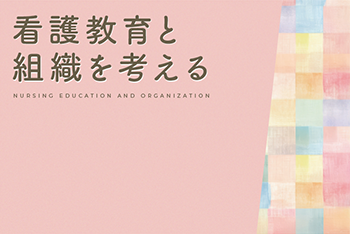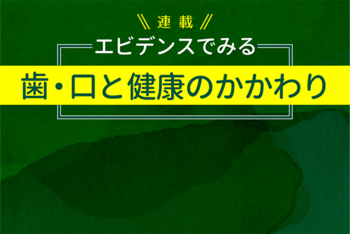家族の入院をきっかけに、医療や看護の道を志す
私は、小学6年生のときに父を食道がんで亡くした。父の入院時、術後でドレーンを挿入したまま外泊したことがあり、看護師からドレーンについて説明を受けたことを今でもよく覚えている。化学が好きだったため、がんの治療薬を作りたいと思い、大学では化学科に進学した。化学に加え生物系科目も学び興味を持ったことから、卒業研究では微生物を利用した有機化合物の合成を行った。しかし、もっと生物系の研究がしたいと思い、修士課程では別の大学院に行き、免疫関連の遺伝子の機能解析の研究を行っていた。
そんなとき、今度は祖父が胃がんで入院した。見舞いに行った際、祖父が尿意を訴え、看護師が尿瓶で介助している場面に遭遇した。このとき、自分は何も手を貸すことができず、自分が行っている研究は将来誰かの役に立つかも知れないが、今目の前にいる祖父の役には立てないという虚しさを感じた。それに対して、看護師は今病気を抱えている人の役に立つ、なんて素晴らしい職業なのだろうと感じた。それ以来、看護に対して興味が湧き、看護とはどういうものなのか本を読んだりして調べた。アルバイトでも人と接することが好きで得意でもあったことから、「病いとともに生きる人に直接かかわりながら貢献できる仕事をしたい」と強く思うようになり、看護師になろうと決めた。
基礎教育で衛生について学ぶ重要性を実感
大学入学後、授業でナイチンゲールの『看護覚え書』を読み、患者の自然治癒力を高めるように環境を整えるという考え方にとても共感した。また、統計学を用いて根拠となるデータを分析し、病院の衛生状態を改善することで死亡率を下げたという業績に非常に感銘を受けた。
看護師になり、集中治療室(ICU)に配属されてからは、微生物や免疫などの研究をしていたことから感染に関心があったため、感染リンクナースとなった。ICUで感染対策の活動をしていく中で、対策をしていても感染が起きてしまうことに対して、それらの対策が本当に効果的なのか、どこに問題があるのかなどを調べたいと思うようになり、病院勤務を続けながら大学院へ進んだ。大学院在学中にICUから感染制御の部署に異動し、院内全体の感染管理に携わるようになった。
その活動のひとつとして、2011年にICUでの手指衛生遵守率調査を行った。2009年に世界保健機構(WHO)が手指衛生5つのタイミングを提唱していたが、それがまだあまり浸透していない時期であった。そこで、スタッフに対して調査結果のフィードバックとともに5つのタイミングについての教育を行ったところ遵守率が上昇した。カテーテル関連尿路感染サーベイランスでは、ラウンド時に個々の患者の尿道留置カテーテルの適応や必要性についてスタッフと共に考えることにより、スタッフが適正使用についてアセスメントできるようになった。また、手指衛生の活動を続けていく中で、実習に来ていた学生が手指衛生を正しくできていないという状況がわかり、学部で講義を行うようになった。このような経験を通じて、看護師になってからではなく、学生のうちにきちんと教育を行うことが重要であると実感した。
看護教員として、学生に自ら考え修得してもらうために
そんな頃、大学時代の先生と大学院時代の先生から、それぞれ別の新設の学部で教員にならないかとお誘いを受けた。教員になることについて、将来の視野には入れていたが、臨床から離れるかどうか悩んだ。しかし、教員になっても、かかわるのが患者ではなく学生に変わるだけで、目の前の人の役に立ちつつ患者に貢献できると考えたことや、お誘いが重なったことからこれは運命なのではと感じたこともあり、大学教員になろうと決意した。
私の専門分野である感染看護学は、大学院では領域として独立しているが、学部では大学によってさまざまな領域に含まれるものであり、私が就任した大学では基礎看護学に属することとなった。基礎看護学では、基礎看護技術などの演習科目を担当する。新設の学部で、初年度は1年生しかいなかったため、基礎だけでなく専門領域の先生も演習にかかわることとなった。
多様な経歴の教員が集まり、指導や評価の方法について話し合う中で、さまざまな意見が出た。その中に、学生が手技をテキストなどの手順通りにできているかチェックすべきという案があった。私が学生のときは、手順通りにきちんとできているかチェックされていたことを思い出したので、その案にあまり疑問を感じなかった。しかし、基礎看護学の教授は、学生が手順通りにできているかをチェックするのではなく、どのようにすると安全・安楽なケアができるか自ら考え、試行錯誤しながら修得することを重視していた。そのような指導方針を聞き、手順を覚えてその通りにできるようになっても、なぜその方法や手順でケアを行うのかという根拠を考えなければ、患者や環境に合わせたケアはできないということに気づくことができた。
それ以来、学生のやっていることが少し間違っていても、指摘してすぐにやり方を教えるのではなく、もっと良い方法はないか問いかけたり、考えるヒントを出したりして、なぜそうするのか自ら根拠を考えてケアを行えるよう導いていくことが教育として重要ではないかと考え、演習や実習において実践している。実際、学生が自分でよい方法を導き出せたときには、とても楽しそうにしており、見ていてこちらも嬉しくなる。また、覚えるのではなく考えて実践しているので、知識や手技が学生に定着することにもつながっている。
.png)
私は現在、大学生だけでなく専門看護師や認定看護師の教育も行っている。臨床の看護師が対象なので、相手の経験を踏まえて本人がよりよい案を導けるように問いかけたり、一緒に考えたりしながら指導している。感染制御の活動においては、スタッフが根拠を理解して自ら実践できるように指導したり、サーベイランスで感染率などのデータを根拠にして改善策を実施したりする。これらはナイチンゲールの実践と通じ、私の目指すところである。これからも自ら考え根拠をもとに実践し、またそのような看護師を育てることで、患者に貢献していきたい。