この連載も35回目となりまして、3年間ほぼ毎月のように4,000字近くをつらつら書いてきたカピバラ。振り返るといろんなことがありました。アディショナルタイムもそろそろ終わり、試合終了の笛が吹かれる時間となりました。
読者の皆さまにおかれましては、3年間にわたってこのエッセイにお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。学会などで、「読んでます」「楽しみにしています」、時には「刺さりました―」と声をかけてくださることで書き続けることができたと思います。
今回でアディショナルタイムは終了とさせていただき、しばしの休息をいただきます。そんなラストのテーマはまさしく、“終わり”についてです。ぜひお付き合いください。
サッカーの試合が終わる時
サッカーの試合が終わる時、ピーーーっと長い笛が鳴ります。審判によってはピッピッピーと吹くこともあります。どちらにせよ、笛が鳴ったら試合終了です。
長いリーグ戦を戦い抜いての最終試合では、サポーターも選手もこの笛でその年のシーズンの終わりを実感し、達成感やら後悔やら、いろんな気持ちがあふれ出る瞬間です。そしてそのあとチームの解散式があり、次のシーズンに向かって、ストーブリーグが始まります。もともとストーブリーグとは野球の言葉(オフシーズン中の寒い時期に炉辺で野球談議をすることに由来するみたい*)ですけど、日本では普通にサッカーでも使われています。移籍市場が開き、チームの再構築が始まるのです。契約更改する選手、海外移籍する選手、契約満了でクラブを去る選手など悲喜こもごも。サポーターも自分の推し選手の動向が気になってしかたありません。補強のための新戦力の獲得も行われます。GM(ゼネラルマネジャー)のチームマネジメントの腕の見せどころ。大物選手や即戦力としてベテランを獲得したり、将来を見据えて若手選手を獲得したり、レンタル選手をそのまま買い取ったり、若手の修行のためにレンタルに出したり、とオフシーズンも話題に事欠きません。
そして次のシーズンは、新体制発表会から始動です。
どんな試合にも終わりはある。そしてどんなチームにも解散の時がある。なんかこれって、大学の年度末や病棟の年度末と同じですよね。出ていく選手もいれば、入ってくる選手もいる。そしてまたチームビルディングが始まり、混乱の時を超えてチームとして機能するようになり、そしてまた解散の時が来る。解散したら、また新しいチームがスタートする。解散しなければ新しく始められないわけですよね。
* カピバラ小ネタ:日本のサッカーシーズンは野球と同じ春から秋ですが、欧州ではサッカーはウィンタースポーツです。ですので、欧州ではストーブの必要な時期はサッカーリーグ真っただ中ということになり、ストーブリーグという概念はあり得ないんですね。で、来年から日本でもシーズンが変わり、8月に開幕、5月終了となる予定です。日本でもストーブリーグとは言えなくなりますね。
一期一会
この言葉は、千利休の茶道の精神を受け継いだ江戸時代の茶人・ 井伊直弼の著書『茶湯一会集』が由来とされています。「一期」とは仏教用語で「人の一生」を意味し、「一会」とは「一度の出会い」を指すそうです。つまり、「一期一会」は「一生に一度の出会い」という意味になります。井伊直弼は、茶会において「この一回の茶会は一生に一度しかないものと心得よ」という教えを説きました。どんな仕事にも終わりの時が来るのですが、自分の精一杯を捧げて没頭している時は、この終わりを実感することはできないものですよね。
カピバラは2015年1月から大学院附属の専門職連携教育研究センター(IPERC)のセンター長を務めていましたが、任期満了で、この度、2025年の3月31日にセンター長の職を辞し、4月1日から新しいセンター長が就任しました。
思えば2015年にIPERCを立ち上げた時から、このセンターの知名度を上げるためにいろいろな仕事を引き受け、周知活動にいそしんだものです。その時にwebサイトに書いたセンター長挨拶が以下の文章です。
2015年(平成27年)1月1日、当センターは開設されました。日本では、ほかに類を見ない新しいスタイルの教育・研究・実践拠点として、日本の保健医療福祉及び高等教育の発展に貢献していきたいと考えています。わたしたちは、これから、「亥鼻IPE」という千葉大学で育てていただいた教育・学習プログラムから得た知見と実践知を基盤として活動していきます。そして学内、千葉県内、日本、アジアとその活動を広く展開します。この活動は、亥鼻キャンパスが中心となりつつも、周りを巻き込み、時代の変化に応じ続けることでしょう。亥鼻キャンパスそして千葉大学に、IPEとIPWが自明のこととして根付いていくことにより、お互いに学び合い、時代の変化に適応しつつ、最善の治療ケアを追求していくことを厭わないよき医療人の育成がより一層充実していくことと信じています。
10年の間には様々な方々と出会い、そしていろいろなことをスタッフのみんなと乗り越えてきました。途中ちょっと疲れたりしたことも正直ありました。しかし気づけば、このセンター開設時のあいさつ文に書いた多くをやり遂げてきた感じもしますし、まだまだいろんなことが残っているような気もします。少なくともIPEは新しい教育、ではなく、必修でやるべき教育になりつつあります。
振り返ることを通常はしないカピバラ、反省も長くて3分間。常に前に進む、前に進めなくとも、後ずさりしても前向きに、をモットーにしてきましたけど、振り返ると、どの出会いも出来事も、今になって思えば一期一会のものでした。その一つひとつが今のIPERCを形づくってきました。
仕事上のアドバンスケアプランニング
読者の皆さまならご存じのアドバンスケアプランニング(ACP)。この本質は単に「延命治療をするかしないか」といった医療選択の話ではありません。むしろ大事なのは、その人がどんな人生を大切にしてきたか、これからどう生きたいか、そのためにどんな医療やケアを望むのか、という価値観の共有であり、その人が生き抜くことを支える対話のプロセスということですよね。だから、一度決めて終わるものではなく、状況の変化に応じて繰り返し継続的に「一緒に考えること」といえます。
ACPを実践することは、単に「その人」の意向を聴くだけでなく、支援者側の「その人はどんな人生を歩んできたのか」「何を大事にしたいのか」をていねいに汲み取ろうとする姿勢への転換でもありますし、当事者にとってはあらかじめ「自分にとって大切なことは何か」を言葉にして伝え続けることによる不確実性への準備ということでもありますね。
今、カピバラは、IPERCセンター長としてのジャーニーを締めくくり、これからのIPERCの発展のために、これまで何を大切にしてきたのか、これからの課題は何かを言葉にして伝える作業と向き合っています。そしてこれは来たるべき、「大学教授」の役割を取り外す、つまり定年というさらなる役割の喪失に備える大切なプロセスでもあるんです。いつかは「終わる」、この最後への準備をすることで、一期一会の今の仕事の有限性を実感し、終わることによる次のターンの始まりをイメージする。“仕事ACP”の実践は、未来志向の対話でもあるのだと、舞い散る桜の花びらを浴びつつ実感しています。こんなにも感謝と希望に満ちた春はこれまでになかったでござるよ。まじに。
さあ、次の10年を生きようではないか。
るろうにカピバラ
と、かっこいいことを言ってはみたもの、センター長の肩書きを脱いだカピバラ。いや、ちょっと寒いっていうか心もとない感じなんですわ。いつの間にかセンター長という肩書きがガンダムスーツみたいになってたのね。今は、ガンダムスーツを脱ぎ、カピバラ本来の生態に戻りつつあるのを感じています。
(本物の)カピバラは大変に社会性のある動物でしっかりと群れをつくって暮らしますけど、ほかの動物とも仲良くなることが得意です。攻撃性が低いのは武器を持たないからで、友好的に生きることで不必要な闘争を避けているのではないかと思われます。バタつかず落ち着いており、温泉に入ってのんびりしている。水が好きなので水辺に寄って行くのですが、縄張りをパトロールするという意識はあんまりないみたい(カピバラ私見)。
さて、カピバラが時々つぶやく「○○でござる」という語尾。これは、これまたご存じの方はご存じの、『るろうに剣心』へのオマージュでござった。もともと流浪人(作品では「るろうに」と称している)とは流れさまよう定まった居場所がないものという意味があります。『るろうに剣心』では、殺し屋として多くの人を殺めてきた主人公の剣心が、刃が内側についている、つまり切れないようにつくられた「逆刃刀(さかばとう)」を携えて、流浪しつつ明治という新しい時代を仲間と共につくっていく過程が描かれています。もう人を殺さないと誓ったなら、刀を捨てて出家すればいいのに、「逆刃刀」を腰に差している。つまり剣心はかつての重たい過去とは決別しないんです。この過去を携えたままで、これからの自分を生きようとする。「逆刃刀」とは自分の罪の痛みなんですね。それを手放さないんです(ここもカピバラ私見)。
力ではなく、落ち着きや間合いで周囲に何かしらの良い影響を与える。居心地の良い場所にとどまるけど、いずれ去って行く。勝ち負けにこだわらず、武器も持たない。しかし「逆刃刀」は決して手放さない。
カピバラもこんなふうに「るろうにカピバラ」になって、過去を手放すことなくしかし振りかざさない大人(マダムカピバラ)として、よき間合いでこれからの新しい時代を楽しみたいと考えているでござるよ。
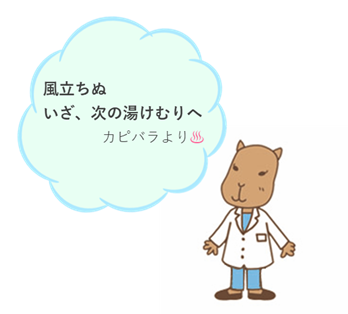





」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)
