皆さん、年末の慌ただしさが落ち着きつつある頃でしょうか。起承転結という言葉がありますが、このたびの世界一周の出張旅を振り返ると、アラバマが起、レスターとドーハが承だとしたら、南アフリカとベトナムが転、そして結はメルボルン。そして一周したら元の場所に戻ってくる。そんな旅の本当の終わりは、朝起きて「ここはどこだっけ? いま何時だっけ?」という見当識の障害がなくなった時でした。
というわけで、ドーハの悲劇で終わった前編。予告どおり、今回は世界一周出張旅の後編でございます。
ブルームフォンテインのホウレンソウ
さて、カピバラ一行、全員がアフリカ大陸上陸は初めてでした。そのため、なんだかステレオタイプなアフリカ観で頭の中がいっぱいでござった。白状すると「アパルトヘイトの国、南アフリカ」「ライオンがその辺を走り回っている南アフリカ」というような考えがあったでござる。
ヨハネスブルグのタンボ国際空港から小さい飛行機に乗り換えて、ブルームフォンテインに到着です。2010年のサッカーワールドカップ南アフリカ大会で、日本代表が初戦をカメルーンと戦い1対0で勝利を収めた場所です。ここにフリーステート大学という総合大学がありまして、アフリカのIPEが熱く盛り上がる起点となったところです。この大学からまっすぐな道をひたすら100kmほど行くと、小さな村があります(お察しのとおり、道端にライオンはいませんでした。でもダチョウが走ってた!)。ここがこの大学のIPEサイトであるコミュニティクリニックがあるところです。この大学のIPEは、コミュニティクリニックでの4年生の診療参加型IPE1週間一本勝負。亥鼻IPEが1年時からクラスルームIPEで積み上げていく知識と理論と態度を、実地で1週間で特訓するのです。地域住民への糖尿病教室を柱とした健康支援が主なコンテンツです。近隣の病院は資金不足と人員不足で病棟の8割を閉鎖しており、このコミュニティクリニックが最初で(ほとんど)最後の健康支援の砦となっています。学生は健康関連専門職の即戦力として期待されています。
ブルームフォンテインでは、糖分と脂肪分の多い食事、飲酒の習慣、野菜摂取不足などにより糖尿病の患者さんへのケア、とくに合併症の管理がなかなか難しいそうです。そんな話をしながら村のスーパーに行ってみると、確かに新鮮な野菜は少ししかなく、糖分の入っていないミネラルウォーターを探すのが大変です。そんな中、スーパーで買い物をしている住民の皆さんが、IPEのファシリテーターを見つけると、今日はどうしたの? と話しかけ、いろんな出来事を伝えてくれるんです。それだけ、学生とファシリテーターが住民の皆さんといつも共に活動しているんだなということがよくわかる光景でした。
このコミュニティクリニックの前庭には、ホウレンソウがたくさん植えられていました。職員の皆さんがここで野菜を育てて、住民の皆さんに配るのだそうです。その方法に地元の実践知と言いますか、expertise(卓越性)を感じました。職員にはアフリカ系の人もヨーロッパ系の人もいます。その人たちがチームとしてIPEを運営していました。
コミュニティで過ごすうちに、南アフリカに勝手に抱いていたステレオタイプな見方がガラガラと崩れていきました。ここは「アパルトヘイトの国」ではなく、「アパルトヘイトを30年前に廃止した国」であり、そこから30年間、さまざまな差別を乗り越えようとして格闘している国なのです。だからこそ、IPEの特質である、「ステレオタイプを意識化し、互いにリスペクトをもち、互いから学び合い、相互の知識や技術を活用し信頼し合う」ということが、住民の皆さんに受け入れられ、学生がそこで参加型IPEを行うことがコミュニティへの貢献となっているのだと思いました。
ハノイのバイク
ブルームフォンテインから延々乗り継ぎを繰り返し、夜中にベトナム・ハノイに到着しました。翌日はミーティングに病院視察にと、ハードな日程となっていました。翌朝早くレストランに行くと、そこには、アジアンなメニューが並び、もちろんフォーもある。ドーハの悲劇のリベンジをしようと朝からフォーを頼み、期待どおりのやさしい味に、舌も身も心も癒されました。どうでもいい話ですけど、カピバラ考えるに、アジアは水が豊富なので麺類が普及してきたんではないかと思いまする。
さて、ハノイ医科大学は町の中心部にあります。病院と大学は道を挟んで対面にあります。大学でのミーティングを終え、病院視察のため移動ということになったのですが、この道、バイクが大量に走っており、かつ信号とか横断歩道などはなく、横断できる気がしません。ハノイ医科大学の大学院生さんが、「カピバラ、私の後についてきてください。そして、立ち止まらない、急に走らない、後戻りしない」と、手を引いてくれました。すると、阿吽の呼吸で私たちをよけて走り抜けるバイクたち。大学院生さんが言うには、「横断する際に、走って来るバイクを意識しすぎて、バイクが予測できないような行動をとってはいけません」とのことです。そして進む方向に片手をまっすぐ突き出し、一定の速度でゆるゆると進む、と、ちゃんと道の向こう側にたどり着いたのでした。信号などの明示的な交通ルールではないが住民に共有されている暗黙のルールと、バイクに乗る人と横断する人の根底にある何かしらの信頼関係により、なんかうまいことなんとかなっているハノイの交通事情でした。
ハノイ医科大学病院はかなり欧米化された病院で、看護師の仕事は診療の補助業務であり、直接ケアはまずもってしません。ベトナムは社会主義国ですから基本的に女性も働いています。一方、伝統的なアジアの家族観があり、家族のケアは女性の仕事です。よって介護の社会化はほとんど進んでいません。ナイチンゲール病棟のような多床室で、病室に男女の区別はありませんが、男性患者が圧倒的に多いみたいでした。そして、身体拘束は誰一人されていない。そもそも患者の行動の自由を制限する、という発想がないようでした。
看護部長兼看護学部教授のアン先生と話したところ、話の中にKAIGOというタームが頻繁に出てきます。ベトナムでは現在のところ国家試験というものはなく、大学で看護学を学び、1年間の病棟実習を経た後に看護師となるわけですが、まあまあ多くの卒業生が日本で介護職として就職していくことを憂いていらっしゃるのです。またベトナムの都市部の病院では欧米化(日本化?)が進み、専門医が大病院で高度な医療をするようになって、患者さんと家族に大病院志向が強くなり、大病院の患者さんが増え、結果として医療従事者の人員不足が生じている。看護師の海外流出が人員不足に拍車をかけるということになっているようです。
アジアのほかの国同様、ベトナムも地方と都市部の医療の格差が大きいようです。そして大病院では看護師以外のソーシャルワーカーや医事担当の事務職なども不足し、患者のマネジメントだけでなく、いろんな「用事」が看護師に「丸投げ」される状況にあり、アン先生は、病院経営層に対して「毎日シャウトしている」とのことでした。
「地域でのプライマリケアが力をつけていかないと、大病院の負担は重くなりますよね」と、カピバラ言いながら、なんか強い既視感。この状況、このやり取り、ものすごく身に覚えがあります。日本もそうだった。医療の高度化と医師の専門分化が進み、高度な治療を求めていらっしゃる昭和の時代の患者さんたち。今振り返ればなかなかにカオスな状況を、介護保険制度の創設、地域包括ケアの推進、専門職の教育の高度化と地道に進めてきて、病院の機能分化が国民の皆さんにご理解いただけるようになりつつある昨今。しかしついこの間までは、日本もハノイと同じような状況だったように思います。
医療・介護制度っていうのは、その国の文化でもありますよね。ベトナム戦争を乗り越え、南北の分断も乗り越え、現在ドイモイ政策(経済再建政策。ドイモイは「刷新」という意味です)を邁進中で、発展目覚ましい、そんなベトナムの地元住民の皆さんの健康にかかわる実践と言いますか、暮らし方を尊重すること、いまいまの限られた医療資源の中でのいい感じのところで医療の水準を住民の皆さんが決め、自分たちなりに更新していくことってホント大切だなと思いました。これはすぐに実現できることではなくて、日本だってまだ発展途上です。
「立ち止まらない、急に走らない、後戻りしない。」—心に刻みました。
メルボルンの留学生ビジネス
そしてハノイから香港を経由し、ついに今回の出張の最終目的地、オーストラリア・メルボルンに到着しました。メルボルンに来たら、日本食ですよね。50mおきくらいにある「IZAKAYA」。ドーハの悲劇のトラウマもありながら、リベンジをすべくホテル近くの居酒屋に入ると、「いらっしゃいませー、日本の方ですか?」と、日本語での対応になんだかじーんとします。日本語で注文できる幸せをかみしめたのでした。
モナシュ大学でのミーティングは、もう今年度末に迫っている留学プロジェクトの具体的な内容についてですので(いろいろとオーストラリアの方々の時間感覚や仕事の進め方について興味深いことはあるんですけど)ここでは割愛し、メルボルンの町に10ヵ所以上ある、私営の学生寮について紹介してみたいと思います。
ご存じの通り、オーストラリアの大学はこれまで留学生をがんがん受け入れてきました。地理的な利点から、中国、韓国などアジアからの留学生がとても多く、大学の寮だけでは受け入れが間に合わないため、私営の学生寮がたくさんあり、タワーマンション学生寮があちこちに立っています。うちの学生さんを送り出す場所の選定のための寮の視察というのが、今回とても重要なミッションでした。
カピバラ一行が宿泊していたホテルは、普通のビジネスホテルで、スーツケースを広げる余裕もなく、シャワールームも両手を広げると壁に当たるような感じ、朝食なしで、それで一泊3万円とちょっと。円安の影響もあり、やたらと高い。しかしタワマン学生寮は、広々としたキッチン付きのワンルーム、眺めも良く、スポーツジム完備、ラーニングスペース、パーティールームなどもついて、一泊1万2,000円とのことで、そこそこ埋まっています。また街のあちこちにアジアの国々のスーパーなどがあり、シドニーもそうでしたがメルボルンも地元の経済を留学生が回しているような感じがします。
オーストラリアは、いわゆる白豪主義と決別し、1990年代から積極的な移民政策を展開し、これが経済成長と高齢化のスピード抑制に効果的でした。一方移民が都市部に集中したことにより、インフラや共生にいくつか課題が生じています。オーストラリアは2023年12月に今後の移民政策概略としてアクションプランを発表し、移民の数を50%削減するとともに、留学生の受け入れについてもより高い基準を設定し、学生の卒業時のスキルレベルの向上を目指すことにしたのです。「留学」が現在のところの重要産業であるオーストラリアであり、大学にとどまらず留学生ビジネスも盛んですが、これからはちょっと違ってくるのかもしれません。オーストラリアもまた共生を実現し、公平性を向上させようと格闘中の国なのだなと思いました。
埼玉でIPEを語る
さてカピバラ部隊は、何のアクシデントもなく体調不良もなく全員無事に帰国し、それぞれの日常に戻りました。そして帰国から2週間後、日本保健医療福祉連携教育学会の学術集会が埼玉県立大学で開催されました。カピバラこれに参加し、群馬大学の李先生のご発表1)をうかがい、ジグソーパズルの最後のピースがはまったような感じを受けました。発表の内容をざっくりまとめると「IPEの思想は、アメリカ型の専門家の集団による切り分けの医療では難しい状況が起きるよねっていうことで生まれてきたもので、IPE初期の1990年から2000年くらいに、IPEのエヴァンジェリストの先生方が、伝統的なアメリカ型医療からシフトしようとしてきたものだ」ということでした。
そして今、もともと北半球で盛んになったIPEは、現在、アフリカ、インド、アジアに波及しつつあります。それに伴い、IPEのこれまでの北半球モデルや枠組みを、その地域の文化的、地政学的な文脈に反映させていけるような、情報の提示と実装方法の転換が必要になってきているんだと思います。日本でも同じです。過去のボーダーを受け継いだり守ったりすることだけにとらわれるのではなく、日本の10年後に必要とされるであろうIPCP(interprofessional collaborative practice)のあり方をイメージして教育をデザインしていくことが重要かと思ったことでした。
旅の終わり
2022年2月のウクライナ危機の際、ケニア共和国のキマニ国連大使は、ウクライナの国際的に認められた国境と領土的一体性の尊重を求めるスピーチを、国連で行いました2)。
「アフリカの国々の国境は他国によって引かれたものです。他国の支配が終わった後、もともとの民族、人種、宗教の同質性で建国しようとしたなら、自分たちは何十年も戦争していたことでしょう」と述べた後、キマニ大使は、「しかし、私たちはその道を選びませんでした。私たちはすでに受け継いでしまった国境を受け入れたのです。それでもなお、アフリカ大陸での政治的、経済的、法的な統合を目指すことにしたのです。危険なノスタルジアで歴史にとらわれてしまったような国をつくるのではなく、いまだ多くの国家や民族、誰もが知らないより偉大な未来に期待することにしたのです。私たちはアフリカ統一機構と国連憲章のルールに従うことを選びました。それは国境に満足しているからではなく、平和の裡に築かれる偉大な何かを求めたからです」と続けて述べました。
今回の旅の終わりに2022年2月のこのスピーチを読み返しました。引用させていただき、旅の記録のまとめにしたいと思います。
そう、最終着陸地点は、変化した自分の認識だったのでした。
1) 李 範爽:諸外国におけるIPEの地域展開;日本保健医療福祉連携教育学会第17回学術集会 シンポジウムⅠ「専門職連携教育(IPE)の地域社会への展開~IPEからIPWへ~」より
2) テレ朝news:ウクライナ危機でアフリカが見せた“怒り”のスピーチ 世界中で大きな反響,〔https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000246701.html?display=full〕(最終確認:2024年12月24日)
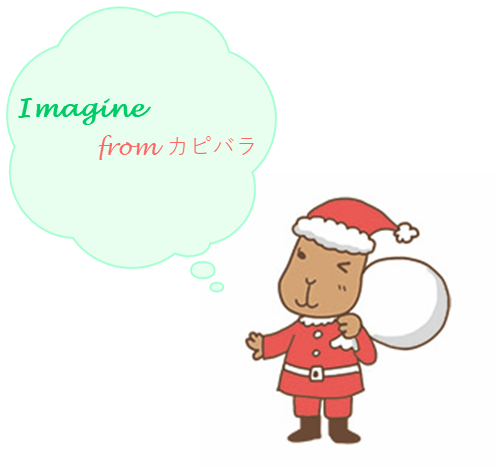
IPEに関する国際シンポジウム 開催のお知らせ
「世界の多職種連携教育のトレンドと展望~ユニバーサルヘルスカバレッジを目指して~」と題し、2つのプログラムをお届けいたします。
すごく豪華な世界のIPEリーダーたちがお話ししてくれます! カピバラも出るよ♡ もちろん参加費無料です!
ご興味のある方はぜひコチラから詳細をご覧ください。参加申し込みは先着順です。
●Part1【オンデマンド視聴】:パネリスト報告・発表
「Global IPE trends and their respective challenges」
2025年1月13日(月)より視聴開始予定
●Part2【ウェビナー】:パネルディスカッション
「The Impact of Promoting Interprofessional Service Learning on Universal Health Coverage」
日本時間 2025年1月25日(土) 18時開始




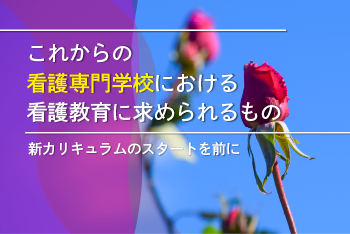

_1685342416837.png)