暑さ寒さも彼岸まで。今年の猛烈な暑さもなんとかお彼岸でつじつまを合わせるかのように気温も急降下しまして涼しくなり、人心地つきましたね。読者の皆さまも、今年もあと3ヵ月となり、一年のエンディングに向けて、全力疾走のご準備も万全のことと拝察申し上げます。
今回の原稿でこの連載も30回を迎えました。ここまで続けてこられたこと、読者の皆さまあってこそのことと感謝の気持ちでござる。そんな節目にカピバラ、カピバラジュニアの結婚式やら世界一周出張(旅行じゃないよ!)などを控えておりまして、自分都合ですけども、来月の連載はお休みをいただきます。いろんな仕事を同僚にお任せし、またリフレッシュして戻ってきたいと思っています。ということで、今回は、「任せる」ということについて書いてみます。
すべてを背負って決める覚悟
先日のフクダ電子アリーナ(通称フクアリ)でのレノファ山口戦で、ジェフ市原千葉の背番号10番・小森選手がハットトリック(一人の選手が1試合で3得点以上決めること)を達成しました。これは19番・岡庭選手がサイドから相手をフェイントでかわしてペナルティエリア内に侵入し、それを止めようとしたレノファ山口の選手に倒されファウルとなり、ペナルティキック(PK、ペナルティマーク上にボールを置いてそこから直接ゴールを狙ってキックする)となったことから生じたものです。
その時点ですでに2点決めていた小森選手が、倒された岡庭選手にPKを蹴らせてほしいとお願いに行きました。でも岡庭選手は自分のチャレンジで獲得したPKを小森選手に任せたくありません。ほかの選手たちも駆け寄り、仲裁に入りますが、なかなか岡庭選手は納得できません。PKは誰が蹴ってもいいんですけど、誰が蹴るのかは事前に宣言する必要があります。審判も相手選手も早く決めるようにプレッシャーをかけます。大卒2年目で現在J2で得点王争いをしている小森選手にはプロサッカー人生初のハットトリックがかかっていますし、岡庭選手だってシュートを決めれば記録がつきますし、どっちの気持ちもわかる。カピバラ、ハラハラドキドキしつつ見守っておりました。数分後、岡庭選手はようやく小森選手に任せることを自ら決めることができたようでした。岡庭選手と幼馴染の44番・品田選手も駆け寄って、岡庭選手の頭をぽんぽんしてなだめます。そして、小森選手が蹴ることになりました。
カピバラのマニアック註:岡庭愁人選手はFC東京からレンタル(期限付き移籍)でジェフに来てくれている選手です。3人兄弟の末っ子で、お兄さん二人もサッカー選手です。とくに次兄さんはジェフアカデミー(プロ選手育成組織)出身という縁もあり、ジェフのホームグラウンドであるフクアリでシュートを決めることは、岡庭選手にとっても特別なことと想像されます。岡庭選手の愁人(シュート)という名前はこのお兄さんがつけてくれたんですって。マニアックついでに、品田選手もFC東京からレンタルで来ている選手で、移籍後すぐに試合に出はじめたものの、3ヵ月くらい、周りとタイミングが合わなかったりなかなか自分を表現できない期間を経て、9月に入ってから調子を取り戻し、今ではジェフになくてはならない選手となっています。岡庭選手と品田選手は一緒にサッカーしながら育ったのです。一つの場面に、こんなにも物語が詰まっているんです。ぐっときますね。
ゴールキーパーはボールが蹴られた方向に反応しましたが、迷いなく振り切った小森選手のシュートスピードが勝ってゴールが決まり、見事ハットトリックとなったのでした。そしてシュートを決めた後、岡庭選手のところに行き、ハグして、感謝の気持ちを伝える小森選手。ジェフサポは、小森選手のチャント(選手を鼓舞する選手固有の応援歌)のあと、岡庭選手のチャントを歌い、両選手にエールを送ったのでした。
サッカーには物語があります(もちろんどんなスポーツにだって物語はあるとは思うけど)。このPKをめぐっても、共に闘うジェフ市原千葉の選手たち、レノファ山口の選手たち、そして審判団、チームの監督とコーチ陣、それぞれのこれまでの人生の物語が交錯した場面だったと思います。っていうかPKってそういうものですよね。イタリアの至宝と言われたロベルト・バッジョが、1994年のアメリカでのサッカーワールドカップ決勝戦でPKを外し、悲劇のヒーローとなったそのあとに、「PKを外すことができるのは、PKを蹴る勇気をもつ者だけだ」と名言を残しましたっけ。
PKに至るまでのいろんな事柄(つまり文脈)、かかわった人たちの思い、それらをすべて背負って、自分とチームのために、ゴールキーパーが守るゴールネットめがけて至近距離からシュートを打ち、決める。これがサッカー選手の責任の取り方の一つであると思ったフクアリの夜でした。
すべてを背負って決める覚悟と勇気が、そして決めて結果を出すことが選手を成長させます。シュートを打つその局面に至るまで、つまりパスをつなぎ、相手守備陣をおさえボールが運ばれてくるそのプロセスにおいて、一人ひとりの選手がやはり何かを背負い覚悟と勇気をもって闘っている。サッカーって、究極1対1の場面でどれだけ勝ち切るか、ってことがキモです。チームスポーツなんですけど、90分の制限時間の中で、守備の選手は相手の攻撃を止める、攻撃の選手は守備の選手を振り切って前に行く、この1対1の攻防の瞬間に永遠を見るからサポーターは応援をやめられないのですね。
「最後の外科医」
ある時、外科医のお友だちがこんなことを話してくれました。
「○○先生はね、どんなに荒れた場に呼び出されても、とにかく、その場を収めちゃうんだよ。多量の出血でぐちゃぐちゃになってて出血ポイントが特定できなくて、若い医者や看護師がばたばたしてても、○○先生が来て、患者さんの横に立つと、場がすーっと収まる。で患者さんが助かる。その先生が来てくれたらもう、ほかの外科医は呼ばなくていいわけ。だから、“最後の外科医”なの。」
「そういう先生がいると、若い外科医はのびのび安心してチャレンジできるんだよね。だけど、なぜだか伸びが遅い。だって自分が全責任を背負って、メスを持たないから。いや当然責任はもって手術に向かうんだけど、本人が自覚できない部分の覚悟っていうところに安心感を得られるというか。全責任は背負わなくていいの。最後の外科医がいるから。それはそれで幸せ。ゆっくり成長することができる。とは言っても、外科医は修羅場を背負って、それをくぐり抜けた数で成長するんだよね。場数を踏むってそういうことだから。自分が“最後の外科医”だっていう腹をくくった数の多さっていうかさあ。」
こういうことって、いろんな職種の成長の場面であるんじゃないかなと思います。「腹をくくる」場面はどんな職種にもある。不肖カピバラにもある。さすがにいまこの場の人の生き死にには関係することはないけれど、それでも余人をもって代えがたい場面、たとえば科目責任者としての授業とか、科研の申請書を書くとか、招聘講演のステージとか、絶対に何かを言わなくてはいけない会議とか。カピバラがいなければどうにもならない場面で、すべてを背負って(っていうのはなんかおおげさではあるけど)何かする、というのはちょっとはある。
でもカピバラ、定年間近になってきて、今までとは違う気持ちもまた生まれてきました。「任せる」ことが、任せた側にもたらす影響を実感するようになってきたのです。任せる時には、「腹をくくる」状況ごと任せないといけないのではないか。となると、「任せて失敗」ということも想定しての選択になるんですよね。失敗パターンをシミュレーションして対策を考えて、しかし、その対策はいったん忘れて任せるみたいな感じです。このような意味で、任されるほうも任せるほうも、ともに腹をくくるといいますか、チャレンジとなります。そしてそのような状況をクリアすることで、任されたほうだけでなく、任せたほうも成長することが確かにあると思います。
若手、中堅が成長する時
若い看護職が現場で成長する時、先ほどのような1対1の場面で決め切る、すべてを背負ってシュートを打つ、自分がいまのこの局面では“最後の看護職”だと思って勇気を振り絞って対応する、というようなことがあるのではないかなと思います。権限のない立場で権限を委譲されて、「最終意思決定」をする、つまりすべてを背負って自分で決める、ということになる。これは経験学習の研究で有名な松尾睦先生の「経験からの学習」理論で言えば、ストレッチ(挑戦的な目標に取り組む)体験です。ただし、ただチャレンジさせるだけでは成長につながりません。このストレッチ体験から自分の仕事のあり方を振り返り、仕事の中に意義ややりがいを見つけ楽しむ、という、「ストレッチ」「リフレクション」「エンジョイメント」が必要です。この3要素を高める原動力が仕事に対する思い(価値)と他者とのつながりであり、これらがそろって仕事をするとき、経験から学ぶことができる、ということですね。
とはいえ医療の現場では、このようなチャレンジが難しい側面もありますよね。患者さんの命や生活が懸かっていると思うと、あるいは時間的に圧迫され同僚に迷惑がかかると思うと、またこれは今まで自分がやってきたことであり、自分ならうまくやれる自信があるという思いがあると、「他者に任せるよりも自分がやったほうが確実で早いしうまくいく」と思うような状況です。確かにそういうことはあるんですけど、これをやり続けると、スタッフに最終意思決定を任せない組織になっていくリスクも大きいのかなと思います。とくに医療安全にまつわる神話が強すぎると、チャレンジをさせない、自分で自分の仕事を決めることを好まない組織になっていき、結果として若手や中堅の専門職が「自分で自分の仕事を決められない」と思ってしまう。なんでも師長さんに聞いてからやるとか、とりあえず先輩に相談してからやるとか、そんなことになってしまう。そういう組織の〇〇長の人の口癖として「だれが責任取るんですか」というのがありますね。
こうなると若手・中堅は「もちろん私は責任取れません」となって、ルーティンの仕事をこなすだけになり、成長実感をもてませんから、つまらなくなって別の職場を夢見てしまう可能性もあります。業務やスタッフを完全に管理下に置くと、置いたほうは安心だと思うんですが、長期的にみると、任せるほう(つまり〇〇長という立場の人)の仕事は増えるばかりで、楽にはなりません。〇〇長さん、いつも残業してるよね、いつも不機嫌でダメ出しばかり、あんな〇〇長さんにはなりたくない、などと思われちゃったりとか、「若手が伸びない」「すぐやめる」「若手を引き上げようと思うんですが、〇〇長という立場にはなりたくないと言われ断られます」という、人材育成としてはしぼんでいく組織になることも多いかなと思います。
任せるほうにとっては①失敗したとしても任せた側がリカバーする、②失敗を自分でリカバーすることまで任せ、見守る、③失敗した後みんなで取り返しに行く覚悟をチームでもったうえでチャレンジする、という3つの「任せ方」のフェイズがあるのかなと思います。サッカーで言えば①は任されたほうがボールを失ったとしても任せたほうが取り返す、②は任されたほうがチャレンジしてボールを失ったとしたらそのボールを取り返すところまでを任せる、③はボールを失った結果相手に一点決められたとしてもチーム全体で反撃し1点返す、という感じでしょうか。プロサッカー選手なら①と②は当然できなくてはいけないこと、③についてはそれがサッカーということだと思います。①②③は選手にとっては基本的にエンジョイメントなんだろうと思います。平たく言えば「サッカーが好き」っていうことですね。若手、中堅が「仕事が好き」と思えるというのは素晴らしいことだと思います。
「任せる」とは丸投げすることではありません。結果への責任をシェアしたうえで若手や同僚のチャレンジがうまくいくように、チャレンジが楽しいと思えるように、いろいろと調整し続けることをい言うのかなと思います。カピバラは、なんかまだまだできてませんけど、とにかくポジティブフィードバックとこちらから声をかける、ってのをやろうって思っています。いざやろうとすると、けっこう難しいなと思います。カピバラ自身が失敗回避神話にとらわれているのを痛感するこの頃です。
風が吹いている
2000年に介護保険法ができた時、あと25年後には団塊の世代が全員後期高齢者になり、医療介護の在り方がこのままでは立ち行かないことになる、だから、地域包括ケアシステムを推進せねば、ということでいろいろな制度改革が行われてきました。2015年には地域の医療状況が厳しくなるから特定行為研修修了者がたくさん必要だということで特定行為研修制度が導入され、現在は1万人を超える修了者が活動しています。
来年は2025年です。風はすでに、超高齢社会への対応から少子化、人口減少への対応へと、ずいぶん前からシフトされています。風は吹き続け、時代のあり様は本当に変化してきました。いま吹いている風のその始まりは、実はずいぶん前から吹いていたのだなと思います。
年齢や性別やいろんなことを越えて、一人ひとりの専門職が自分の仕事と人生を自分で管理し、目指すべき方向性を自分で見極めてそこに向かってチャレンジしていくことが、ますます必要ですね。始まりの続き、新しき日々はここにある、でございます。
1)松尾睦:職場が生きる人が育つ「経験学習」入門,ダイヤモンド社,2011年
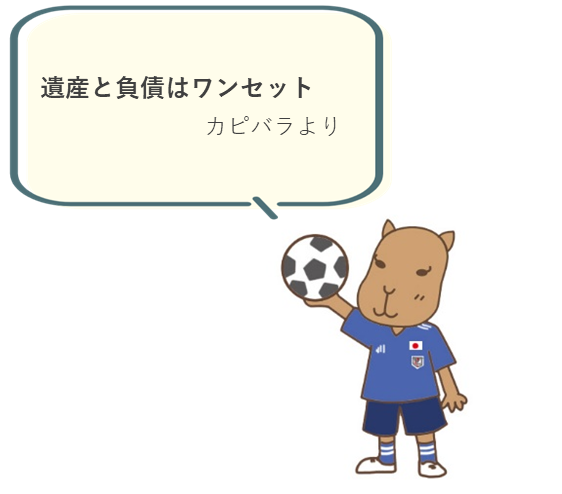



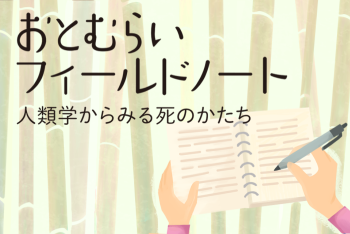


_1695266438714.png)