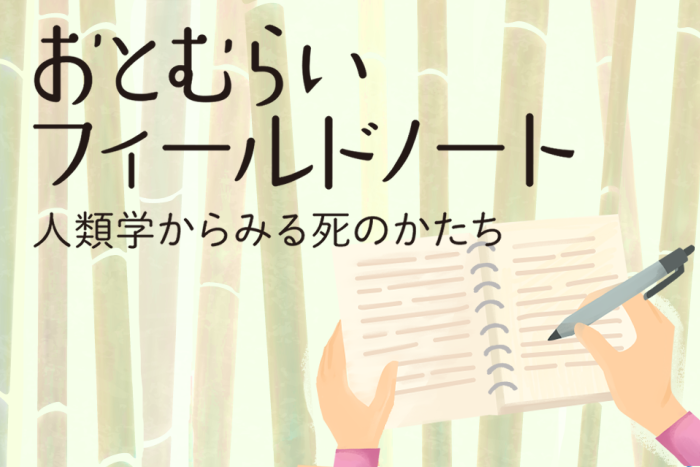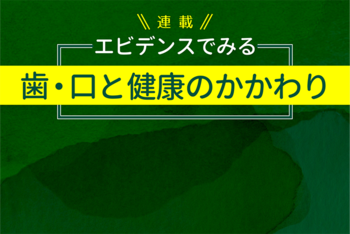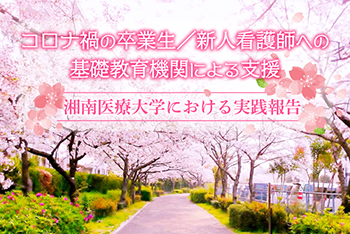現在わたくしはプロ野球の日本シリーズが行われている真っ最中に、ヒイヒイ言いながら今回のコラムを書いているのですが、つい先ほど激戦を制して阪神タイガースが日本一の栄冠に輝きました。なんと38年ぶりということですから阪神ファンには待ちに待った歓喜の瞬間。皆さんが今回のコラムをご覧になるときにはすでに終わってしまっているとは思いますが、おそらく御堂筋あたりで優勝パレードが盛大に行われるのでしょう。
それはさておき、皆さんが「優勝パレードとお葬式は相通ずるところがあるね」と誰かから言われたら、きっとキョトンとしてしまうのではないでしょうか。ところがどっこい、それなりに共通点があるのです。それは「皆でゾロゾロと列をなして歩く」ということ。なんだ、そんなことか……と呆れないでください。お葬式の場合はパレードではなく葬列と呼びますから、表現はかなり異なるものの、実は結構深い関係なのです。
お葬式のハイライト
葬列は俗に「野辺送り」とも言われています。すなわち、死者の亡骸を墓地や火葬場へ運ぶことを指しますが、以前は墓地も火葬場も人気のない野原(野辺)にあったので、このように呼ばれているというわけです。さて、ここで質問。お葬式って、どこで何をしているイメージがありますか? たぶん多くの方々が「皆で葬儀会館の式場に座っていて、お坊さんが祭壇の前で読経をあげている光景かなぁ」と答えるんじゃないでしょうか。
しかし実はこれ、高度経済成長期(1950~60年代)あたりから徐々に広がってきたイメージなのです。では、それ以前に同じような質問を投げかけたらいったいどういうことになっていたかというと、ほとんどの人びとが「皆でゾロゾロと歩いていく野辺送りの姿かなぁ」と答えたであろうことが容易に想像できます。というのは、かつての葬儀のハイライトは現代のように「閉じられた空間に一同が集う」ことよりも、むしろ「開放的な空間を亡骸と一緒に皆で移動する」ことにあったからなのです。もっとも、大正時代あたりからとくに都市部で徐々に自動車の数が増え始め、電車の線路や踏切があちこちに設けられるようになると、人口が密集している地域では交通網が障壁となって葬列を行うのが難しい状態になりましたから、「ほとんどの人びとが」というのはちょっと言い過ぎの感はあるかもしれません。それでも全国的にみれば、圧倒的多数の人びとが「お葬式=葬列」というイメージを抱いていたと言って差し支えはないでしょう。
死者をおくる、死者になる
ここで、前回の「白い喪服」の写真を見てください。まさに今から一同そろって野辺送りに向かうという光景で、右脇にいるお坊さんなどは「おっ、そろそろ行くのかな。じゃあ列の中に入らなきゃ」なんてタイミングを探っている感じにも見えますね。さて、この写真には続きがあって、いよいよ野辺送りが始まると以下のような光景になります。

農山漁村文化協会,2006より引用]
「写真を間違えてるぞ! これはお葬式じゃなくて、お祭りじゃないか」と思われた方、間違いではないのでどうか怒らないでください。まあ、それも無理はありません。白の手ぬぐいを被った男性たちが担いでいるのは、一見するとお祭りに付きもののお神輿(みこし)にしか思えませんから。神様に乗っていただく場合は畏敬の念を込めて神輿と言いますが、この輿(こし)というのはそもそも複数の人間が担いで何かを運ぶための道具全般を指す言葉。この写真に描かれている輿には、もちろん亡骸が乗せられています。そして現在では葬儀を象徴するアイテムといえば祭壇が挙げられますが、かつてはこの輿がまぎれもなく最重要にして必須のアイテムでした。
ちなみに葬具、つまりお葬式に用いるさまざまな道具のほとんどは死の穢れ(けがれ)を祓う(はらう)という意味合いもあって、昔はお葬式のたびに作っては一回限りで捨ててしまうことが普通だったのに対し、この輿だけはずっと保管しておくことが多かったようです。死者を乗せてあの世に送り出す、その最期を飾る大事な道具ということで、それぞれの村や町などで独自に贅を凝らした輿を作っていたわけですから、やはりそのたびに作っていてはお金も労力もかかりますし、何よりもモッタイナイ。お祭りに使う神輿や山車を町内会の倉庫などに保管しておくのと似ていますね。さらにもうひとつ、また別の葬列を見てみましょう。

これは終戦直後の昭和20年代に撮影されたもので、やはり同じように輿を担いでいます。その前に立っている白い裃(かみしも)を着ている男性が喪主で、さらにその前にいる白の着物姿の女性はおそらく故人の妻でしょう。前回のコラムでは弔いの色に触れましたが、ここからも身内の喪服は「白」が基本だったというのがわかりますね。このように葬列というのは誰が何を着て、どこに並び、どのような葬具を持つのかということが地域ごとの慣習でだいたい定められていました。言葉を換えると、葬列というのは故人を中心とした人間関係をギュッと凝縮して、一目で知らしめるものでもあったのです。たとえば下の写真のように現在でも葬列の順番を(葬列そのものは行わないにもかかわらず!)葬儀会館のロビーなどに貼り出して、かつての風習を伝えている地域もあるんですよ。

過密した交通事情やなにかと忙しいライフスタイルもあって、今日では野辺送りの光景を見かけることはごくまれになってしまいました。輿に乗せた亡骸の前後に連なって皆で歩き、一歩進むたびに刻々とうつろっていく景色を見つめながら故人との記憶を手繰り寄せ、そしてあの世へと送り出す。そうやって故人はゆっくりと社会のなかで生者から死者になり、その事実を葬列によって人びとに知らせ、それを見た者が受け止めていく。
いささか不謹慎とは思いながらも優勝パレードとお葬式は相通ずるところがあると冒頭で言ったのは、このような「経験の分かち合い」という次元で共通しているからでもあります。最後の一球がキャッチャーミットにおさまった瞬間、たしかに阪神が優勝したという「事実」は確定しましたが、その事実が多くの人びとの「記憶」になっていくためには、六甲おろしの大合唱からビールかけの祝賀パーティ、そしてパレードにいたるまで、その瞬間を皆で共有するプロセスが必要です。仮に、いつもと同じく審判の「ゲームセット!」のかけ声で試合が終了して、その後はとくに何もなし……ということだったら、どうでしょうか。皆で優勝したという事実を噛みしめながら感覚を共有し、ほかの人間にもそれを知らしめることで、優勝したチームに「なって」いく。そのような経験を分かち合うためには、皆で歩くという行動はある意味でもっとも適しているのかもしれません。