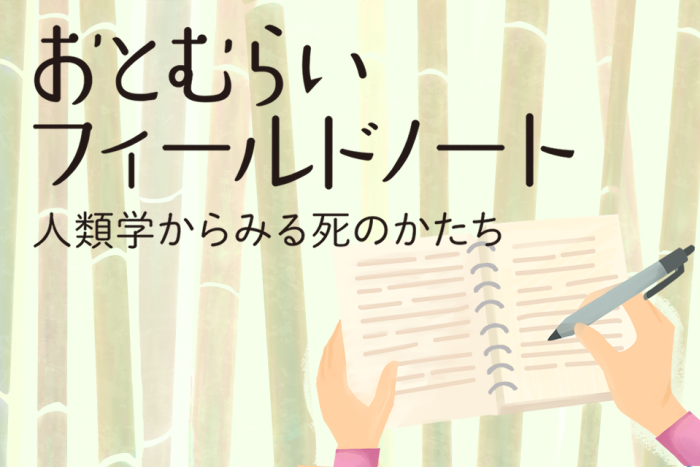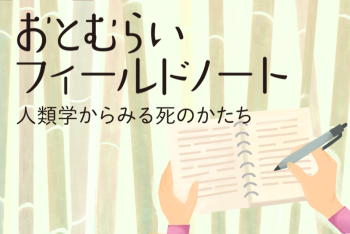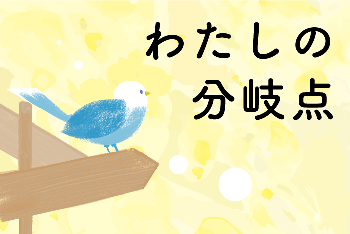先日、ふと幼稚園の前を通りがかったときに、なんとも懐かしい光景が視界に飛び込んできました。園児たちが楽しそうに電車ごっこをしていたのです。皆でロープを握って一列に並び、先頭の子どもが「しゅっぱつしんこう!」と勢いよく告げて歩き出す姿は、もう微笑ましいの一言に尽きますね。しかし、ぼんやりと「そうかァ、令和のちびっ子も電車ごっこをするんだなァ」などと眺めている内に、それとはまた別の、でもどことなく似通った光景がワタクシの脳裏を過ってしまうのでした。当然、おとむらいに関係ある光景です。ここまでいくと職業病というか病膏肓に入る(やまいこうこうにいる)というか、我ながら呆れてしまいますが、それではその「どことなく似通った光景」とは一体何かというと……。
善の綱
このコラムは前置きが長いのが毎度のことだから、きっと本題に入るのはもう1回か2回ほど画面をスクロールしてからだろうなと思ったでしょう? ふふふ、残念でした。今回ばかりはそんな悠長なコトはしていられないのですよ。なぜかというと原稿がワタクシ史上最高と言ってよいほど遅れに遅れ……いえ、何でもありません(南江堂のYさん、ごめんなさい!)。何はともあれ、早速その光景を写真で見ちゃいましょう。
.jpg)
女性たちが白い布を手に握りしめながらゾロゾロと歩いていますね。少しばかり不謹慎ではありますが、ワタクシがこの光景を電車ごっこから連想した理由がお分かりいただけるかと思います。これは善の綱(ぜんのつな)と呼ばれる習俗で、これまでのコラムで何度も登場している野辺送り、つまり葬列で行われることが通例。上の写真は高度成長期真っただ中の1968(昭和43)年に宮城県の七ヶ宿町で行われていた葬列を撮影したものですから、約半世紀ほど前にはなりますが1)、現在でもおとむらいの古式ゆかしい流儀が残っている地域ではちらほらと見かけるものでもあります。縁の綱(えんのつな)や名残の綱(なごりのつな)と呼ぶこともあったり、あるいは善ではなく「禅」の字を当てたりすることもあるのですが、いずれにしても輿や棺などに結びつけた長い白布を葬列に加わった人びとがめいめいに握って故人を送るという点では共通していると言えるでしょう。そしてまた、この善の綱にはもう一つ共通点がありました。それは、ほとんどの場合で善の綱を持つのは女性か、さもなければ子どもであったということ。参考までに別の地域で行われていた善の綱の光景を下に挙げておきますが、やはり女性や子どもが善の綱を持っています。
.jpg)
それにしても、なぜ女性なのでしょうか。最初に掲げた宮城県七ヶ宿町の写真も含めて、全国各地の民俗を克明に記録し続けてきた民俗学写真家として名高い須藤功氏は、次のように語っています。
死者にとっての縁の綱は、死後を善所に導いてくれるということになろうか。善所を天国と解してもよい。天国に導く者はまた天国に導かれるということで、そこに縁が生ずる。かつて、「三界に家なし」といわれた女たちにとって、それは死後救われる唯一の道で、そのために縁の綱には女が連なる、ということだったのかもしれない。2)
三界というのは「全世界」とほぼ同じ意味を持つ仏教用語ですが、この「三界に家なし」という言葉は要するに「女性は、幼いときには親に、嫁いでからは夫に、老いてからは子どもに従って毎日をあくせくと暮らすことになるため、どこにも安住の地がないまま一生を送ることになる」ということを指しており、何事につけ男性を目上に位置づける家父長制のしきたりに縛り付けられていた女性たちの苦しさを表現した慣用句として、かつては広く語られていました。もちろん現在ならば(というよりも現在であろうがなかろうが)否定されて然るべき因習ですが、概してそのような風潮に社会全体が覆われていた時代が長らく続いたことも事実。あくまで一つの解釈ではあるものの、善の綱という習俗には、三界を離れた後の「あの世」ぐらいは安らかでありますように……という女性たちの切ない思いが込められていたのかもしれません3)。
願いをむすぶ、思いをつなげる
ところで、この善の綱を「あっ、おとむらいじゃないけど見たことがある!」という読者もいらっしゃるのでは。そうなんですよ、この善の綱は寺社で行う各種の催事や、はたまた地域のお祭りなどでも時折行われているのです。そして葬列ではない場面で行われる善の綱は、男性が持つこともあれば、それこそ老若男女問わず誰でも触れることができる場合も多いという点で違いがあります。

たとえば、上に掲げた写真の左側にあるのは長野県の善光寺で7年に1度行われる本尊の御開帳の光景ですが、境内の中央に立てられた回向柱(えこうばしら)と呼ばれる柱から一本の綱が延びているのが見えるでしょうか。これもまた同じように善の綱と呼ばれていて、本堂に置かれた前立本尊(まえだちほんぞん)4)の右手に結ばれています。あたかも電流がビリビリと流れて充電(というか感電?)するかのように、仏様のありがたいパワーが善の綱を通じて回向柱に、そしてさらに回向柱に触れた人びとへと伝わってきそうですが、それと同時にワタクシなどは芥川龍之介の『蜘蛛の糸』よろしく、極楽浄土での救いを求める罪深い衆生がこの善の綱にすがるといった印象も持ってしまいますね。あるいは、回向柱の「回向」というのは一般に「現世で善行を重ねて積んだ功徳を他の者に分け与えること」を意味しますから、善の綱を通じて「これほど善い行いに励んでいるのですから、亡くなったご先祖様をあの世で幸せにしてくださいね」と仏様にお願いしているのかもしれません。
一方、写真の右側にあるのは愛知県の奥三河で行われている花祭り5)という祭礼の光景。これは奥三河の各地で冬に催されるもので、それぞれの地域で独自の特色があるのですが、神楽を奉納した後で祭りが終わりに近づくと、祭場の中央に置いた竈(かまど)の周りを善の綱を持って男性たちがグルグルとまわる「花育て」の儀礼が行われると言います。一説によれば、この儀礼は生まれ変わって再び成長することを象徴的に表したもの6)とされていますから、先ほどの善光寺の御開帳と相通じるような「現世と来世をつなぐ」、そして「生者と死者をつなぐ」というイメージで捉えることもできるでしょう。
実を言うと、この善の綱という習俗が一体どこから来ているのかという歴史的な経緯については、管見の限りでは未だ断定することが難しい状況です。ただし、阿弥陀如来の導きによって極楽浄土への転生を願うという、いわゆる浄土信仰が拡大した平安末期には、この善の綱とよく似た臨終の作法が、特に貴族階級の間で流行したことがありました。それは、臨終の際に仏像や仏画を枕元に置いて糸をかけ、その糸の端を手で引きながら最期の時を待つというもので、もしかするとこの習わしが徐々に形を変えながら広まったのではないかと推測することもできます。
いずれにしても、この善の綱という習俗の背後には「仏様に救済してもらいたい、極楽浄土へと導いてもらいたい」という願いに加えて、「わたしが旅立っても、あなたとつながっていたい」そして「あなたが旅立っても、わたしとつながっているよ」という思いもあると言えないでしょうか。何かと個人化が進んでいると言われる現代ですが、実際のところは一人で生きて、一人で死ぬことはできません。それは自分一人だけでは電車ごっこが出来ないのと同じようなもので、いつの時代でも、どんな社会でも、やはり人間は誰かに生死を託したり、あるいは誰かから託されたりという持ちつ持たれつの関係が必要です。言わば善の綱とは、そんな関係=縁を誰かと結んで、世代を超えてつなげていくための道具でもあるのでしょうね。
2)須藤功:葬式 あの世への民俗,青弓社,p.68,1996.尚、この引用文では「縁の綱」の語が用いられていますが、本文中の「善の綱」と意味は同じです。
3)地域によっては善の綱を男性が持つ事例も今までに報告されているものの、分布としてはやはり少数派です。ちなみに、おとむらいの研究で膨大な業績を残した民俗学者の井之口章次氏は、先ほどの須藤功氏とはまた違った視点から次のように述べています。「(前略)近親者はすでに他の重要な野道具を持っている。残りの人が、持つべき野道具もないような人が、善の綱につながることになる。したがって遠い親族、それが少なければ、役目のない弔問者が善の綱につく。葬列の野道具の中には重たいものもあるから、男には何かれと役目がある。どうしても女性には出番が少ない。そういうところから、善の綱につく人には女性が多いようである。500年あまり前の記録には、男が善の綱につらなった例が残っている。いつとはなしに、主として女性が持つもののようになったのであろう」(井之口章次:生死の民俗,岩田書院,p.69,2000)。
4)善光寺の真の本尊で、俗に善光寺如来とも呼ばれている一光三尊阿弥陀如来は常に厨子(ずし)の中に安置されており、過去はおろか未来永劫、誰も直接拝んではならない秘仏とされています。というわけで「本尊は過去に何度も生じた火事で焼失してしまっていて、実は存在しないのでは……」という説もあるぐらいなのですが、本文で述べられている前立本尊はつまり本尊の分身で、御開帳で公開されるのもこの前立本尊です。だって、真の本尊が安置されている厨子の扉は、なんと当の善光寺のお坊さんであっても絶対に開いちゃダメということになっているのですから!
5)一般に、花祭りとはお釈迦様の誕生を祝って寺院などで毎年4月8日に行われる灌仏会(かんぶつえ)という仏事を指すのですが、奥三河で行われている花祭りは時期が異なるだけでなく、そもそも神事として位置づけられているので、灌仏会とは名前が同じというだけで特に関係はありません。ちなみに写真で示したのは奥三河の東栄町で行われていた花祭りの光景ですが、そこで行われる善の綱も、宮城県七ヶ宿町と同じように大きな湯釜の周りを3回グルグルとまわるのだそうです。ただし、東栄町では「善」の綱ではなく、「縁」の綱と呼ばれています。
6)上掲2:葬式 あの世への民俗,p.67