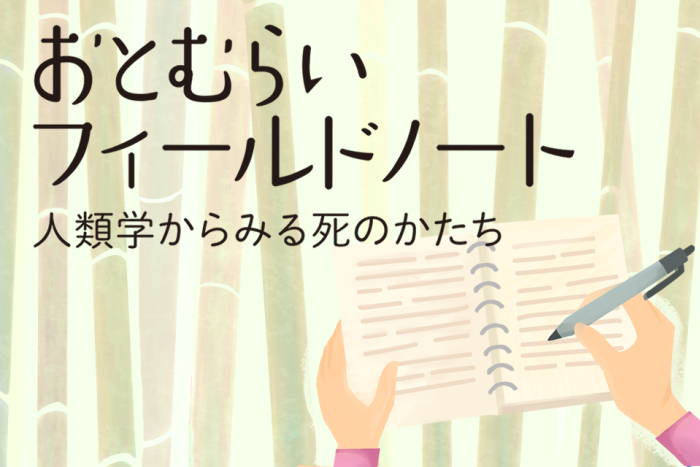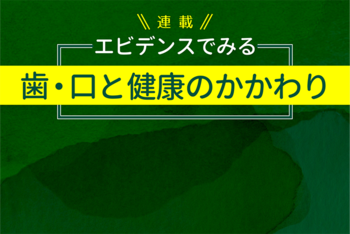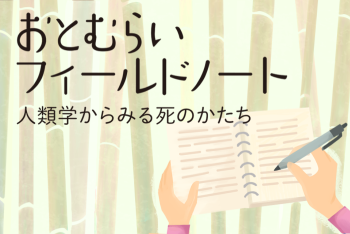前回の「母と子のものがたり(後編)」の最後に、お釈迦様の「命あるものは全て、ろうそくの灯が消えたり点いたりするように、生じたり滅びたりする」という言葉が出てきましたね。それでは、命あるものと聞いて皆さんはどのような「もの」を思い浮かべるでしょうか。
おそらく、この場合の「もの」とは人間を指し示す「者」、さもなければ動物や植物などの「生きもの」を思い浮かべることが普通かもしれません。では、それが一般的な生命体とはちょっと呼び難いような「モノ=物」で、そしてモノにも命が宿っているとしたら……?
モノのおとむらい
さあ、例によって例のごとく「何のこっちゃ!?」というマクラから今回も始まりましたが、ここで皆さんにもこれまでのコラムを思い返してほしいのですよ。ほら、第3回や第4回でも、「命」が人間の歴史のなかでどのようにイメージされてきたかという話題に触れてきたでしょう。ところがこの「命」というのは、おとむらいの文化に限って言えば、特に人間だけが持っているというわけでもないのです。まずは論より証拠。下の写真をご覧ください。

もしかすると「何これ?」という読者と、「ああ、はいはい!」という読者に分かれるかもしれませんが、さて皆さんはどちらだったでしょう。これはいわゆる「針供養」の光景で、折れたり曲がったりして使えなくなった針を供養するための習俗。上図の左の写真のように、長年にわたり使い続けてきた針に感謝し、その労をねぎらうために豆腐やコンニャクに刺して供養します1)。かつては針仕事に関係のある職人や商店は言うに及ばず、それぞれの家でも針供養を行うことが珍しくありませんでした。というのも、安価な既製服や布製品がいつでも手に入る時代が到来するまでは、お裁縫が現在と比較にならないほど家事のなかで大きな割合を占めており、針さんたちはブラック企業の社員よろしく来る日来る日も酷使されていたからです。
ちなみに毎年2月8日や12月8日2)になると、上図の真ん中(東京・浅草寺)と右(愛知・若宮八幡社)の写真のように寺社の年中行事として針供養が行われることも多いので、「自分ではやったことがないけれど、見たことはある」という方もいらっしゃるのでは。いずれにしても、供養というのは「人の死後、亡き人の冥福を祈って善事を修してその功徳を手向けること」3)であって、要するに針供養は「今まで頑張ってくれて、どうもありがとう」という感謝と敬意を込めたおとむらいに他なりません。長年にわたり自分の仕事に尽くしてくれた道具、はたまた自分にいつも寄り添ってくれた大切な持ち物など、そんな「モノを超えたモノ」が皆さんの身近にもあるはず。私たち人間はそんなモノにも命の存在を感じとり、人間の死者と同じく最期の別れを惜しんできたのです。
おとむらい=ありがとう
このような「モノのおとむらい」は針だけに限りません。それどころか、もう枚挙に暇がないほどです。先ほどの針供養と同じように、生活の身近にある道具を例にとってみると、皆さんのお住まいの近くでこんな石碑があるのを見かけたことはありませんか?

まず左側の写真は、料理で使う包丁を供養するための「包丁塚4)」。この写真は料理の神様として知られる磐鹿六雁命(いわかむつかりのみこと)を祀っている高家(たかべ)神社の包丁塚で、この神社では毎月17日に「包丁供養祭」が行われています。ちなみに高家神社はその祭神の由緒もあって料理人や食品業者などの崇敬を集めていますが、季節ごとに神事として奉納される「包丁式」でも有名ですよね。古式ゆかしい装いの包丁人(料理人)が包丁と箸だけを使って一切手を触れずに魚をさばく見事な姿は、もう圧巻の一言。メディアでもよく報道されていますから、皆さんもご覧になったことがあるかもしれません。
そして右側の写真は、第12回でも登場した天神様、つまり菅原道真公を祀っている太宰府天満宮の「筆塚」。上にデデン! と巨大な筆が鎮座しているのはどことなくユーモラスでもありますが、それにしてもなぜ天満宮に筆塚があるのでしょうか? それは、博学多才で知られた道真公は空海や小野道風(みちかぜ/とうふう)と並ぶ「書道三聖」、つまり書道の神様としても名高いから。そうそう、この太宰府天満宮も先ほどの高家神社の「包丁供養祭」と同様に、毎年9月になると使用済みの筆を筆塚に供えて供養し、合わせて書道の上達を祈願する「筆塚祭」が行われるんですよ5)。
ここで例として挙げた包丁塚や筆塚は全国各地にあり、それぞれ独自の由来を持っていますが、先ほど枚挙に暇がないとお伝えしたように針、包丁、筆の他にも「モノのおとむらい」をめぐる習俗はきわめて多岐にわたります6)。それもこれも、大切にモノを使い続けるという心は、やはりどこかで命に対する感謝に、そして現世から去っていく存在に対して「ありがとう」を告げたいという思いにもつながっているからなのでしょう。その点ではモノも人間も、等しく「命あるもの」と言ってよいのかもしれませんね。とすると、技術の進歩によって新しいモノが次々に生み出される現代では、その内に「スマホ供養」なんていう文化が登場するのかも……7)。
2)2月8日と12月8日は「事八日(ことようか)」とも呼ばれており、この日を農作業・家事・祭事などの節目としたり、災厄を祓ったりするさまざまな行事が古くから伝えられています。針供養も、この事八日のどちらか一方、もしくは両方に行われることが通例です。
3)藤井正雄:供養.民俗小辞典 死と葬送,新谷尚紀,関沢まゆみ(編),pp.272-273,吉川弘文館,2005
4)ただし高家神社では、正式には「包」の旧字である「庖」の字を用いて「庖丁塚」や「庖丁式」と表記しています。
5) 余談ですが太宰府天満宮には包丁塚もあり、包丁を供養するための祭事も年に一度行われているのです。包丁塚と筆塚の両方があるなんて、さすが道真公!
6) さらに別の事例を挙げると、「人形供養」もその最たるものかもしれません。地域をあげての行事として行われる場合などもあるようですが、それ以前に人形っておいそれと「古くなったから捨てよう」という気にはなりませんよね。実はこの人形もおとむらいとは密接な関係があるのですが、さらに話が長くなってしまうのでまた別の機会に。
7) なぁんて、話にオチをつけて「ふぅ、ようやく終わった。早く南江堂のYさんに今回の原稿を送らないと」などと一息ついていたのですが、「もしかしたら……」と念には念を入れて調べてみたところ、なんと! すでに存在するではありませんか! 自らの不勉強さを恥じ入るばかりです。というわけで、福岡・鳥飼八幡宮の「スマホ・PC供養祈願」を一例として挙げておきましょう。詳しくは〔https://hachimansama.jp/prayer/data〕(最終確認:2025年4月1日)をご覧くださいませ。