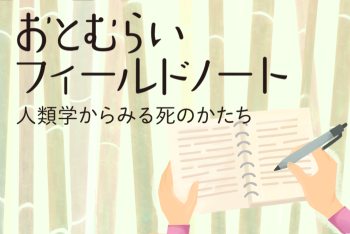前回の原稿を南江堂のYさんにポチッとメールで送って一息ついた後、ワタクシはふと気づいてしまったのでした。「あっ……どうせ母と子というネタで書くのだったら、母の日や端午の節句(子どもの日)がある5月に合わせればよかったじゃないか!」と。まあ、些細なことではあるんですけどね。でもほら、毎回冒頭に書いているマクラも季節の話題から入ることが多いじゃないですか。5月の風物詩もそれはそれで色々ありますが、「ゴールデンウィークとおとむらい」とか、「鯉のぼりとおとむらい」とかっていうのも少し無理があるし……えっ、話が長い? 大変失礼いたしました! それでは前編のページを開くのも面倒だという方々のために……いえ、読者の皆さまを1ヵ月もお待たせしたお詫びとして、まずは献身的で心優しいワタクシがこれまでのあらすじを述べておきましょう。
これまでのあらすじ
むかしむかし。インドのサーヴァッティという栄えた町の片隅に、キサーゴータミーという女性がいたそうな。悲しいことに、彼女は生まれたばかりの赤ちゃんを病で亡くしてしまい、絶望の底に突き落とされていました。「赤ちゃんを返して……」とうわ言のように呟きながら、彼女は町のあちらこちらを迷い歩くものの、死者を生き返らせることなど誰にもできるはずがありません。
一方その頃。皆さんご存知の、あのお釈迦様が弟子たちを連れてサーヴァッティに近い森を訪れていました。弟子のひとりがサーヴァッティの市場へと出かけたところ、悲しみに暮れたキサーゴータミーが「誰か赤ちゃんを生き返らせるお薬を……」と行き交う人びとにお願いしているではありませんか。その切ない姿をみた弟子は、「私はそのお薬を知っているかもしれないお方を、知っていますよ」と彼女に語りかけました。そして、弟子に案内されてキサーゴータミーがお釈迦様のもとにやってくると、なんとお釈迦様は「ええ、その薬を知っています」と言うではありませんか。ところが、そのお薬のつくり方を聞いたキサーゴータミーは、感謝の涙を頬にぽろぽろと流しながらも、思わず「えっ……!」と驚いてしまいました。
さて、そのお薬は一体どうやってつくるのでしょうか?
その一粒があれば
お釈迦様の言葉には、キサーゴータミーだけでなく、その場にいた弟子も口をあんぐりと開きながら同じように「えっ……!」と驚いてしまいました。でも、当然といえば当然。お釈迦様は穏やかな表情のまま、事も無げにこう告げたのですから。
「ケシの実1)を一粒、持っておいで。それでお薬をつくってあげよう」
何しろ、死者を生き返らせるという魔法の薬に用いる貴重な材料です。前編でお話した通り、キサーゴータミーはお金がどれだけかかっても、あるいは自分の命を差し出しても構わないと覚悟を決めていたのですから、驚くと同時に「そんな取るに足らないもので、しかも一粒だけでお薬ができるなんて……」と、呆気にとられてしまいました。というのも、ケシの実はどこの家にも置いてある香辛料で、それは豊かな家でも貧しい家でも違いはなかったからです。ただし、お釈迦様は彼女の瞳を見つめながら、続けて「だが、そのケシの実はこれまでに死者を出したことのない家から、もらってくる必要があるのだよ」とも仰いました。
おそらくそこに何かお薬をつくるための秘訣があるのかもしれませんが、いずれにせよ大勢の人間が暮らしているサーヴァッティの町ならば、そんな家はいくつもありそうです。それにケシの実を一粒だけならば、誰でも惜しみなく分け与えてくれるに違いありません。そう思ったキサーゴータミーは、「さすがは悟りを開いた尊いお方、きっと私には思いも及ばない神通力をお持ちなのだろう」と思いながら、再びお釈迦様に何度も何度も感謝の言葉を伝えると、その一粒を手に入れるために大急ぎで町へと戻るのでした。
さて、赤ちゃんの亡骸を胸に抱きしめてサーヴァッティの町へと舞い戻ったキサーゴータミーは、まずは自分の掘っ立て小屋のような家も含めて、貧しく小さな家々がギュウギュウにひしめき合って暮らす吹き溜まりのような路地裏へとやってきました。身寄りのない彼女ではあったものの、そこにある家々はお互いに持ちつ持たれつのご近所さん。最愛のわが子を失った自分の境遇を話せば、きっとケシの実の一粒ぐらいはもらえるはずだと考えたからです。
最初に彼女は、隣に住んでいる物売りのおじさんの家を訪ねてみました。ところが残念なことに「もちろん分けてあげたいさ。何しろ俺自身がケシの実を売り歩いているぐらいだから、いつでも置いてあるよ。だけど、おととしに女房を亡くしたのをお前も覚えているだろう? 悪いなあ」と言われました。ということで、今度はさらにそのお隣に住んでいるおばさんの家に。すると、そこでもまた「おや、どうしたい。ケシの実がほしいだって? それは朝飯前だけど、ちょうど生きていればお前と同じぐらいの歳になっていた娘を10年前に……。アンタがこの町で暮らし始めるよりも前のことだから、言ってなかったね。他の家に行っておいで」と言われ、そうやって次々に聞いて回り、この路地裏にある家からは全て「ごめんね……」「悪いけど……」と断られてしまいました。
その一粒でさえも
彼女は別に意地悪をされていたわけではありません。むしろ誰もが、キサーゴータミーの胸に抱かれて生気をすでに失っている赤ちゃんの亡骸を見れば、ケシの実一粒ぐらいは差し出してあげたかったのです。そこで、彼女は「ここに住んでいるのは私と同じように貧しい人びとだから、満足にお医者さんにも診てもらえず、お薬ももらえなくて、家族の誰かが亡くなってしまったのだろう」と考えました。
次に彼女が向かったのは、お金持ちとまでは言えずとも、まずまずの暮らしをしている人びとが住む場所。あまり知り合いもいませんでしたが、わが子を生き返らせたい一心で「ケシの実を……」と訪ねてみたところ、そこでもまた結果は同じ。なかには「ほら、家のなかに入っておいで。まさにいま、私の妻が息を引き取ったところだ。お前の赤ちゃんと同じ、あのはやり病で……」と悲痛な顔で彼女を招き入れる者もいたぐらいです。
「その日暮らしの私や、あの路地裏の住人と違って、食べものにも着るものにもあまり困っていないような家でも……」と、キサーゴータミーがガックリと肩を落としてしまったのは言うまでもありません。それから3日3晩のあいだ、彼女はほとんど一睡もせず足を棒のようにしてサーヴァッティのあらゆる場所を歩き回りましたが、やはり返ってくるのは「悪いなあ……」「申し訳ないけど……」という言葉ばかり。思いつめた彼女は、最後に緊張した面持ちで、宮殿のような大豪邸に向かいました。
そこは、このサーヴァッティの町一番のお金持ちと言われる長者の家。「このお家ならば、みんな毎日美味しいものを食べて優雅に暮らしているから病気にかかることもないだろうし、高いお金を払ってお医者さんに診てもらうこともできるだろうし、ケシの実の一粒ぐらい……」と思ったものの、彼女にとっては雲上人どころか異世界の住人と言えるほど高貴な、そして縁遠い存在ですから、おいそれと頼みごとをするわけにもいきません。それでも彼女は必死の思いで門番に理由を告げて、長者に会わせてもらえるようにお願いをしたのです。
すると、ほどなくして彼女はその広々とした大豪邸へと招き入れられました。ふわふわの絨毯。宝石を散りばめた椅子。壁には数億円は下らないと思われるピカソの絵がデカデカと……ごめんなさい、時代と場所を間違えてしまいましたね。それはともかく、何もかも彼女が見たこともないようなものばかりで、こんな豪華で贅沢な暮らしをしている家で死者を出すなど思いつくはずもありません。そして金糸と絹であつらえた服を着た長者がゆっくりと現れると、キサーゴータミーに「これを見なさい」と語りかけ、静かに巻物を広げ始めました。
よく見ると、その巻物は家系図。「これが私の祖母で、喉に果物を詰まらせてあっけなく逝ってしまったんだ。この伯父は3年前に葬儀をしたのだが、その前に何年も病に苦しんでいてね。そうそう、ここにあるのが私の15番目の息子だ。この前の戦争で敵に討たれてしまったよ。そしてつい先日、この曾孫が庭の池に落ちて……」と、長者はテーブルの端から端まで広げた家系図を指でなぞりながら一人ずつ、亡くなった身内のことを切々と語るではありませんか。そして最後に「キサーゴータミーとやら、そういうわけなのだ」とおもむろに呟き、家系図にある自分自身の名前を指しながら「私だって、もしかしたら明日にはもうこの世にいないかもしれない。でも、それがいつになるかは私にはわからない。お前もそうじゃないかね?」と、ため息をつくのでした。
誰もが、いつかは
次の日。キサーゴータミーは疲れ切った足取りで、お釈迦様が瞑想に耽っている森へと再びやってきました。その気配を感じたお釈迦様はゆっくりと目を開け、キサーゴータミーがそれに応じるようにお釈迦様の前に座り声を震わせながら「ケシの実は……」と言いかけたのですが、彼女はそのまま言葉を止めてしまいます。もちろん、ケシの実を探し出すまでは諦めないので待っていてほしいとお釈迦様に告げることもできたでしょう。そうしないと、いまも抱きしめている赤ちゃんは生き返らないのですから。
しかし長い沈黙の後、キサーゴータミーは何日も腕に抱き続けていた、そして冷たくなった赤ちゃんの亡骸をそっと手放すとお釈迦様の前に寝かせて「……ありませんでした」と声を絞り出すように呟き、「でも、私は分かりました。実は生きている人よりも死んだ人のほうが多くて、そして死んだのは私の子どもだけではない、ということを」と言葉を紡ぎ出しました。彼女にとって、それを告げるのは辛く悲しいことに違いありません。でも、お釈迦様はそれを待っていたかのように静かに頷いて彼女の言葉を受けとめると、次のようにキサーゴータミーへと語りかけました。
「よく分かりましたね、キサーゴータミー。そう、誰もが、いつかは、死ぬ。そして、そのことを誰もが本当は心のなかに思ったり感じたりはしているのだけれど、『分かる』者は少ない。しかし、あなたは分かった。人間だけではありません。命あるものは全て、ろうそくの灯が消えたり点いたりするように、生じたり滅びたりする。でも、それを分からないまま100年生きるよりも、そのことを分かって1日生きることのほうがすばらしい」
大きなお城に住んでいる偉い王様2)でも、ありとあらゆる金銀財宝を集めたお金持ちの長者でも、日々の暮らしに苦しむ貧しい者でも、どこの国に生まれても、どの時代に生きていても、この世に生まれついた者はいつか死ぬ。そのことを語るには、「人は誰でも死ぬのだから」とただ一言告げるだけでもよかったはずです。しかし、お釈迦様はそうしませんでした。もしかするとお釈迦様のようなお方ならば、それこそ摩訶不思議な神通力でも用いて赤ちゃんの息を吹き返らせることもできたのかもしれませんが、それもしませんでした。
1日でも一瞬でも、生きているということはただそれだけで、すばらしい。そしてキサーゴータミーのような辛い出来事を経て、何かを心のなかに得て生きることは、もっとすばらしい。そのすばらしさはあなただけのものではなく、「あなたと、あなたと一瞬でも共に生きていた赤ちゃんのもの」で、だからこそ他の誰にも奪えない。お釈迦様は、そうキサーゴータミーに伝えたかったのでしょう。その後の言い伝えによると、キサーゴータミーは出家して比丘尼(びくに)に、つまり尼僧になってお釈迦様と一緒に旅をして、自ら大勢のお弟子さんを導く存在になったのだそうな。
「ケシの実を一粒、持っておいで」という言葉は、彼女がこれからの人生を送るために処方した、お釈迦様なりのグリーフワーク(グリーフケア)の「お薬」だったのかもしれませんね。
2)そう言えばお釈迦様自身も、王様ではありませんがシャーキヤ族=釈迦族という人びとが統べる王国の紛れもない王子様でした(なので、シャーキヤ=釈迦とも呼ばれているのです)。仏教に明るい読者の方々は「四門出遊」のエピソードもおそらくご存知でしょう。まだ王子様だった頃のお釈迦様がある日、生まれて初めてお城を出てピクニック(?)へと出かけることになったのですが、城門を出ようとするときにヨボヨボになった老人に出会い、悲しくなって引き返してしまいました。その後、気を取り直して別の城門から出かけようとしたら、今度は門にもたれかかって苦しんでいる病人を見かけ、「人生はこんなに苦しいのか」と思ってまた引き返すことに。さらに別の城門に行くと、今度は死んだ人間の亡骸が……。その後は言うまでもありませんね。そして四度目にして、またまた別の城門から出かけようとすると、そこには悟りを求める修行者が。その姿を見て、お釈迦様は出家を決意したというエピソードです。ちなみにワタクシの知り合いは、若い頃に「ギタリストになる!」「デザイナーになる!」「漫画家になる!」とか宣言してはすぐに飽きて止めてしまうということを繰り返していたのですが、挙句の果てに「オレ、役者になる!」と親に告げたところ、母親から「お釈迦様じゃないんだから、いい加減にしろ!」とこっぴどく叱られたそうな。まあ、四門出遊の話とは似ても似つかない次元ではありますが、これもまた「母と子のものがたり」ということで。

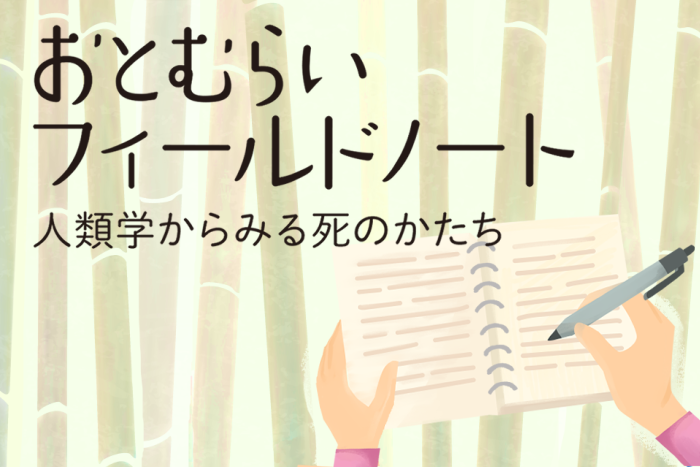


_1695266438714.png)