看護師の方々から、「まだ小さな子どもの患者さんの死に立ち会うのは、本当につらい」という話をよく聞きます。もちろん全ての患者さんの生命は平等で、お年寄りであろうが子どもであろうが年齢でその重さが変わるわけではなく、その崇高な理念を看護に携わる全ての皆さんが強く意識されているのは言うまでもありません。ただ、理性ではよく分かっていても、言語化しがたい感情がどうしてもあふれてしまうのでしょう。そして、その気持ちは子どもに先立たれてしまう親であればなおさらのことです。
おとむらいの文化を研究しているワタクシも、「子どもの死」という悲痛な場面にときどき出会うのですが、そんなときにいつも思い出す古い物語があります。どれだけ古いのかというと、今からおよそ2500年前のこと。というわけで、今回はあるひとりのお母さんの話をしましょう。そう言えば、その他におそらく誰もが知っている人も登場します。もしかすると「人」ではないかもしれませんが。
お願いだから……
むかしむかし。日本から遠く離れたインドに、「ここに来ればなんでもある」と言われるほど栄えたサーヴァッティという町がありました。通りにはいつも多くの人があふれ、さまざまな国からやってきた商人や旅人が行き交い、その賑わいと華やかさは本当に目を見張るような光景であったそうな。
ある日のこと。ひとりの女性がサーヴァッティの町をふらりふらりと彷徨っていました。砂漠でオアシスを求めるように虚ろな目をしていて、その足取りは今にも倒れてしまいそうです。身につけている衣服も体も汚れ切って、髪は乱れたまま。彼女が道を歩いていると街路にごった返していた人びとは、まるで腫れ物に触れるような目つきをして、そそくさと左右に分かれて彼女を避けました。たしかに、彼女の心は散り散りに引き裂かれて明らかに錯乱しており、高熱に冒されたかのごとく焦点の定まらない瞳を宙に泳がせてブツブツと何かをつぶやいてるのですから、周りの人びとが不気味に感じて避けてしまうのも当然といえば当然なのかもしれません。
とは言え、なぜ彼女がそうなってしまったのかは誰の目にも明らかでした。彼女の名前は、キサーゴータミー。サーヴァッティの片隅で貧しさに喘ぎながらも夫と仲良く暮らしていたのですが、昨年その夫に先立たれてしまいました。もちろん、それも彼女の心を悲しみの底に落としていた原因のひとつではあります。でも、まだ彼女には心の支えが残されていたのです。それは、旅立ってしまった夫との間に、つい数ヵ月前に生まれた最愛のわが子。
ところが、無情な運命が彼女を襲いました。その子どもがようやく両足で立てるようになった頃、はやり病に罹って夫と同じように息を引き取ってしまったのです。おそらく皆さんもご存知のように、かつては世界中のどこでも、生まれたばかりの赤ちゃんが亡くなってしまうということは現代と比較にならないほど多い出来事1)ではありました。だからといって、子を失った母親の悲しみは今も昔も変わりません。キサーゴータミーはもうどうしていいか分からず、肌が土気色に変わって硬くなっていく赤ちゃんの亡骸を胸に抱きしめて、「お願いだから、生き返らせて……」「お願いだから、私の可愛い赤ちゃんを返して……」と、うわ言のように唱えながら、サーヴァッティの町を当て所もなく迷い歩いていたのです。その姿を見た町の人びとは、キサーゴータミー自身があの世でさすらう亡者になってしまったかのような不気味さを覚えはしたものの、彼女の境遇を思えば誰もが「かわいそうに」「何とかしてあげたいけれど……」と同情しました。でも、どうすることもできません。
そのお薬を知っている人を、知っている
一方その頃。あるひとりの尊いお方が弟子たちをつれてサーヴァッティに近い森を訪れていました。先ほど、むかしむかしのインドと聞いて、「もしかしたら」と思った方もいることでしょう。そのお方の(人間としての)名前はゴータマ・シッダッタ。そう、現在の私たちがお釈迦様や仏陀と呼んでいる、仏教を開いた聖人です。しかし、いくらお釈迦様とはいえ、とりあえず現世では生身の肉体なのですから何かを食べないわけにはいきませんし2)、それは弟子たちも同じこと。弟子の一人がサーヴァッティの市場に皆の食べものを買いに行くと、あのキサーゴータミーが疲れ切った姿でうずくまっていました。
見れば、彼女はますます正気を失って、目の前を過ぎる人びとに物乞いをするかのように「誰か私の赤ちゃんを生き返らせるお薬をくれませんか。何でもします。何でもしますから。お願いだから……」と弱々しい言葉で呼びかけているではありませんか。言うまでもなく、死者を生き返らせる薬などありません。けれども、その切ない光景をみた弟子は、自分の師であるお釈迦様ならば何とか彼女を悲しみの底から救い出してくれるかもしれないと思って、こう語りかけました。「お母さん、残念ながら私自身はそのお薬は知りません。だけど、そのお薬を知っているかもしれないお方を、知っていますよ」と。
その言葉を聞いたキサーゴータミーは、冷たくなった赤ちゃんの亡骸を抱きしめながら一瞬にして生気を取り戻したかのように立ち上がり、一縷の望みを賭けて「本当ですか。もしも本当ならば、もう私の命を投げ売ってもかまいません。ぜひ、そのお方のもとに連れていってください」と弟子にお願いしました。彼女にとってそれは偽らざる本心であり、わが子が生き返ってくれるのであれば、代わりに自分の命を差し出してもよいと思っていたのです。
さて、その後。弟子とキサーゴータミーは、森の奥で静かに瞑想に耽っていたお釈迦様のもとを訪れました。いったい、そんなお薬を手に入れるにはどのようなことをしたらよいのだろう。一生かかっても支払うことができるかどうか分からないようなお金が必要だろうか。それとも、本当に自分の命を差し出さないと手に入らないような魔法のお薬なのだろうか。そんなことを考えていた彼女は、お釈迦様におずおずと「私の赤ちゃんを生き返らせるお薬を知っていますか」と問いかけました。すると、お釈迦様はゆっくりと瞑想から目覚めて、穏やかに「ええ、知っています」と言葉を返しました。もうそれを聞いただけで、彼女はお釈迦様が座っている足元にすがりつき、泣きじゃくりながら何度も何度も「ありがとうございます」とお辞儀をしたのは言うまでもありません。
しかし、続けてお釈迦様が告げた言葉を聞いて、彼女は目に涙をためながらも思わず呆気に取られてしまったのです。それは、その場にいた弟子も同じでした。だって、そのお薬のつくり方は、まったく想像を絶するものだったのですから。
あぁ……でも、今回もまた紙幅が尽きてしまいました。まあ、紙じゃなくてパソコンで書いてるんですけどね。さてさて、お釈迦様がキサーゴータミーに伝えた「死者を生き返らせる薬」とは、一体どうやってつくるのでしょうか。せっかちな読者の方は前回と前々回に続いて「また“続きはCMの後で”なのか!」とお怒りになるかもしれませんが、どうかお許しを。えっ、「ネットで検索して調べるからいいよ」ですって? それも止めませんけれど、ほら、何と言いますか、余韻を残すというのも世知辛い昨今では大事なことじゃないですか。……などと言い訳を重ねつつ、この物語3)の続きは次回の後編までお待ちくださいませ。
2)余談ですが、一説によるとお釈迦様が亡くなったのはキノコの料理で食当たり(?)になったからと言われています。意外と人間臭い……と言ったら不謹慎でしょうか。
3)実はこの物語は仏教学などの分野で「キサーゴータミー説話」として知られているもので、きわめて初期の仏典に登場するだけでなく、日本でも子ども向けの童話などに意訳されています。なので、こんなに勿体ぶらなくても、すでに知っているという読者の方は多いかもしれませんね。なお、このキサーゴータミー説話はそれぞれの時代ごとの仏典で微妙に内容が異なっていたりもするのですが、今回のコラムで書いた説話の大意は主に赤松孝章氏による論文「キサーゴータミー説話の系譜」(高松大学紀要, Vol.34, pp.1-15,2000)を参照させていただきました。

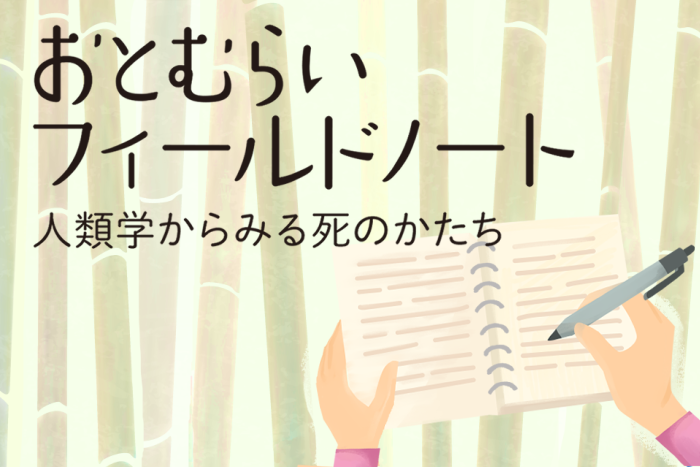



_1685342416837.png)
