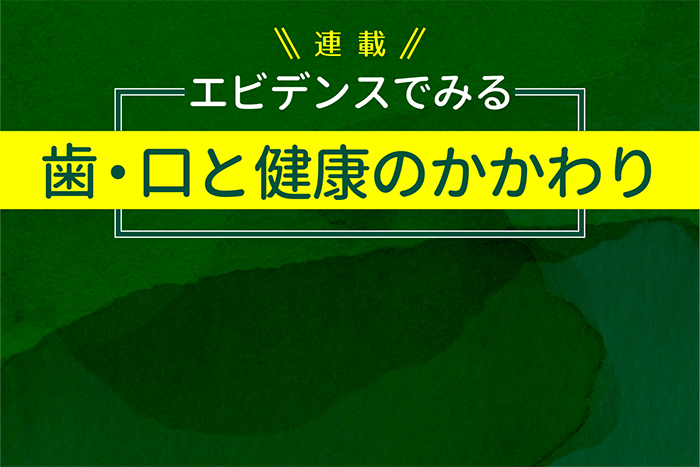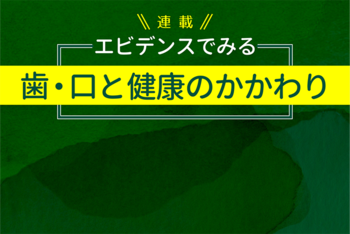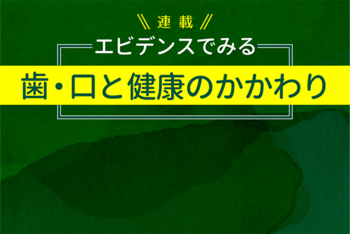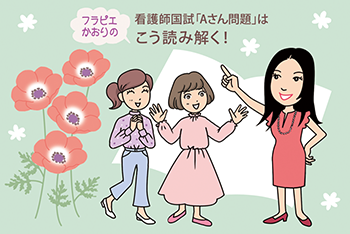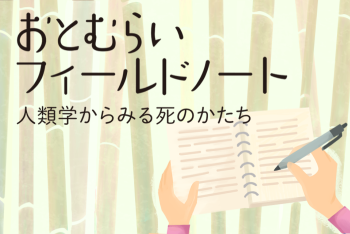口臭には様々な原因がある
近年、“スメル・ハラスメント”という言い方もあり注目を集める「口臭」。他人の口臭は分かるとは言え、自分の口臭はなかなか気付きにくいものです。長く続いたコロナ禍で毎日のようにマスクを装着し、初めて自分の口臭に気付いた人も多いのではないでしょうか。
口臭というと、原因には口腔内が衛生的ではない、体質、あるいは、ニンニクなどを食べた後を想像するのではないでしょうか。実は他にも原因があり、以下のように大きく5つに分けられます。
①生理的口臭
誰にでもある臭いで起床直後や空腹時、緊張時には特に強まります。VSC(揮発性硫黄化合物)が臭いの主成分です。
②飲食物・嗜好品による口臭
ニンニク、ネギなどの食品や酒、タバコ等の嗜好品による一時的な口臭です。
③病的口臭
歯周病や舌苔、舌がんなどの口腔が由来の場合と、鼻・喉(のど)の病気、呼吸器系の病気、消化器系の病気や糖尿病、肝臓疾患などの口腔以外(全身)が原因で起こる場合があります。
④ストレスによる口臭
ストレスで唾液が減少し発生する口臭です。
⑤心理的口臭
実際には社会的容認限度を超える臭いはないが、自分自身で強い臭いがあると思い込むもの。仮性口臭症とも呼ばれます。
実は思い込みの口臭も多い
口臭で歯科を受診される方の口臭の原因を調べてみると、心理的口臭(仮性口臭)であることが実は多くあります。実際に筆者も何度も経験しています。
●エビデンス
少し古いデータですが、1999年に新潟大学の宮崎秀夫氏らの報告によると、新潟大学歯学部附属病院・口臭クリニックの初診患者210名に対して口臭の原因を調べると、病的口臭が最も多く(40%)、次いで仮性口臭症が35%を占めていました(図1)。仮性口臭症は生理的口臭(21%)よりもかなり多くなっています。
[宮崎秀夫ほか:口臭症分類の試みとその治療必要性.新潟歯学会雑誌 29(1):11-15,1999より引用]
口臭の異常から推察される病気とは?
口の中が清潔に保たれ、かつ臭いの原因となる、または推測される食物を食べていない場合、口臭の原因として考慮する必要があるのが先述の分類で示した「病的口臭」です。
たとえば、胃の酸が食道に逆流して炎症などを引き起こす「逆流性食道炎」や胃の粘膜が傷害される「胃潰瘍」だけでなく、時には「便秘症」といった腸の疾患も含めて、様々な疾患が口臭と関わることが明らかにされています。
また、舌がん等の口腔内のがんや消化器系、呼吸器系でがんが発生した場合、がんに侵されて腐敗した組織の悪臭が口を通して不快な口臭として感じられることもあります。
肝臓の機能が低下した肝硬変や肝臓がんでは、食物の代謝などで発生する体内のアンモニアを尿素に変えて解毒し体外へ尿として排出する肝臓の機能が低下するため、アンモニア臭(肝性口臭)が認められます。
歯科の定期健診で来院されたTさん(60代、男性)は「歯の調子はいいんやけど、体調がいまいちでな」とのこと。内科を受診したかと尋ねると、「まだやねん」とのお返事。よく見ると顔色は黒ずみ、アンモニアらしき臭いもあるため、歯科の後で内科受診を勧めました。
翌日、パソコンでTさんの内科カルテを確認すると、「肝硬変」の文字が。口臭が病気のサインになることを実感した体験でした。
糖尿病に特有な口臭
現代の国民病である糖尿病と歯周病の関係は第5回で紹介しましたが、その糖尿病のある人は特有の口臭がすることが知られています。糖尿病性口臭は熟し過ぎた果実のような甘酸っぱい臭いが特徴で、臭いの原因物質がアセトンであることが明らかにされています。
●メカニズム
糖尿病が進行するとインスリンの低下により糖がうまく代謝されなくなり、その代わりに脂肪やタンパク質がエネルギー源として使われます。その際、代謝産物としてケトン体という物質が生成されますが、アセトンはこのケトン体に含まれるのです。
●エビデンス
2014年に公表されたオックスフォード大学の研究報告では、アセトン臭と血中のケトン体の濃度の関連性を調べました。
この研究では呼気に含まれる微量のアセトンを検出する携帯型の検査機器が開発・使用されました。研究チームは、オックスフォード小児病院に通院する7~18歳の子ども113人、および20人の1型糖尿病の子どもを対象に、開発した検査機器を用いて試験しました。その結果、呼気のアセトンが血中のケトン濃度に相関することが確認されました(図2)。
糖尿病が進み、体内のケトン体濃度が上昇した状態を放置してケトアシドーシスになると、喉の渇きや頻尿、全身の倦怠感などの症状が現れます。さらに悪化すると、呼吸困難や意識障害、昏睡等の命に関わる危篤状態につながる可能性があります。
ですから、特有の甘酸っぱい口臭が強くなった場合は、医師の診断を仰ぐなどの早急な対応が必要となります。
口臭予防の基本は歯磨き(口腔ケア)
以上のように、全身性の病気が由来の口臭もありますが、何と言っても多いのは歯周病などの口腔内が由来のものです。ですので、口臭予防のために一番大切なのは、やはり歯磨き(口腔ケア)です。口臭の原因となっている食べかす(食渣)を歯ブラシで丁寧に取り除くだけでなく、臭いガスを放出する歯周病菌などの細菌も排除するのです。
また、口臭の原因で大きなものの一つに舌表面の舌苔があります。舌の表面が白かったり茶色かったりして舌苔がある人は、専用の舌ブラシを使った舌清掃をお勧めします。
さらに、清掃不良な義歯も口臭の原因となります。しっかりブラシでこすり洗いした後に洗浄剤に浸け置きするようにして下さい。
これらの口腔ケアを徹底しても異常な口臭が持続する場合は病的口臭の可能性がありますので、速やかに医療機関を受診するようにしましょう。
* * *
ところで、口臭については、親しい間柄でも相手に伝えるのはちょっとした勇気が必要で、誰かに指摘される機会も少なく、なかなかデリケートなものでもありますね。
この厄介な口臭を客観的に評価するのが、口臭測定器。吐く息に含まれるVSC(揮発性硫黄化合物)の濃度を測定し、数値化して口臭を評価します。一般の歯科医院等にも置いている場合があるので、興味があれば問い合わせてみて下さい。
【参考文献】
1)島谷浩幸:歯科から見る農作物と健康(5)農作物と歯磨きで爽やかな息に.農業および園芸(養賢堂)97(10):922-925,2022