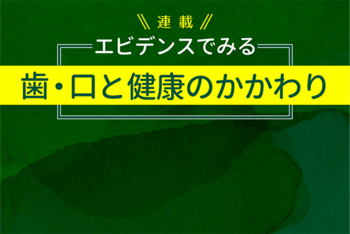恩師の一声で教員として戻った母校
5年間の臨床経験を積んだのち、母校に戻り教員として看護基礎教育に携わることになった。学生時代に担任として受け持って頂き、非常にお世話になった恩師から声がかかったのだ。卒業の際にも恩師からは「いつか学校に戻ってほしい」という言葉を頂いていた。しかし、高校卒業後に福岡の実家を離れて奈良の学校に入学した私は、いずれは福岡に帰りたいという気持ちもあり、母校で看護教員になるというビジョンは全くなかった。正直なところまだ臨床にいたい、もっと自分の看護を実践したい、という気持ちもあったが、「先生(恩師)が言うなら」と異動の打診を引き受け、私は思ってもみなかった看護教員としての道を母校で歩み出すことになった。
力を秘めた原石たる学生たちと教員としてかかわり続ける毎日は、当初の想像以上に楽しいものだった。とくに実習において、学生と共によりよい援助を目指して看護計画を立て、彼らがすばらしい看護を実践できた時のうれしさは計り知れなかった。自分の考えるよい看護を精一杯彼らに伝えて「この人に看護してもらいたい」と言われるような看護師を育てたい、という目標もできた。教育をもっと深めたくて、がむしゃらに教え自らも学んだ。
その反面、仕事にのめり込みすぎてふたりの娘たちに寂しい思いを何度もさせてしまった。
娘たちがまだ小さかったある休日のこと。家族4人で遊園地に行く約束をしたのだが、ちょうど出かける直前に突然自宅の電話が鳴った。担任として受け持っていたある男子学生の母親からだった。かねてより学生から「情緒不安定な母とどう接すればよいのか」と相談を受けていたため、私は電話が長引くことを悟ったが、彼女の話を聞かないわけにはいかなかった。当時は携帯電話などなかったから、リュックを背負い帽子をかぶって準備万端になった幼い子どもたちの前で、私は二時間半近く学生の母親と電話をした。
その翌日、娘たちに「ママは学校のお姉ちゃんたちのほうが(私たちより)大事?」と聞かれた。何ということを言わせてしまったのだろうか…。電話を切らなかったことに後悔は一切ない。しかし、子どもを優先してやれなかった引け目を感じ、教員を辞めるべきなのかと悩んだ。そして頼ったのが、上司となったかつての恩師だった。「子どもたちはちゃんとあなたの背中を見ているよ。あなたが一生懸命仕事をすれば、きっとまっすぐに育ってくれる」と相談に乗ってくれた先生の言葉に、奮起せねばならないと決意を抱いた。
あまりに突然の恩師との別れ
知らぬ間に進行していた恩師の病
学生時代は教員として、母校に勤務し始めてからは上司として育ててくれた恩師は、「この人にだったらついていきたい」と思わせてくれる人だった。数え切れないすばらしい人たちと出会い、支えられてきた人生だが、恩師からは看護師、看護教員としてだけでなく、主婦として、母としても様々なことを教えてもらってきた。とくに子育てをしながら教員としてここまでやってこられたのは、やはり恩師の存在が大きい。ふたりの娘を産んだ者同士、その背中を追い続けてきた。
しかしある時、恩師に病気が見つかった。発覚した時にはすでに手がつけられない状態にまで進行していたのだった。当時教務主任だった恩師はホスピスに入院することになり、急遽学校を去った。そして私はその後任となった。右も左も分からない、引き継ぎもできないままだったが、同僚(現在の教務主任)と「とにかくがんばろう」と励まし合いながら管理業務や学校運営に取り組んだ。仕事をこなしながら、奈良の学校から大阪のホスピスまで週に1回はお見舞いに通った。目に見えて衰弱していく中でも、恩師はたくさんのことを教えてくれた。業務はもちろん、「あなたにはずっとこの学校に残って教育をしてほしい」「学校を頼んだよ」と繰り返す恩師から、本学の教員としての心を引き継いだ。

同僚の中嶌 雅子(なかしま・まさこ)先生(中央・現在の同校教務主任)
もう一度だけ、教壇に立ってほしい
「もう一度、恩師に教壇に立ってもらわないといけない」。慣れない業務に追われ毎日を過ごしていたある日、ふとそう思った。恩師の中で、教育への情熱はまったく消えていない。それなのに、挨拶もできないまま学校を去ってしまうなんてだめだ、という思いが唐突に頭をよぎったのだ。ちょうど11月に差しかかったばかりの頃だった。
突然の思いつきではあったが、学生たちや教員に「11月3日は祝日だけど、できる限り学校に集まってくれないか」とお願いをした。恩師の状態を説明して「先生の“最期の授業”を行いたいのだ」と伝えると、学生たちは休みの日にもかかわらず校舎の一室に集まってくれた。恩師のご家族にも協力を頼み、ご主人と当時大学生、高校生だったふたりの娘さんに学校まで付き添って頂いた。私にとっては賭けだった。自分の勝手で強行した“最期の授業”によって、もしかしたら恩師の病状が悪化してしまうかもしれない。それでも、これだけ看護基礎教育に尽くしてきた人がもう教壇に立てないなんて…、という思いが勝ったのだ。
恩師は元来、学生に弱い姿を決して見せない人だった。それは“最期の授業”当日も変わらなかった。車いすで移動する恩師の姿が学生の目に触れないよう、私は集まった学生たちに教室の中で待っていてほしいと伝えた。介助を受けながら教室まで辿り着いた恩師は、日頃床に臥していることなど全く想像もつかせないほどに、しゃんと背筋を伸ばして教室に入っていった。
この時恩師が残してくださった言葉を、なぜだか私はひとつとして覚えていない。それでも、思いのままに語る恩師や静かに耳を傾ける学生、若い教員たち、教室の窓越しに見守るご家族の姿…当時抱いた感動とその場の光景は今も脳裏に焼きついている。
“最期の授業”は家族にとってのグリーフケアに
恩師のふたりの娘さんは、私の娘と同じように「ママは学校のほうが大事なんだ」と思って育ってきた子どもたちだったのだという。幼少期からずっと、彼女たちは母親が仕事に打ち込むことに対してよい印象がなく、そのことに恩師自身も苦しみ続けていたのを、私は知っていた。
そんな彼女たちは“最期の授業”の日、「来てよかったです」とわざわざ私に声をかけてくれた。恩師の周りに学生たちが集まる様子を見て「母が仕事が好きだった理由が分かりました」とも言ってくれた。彼女たちがふとつぶやいた「母はすごい人だったんですね」という言葉に感じた気持ちは、一生忘れないだろう。そうだよ、あなたたちのお母さんはすごい人だったんだよ。恩師の娘さんたちにそう伝えられたことが、何よりもうれしかった。
当時、恩師の娘さんたちはすでにそれぞれの夢に向かって、母親とは違う道を歩み出そうとしていた。ところが今、お姉さんは教員として、妹さんは看護師として働いているという。“最期の授業”は学生や教員へのメッセージとなっただけでなく、母親が看護教員として生きてきた証を目の当たりにするという、彼女たちにとっての最良のグリーフケアにもなったのかもしれない。そう思うといっそう喜びがこみ上げる。
“最期の授業”から1ヵ月後、ちょうど年末までに提出が必要な実習施設変更申請の書類作成に追われているさなかの12月4日、恩師は息を引き取った。未だにこの話をすると、涙をこらえきれないことがある。それでも、この経験を毎年私は必ず学生たちに伝えている。恩師自らの後押しもあり、「その人らしく生き、その人らしく最期を迎えられるよう援助する」看護の尊さを、今に至るまで語り続け、教材とさせて頂いているのだ。
すべての経験、すべての出会いのおかげで教員を続けられた
こうして振り返ると、楽しいことや面白いと感じたことだけでなく、苦い思い出や辛く厳しい経験であっても、どれも今の私の糧になっているのだと実感する。経験を通して得た人との出会いや気づき、心の動きといった全てによって、私は看護教育を続けている。
迷い悩むことは何度もあったが、今は教員を辞めずここまでやってきて本当によかったと心から思えている。娘たちは優しい子に育ってくれた。長女は理学療法士として、次女は教員として社会に出た。医療従事者に教育者、看護教員という私のアイデンティティをちょうど半分こしたような進路に、彼女たちにも少しは母親としての背中を見せられたのではないかと思う。あの時、恩師が言ってくれた通りだ。そして私はもうすぐ「ばぁば」になる。
この先もまだまだ大切な人たちと出会う機会は続くだろう。これからも人とのかかわりを楽しみ、人への感謝を忘れずに、残りの教員人生を楽しみたい。