今回のコラムをお届けする時期は、七十二候で言えば梅子黄(うめのみきばむ)の季節。その名が示すように梅の実が熟してくると、もうすぐ夏という気分が徐々に高まってくるのを感じます。そうそう、梅と言えば「東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 主なしとて 春を忘るな」なんていう歌もありましたね。梅の実ではなく「花」なので、季節はちょっと遡りますけれど。
それはさておき、この歌を詠んだのは学問の神様にして、天神様の愛称でも親しまれている菅原道真。道真を祀る天満宮は全国各地にありますから、読者の皆さんも受験や国試などに際して道真に祈願をされたこともあるのではないでしょうか。そう考えると老若男女を問わずトップクラスの人気度を誇る神様ですが、実はこの菅原道真は人気だけでなく別の意味でもトップクラスかもしれません。では、どんな意味で……?
非業の死を遂げると……
皆さんもおそらくご存知のとおり、菅原道真は平安の世に生きた実在の貴族で、天才の名をほしいままにした人物。それがあるとき突然失脚させられて、京の都から遠く離れた太宰府へと左遷されたまま朝廷に舞い戻ることもなく、失意の内に亡くなったエピソードで知られています。現代の感覚からすると「何かと慌ただしい都であくせく働くよりも、地方でノンビリできてよかったのでは」なんて思う方もいるかもしれませんが、とんでもありません!そんな生やさしいものではなかったのですよ。
朝廷のほぼ頂点に位置する右大臣の官職にあったにもかかわらず、ほぼ何の権力も持たない地位に降格させられて、「現地へは自腹で行くこと。給料は今後一切なし。仕事もなければ部下もいませんのでよろしく」なんて言い渡された挙句、衣食住にも窮する極貧の生活を強いられたわけですから。つまり「野垂れ死にしろ」と流刑を宣告されているようなもの。ちなみに道真を排斥しようと企んだのは、ただいま某大河ドラマで恋に政治に大活躍中(?)の藤原氏の面々とされています。道真が生きていた頃はそのドラマよりもだいたい半世紀から1世紀ぐらいは遡るのですが、もうその時には藤原氏が権力の中心を占めており、家柄ではなく自分の才覚でどんどん出世を重ねていく道真は疎ましい存在だったのでしょう。
というわけで先ほどの「東風吹かば」の歌にしても、梅の香りが漂ってくる風雅な情景を詠んだようにも思えますが、実は都を離れるときの悲痛な心情が込められているのです。そして左遷からわずか2年後の延喜8(908)年。道真は自らの不遇を嘆きながら、大宰府で息を引き取りました。もう、これを非業の死と言わずして何と言ったらよいでしょうか。しかし話はここで終わりません。というよりも、ちょっとばかり不謹慎ではありますが、むしろ道真は亡くなった後から本領を発揮するのです。それでは菅原道真が死後どうなったかというと……。

そう、道真は今回のタイトルにあるように最強にして最「恐」レベルの怨霊と化してしまったのでした。まあ、あんなにヒドくてムゴい仕打ちを受けたのですから、無理もありません。では道真の祟りとはどのようなものだったのかというと、道真を左遷に追い込んだ藤原時平をはじめ、藤原氏の血筋を引く者は皇族に至るまでバタバタと若くして亡くなるという事態が相次いだばかりか、上の図で描かれているように内裏(だいり)のど真ん中に天を割くような雷が落ち、大勢の死者が生じるという凄まじいことに。転げ回って逃げまどう貴族たちの姿はどことなくユーモラスにも見えますが、怒りに満ちた雷神となって情け容赦なく雷を落としている道真の姿は、もう「人ならざるもの」としか言いようがないですね。まさしく天変地異にして大災害と言えるその猛威に、当時の人びとは「祟りじゃーっ!」と恐怖をおぼえながらブルブルと震え上がったことでしょう。
御霊信仰
とは言え、もちろんこれは想像力のなせるわざ。本当にこんな災いを菅原道真がもたらしたのか、そして怨霊なんて存在するのかと問われれば、私も含めて現代人のほとんどは「いや、それはちょっとありえないでしょ」と答えるに違いありません。しかし、それはあくまで現代からみた話であって、当時の人びとにとっては道真のように非業の死を遂げた者の魂が怨霊と化してしまうことも、その怨霊がもたらす災厄をいかにして避けるかということも、かなり現実的で切実な問題でした。では、その問題をどうやって解決すればよいでしょうか?
まずは、ひたすらゴメンナサイと謝って怨みを鎮めてもらうことが思い浮かびますね。たとえば菅原道真の時代よりもさらに遡る奈良時代末期のこと。桓武(かんむ)天皇の弟にして皇太子でもある早良(さわら)親王が、とある暗殺事件に関与していたという罪を着せられて、無実を訴えるために絶食したまま憤死するという事件がありました。その直後から貴族たちが相次いで不穏な死を遂げ、おまけに都に疫病が大流行して洪水まで起きるという事態となったために、時の朝廷は早良親王に陳謝するためのさまざまな儀式を行ったと伝えられています。また、怨霊に関する研究で名高い三重大学教授の山田雄司氏によると、怨霊という言葉が初めて現れたのは、この早良親王について書かれた歴史書の記録なのだとか1)。
そしてゴメンナサイだけでなく、怨霊を神格化して悪から善に変わってもらうということもよく行われていました。つまり、祟りによって人を呪い殺したり、疫病や洪水などの災害を引き起こしたりする力があるのならば、それはもう「神様」に違いない。ならば「よい神様として祀る」ことによって、災いではなく福をもたらしていただこう……ということですね。このような信仰のありかたを「御霊信仰(ごりょうしんこう)」と呼びますが、この点について、宗教学者の藤井正雄氏による指摘を以下に参照してみましょう。
生前において自らの意志を全うできなかった人間、意に反して横死した人間は、その死後にも遺念余執が残るとされ、それゆえにタタリ(祟り)という形態をとって、残された生ける人びとに悪い影響を与えることから、その横死した人間を神として祀り上げるという風習がある。(中略)この根底には古代・中世以来の御霊信仰が存している。
上記の通り、怨霊を神として祀って、崇敬の対象である「御霊(ごりょう)」に転換するという宗教観は、日本には古くから存在します。菅原道真も鎮魂のために各地に社殿が建立されるようになると、「怨霊という側面が希薄になり、菅原氏の家職としての儒家との関わりで、儒家の神、さらには詩文の神として崇められるようになった」2)。そして先ほどの早良親王に加えて、保元の乱で讃岐に流された崇徳(すとく)天皇(崇徳院)や、朝廷に対抗して討伐された平将門など、御霊信仰に根ざした崇敬の対象となっている歴史上の人物は枚挙に暇がありません。さらに社寺を建てて祀るだけでなく、かつては疫病や災害が生じるたびに、それらの災いをもたらしたと思われる怨霊を鎮魂するための御霊会(ごりょうえ)という儀式が宮中行事や祭礼として盛んに行われていました。かの有名な京都の祇園祭も以前は「祇園御霊会」と呼ばれていて、怨霊を鎮めて疫病の災いを払うことを祈願するための紛れもない御霊会だったのです。
もっとも、現在でも大きな災害や事件が起こるたびに「それは死者の祟りのせいだ」とか、「人びとの行いが悪いから怨霊が災いをもたらしたのだ」などと語る人はいます。いくらおとむらい研究者とはいえ、私自身はそういう語り口に与することは絶対にできませんし、現実に被害に遭っている人びとの心情を思えば尚更のこと。ただし御霊信仰とまでは言わずとも、死者への畏怖というものは、現代人でも心の片隅に持っていても良いような気がするのです。ウクライナしかり、ガザしかり、今日も世界のどこかで大切な命が戦火により無残に失われていますが、もしかすると戦争や紛争を抑止する最大の力は地雷でも核ミサイルでもなく、「死者に対する想像力」なのかもしれないな……などと思ったりもする今日この頃です。さて皆さんはいかがでしょうか。
1)山田雄司:もののけ・怨霊・御霊.民俗学事典,民俗学事典編集委員会(編),p.550,丸善出版,2014
2)山田雄司:跋扈する怨霊,p.82,吉川弘文館,2007

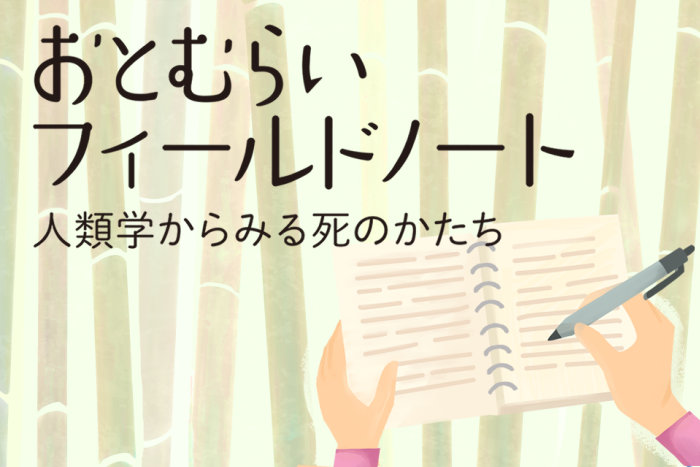

_1685342416837.png)


