助産の現場で感じた怖さから、法科大学院へ
私は「お産を呼ぶタイプ」の助産師らしく、新人時代には先輩から「金子と一緒の勤務はいつも忙しくなるよね~」と言われていた。分娩介助の経験が積めるありがたさと、多忙な日になる苦しさとの板挟みだった。勤務のたびにお産があり、時間に追われて淡々と業務をこなし、ケアの振り返りが不十分になった。「もっと対象者にていねいにかかわりたい」という想いに反して余裕のない日々が続き、自責の念に駆られ、そこに疲労感が重なりバーンアウト気味になった。
そんな中、分娩中に突然、常位胎盤早期剥離が起き、急速遂娩になった事例があった。スタッフ全員で力を合わせて対応したが、生まれた児は全身紫色で弛緩しており、NICUへ搬送された。やれることを全力でやった状況だったが、先輩がこぼした「赤ちゃんの予後によっては訴えられたりするかもね…」という言葉が心に重く響いた。医療者が誠心誠意対象に向き合っていても、トラブルやミスは起きる。医療訴訟が起きやすい産婦人科で働く中で、いっそうその怖さを感じ、多忙を極める医療者を法律はどのように護ってくれるのかと興味をもった。そして医療職の立場が分かる弁護士になろうと法科大学院に入学した。
大学院で法律を学び、自分の性質に気づく
お互いの権利が衝突して紛争が生じたとき、公平に問題を解決するために法律が適用される。他者と向き合って、自己の権利を守るために対峙する…。それが法律の世界だった。こちらにも相手方にも正義があり、折り合いがつかないとどちらかが勝ち、一方は負ける。法律の勉強は楽しかったが、「私は人と対峙するよりも、同じ方向を見つめ、寄り添い、ともに歩みたい」と改めて思った。そして、「患者に伴走する医療者」という仕事が自分の性質に向いているのではないかと気づいた。
再び、助産師としてお母さんたちに寄り添いたい
法科大学院生のときに自らが妊娠出産を体験し、年配助産師の手厚く温もりのある援助を受けて、「私も助産師として、もう一度お母さんたちを支援したい」と実感した。
大学院を卒業したものの司法試験は受けず、再び助産師としてレディースクリニックに勤務し、妊婦健診や母乳外来を担当した。自分の出産育児体験を踏まえてより具体的な保健指導が行えるようになり、お母さんたちの気持ちにじっくりと向き合え、充実した毎日だった。保健指導を通して、共感・受容する、労わる、相談にのる、自己肯定感を向上させる、エンパワメントする、レジリエンスを高めるという役割を担い、やりがいを感じた。
看護専門学校の専任教員へ
その後、助産学校時代の恩師からお声がけいただき、母校の実習担当教員を経て、現職である公立春日井小牧看護専門学校(以下、カスコマ)の教員になるに至った。子どもの学校生活に合わせやすい教員の仕事は、自分のライフステージとちょうど合っていた。
カスコマは、愛知県春日井市と同小牧市が共同で設立し、運営している。地域社会に貢献できる看護実践者の育成を目指しており、学生の多くが両市の市民病院に就職し、地域の高度医療を支える重要な役割を果たしている。
カスコマに入職した当初の私は、「カスコマは職業訓練校だから、学生に看護に必要な基本的知識・技術・態度をしっかりと身につけさせ、社会のニーズに対応できる看護師に育てたい」という想いが強かった。そのために「私が」「先輩看護師として」「社会人として」必要だと考えていることを、学生にしっかりと「教えなければならない」という気持ちでいた。今思えば、教員からの一方通行な価値観や常識の押しつけを学生にしていたことが多かったと思う。学生との距離感も遠かった。
そんな私を変えたのは、看護教員になって4年目、初めて1年生の担任をしたときの経験だった。右も左も分からない新入生を受け持ち、私自身も新たな気持ちで、常に学生の立場に立って考えながらクラス運営をするように気をつけた。学生が問題を起こしても、先入観を持たず批判的にならず、まずそれに至った経緯を確認し、学生の気持ちを大切にした。卒業後にその学年の学生が「出来のいい学年ではなかったが、先生が自分たちを最後まで信じてくれていたので、それに応えたい一心でみんなで努力できた」と言ってくれた。その言葉を通して、「教えられる」「やらされる」ではなく、学生が「自ら学ぶ」「やろうとする」ように、見守る、寄り添う、信じることが教員の仕事なのだと、改めて気づいた。
法科大学院に通っていたときに気づき、助産師として保健指導をしていたときに大切にしていた「伴走者」の立ち位置を、どうして「教員」として教壇に上がった途端に見失ってしまったのだろうと反省した。また、卒業生からの「カスコマで学んだことで一番大切だったのは、『看護の心』だったと思います」という言葉を聞いて、胸が打たれた。「今、仕事でうまくいかなくて悩むこともあるが、学生時代に体験した『看護の楽しさ』を思い出すと、頑張る力が湧いてくるんです」とも言われた。
信頼できる教員の温かな見守りのもと、知識の連結が楽しいこと、患者に合ったケアを創造することの歓び、やりがい、自己効力感、チームメイトとの協力の大切さなどの体験を得て、看護の厳しさを乗り越えられる力を養う…、そんな教育を学生は必要としているのではないか。新人看護師の離職率が高いなか、タフに長く看護を続けられるための「看護の心」「看護の楽しさ」を、看護学校でていねいに育んでいく必要性を感じた。
「カスコマ」で、人としても看護教員としても、学生とともに成長していく
看護教員になるまでにいろいろな職種を経験し、紆余曲折があった。しかし、今までの人生の中で一番長く楽しく仕事ができている。育児・家事と仕事の両立は大変だが、カスコマの上司や同僚はいつも親身に相談に乗ってくれ、ライフワークバランスが図れるようにお互いに協力している。教員である私自身も、信頼できる教職員に見守られながら、自分らしく充実した日々を過ごせている。
私にとって看護教員は自ら目指した仕事ではなく、恩師の助言などに導かれて、「気がついたらなっていた仕事」という印象がある。最近読んだ本に、『使命は向こうの方からやってくる』と書いてあり、それが心に響いた。私の人生において「看護教員」が「使命」のひとつであるならば、なおいっそう真摯にこの仕事に向き合い、学生とともに成長し続けなければならない。アットホームなカスコマの雰囲気の中で、尊敬する上司や同僚と力を合わせて、学生の伴走者として、ともに未来へ歩んでいきたい。


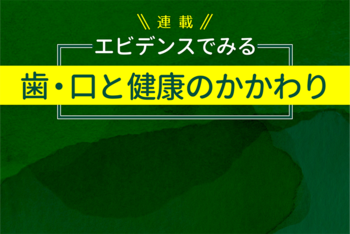


_1640312949187.png)