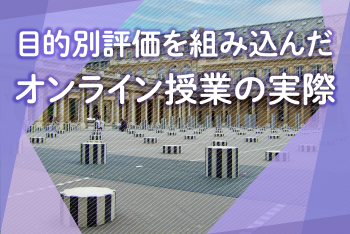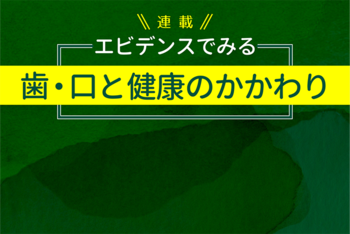人には、誕生から死まで、たくさんの「セレモニー」があります。看護学校職員になった私は、入学式や卒業式という人生の節目・門出を祝うセレモニーの主催者側になりました。そのセレモニーに参列している学生や保護者にとっては、今このときが分岐点です。そんな彼らの姿を見ながら、ふと私自身の分岐点は……と考えると、あの選択をしてよかったと思えることもあれば、タイムリープし再チャレンジしたくなることもあります。今回は、その一部を紹介します。
私のセレモニー:看護師人生のスタートライン
私が中学2年生のある日祖父が入院していた病棟の師長から「お孫ちゃん(私のこと)、怖くないの?」と廊下で声をかけられました。というのも、当時の私の記憶では、祖父の手足はガリガリの真っ黄色、目も黄色、私と叔母さんを間違える。そんな状態でした。しかし、私は祖父の手浴や足浴を看護師さんと一緒に週2回ほど、数カ月間にわたって行っていたのです。「怖くないです。私だけでも手を洗えますか」と当時の私は答えたそうです。そんな中学生の姿が病棟内で話題になり、病棟師長から、高校の衛生看護科を紹介していただきました。スタッフのみなさんが、面会にきた親戚にも「お孫ちゃんは(看護師に)向いてる」とも言ってくださり、その気になった私を含めた家族は、中学生で看護師という職業を選択しました。この病院は祖父が最期を迎えた病院でもありますが、私の看護師人生のスタートラインでもあり、今でも外観を見るたびに初心に戻れる場所でもあります。
実は、この病院には、附属の看護学校(全日制3年課程)がありました。それなのになぜ師長は、高校普通科を卒業後にこの附属看護学校に進学することを勧めなかったのか? と考えたこともあります。ひょっとしたら、地元に若者を残す、労働者の確保など、社会の流れや大人の事情があったかもしれません。師長の本意はわかりませんが、私にとっては自分の将来が決まる大きな分岐点となりました。
ある患者とのセレモニー:看護師としての後悔が残る記憶
晴れて看護師となったのち、救命救急センターに配属されたばかりのころにも、分岐点となる出来事がありました。当時のセンター長から「救命は、最後のセレモニーの場でもある」と配属初日に言われたものの、そのときはセンター長の言葉がピンとこなかったことを記憶しています。しかし、私はその言葉の意味の重さを日に日に実感していくことになりました。
ある日、交通外傷の60代女性Aさんが搬送されてきました。私は、彼女が持っていたというぐちゃぐちゃになったイチゴのホールケーキを救急隊から預かりました。Aさんは、いつ心停止するかわからない状態で、家族の到着を待っていました。そのとき、「お母さん!」と叫び声が聞こえ、振り返ると、新生児を抱いた若い女性が立ちすくんでいました。その若い女性は、Aさんの娘さんでした。抱いていた赤ちゃんは、Aさんの初孫さん。Aさんは、本日退院された娘さんに会いに行く途中で交通事故に遭ったようでした。私は、ビニール袋に入れた衣服や救急隊から預かったケーキを娘さんに渡しました。娘さんは、「こんなの(ケーキ)いらない。これさえ買わなかったら…」と、それを拒否しました。赤ちゃんを抱きフラフラの、現実を受け止められない娘さんの姿が目の前にありました。
当時の私は、決められたことを忠実に行うことしかできず、あのケーキも決まり通り家族にお返ししました。しかし今でも、「あのケーキは、家族にとってどんな存在なのか?」「病院で処分するべきだったのか?」と思うことがあります。死亡確認・エンゼルケア・霊安室への移動と時間が過ぎてゆく中、抱っこ紐を使わずに両手で新生児を抱き続けていた娘さんに何かできたのではないかと、患者さんと家族に十分な配慮ができず、最後のセレモニーを最良にできなかったと、今でも後悔しています。
ある学生たちとのセレモニー:医療者として、患者の死を受け止める
最後は、看護教員という立場になり、患者さんとの関係性も変化してきたころの話です。ある実習施設に、学生たちがたいへんお世話になった、Bさんという患者がいました。Bさんからは、1年生の基礎実習や3年生の領域別実習などあらゆる実習で、学生が全身全霊で学ぶ機会をいただきました。Bさんは「学生には未来がある」と言われ、学生のどんな失敗に対しても温かく、チャンスをくれる方でした。私に対しても、「看護教員はとてもよい仕事、よい看護師を育ててね」と笑顔でおっしゃいました。
しかし、そんなBさんの病いは進行していました。そしてある日、病棟の指導者から「Bさんが、いよいよだと思う。学生さんたちに会いたがっていた。話せないかもしれないけど病棟にこられないか?」と朝に電話がありました。その施設に附属の学校であったため、授業を調整し、昼休みに学生たちを連れてBさんのもとへ行きました。病棟に到着すると、指導者から「何日か前の夜勤のときに、Bさんが学生さんたちに手紙を書いて床頭台に入れていた。勝手に出すわけにもいかないし……。本当に会いたがっていたから、間に合って良かった」と言われました。病室に入ると、Bさんは努力呼吸で、まだ少し意識があり、3年生の声掛けにも頷いてくださいました。1年生は、ビックリしたようすでドアの前に立ちすくんでいましたが、3年生が手を握るように促しました。学生たちに囲まれて、Bさんはやがて息を引き取りました。
昼休みの数分間でありましたが、Bさんに会うことができ、学生たちが医療者として死を受け止める姿から、私は彼らの成長を感じました。また、プロの看護師ではなく、学生という存在にしか患者さんに与えられない何かがあることに気づきました。Bさんは、学生の成長という変化を毎回感じ楽しんでいたのかもしれません。それ以来、実習指導に対する私の考え方は変化しました。看護師免許取得後30年になってしまった私には不可能な「学生にしかできないこと」があると思い、学生指導をしています。患者さんの死によって、その方の姿としての存在は終わります。しかし、それは残された人の何かの始まりでもあり、いろいろな意味でのセレモニーなのかもしれません。

看護教員は、はじめてユニフォームを着る、はじめてスタッフステーションに入る、他人に身体にはじめて触る、患者さんとかかわるなど、学生の「はじめて」に立ち会います。学生にとっての節目(セレモニー)です。看護教員として、そのセレモニーが充実したものになるよう裏方として支えてゆくのが、私の役割だと今回のリレーエッセイから気づきました。主演女優として初エッセイに取り組ませていただき、ありがとうございました。


_1685342416837.png)