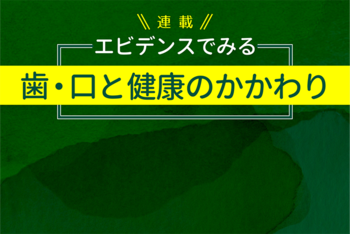「人には理(ことわり)がある」「その人の可能性を信じる」。私自身がそのような眼差しに恵まれ、歩みを支えてもらった。何年経っても簡単ではないけれど、看護教員として人として、自分のそういう眼差しが誰かのちょっとした支えになり、次はその誰かから他者へ、というようにつながり、循環していくと良いなと思う。
学生だった私が受けた、あたたかな眼差し
私の生家は経済的に余裕が無く、私の下には勉強好きな弟や妹が控えていた。なりたい職業は教師だったが、強い意思がないなら遠慮した方がいいと思った。一方、看護師には、進学費用が格安で生涯働ける職業、「手に職」というイメージがあったため、第2の選択肢となった。シスター寺本松野著『看護のなかの死』1)を読み、ターミナル期の人の人生に看護の主体性と独自性をもってかかわる仕事に魅力を感じたことで、私は看護師となる道を選んだ。
入学した看護学校は軍隊を連想するところだった。寮の規則は細かく、門限に遅れると上級生でも寮生全員の前で糾弾された。知識は「注入」されるが腑に落ちず、臨地実習を丸ごと任された指導者から感情的に詰問された。ケアリングが感じられない看護職の姿に失望し、教員や指導者たちから語られる「看護」に不信感を抱いた。私は彼らに反発するように投げやりになり、成績も低迷した問題のある学生だったと思う。
それでも、当時出会った教務主任のY先生とZ先生を信頼できたことが、私の心を看護につなぎとめた。お二人が語る「看護」には、人間への愛があふれていて素直に惹かれた。それに、学生を尊重する態度と、看護への向き合い方の間に矛盾がなくて心に沁みた。問題児だった私は、ここに書けないようなこともしたが、Z先生は私の話を聞いて目をつぶってくれた。私と向き合い、おそらくご自分の責任で卒業まで見守ってくれたのだと思う。私が教員になったとき、同窓会に行くとZ先生が壇上で挨拶をするよう勧めてくださった。私の成長を捉えて喜んでくれていることが伝わり、ありがたかった。
私を理解し可能性を信じてくれたその姿勢は、「人には理がある」という私の人間観へとつながっている。看護学生時代には、患者さんにも助けられた。こんな私に愛情深く心と身体を差し出してくださった。そして、卒業前も看護師となってからも見守ってくれる先輩方、尊敬できる師長、主任、私を尊重し可能性を信じてくださったたくさんの方々により、軍隊式の“北風”には頑なだった私が、暖かな“太陽”によって溶かされ成長させてもらった。
語り合うことで自分や相手を見つめる場を作る
縁あって看護教育に携わり、かつてなりたい職業であった教師になった。志が近い仲間と話をしながら、本来どうしたらよいのか、正解の定まらないことをあれこれ考えてきた。仲間と語り合った経験は、対話的なリフレクションそのものである。聴いてくれる人の存在を得たとき、語る言葉が生まれる。うまく表現できずくすぶっていた私の思いは語る相手の存在でほぐされていった。
「看護教員には、リスペクトしあい安全に語り合える場が必要だ。そこから違う景色が見えてくる」。自身の経験からそう考え、修士課程の在学中に看護教員のリフレクションの場「リフレの会」を作った。休止期間も挟んだが、形を変えながら現在まで続けて取り組んでいる。リフレの会の活動の中で、看護や教育の対象となるその人を、また語り手と自分自身とを重ねあわせながら理解しようとするとき、「この人はだからこうしたのか」「私はここに価値を置いているのか」といったことが見えてくる。それはその人の、あるいは自分自身の理ではないかと思っている。そして、学生に対しても、「患者さんの理を見つけてくれたらいいな、一緒に考えたいな」と願っている。
現状を超えてゆく学生の実践
時に学生がすごい力を発揮してくることがある。彼らは臨床で「こういうものだ」と思われがちなことを、患者さんにコミットして新しい眼差しで突き抜けていく。
たとえば、かつて私が担当した学生Aさんは、40歳代の男性である患者B氏を受け持っていた。B氏は、最初に受けた糖尿病の指摘を20年に渡り放置していた。しかし、数年前に糖尿病性足病変で感染を起こし初めての医療を受けた。片足の切断に至った後、受け持ち時も足の感染で入院治療中であった。Aさんが糖尿病や合併症の話をしようとしてもB氏に「大丈夫だから」といってかわされ、とりつく島がなかった。そしてそれは看護師に対しても同じであり、看護師たちは諦めているように見えた。
Aさんと知恵を絞り、AさんからB氏に「自分が勉強してきたので一緒に聞いてもらえないだろうか」とお願いした。すると、“上から目線”の「指導」ではなく、あくまで学生自身の勉強に付き合ってもらえないかというお願いが、B氏の「年長者として学生の学びを応援したい」という素直な気持ちを引き出したようだ。AさんはB氏に「勉強してきた」と言って伝えたいことや考えてほしいことを共有した。そのうちにB氏から自分自身の気持ちや背景を語ってくれるようになった。生活保護を受けながら知人に仕事を紹介してもらって夕方から朝まで働いていること、生活保護の受給に必要な要件である寮生活をしており、入浴時刻が決められているので夜に仕事をしていると入浴できずシャワーもないこと、共同のキッチンは狭く料理をする環境ではないこと、などである。つまりB氏に標準的な食事指導やフットケアを伝えても実施は難しく、療養生活には独自の工夫が必要であった。Aさんは一つひとつB氏に提案しながら、実現可能な療養をともに考え、B氏も自分事として受け止め考えるようになった。
その人の可能性を信じて、回る好循環
このような学生のケアリングは、専心没頭2)といわれるように、自分の受け持ち患者に一生懸命にかかわりその人を理解しようとする姿勢から生まれる。諦めずその人の可能性を信じて挑む学生の力に目を見張るし、誰もが何かのきっかけで力を発揮するときがあると思う。かつてのくすぶっていた私では遠く及ばないが、学生が専心没頭できることに感嘆する 。私を信じてもらえたように、私も誰かの可能性を信じて応援したい。学生の可能性を信じ、学生は患者の可能性を信じる。そうした好循環が生まれると良いなと思う。それは、自身の可能性を信じることにもつながっている。
1)寺本松野:看護のなかの死,日本看護協会出版会,1975
2) Noddings N:ケアリング―倫理と道徳の教育―女性の観点から(立山善康ほか訳). 晃洋書房, 1997


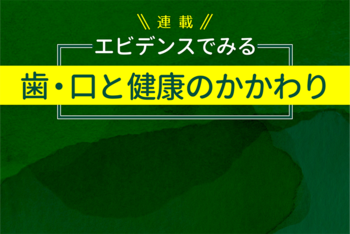
_1647426327768.png)