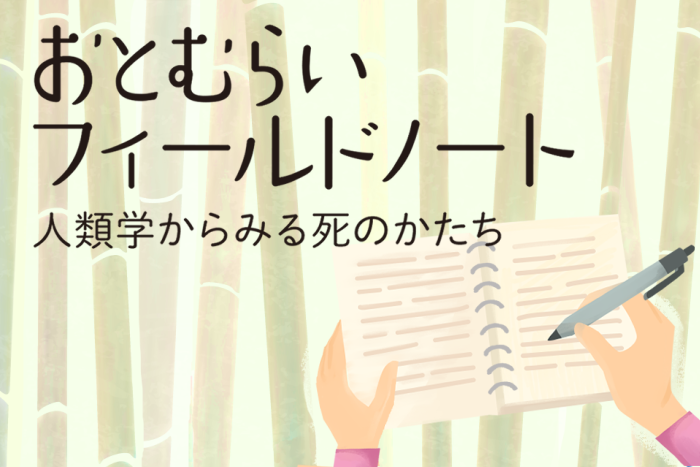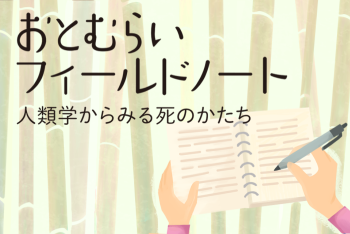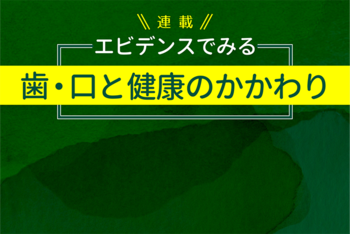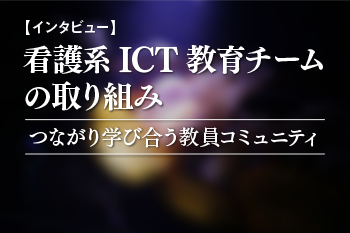すでに暦の上では立秋を過ぎました。季節の挨拶としては「残暑お見舞い申し上げます」ということにはなるのでしょうが、残暑どころか酷暑に精も根も尽き果ててしまっている方も多いはず。それでも夏は楽しいイベントが目白押しです。そんな楽しい夏の風物詩と言えば、これはもう誰もが真っ先に「盆踊り」を思い浮かべるに違いありませんよね!
えっ、たしか前回も同じようなことを言っていた? しかも「盆踊り」ではなく「肝試し」だったような? いやいや、それはほら、いわゆるデジャヴっていうヤツですよ。「そうだ、前回の原稿をコピペすれば横着できるぞ!」などと悪だくみをしたわけでは、決してありま……いや、その……。
「盆」って一体なに?
……まあ、それはともかく、盆踊りが今も昔も変わらず「日本の夏」の情景として思い浮かぶというのは、あながち間違いではないようにも思うのです。
炭坑節やら東京音頭やらの曲に合わせて、櫓(やぐら)の上から太鼓の音が響いては夏の夜空に吸い込まれていく。その櫓を浴衣姿の老若男女がぐるりと取り囲んでは楽し気に踊り、さらにその周囲を取り巻く夜店では子どもたちが小銭を握りしめては焼きそばにしようか、それとも金魚すくいにしようかと迷っている。私などはそんな、ちょっと昭和的な思い出がよみがえってきますが、さて皆さんはいかがでしょう。
ところで、そもそも盆踊りの「盆」とは一体何なのでしょうか? 盆踊りだけでなく「お盆」という言葉自体もまだまだ健在ですから、ある程度のイメージは湧くかもしれませんが、ここでちょっと確認しておきたいと思います。
<盆>
旧暦7月15日を中心として先祖の霊魂を迎え供養し、まつる行事。家ごとに先祖諸霊を仏壇や盆棚に迎えて供物をささげると同時に、先祖の遺体が眠る墓地への墓参も併せ行われる。その淵源は中国西晋(265-316)の竺法護訳『仏説盂蘭盆(うらぼん)経』にもとづく盂蘭盆会(うらぼんえ)に求められ、『日本書紀』推古14年(西暦606)7月15日の設斎の記事が日本における初見である。その後、天皇を中心とする古代の貴族社会で行われてきた仏教行事であるが、中世、近世と長い歴史を経る中で広く民俗の伝承としても多様な展開を見せている。1)
上記の引用にある通り、盆というのは「先祖の霊魂を迎え供養し、まつる」ための夏の一時期のことであり、またその間に行われるさまざまな行事や習俗のことも指すわけですが、源流をたどると非常に古い歴史を持つことを察してもらえることでしょう。とはいえ、まだ皆さんの頭のなかには「じゃあどうして『盆』って言うの?」という疑問が残されていますよね。
実は、よく分かっていないところも多いんです。お盆の起源をさかのぼると、今から約1400年前の『日本書紀』で盂蘭盆会について触れられており、その盂蘭盆会が『仏説盂蘭盆経』という中国で編まれた経典の教えに基づいて行われたと書いてあるのは間違いない事実。そしてこの『仏説盂蘭盆経』は、お釈迦様の十大弟子の一人である目連(もくれん、モッガッラーナ)が、地獄に堕ちて苦しんでいる自分の母親を助けたいのにどうにもできず、お釈迦様に相談すると「修行に励んでいる僧侶に食べものを捧げるなどして、母親のための供養をしなさい」と告げられたのでその通りにしたところ、母親は立ちどころに地獄から救い出されて極楽に迎えられたという「目連救母」の物語を元にしていることで知られています。でも、この経典には「盂蘭盆」という名前がついているくせに、その言葉の意味や由来は明示されていないんですよ!まったく、ちゃんと書いてくれないと後で困るんですよね……ブツブツ……。
と、昔々の偉いお坊さんにこんな理不尽な愚痴を言ったワタクシ自身が地獄に堕ちてしまいそうですが、それはさておき、近年まで盂蘭盆とは、唐の時代に中国で編まれた『一切経音義』という、経典の解説書のような文献に出てくる「ウランバナ(ullambana)」という梵語(サンスクリット語)のことだろうと推測されていました。『一切経音義』では、「ウランバナ」を中国語に訳して漢字に置き換えると「倒懸」、すなわち目連の母親がまさに地獄で味わっているような「逆さまに吊られているかのような苦しみ」という意味であると述べているので、お盆=盂蘭盆会とはそのような苦しみに喘いでいる先祖を地獄から救い出すために、せっせと供養する儀式や行事のことだという意味にも取ることができて、何となくつながったような気もします。
ところがどっこい、「ウランバナ」も「倒懸」も、最近になって初期の経典には全く見当たらない言葉ということが分かってきました。それでは日本における「盆」という言葉と発音の由来であり、前述の『仏説盂蘭盆経』にも用いられている「盂蘭盆」という言葉は、一体どこからやってきたものなのか? 現在では3世紀以降のイラン系ソグド人の言葉で「死者の霊魂」を意味する「ウルバン(urvan)」から来ている2)とか、出家した人に捧げるための「ご飯を盛ったお盆」を意味していたとされるサンスクリット語「オーダナ(odana)」の音が変化した「オーラナ(olana)」なのではないか3)等々、いくつかの説が示されています。たしかに、いずれも現在のお盆に連なる意味合いには当てはまりそうな言葉ですから、何ともこれは甲乙つけがたいところです。人類学者としてはできれば紀元前にタイムスリップして、お釈迦様の弟子になってフィールドワークして探ってみたいところですが、たぶん初日でギブアップしちゃうだろうなあ……。
迎えて、送って、集まって
今回は「お盆の謎」などというタイトルをつけておきながらモヤっとした感じが残ってしまいましたが、実を言うと謎はまだまだ残されています。ええ、分かっていますよ。「盆踊りって、一体いつ頃からあって、そもそもどうして皆で踊るの?」って聞きたいんでしょう。まあ、自分で最初に盆踊りがどうのこうのと書いてしまったから自業自得ですよね…。
しかし、最初に宣言しておきますが、これもまた結構分かっていないことが多いのですよ。歴史の記録をたどると、すでに室町時代の文書には「盆ノオドリ」という記述が出てくるのですが、これは現在のように地域の人びとが集まって親睦を深めるといった趣旨よりも、むしろ中世の庶民文化に浸透しつつあった風流(ふりゅう)、すなわち非日常の趣向を凝らした芸能や芸術全般のトレンドを背景とするものでした。何かと慌ただしく、ままならないことも多い日常生活から解放されたい人びとが、誰とはなしに思い思いに着飾って、あるいは奇抜な仮装をして市中に繰り出しては踊り明かす。言ってみれば、室町時代の「土曜の夜はディスコでフィーバー!」(古い!)といった感もあったのかもしれません。
一方、この流れとはまた別ではあるものの、上記の風流にも相通ずる「念仏踊り」も盆踊りの源流の一つに位置づけることができます。これは元々、平安時代の僧であった空也(903-972)から始まったと言われていますが、皆さん、どこかでこの空也の姿を見たことがありませんか? ほら、口から「南無阿弥陀仏」を象徴する6体の仏様を出している、あの何とも味わいのある彫像ですよ。

空也は後世に「市聖(いちのひじり)」という名でも呼ばれているように、高僧でありながら世俗の人びとと密接に触れ合い、また鉦(かね)や太鼓を鳴らして踊りながら念仏を唱える「踊り念仏」を通じて仏教の教えを一般大衆に広めたことで知られています。そして今でもこの「踊り念仏」の流儀は、空也が創建した京都の六波羅蜜寺で毎年12月に行われる「空也踊躍(ゆやく)念仏」という年中行事として伝えられているんですよ。
ここで、おそらく「あれ、“踊り念仏”って言ってるけど、“念仏踊り”じゃなかったの?」と気づいた人もいるはず。そう、この区別はちょっとばかりヤヤコシイのです。「踊り念仏」という場合は、あくまで念仏を唱えるという仏教儀礼としての意味合いに比重が割かれているのに対し、これが徐々に民間に拡大して芸能化・娯楽化していったものを「念仏踊り」と指すことが一般的です。とは言っても、両者は明確に区別できるわけではなく、また現在も各地で「念仏踊り」と称して行われている習俗は多々あり、単純に括れないほど多彩なことも事実。要するに、現在の盆踊りは先ほどの「風流」に属する市井の習俗や、今述べた「踊り念仏」や「念仏踊り」の所作、そして土地ごとの多種多様な習俗が混ざり合って出来上がったと考えることができるため、一口に盆踊りと言っても、その源流には色々なものが存在するのです。

ただ、それらに共通する背景には、やはり最初に述べた「先祖の霊魂を迎え供養し、まつる」という人びとの思いが深く横たわっていると言ってよいでしょう。たとえば福島県のいわき市を中心として伝えられている「じゃんがら念仏踊り」では新盆(にいぼん)を迎えた家に、つまり去年のお盆からの1年間で新たに死者の出た家に鉦や太鼓を鳴らしながら近隣の人びとが訪れて、その家の庭や軒先で死者を供養するために踊り、終わると今度はまた次の家へと向かいます。古式ゆかしく「念仏踊り」の名を残している地域の盆踊りでは、この事例のように新盆の家に踊りの担い手が出向くという形式を伴う場合が少なからず見られますが、校庭や広場などに不特定多数の人びとが集って輪になって踊るという現在の一般的な形式であっても、踊りが一段落する(あるいは一曲が終わる)たびに「次はぁ~、田中家ぇ~」とか「田中家のためぇ~」というようなアナウンスを入れる地域もあるんですよ。これは要するに、「じゃあ次の踊りは、新盆を迎えた田中さんの家のために、そしてお亡くなりになった○○さんの供養のために」と皆に告げているんですね。
このように、盆踊りの源流をたどると、死者を迎え、供養してまた送り返すための行事でもあり、皆が集まって楽しむための機会でもあったのです。迎えて、送って、集まって、過ぎゆく夏の楽しい一時を記憶に留めながら、亡き人にも思いを馳せる。こんな夏の風物詩が、これからもずっと続くといいですね。
1)新谷尚紀:「盆」,民俗小辞典 死と葬送,新谷尚紀,関沢まゆみ(編),p.246,吉川弘文館,2005
2)同上, 「盂蘭盆会」, p.250
3)KARASHIMA, Seishi:“The Meaning of Yulanpen 盂蘭盆: “Rice Bowl” on Pravāraṇā Day”, 創価大学国際仏教学高等研究所年報16: 289-305, 2012