臨床時代、副看護師長に就任して病棟の臨地実習指導者となったことが、看護教育の道を歩み始めるきっかけだった。実習指導者講習会で成人への教育と高等学校以前の教育の違いに触れ、実際に講習会受講生の立場として実習先の病院で指導を受ける経験をした。そこで指導者として、学習者とどう接するとモチベーションを高く持ってもらえるのか、安心して学んでもらえるのかを体感し、教育の面白さを知った。この経験を機に、まずは臨床教員として学生たちとかかわっていく道を選んだ。
ひとりよがりな指導では伝わらないことに気付く
臨床教員となって日々実習指導において学生と向き合うにつれて、ほとんどの学生は看護の基本となる「人体の構造と機能」を押さえられていないのだと分かってきた。たとえば「胃は何をしている臓器なの」と質問すると、「胃酸を出している」「タンパク質を分解している」と回答してくる。つまり枝葉のような細かい内容は覚えていても、肝心の本質、ここでいう「胃は食物を消化する臓器である」ということを捉えられていないのだ。学生の頃から解剖生理学が好きだった私は、なぜ彼らが人体のしくみに興味を持てないのか、解剖生理学の意義や面白さを感じ取れないのかが不思議で仕方なかった。そのため、私の指導は必然的に身体のはたらきを理解させる方向に傾けられた。
そんな中、唐突に学生に泣き出されたことがあった。実習中の控え室、病棟実習を終えて戻ってきた彼女に指導をしている最中だった。コミュニケーションもしっかり取れていて、指導者として良好な関係を築けていると思っていた学生だったため、なぜ泣いているのかが全く分からず焦って話を聞いてみると、「先生の言うことは回りくどい、よく分からない」と言われた。衝撃的だった。
思い起こすと、この時私は“言わせたい回答”を頭の中に想定しながら、それを学生の口から聞けるまで何度も発問して待ち続けるような指導をしていた。私自身の理解のスタイルに沿った指導方法だったのだが、この学生にとっては何を求められているのかが分からず、泣くほどに追い詰められるものだったことに初めて気付いた。この方法が彼女の理解しよう、がんばろうという気持ちを引き出すどころか、かえって不安にさせてしまったのだろう。
追求していく聞き方で理解が進む学生もいれば、まず指導者が答えを示したうえで考えてもらう方がよい学生もいる。患者と同じで学生にも個別性があり、全員一律の働きかけでは通用しないのだ、と自身の指導方法を反省し、見直す機会となった。
その後は看護師スタッフへの指導とは学習者が違うことを踏まえ、もっと学生たちのことを知るように努めた。レディネスを把握し理解度を探って、学生にどんな筋道で伝えることがよいかを見極めるため、トライアンドエラーを繰り返して伝え方を考えた。枝葉を見がちな学生にもまずは「知っていること」が素晴らしいのだと伝えて、できていることを認めてさらにできるよう声かけを重ねた。
このように学生との対話を繰り返す中で、「解剖生理学がなぜ大事で、看護にどう活かせるのかをもっと多くの学生に伝えたい」「知識を得ることを目的にするのではなく、根拠や明確な意図をもって観察やケアができる看護師を一人でも多く育てたい」という気持ちが強まっていった。それなら教育機関であれば、病棟以上に多くの学生とのかかわりを持つことができ、伝えたいことを今以上に多くの学生に伝えられるのではないか。そう思うようになり、私は臨床を飛び出して看護教員になることを決めた。
学生の「分かった!」を引き出すための追求
大学の教員になってからも、「学生にいかにして分かりやすく伝えるか」「どのようにして本質をつかんでもらうか」を追求して試行錯誤し続けてきた。「どうしたら解剖生理学への興味を持たせられるか」は難しいテーマであり続けているが、生理的な現象を身近なものに例えたり、教材を工夫したり、臨床教員時代の経験を生かして発問の仕方についても学生の個別性に合わせられるよう試みてきた。その結果、学生たちが目を輝かせて「分かりやすかった」「もっと早く聞きたかった」と言ってくれた時は、やはりとてもうれしいものだ。
彼らの「分かりやすかった」には、「難しい知識を得るだけではなく、教員の問いかけを通して自分が理解できる(している)範囲の知識から、その答えを導き出せたことがうれしい」という成功体験も大きく影響すると考えている。そういったうれしさや分かりやすく伝えられたキャッチーな事柄は学生の印象に残りやすいし、忘れない。それが結果的に患者に起きている症状や疾病、またさらに本質的なことへの理解につながる機会になればと思っている。
私の指導がきっかけで循環器看護の道を選んでくれた学生
キャリアを積んでようやく分かってきたことだが、学生は目の前に出されたものを学ぶ、という高等学校までの学び方に慣れているので、「何のためにこれをしているのか」が理解できていないことが多い。たとえばこれはどんな薬で、体の中のどこに反応して、どんな作用が起きるから症状がどのように良くなるのか、という作用機序の流れを飛ばして、「この薬はこの疾病で使う」と暗記的に覚えるようになっているのだ。だから、学生に発問していく中でどこまで分かっていて、どこから先が分かっていないかの境目を探って、その境目にアプローチしていくことが大切なのだと考えている。
かつて、担当していた大学2年生が実習で患者のバイタルサインを測定していたが、話を聞いてみると測定の意図を全く理解していない、ということがあった。測らないといけないから測る、測るかどうかが大事で、データが得られればそれで満足、といった具合だ。そこで、バイタルサインを測定することが患者の状態判断につながることに気付いてもらえるように、血圧の算出式を示して「なぜこの情報とこの情報を掛けるのだろう?」「それぞれの情報の数値が変わる時は、何が影響しているだろう」と一緒に考える時間を設けた。彼は何もかもが分からない状態だったから、「最初から全部分かろうとしなくてもいいから、自分の中で引っかかるところ、考えられそうなところを見つけてそこだけは理解しよう」というスタンスで問いかけたし、何よりまずは仕組みが分かることの楽しさが伝わるように試みた。
この方法は彼に合っていたようだった。私の指導がバイタルサインについての理解を深めただけではなく、彼が循環器看護の魅力に気付くきっかけとなっていたと知ったのは、当人から国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)に就職したと報告された時だった。就職先を選んだ理由のひとつとして、当時のことを話してくれたのだ。自分とのかかわりが「看護職としてこの分野を専門にやっていきたい」という思いにつながったことはもちろん、彼はこれからも循環器に関する知識や技術を臨床でしっかり身につけ、それを患者に還元してくれるだろう、という期待を持てたことはこの上ない喜びだった。
“教える”のではなく“伝え”、共に学び続けたい
ここまで意図的に“教える”という言葉を使ってこなかったが、これは私が日頃から“教える”のではなく“伝える”という姿勢で学生たちと学び合いたいと強く思っているからだ。教育を通していろいろな課題にぶつかることはいつだってあるし、自分の教育に満足しているわけでもない。考え方ひとつではあるが、“教える”立場となるとそれが言動に表れ自分が成長することを失ってしまうような気がするのだ。
これまでの知識や経験、考えていることを学生に“伝え”て、学生たちがそれをさらに高めていくことで、世の看護そのものがもっともっと大きく前進していけるのではないかと思っている。学生は教育者のメッセージを受け取って学び、教育者は学生の反応を通して教育を学ぶ、共に学びみんなで看護を考えていけるような関係性を、これからも学生たちと築き上げていきたい。


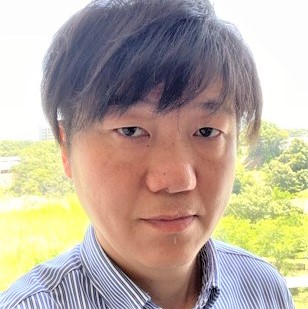
_1640312949187.png)


