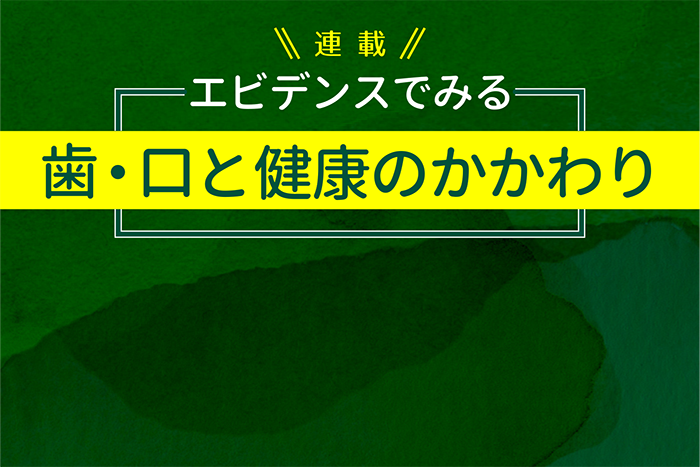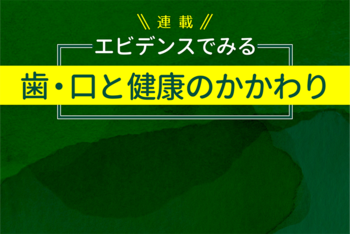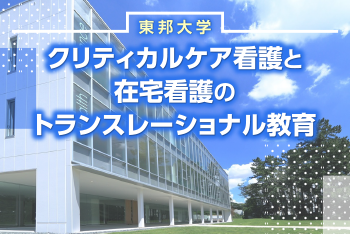ブラキシズムと隠れ歯ぎしり
ブラキシズムとは歯ぎしりや食いしばりなどの顎の行動の総称であり、一般的に「睡眠時ブラキシズム」と「覚醒時ブラキシズム」に分類されています。
睡眠時は寝ているので当然ながら意識はありませんが、覚醒時でさえ無意識のうちにブラキシズムをするようになると、顎関節やその周囲組織に負担を与える可能性が高まります。
歯ぎしりをしていてギリギリと軋むような音を立てるのは実際にはおおよそ2割程度で、残りの8割は音がしないとも言われています。このような“隠れ歯ぎしり”が多いのが実情です。
以下本稿では、ブラキシズム全体を「歯ぎしり」と称して解説します。
歯ぎしりの頻度や治療法
〇エビデンス
一般的に歯ぎしりは年齢に関係なく認められるものですが、2021年にBulanda氏らが報告した研究では、特に子どもは歯ぎしりの保有頻度が多く、20~30歳代ではおおよそ15%であり、それより若い年齢層ではさらに多くなる傾向が認められました1)。
〇子どもの歯ぎしり
通常、年齢を重ねるにつれ歯ぎしりの頻度は減少していくので過度の心配は必要ありませんが、子どもの歯(乳歯や萌出して間もない幼若永久歯)は歯質が大人の永久歯と比較して軟らかいため、噛み合わせによる摩耗(咬耗)が進行しやすくなっています。
さらに、乳歯の構造の特徴として歯の最表層にあるエナメル質が薄いため、咬耗が進めば水がしみるといった知覚過敏が起こったり、さらに悪化すれば歯の中の歯髄組織(一般に「歯の神経」と呼ぶ)までダメージが及んで激しい疼痛を伴ったりすることも懸念されます。
したがって、子どもの歯ぎしりは注意深く見守り、明らかに認められた場合は早期の対応が望まれます。
〇治療法
歯ぎしりが強い場合は、歯の咬耗を防ぐために、シリコン素材の軟らかくてクッション性のあるマウスピース(夜の就寝時を中心に装着するため「ナイトガード」とも呼ばれます)を作製して対応したりします(図1)。

歯ぎしりと睡眠時無呼吸症候群(SAS)は互いに影響
夜間の歯ぎしりは単に口の中だけの問題にとどまらず、睡眠時無呼吸症候群(SAS)との関連性も指摘されています。
SAS(Sleep Apnea Syndrome)とは、さまざまな原因で睡眠中に気道が閉塞され呼吸が止まる無呼吸状態に陥り、慢性的な睡眠不足を引き起こす症候群です。
近年になり、歯ぎしりとSAS、さらには糖尿病の発症の間に関連性があることが分かってきました。
〇エビデンス
2005年に米国のKevin氏らが報告した研究では、1,387人の一般住民を対象として、糖尿病とSASの合併率を調査しました2)。
その結果、無呼吸低呼吸指数(AHI:SASの重症度の指標)が大きくなるほど、つまりSASが重症化するほど糖尿病を合併する率が高いことが明らかになりました(図2)。

また、年齢・性別・体型といった条件に関して補正したところ、SASがある、AHI 15以上の人は4年以内に糖尿病を発症するリスクが、AHI 5未満の人に比べて約1.62倍も高まることも判明しました。
SASになると、寝ている間に呼吸が止まることが多くなり、何度も目が覚めたり息苦しい感覚になったりする結果、睡眠の質が大幅に低下します。
詳細なメカニズムは明らかにはなっていませんが、良質な睡眠が妨げられると、交感神経の活性化、およびそれに伴う歯ぎしりや心拍数増加、ストレスホルモンの過剰分泌などが起こり、これらのさまざまな要因によって糖代謝の異常につながることが推測されています。
また逆に、夜間に歯ぎしりをする習慣があると、脳の一部が常に活性化して中途覚醒が継続してしまう結果、SASを起こすリスクも上昇します。
このように歯ぎしりとSASは互いに影響を及ぼし合うことを理解しておきましょう。
SASが疑われたら、早急に対応を
SASは患っていることを本人が自覚していない場合が少なからずあり、仮に気付いていたとしてもその重大性を認識していない可能性があります。
SASの特徴の一つとして、大きないびきをかく頻度が高いことが明らかにされていますので、もしSASが疑われるような場合は、速やかに耳鼻咽喉科や呼吸器科を受診し、SASかどうかを判定する検査を受けるように勧めてください。
参考として、SASの治療は症状などに応じ、保存的治療としての薬物療法や経鼻的持続陽圧呼吸療法(CPAP)などのほかに、外科的治療(手術)も行います。
歯科では歯ぎしり治療とは異なる形態で、硬いレジン素材のSAS専用マウスピースを作製しますが、こちらも健康保険の適用で実施することができる治療ですので、ぜひ活用しましょう。
* * *
Sさん(60歳代、男性)は「歯ぎしりが強いと嫁さんに言われてな」との訴えで歯科受診されました。よく話を聞いてみると、「最近、夜の寝つきも悪い」とのこと。
お口の中を見てみると、確かに歯ぎしりが習慣化した人に特有な平らに擦り減った歯が多く、歯ぎしりの悪影響が出ていることが推測されました。
そこでSASを疑いましたが、あいにく当院ではSASの治療は行っていません。対応できる専門病院(口腔外科)へ紹介状を書き、診てもらうことにしました。
後日、紹介先の病院から返事があり「SASと診断され、マウスピース作製。睡眠障害は改善傾向」との内容が記されていました。
速やかな対応・紹介が患者のQOL(生活の質)の早期改善につながることを、改めて実感しましたね。
1)Bulanda S et al: Sleep Bruxism in Children: Etiology, Diagnosis, and Treatment-A Literature Review. Int J Environ Res Public Health 18: 9544, 2021
2)Kevin J Reichmuth et al: Association of sleep apnea and typeⅡdiabetes: a population-based study. Am J Respir Crit Care Med 172(12): 1590-1595, 2005