あけましておめでとうございます。今回のコラムが皆さまのもとに届くのは、おそらく松の内も過ぎてお正月気分も徐々に薄まりつつある頃でしょうか。お正月気分どころか年末年始のお休みも返上して仕事に追われていた方々もいらっしゃるとは思いますが、お正月をゆっくりと過ごすことができた読者にも、何かと慌ただしくてグッタリとしてしまった読者にも、何はともあれ「おとむらいフィールドノート」が一服の清涼剤になれば幸いです。2025年もどうかご愛顧のほどを。
さてさて、ワタクシも新たな年を迎えるにあたって初詣へと出かけましたが、もしかすると「あの先生」は寺社仏閣にお参りして無病息災を祈願したことも、あるいは合格祈願や厄払いなどをしたこともないかもしれませんね。何しろ、前回お伝えしたように「余は断じて無仏、無神、無精魂、則ち単純なる物質的学説を主張するのである」なんて生前に語っていたぐらいですから。
告別式の誕生
というわけで、今回は後編として引き続き兆民先生のお話を。そう、明治時代の自由民権運動を率いた中心人物であり、当時の世相に大きな影響を与えた思想家として知られる中江兆民のことです。
前編の内容をざっと振り返っておくと、まずワタクシはこの中江兆民の葬儀が「おとむらいの現代史を大きく変える契機になった」とお伝えしましたね。ただし、上で述べたように兆民先生は筋金入りの無神論者。葬儀なんて別にしなくて構わないし、そもそもカミサマだろうがホトケサマだろうが、何らかの宗教に基づいて自分が弔われるなんてまっぴらゴメンという考えの持ち主だったのです。そして1901年(明治34年)12月13日に満54歳でこの世を去ったのですが、遺族・友人・弟子などの遺された人びとは「故人の遺志は尊重したいけど、何もしないというのも……」と頭を抱えてしまいました。さて、一同揃ってあれこれと相談した結果、兆民先生のおとむらいは一体どうなったのでしょうか。
前編から1ヵ月も待っていただくことになりましたが、その「一体どうなったのか」をようやくお伝えすることができます。ここで、当時の主だった新聞に掲載された死亡広告1)を見てみましょう。
中江篤介2)儀本日死去致候に付此段為御知申上候也
明治三十四年十二月十三日 男 中江丑吉 親戚 浅川範彦
遺言に依り一切の宗教上の儀式を用ひず候に付来る十七日午前九時小石川区武島町二十七番地自宅出棺青山会葬場3)に於て知己友人相会し告別式執行致候間此段謹告候也 友人 板垣退助 大石正巳4)
おや、何だか現在の葬儀でもよく用いられる「告別式」という言葉が出てくるじゃないですか。実はこの告別式、兆民先生の葬儀以前にそんな言葉は影も形も存在しませんでした。要するに中江兆民の葬儀が行われた1901年(明治34年)12月17日は、まさに日本のおとむらい史における「告別式、爆誕!」の瞬間だったのですよ。
爆誕! などと少しばかり大げさ(というか不謹慎)な表現を用いてしまったものの、それから約120年後の現在に暮らす私たちの多くが「もっと昔からあったんじゃないの?」と思うほど告別式という言葉が浸透していることに加えて、人為的に編み出した儀式のスタイルが一つの文化になったということを踏まえれば、もうこれは「爆」発的な影響をもたらしたと言っても過言ではないでしょう。では実際に兆民先生の葬儀では何が行われたのか。葬儀の近現代史の研究で大きな業績を上げ、中江兆民の葬儀と死生観についても詳細に考察している大正大学教授の村上興匡(こうきょう)氏によると、それは以下のようなものでした。
通常の葬儀であれば、喪家から出棺したあと、葬列を組んで寺院に赴き、葬儀式をなす。その場合、本堂に棺を安置する。中江告別式では、寺院に代えて青山葬儀所が使われ、僧侶の読経に代えて、弔辞、演説、弔歌の献読などが行われ、焼香の代わりに棺前告別が行われたと見ることができる。葬儀式の順序・枠組みとしては、当時行われていた葬儀と大きく変わるものではなく、僧侶が関わる宗教儀式部分を他のもので代替した形といえる。5)
実は村上氏が指摘しているとおり、あくまで「順序・枠組みとしては、当時行われていた葬儀と大きく変わるものではなく」と見ることもできるんです。ただし重要なのは、会葬者が「一人ずつお別れを告げる」という行為を告別式と名付け、特定の儀式として概念化し、それを葬儀のハイライトに据えたこと。これって私たちが現在行っている、ごく普通の葬儀の形式ですよね。でも、それがかつては「普通ではなかった」ことは、このコラムを以前からご愛読いただいている方々ならばおそらく分かってくれるはず……かな?
兆民先生にお別れを
さあ、ここで以前からの愛読者も、勿論そうでない方も、第6回のコラム「亡き人をおくる」の内容をちょっとだけお読みいただけますでしょうか。お時間のない読者は冒頭だけでも構いませんよ。そこには、こう書いてあるはずです。かつての葬儀のハイライトは現代のように「閉じられた空間に一同が集う」ことよりも、むしろ「開放的な空間を亡骸と一緒に皆で移動する」ことにあった、と。いやいや、今回のコラムを見越して約1年前に伏線を張っておいた甲斐がありました(勿論ウソですよ、ごめんなさい)。
つまり、兆民先生の葬儀はそれまでの葬列中心主義とも言えるおとむらいのコンセプトを、祭壇と棺の前で行う告別中心主義にしたという点で大々的な変革だったのです6)。しかし、それは「自己の最期において無葬式にこだわる中江兆民と、何らかの形で葬式を行おうとする遺族、友人の妥協の産物」7)でもあったわけで、言ってみれば板垣退助をはじめとする友人たちが苦肉の策として編み出した発明だったとも言えるでしょう。
ただし、兆民先生のおとむらいの直後はたしかに告別式という形式で葬儀を行う例が徐々に増えていったものの、その多くは法曹関係者や学者など「知識人」に属する人びとによるものだったそうです。では、それが一般庶民にも普及していったのはなぜか。これもまた第6回のコラムで書きましたが、まずは大正時代あたりから道路や鉄道が飛躍的に発達し、特に人口が密集している都市部では交通網が障壁となって葬列を行うのが難しい状況8)になったことが理由として挙げられます。さらに、産業構造が農業主体から商工業主体へと変遷するにつれて「勤め人」的な人口の割合が増えていくと、地縁や血縁が中心となって葬列を行うような従来の葬儀に比べて「葬儀に参加する時間が限定され、より薄く広い範囲で多数の会葬者が参加」9)できる告別式のスタイルが好ましいものとして受けとめられるようになりました。
こうして衰退していった葬列と入れ替わるように告別式は全国的に浸透し、先ほど述べたように現在ではごく普通の光景となっています。それでも、亡き人の死を悼み、別れを惜しむという思いはおそらく今も昔も変わりませんよね。私がもしも兆民先生の友人10)や弟子だったら、やはり「お別れを告げたいな」という思いが募ると思います。だって、何もしないなんて寂しいじゃないですか。ただ、告別式というアイデアを捻りだすような才覚は持ち合わせていませんけれど……。
2)中江兆民の本名で、篤介と書いて「とくすけ」と読みます。ちなみに「兆民」は生前に「秋水」という雅号も用いていたことがあり、この雅号は前回の注8)で触れた弟子の幸徳秋水(本名:伝次郎)に与えられました。師弟関係の深さが分かるエピソードですね。さらに加えると、この死亡広告に記載されている中江丑吉(うしきち)とは兆民の長男で、葬儀当時は13歳。後に中国の政治思想を専門とする研究者となりました。浅川範彦は兆民の従兄弟で、あの北里柴三郎に師事した著名な細菌学者。大石正巳は兆民と同じく土佐藩の出身で自由民権運動に身を投じ、衆議院議員や農商務大臣を歴任。何とも多士済々な顔ぶれです。
3)現在の青山葬儀所です。都立青山霊園の一角にあり、著名人がよく葬儀を行うことでも知られていますね。2025年1月現在、整備中のため利用休止となっていますので、ご利用をお考えの皆さまはしばらくお待ちを。
4)村上興匡:中江兆民の死と葬儀,東京大学宗教学年報,Vol.19,p.2,2002
5)前掲4),p.3
6)ただし、中江兆民の葬儀では葬列も行われたようです。「ようです」と奥歯にものが挟まったような物言いになってしまうのは、当時の新聞等の資料では「主に『告別式』がいかに行われたかについて詳述するものがほとんどであり(中略)葬列の様子については特に記述されていない」[村上興匡:前掲4),p.2]からで、いずれにしても葬列ではなく告別式がメインになっていたことがうかがえます。
7)前掲4),p.9
8)この状況をさらに加速させたのが1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災であり、東京ではそれ以降ほとんど葬列が見られなくなったと言われています。
9)村上興匡:告別式.民俗小辞典 死と葬送,新谷尚紀・関沢まゆみ(編),pp.105-106,吉川弘文館,2005
10)ほとんど蛇足でしかありませんが、実は以前のコラムで兆民先生と非常に関係の深い友人が登場しているんですよ。それは、第9回「逆さまの文化」に登場したフランス人の挿絵画家、ジョルジュ・ビゴー(1860-1927)。1882年(明治15年)に来日したビゴーは兆民が開いた仏蘭西学舎でフランス語を教えていただけでなく、そのジャーナリスティックな視線で自由民権運動にまつわる諷刺画もたびたび描いており、兆民もまたビゴーの活動に協力を惜しまなかったと伝えられています。

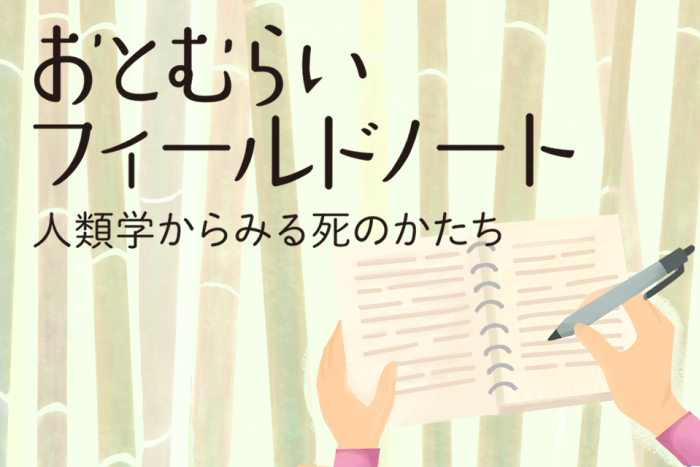



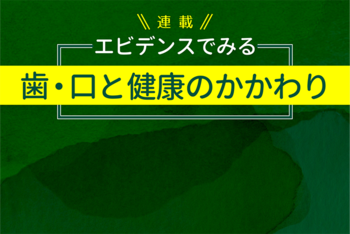
_1685342416837.png)