実習生とのかかわりを機に教員になることを決意
自分の元気を誰かの役に立てたいと看護の道を志した。元々女性の健康支援に興味を抱き、母性看護学の授業に面白さを見出していたが、学友の影響を受けて助産師の仕事に興味を抱き、また著名な助産師が「助産師は女性とその家族の性と生殖の健康を守るスペシャリスト」と述べていたのを見て、助産師が幅広く活躍できることを知り、助産師になることを決意した。
しかし、就職活動の時期を迎えると「今の自分は助産師として働いていくのに何かが足りないのではないか、もっと学ばないといけないのではないか」という漠然とした気持ちが強まり、大学院への進学を決めた。
そうして得た大学院での恩師との出会いは、私が教員という職業を意識したひとつのきっかけとなった。ありのままの私を受け入れ、どんなときも親身になってくれる、一緒にいると心が和らぐとても温かい人だった。ユーモアがあって授業も面白く、学生からの人気も高かった。女性としても教員としても素敵な恩師の姿を見て、「先生のようになりたい」と強く憧れた。研究にも面白さを見出しており、もっと突き詰めてみたいという気持ちも強かったが、修士論文で満足のいく考察が書けず、臨床の引き出しがないことを痛感したこともあり、まずは臨床でしっかり経験を積むことを優先しようと考えた。
しかし、臨床で働き始めて数年後に私は出産し、子育てと仕事を両立しなければならなくなった。実際のところ“両立”からは程遠く、子育てに追われ、子の体調不良で仕事を休まざるを得ない日が増えた。何よりも子育てが優先されるような、そうしなければならないという気持ちで過ごす日々だった。
そんな中、勤め先の病院で受け入れた臨地実習の看護学生たちとのかかわりを持った。母性看護学実習の終了時に彼らが挨拶に来た際、私が何の気なしに「実習はどうだった?」と聞いたところ、学生たちは目を輝かせて「とても楽しかった」「お母さんにおめでとう、と言えるのがいいなと思った」などと答えてくれた。
彼らの表情を見て、学生時代に抱いていた、しかし忙しさにかまけて忘れかけていた、やりたいことや好きなことへの気持ちを思い出した。と同時に、自分の好きだった助産学・母性看護学を好きでいてくれる人とかかわることがこんなに嬉しいのか、と知った。「こんな人たちと一緒に過ごせるなら教員もいいな」と、私は看護教員への転職を決意した。
“看護教員”であることの難しさ
年度の途中に大学へ入職し、翌週から早速実習が始まったのだが、初めての“看護教員”としての役割に難しさを感じた。臨地における自分の立ち位置がわからないのである。臨床のスタッフではないからケアはできない。あくまで患者とかかわるのは学生であり、教員は一歩引いた立場から学生が適切なケアをできるよう、患者との関係が良好になるよう立ち回らねばならない。
それまでと違う自分の役割にもどかしさを感じながら、分からないことをとにかく聞ける人に聞いた。 他の教員に質問したり、時には学生に「他の実習ではどうだった?」と声をかけ、他の教員の指導方法について教えてもらったりすることもあった。看護教育や実習関連の書籍も読み漁り、研修も受講し、がむしゃらにもがきながら学ぶ毎日を過ごした。
もうひとつ苦慮したのが学生の反応であった。私が母性看護学の楽しさを精いっぱい伝えても、学生は楽しさを見出してくれなかったり、看護師としての進路に迷ったりして、そのためにモチベーションが上がらず勉強不足に陥っていると思われる学生もいた。実習で接する母子の様子を見て自分自身の辛い親子関係を思い出してしまう学生もいた。
私自身も初めての経験だらけで肩に力が入っており、うまく状況を俯瞰できないくらいにストレスが蓄積していたのだろう。“先生”として聞かれた質問にはすべて答え、きちんと教えないと、という思いは強まるばかりであり、実習指導に全力で臨んでいるうちにいつしか心身共に疲れ果ててしまっていた。
肩の荷が下りて見えてきた看護教員の仕事
転機が訪れたのは、たまたま大学の廊下で近くの研究室の先生と話をしたことだった。疲れたと弱音をこぼす私に、その先生は「あなた一人で学生を育てているわけではないから」とアドバイスをくれた。「学部の教員が50人いるなら、あなたにかかる責任は50分の1でしょう。気負わずあなたの持ち味を生かして」という言葉をかけてもらい、自分が看護学を背負っているわけではない、教員みんなで学生を育てているのだと気付き、やっと少し肩の力を抜くことができた。
冷静になると、自分は学生と同じペースで前に進めていなかったのだと分かった。例えば、新生児を観察していて頭部に明らかなこぶが認められても、学生の目に留まらないことはよくある。かつての私はそれを「なぜ分からないのか分からない」と思い指導を焦っていた。しかし、学生と自分たち臨床経験のある教員では見える世界が全く異なっていることに思い至ってからは、「なぜ分からないのか分からない」のは、学生と同じ視点に立てていないためなのだと理解した。
それからは、新生児の観察に不足があっても「ここに頭血腫があるよ」と教えるのではなく、「隣の赤ちゃんと何か違うところはないかな」と声をかけ、少し立ち止まってもらうことにした。また、質問を受けた場合もすぐに返答するのではなく、教科書を一緒に見たり、問いかけたりして、学生とともにゆっくり考えるようになった。
学生の知識と臨床の場面がつながるよう、目の前のことを咀嚼して伝え、同じ視点から共に振り返るプロセスを経ることも、看護教員の役割なのだと感じるようになっていった。
.png)
学生を通して彼らと同じ景色を見続ける楽しさ
気負いすぎずに学生と向き合えるようになってから、学生や彼らを通した患者とのかかわりが私自身にもたらしてくれるものも多いことを知った。学生が患者と向き合い、一緒に悩んだり考えたりすると、教員の自分には見えていない生き生きとしたものを発見してくれる。学生から「そこに気付いたんだ」、というような視点の報告を受け、自分は見えなくなってしまったものが見える学生にうらやましさを感じることもあるが、教員でいれば学生の目を通して同じ景色を見続けることができる、という喜びもまた感じている。驚くほどみずみずしい感性をもって豊かに学ぶ姿、大学4年間を通して目覚ましい成長を遂げる学生を見続けられるこの仕事の素晴らしさを思い知る機会は本当に多い。
臨床時代に出産した娘は高校生になった。今回のリレーエッセイの依頼を受け、娘に「私のエピソード何かない?」と聞くと、「学会に一緒に行けたのが嬉しかった」「夜遅くまで勉強していた」「学生の課題を真っ赤になるくらい添削していた」などたくさん挙げてくれた。同時に「ママのすごいところは、仕事と家庭とやりたいことのバランスがとれているところだよね」と言われて、様々な感情がこみ上げた。
忙しさのあまり自分は娘に何もできていないと心苦しく思っていたが、一生懸命に頑張ったことや楽しそうな様子は伝わっていたと気が付き、本当に嬉しく、感慨深く思った。そういえば、「実習指導教員の中で、坂本先生が一番楽しそうにしていた」と学生に言われた時も同じ気持ちになったものだ。
母親としても教員としても自分のありのままの姿を見せていけばよいのだ、と気付かせてくれた家族や学生、周囲の様々な人に支えられていることのありがたさを噛みしめながら、看護教員というこの魅力的な仕事にこれからも邁進していきたい。





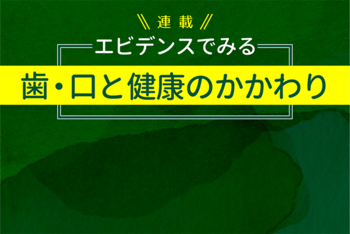
_1695266438714.png)