なんと! 昨年7月に始まったこの「おとむらいフィールドノート」も今回で一周忌……じゃなかった、一周年。これも読者諸氏のご愛顧があってこそ。今後とも温かく見守っていただければ幸いです。というわけで第1回から四季が一巡して、待ちに待った夏が再びやってきますね。そして夏の風物詩と言えば、これはもう誰もが真っ先に「肝試し」を思い浮かべるに違いありません。えっ、もっと他に思い浮かべることがある? いいんですよ、そういうことにしておきましょう。毎回毎回、こうやって話のマクラをこじつけるのは大変なんですから……。
あの世の定番モード
でも、今回は別に肝試しの話がメインではないのです。ここでちょっと、皆さんも肝試しの記憶を振り返ってみてください。暗い夜道を怖がりながらブルブルと震えて歩いていると、いきなり「うらめしや~」と白い着物を着た幽霊(に扮した人)が現れて、キャーッ! と悲鳴をあげる。大体、こんなところがお決まりの光景ではないでしょうか。スーツを着てネクタイを締めたビジネスマンが「どうもこんばんは」なんて現れても、なんだかしっくりこないですよね。それでは唐突ですが、ここでクイズ。このコラムを以前からご愛読いただいている方は「白い着物を着て、額に三角形の白布を当てている」という、あの典型的なザ・幽霊の絵をどこかで見たことがあるはず。さあ、一体いつ登場したか思い出せるでしょうか。
答えは、第9回でみた挿絵画家ビゴーの「臨終(Deathbed Scene)」の絵。今まさに息を引き取った故人の遺体が死装束に身を包まれて横たわっている姿を克明に描写しています。この絵は明治時代の半ば頃に描かれたものですが、今でもこの死装束のスタイルは圧倒的な定番と言っても過言ではありません。私が資料として持っているマイ死装束を、研究室のテーブルに広げてみましたのでご覧ください。合わせて、このコラムにも何度か登場してもらっている国立歴史民俗博物館副館長の山田慎也氏による説明も添えておきましょう。

死装束
死者が納棺に際して身につける衣装。多くの場合、白の麻や木綿を用いた帷子(かたびら)・手甲(てっこう)・脚絆(きゃはん)・頭陀袋(ずだぶくろ)や三角の額あてなどを着け、草鞋(わらじ)や笠、杖などを持たせる。その時、帷子は左前に着せ、足袋なども左右逆や裏返しにする時もある。この装束は旅装束であり、これは死を旅立ちと捉えているためであるが、浄土真宗などのように教義上、旅立ちとしての死を否定する場合は、このような装束にしないこともある。1)
というわけで、幽霊=死んだ人間=死装束を着ているという連想で、幽霊と言えば死装束というスタイルがおそらく定着したのであろうと推測されます。いくつか補足しておくと、上記に挙げられている「三角の額あて」は天冠(てんかん・てんがん)などと呼ばれることも多く、また「頭陀袋」は三途の川の渡し賃とも言われる六文銭を入れるために用いるとされています。いずれにしても手甲や脚絆なんてアイテムからして、時代劇によく出てくる旅姿や、あるいはお遍路巡りなどの服装にも相通ずるところがありますよね。それもそのはずで、上記の通り死装束というのは基本的にあの世へ「旅立つ」ためのスタイルなのです。
ちなみに山田氏の引用文には「浄土真宗などのように教義上、旅立ちとしての死を否定する場合は、このような装束にしないこともある」と書かれていますが、これはなぜか? 実は浄土真宗の厳密な教義では、亡くなった人間は阿弥陀如来の導きで「即身成仏」する、つまり死後すぐに極楽浄土にたどり着けるので、特にあの世で旅をする必要がないんです。また、同じ理由で(幽)霊もいないということになっているので、浄土真宗の葬儀では香典袋に「御霊前」とは書かないのが通例。だって、亡くなったらすぐに仏様になるわけですから。
死装束の来し方行く末
しかし実際には「着せる」のではなく単に「被せる」場合も非常に多く、浄土真宗でもさまざまな事情で死装束を遺体に着せる場合をしばしば見かけます。また、故人や遺族の意向、そして地域の風習などによる差異もあるため、先ほど示した死装束のスタイルは定番とは言いながらも細かい部分は色々と違いがあるというのが妥当な見方と言えるでしょう。その一方で、死者に特別な装いをさせるという文化そのものは、それこそ非常に長い歴史を持つものです。実はこの点についても以前のコラムにちょっとしたヒントが隠されているのですが、お分かりになりましたか?
ここで、第11回でみた「龕師(がんし)」の絵と、そこに添えられている文章を見てみましょう。「死て身にそふものハ経かたひら・六道銭」、つまり遺体には先ほど挙げた帷子や六道銭といったアイテムを用いるとしっかり書かれていますね。これは元禄3年(1690年)に刊行された「人倫訓蒙図彙(じんりんきんもうずい)」という文献から引用したものですから、少なくとも300年以上前には現在と似通った死装束が一般的になっていたことが推測されます。さらに、「あの世に旅立つ」ための旅姿というコンセプトにいたっては、それこそ古代にまで遡って痕跡が見受けられるんですよ。たとえば、葬送儀礼における服飾の文化に詳しい学習院女子大学名誉教授の増田美子氏は、次のように述べています。
5世紀後半になると、人物埴輪から死装束をうかがうことができる。(中略)男性の人物埴輪は殆どが手甲と足結(あゆい)をしているが、手甲と足結をした姿は、旅装束であり、あの世への旅立ちの姿と考えて間違いないであろう。これらのことから、当時の死装束は常用の形態の衣服に足結をし、手甲を付けたものであった可能性が大きい。2)
足結というのは動きやすいように膝の上あたりで袴をキュッと縛る紐のことを指しますが、先ほど出てきた手甲も含めて、やはり古代の人びとも死者の服装として旅姿のイメージを強く持っていたことが分かります。このような死装束のスタイルが今後も続くかどうかは全くもって予測不能ではあるものの、明治維新から約150年を経て洋装がこれだけ浸透してくると、もしかすると死装束も和装から洋装へというトレンドが今後起きてもおかしくはありません。
さてそうなると、未来の肝試しで幽霊役となった人は一体どんな服装をすればよいのでしょうね。
1)山田慎也:「死装束」.民俗小辞典 死と葬送,新谷尚紀,関沢まゆみ(編),p.54,吉川弘文館,2005
2)増田美子:葬送儀礼と装いの比較文化史,p.43-44,東京堂出版,2015

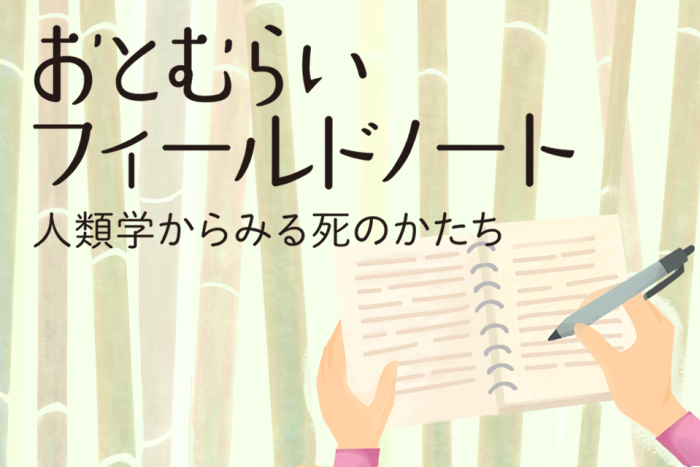

_1685342416837.png)


_1695266438714.png)