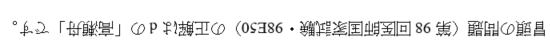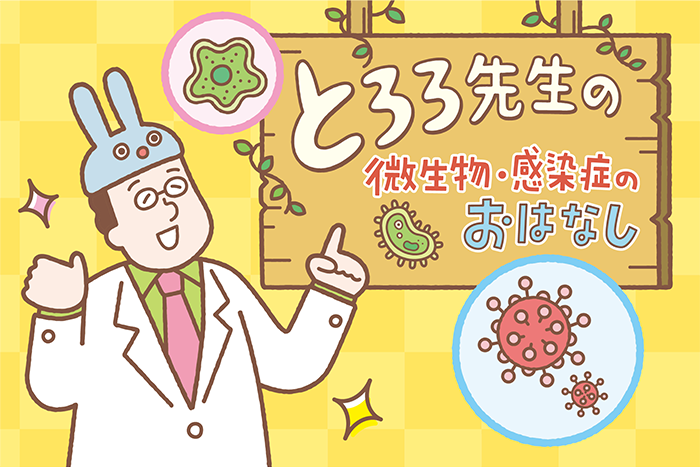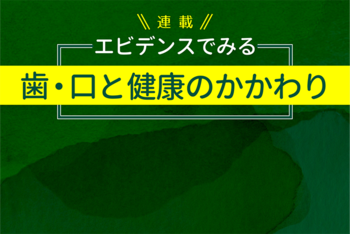さて、今回はいきなり問題からスタートです! ! !正解は1つ。

・
・
・
実はこちら、少し古いですが、第98回(2004年施行)の医師国家試験の問題なんです(98E50)。みなさん、解けましたか? 答えはまた後ほど…。
医師国家試験には「一般教養問題」が出る⁉
みなさんご存知のように医療職の国家試験には「出題基準」というのがありますね。医師国家試験では、正答率絶対評価(80%)である「必修問題」の出題項目の中に、以下のようなものがあります。
【必修の基本的事項】
大項目18「一般教養的事項」
中項目A「医学史、人文・社会科学、自然科学、芸術、哲学などに関連する一般教養的知識や考え方」*
(最新の「医師国家試験出題基準」(令和6年版)より)
*とろろ注:この中項目には小項目は指定されていない
冒頭の問題は第98回と少し古いのですが、基本的にこの「一般教養問題」に関する出題項目は近年、特段の変更はありません。
看護師、保健師、助産師、薬剤師などの国家試験出題基準を調べてみたのですが、このような「一般教養的事項」を出題範囲に指定している国家試験は医師の他にはありませんでした。ではいったい、いつから「一般教養的事項」が医師国家試験の出題項目に入っているのか…興味がある方は調べてぜひ教えてください。
疾患と俗称についての一般教養問題
すみません、このコラムは「微生物・感染症に関するお話」がテーマなのに、ちょっと脱線してしまいました。それでは、今度は感染症に関する過去の教養問題を取り上げてみましょう。

こちらは第104回(2010年施行)の医師国家試験の問題です(104C14)。さて、いかがでしょうか。さきほどと同じように正解は1つです。
「食あたり」「水あたり」「湯あたり」
……そうです。正解はaですね。
bの食中毒は一般に「食あたり」といわれます。食べ物に起因する健康障害という意味で、本当の原因は細菌・ウイルス・原虫などの「微生物」だけではなく、寄生虫(アニサキスなど)、化学物質、自然毒(毒キノコとかフグなどが有名)などもあります。
また、食あたりとよく似た言葉に「水あたり」というのもあります。これは飲み水が原因の健康障害なのですが、一般的には旅行、それも海外旅行にいって現地の飲食物で下痢を起こすことを指しているようです。医学的には「旅行者下痢症(travelers’ diarrhea)」と言われます。手元にある『トラベル・アンド・トロピカル・メディシン・マニュアル』(メディカル・サイエンス・インターナショナル社,2012)のp.111には、2週間の旅行期間で多くて60%の旅行者が罹患する、とありますので、海外旅行で最も一般的な健康障害は下痢である、と言っても言いすぎではないかと思います。
旅行者下痢症の原因として有名なものは毒素原性大腸菌(ETEC)でして、この菌、なんとコレラ毒素を産生する大腸菌なんです。そりゃあ、水のような便が出ますよね(コレラでは「米のとぎ汁様便・rice water stool」といわれます)。私、過去にフィリピンでおそらくこの菌に感染して、もう大変でした。このお話はまたの回に、ということにしますね。
ちなみに「湯あたり」とは、お風呂に長く入りすぎて「のぼせて」しまうことですが、はて、正式な医学名称はなんていうんでしょうね。そもそも病気じゃないのかも……。
高等な(?)引っかけ問題も登場
cはもちろん間違いなのですが、この出題委員のおやじギャグが理解できますでしょうか。
足がつることを一般に「こむら返り」といいますよね。こむらは「ふくらはぎ」の古語なんだそうです。ところが関西ではこれを「こぶら返り」ということがあるんです。この引っかけ、分かりますか? そうです。こぶら→コブラで、毒ヘビのコブラと引っかけて、「蛇咬症(へびこうしょう)」ですか、と出題したわけです。あまりに高等な引っかけで、某予備校の自己採点集計ではたしか0.3%の受験生しか選択しなかったんじゃなかったかな…。
dも引っかけですね。みずむし(足白癬)、ぜにたむし(体部白癬)、いんきんたむし(股部白癬)、しらくも(頭部白癬)などはいずれも「白癬」の俗称で、白癬菌と総称される真菌が原因です。「○○むし」といわれると、寄生虫かなあ、と思ってしまうんでしょうか。
eは、この問題の選択肢の中では唯一、医学的な知識が必要な問題です。鳥目は「夜盲症」のことで、暗いところに視覚が順応できない状態です。それはビタミンA欠乏症ですよね。高校生でも生物を選択していたら分かるかな? ビタミンC欠乏症は「壊血病」でしたね。
英語にも「専門用語」と「一般用語」がある
次、こういうのはどうですか? 実はさきほどご紹介した出題基準の大項目18には2つの中項目があって、Aは一般教養的知識なんですが、Bは「診療に必要な一般的な医学英語」となっています。ただ、この問題は単なる医学英語の知識だけじゃなくて、かなり教養的な要素も含んでいますので、AとBの「合わせ技で1問!」のような感じです。

こちらも第104回(2010年)の問題です(104F03)。
これは良問でして、感染症の病名を英語で言おうとすると、実は専門的な用語と一般的な用語の2つがある場合があります。日本語でもそうですね。たとえばcは水痘ですが、日本語でも「みずぼうそう」の方が一般的にはなじみがあると思います。英語ではvaricellaですが、chickenpoxが一般的な用語です。麻疹(ましん)は一般的に「はしか」と呼ばれますが、英語ではmeasles。風疹は正式にはrubella、これはルビーと同じ語源で、紅い皮疹が語源だと思います。ただ、一般的にはGerman measlesと呼ばれます。直訳すると「ドイツばしか」ですが、日本語でも風疹のことを「三日ばしか」といいますので、麻疹の別バージョンととらえていたのは洋の東西を問わないんだと思います。
いろいろ調べてみましたら、風疹のことをthree-day measlesということもあるそうで、それなら日本語の「三日ばしか」とまったく同じですね。風疹と対照させてあえて「麻疹」という場合にはten-day measles(十日ばしか?)という言い方もあるそうです。
ちなみにa、b、dは解剖学の用語で、aは脊椎spineですが、日本語でも「せぼね」が一般的ですね。これに相当する英語がbackboneです。bも同じで、「腹部」に相当するのがabdomen、「はら(腹)」に相当するのがbellyですね。dは間違いで、foreheadは前頭部=額(ひたい)のことですが、craniumと言っちゃうと頭蓋骨全体を指してしまいます。頭蓋骨の一般的な英語はskullですね。ちなみに正しく対応する単語は何ぞやと調べてみたところ、前頭部の解剖用語としてはラテン語を語源とした「sinciput」というものが出てきました。eは病名の英語でして、insomniaは「不眠症」のことなので、sleeplessnessで合っています。辞書で調べたら、ずっと起きたままという意味でwakefulnessでも正解なんだそうです。
ちなみに、マコーレ・カルキン主演の映画「ホーム・アローン」シリーズの1だったか3だったかでは、出演者の「Chickenpox!」という叫びに対し、日本語版字幕では「水ぼうそう!」ではなく、「はしか!」と誤って表記されるそうなんです。これは本学の非常勤講師である川村尚久先生(大阪ろうさい病院感染症科・小児科)が講義でおっしゃっていたネタです。ぜひ、ツ○ヤでレンタルして探してくださいね。
.png)
実は冒頭の「森鷗外」問題に関連して私、本学医学部の卒業試験で「夏目漱石の作品のうち、壮年期における自殺を題材にしているのはどれか。」(5択は略。正解は「こころ」)という問題を出題したことがあります。6年生からは大ブーイングで、「国試の受験生に読書を強要するのか!」とえらい怒られたのですが、5年生以下の学生さんはおおむね好意的にとらえてくれました。学生の間にいろんな本を読まないといけないよねぇ、ということに気づいてくれたんだと思います。実は私、高校生のときも大学生のときも、定期試験が迫ってくるとなぜか小説が読みたくなって、実際読み耽って失敗した経験が何度もあります……。教養を積むのは大切ですが、本を読むのは時間があるときの方がいいですね。