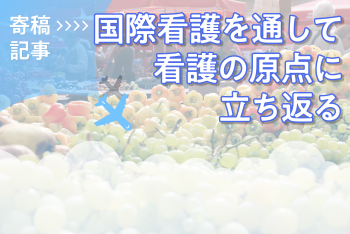さて今回は、微生物・感染症の類型(分類)についてお話ししようと思います。これ、簡単そうで実は複雑なんですよ・・・。
感染症法と学校保健安全法による分類
感染症・ゴロ合わせの回(連載第22回)でお話ししましたように、1999年までわが国には「伝染病予防法」がありました。その当時は、特別な取り扱いが必要な感染症は原則11種類だけで、これらは「法定伝染病」と言われていました。ところが新しい法律、通称「感染症法」(正式には「感染症の予防および感染症の患者の治療に関する法律」)では、感染症の「類型」を規定しました。つまりレベルに分けて対応しましょうということになったわけです。ここで一類感染症から五類感染症までの類型(表1)ができました。一類感染症には、エボラ出血熱とかペストとか、わが国に常在しない、致死率や伝染性が高い疾患が入っています。一方、五類となると、こちらは全数届出と定点把握の2種類がありますが、基本は「サーベイランス」で、症例数の増減を監視することが主体となります。

実は、感染症の分類には他の法律もかかわっています。有名なのは「学校感染症」(表2)を規定している学校保健安全法です。こちらの施行規則では「出席停止の期間の基準」というのが決まっていて、当該感染症に罹患している人はその期間、原則出席停止になります。感染症に罹患している学生・生徒などに出席停止を命じるのは校長であって学校医ではないんですよ。これ、医師国家試験の引っかけ問題でよく出ます。
一方、校内で感染症が流行したときに感染症に罹患していない人も含めて休ませる、いわゆる学級閉鎖や学年閉鎖(学校保健安全法第20条でいう「臨時休業」)をさせるのは、校長ではなく「学校の設置者」なんです。県立高校なら知事、市立中学なら市長なんですが、普通は教育委員会が判断していると思います。私立なら学校法人の理事長です。これも国家試験のヤマです。ちょっと話がそれてしまいましたが、学校感染症は「第一種」から「第三種」までが規定されています。というわけで、こっちは「第○類」ではなく「第○種」っていうんですね。

予防接種法による分類
さらにもうひとつ、感染症の分類をしている法律があります。予防接種法です。いわゆる定期接種は2種類で、おもに子どもが罹患するのを防ぐための予防接種と、高齢者が罹患するのを防ぐための予防接種があるんです。前者はどちらかというと集団予防の観点も含まれていて、対象者は「義務」ではないんですが接種を積極的にお勧めしますよという「勧奨接種」で、費用は市区町村が全額負担してくれます(義務といえばむしろ、市区町村が住民に対して予防接種を実施する「義務」があるともいえますね)。
一方、後者は高齢者がご自身の健康を守るという個人予防の考え方でして、費用は負担してくれても一部だけというのがほとんどです。第28回で取り上げた「帯状疱疹ワクチン」がこれに当たりますね。その他にインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン、そして新型コロナウイルスワクチンがあります。予防接種法の改正で後者(高齢者対象)の定期接種が初めて導入されたとき、前者(子ども対象)の対象疾患を「1類疾病」、後者を「2類疾病」と呼ぶことになりました。ところが、「1類」だと、最初にお話しした感染症法での「1類感染症」と呼び方が同じで混乱を招くという理由で、しばらくしてから「A類疾病」「B類疾病」と言い直したのです(表3)。日本の法律でなかなかAやBを使うものはないんで、ちょっと珍しい呼び方ですよね。当初私は、「藤子不二雄A」みたいだな、と思ってました。あ、Aさんは○囲みでしたっけ・・・。

病原体は「種」
感染症の分類はだいたいこんなもんなのですが、実は感染症法は2007年に大幅に加筆されて改正施行されています。増えた条文では、特定病原体等を規定しています。これ、国が管理する必要がある特定の病原体および細菌毒素について決めているものです(病原体と毒素があるんで「等」になってるわけです)。ということで、「病原体の分類」というのもあります。ただこの分類も感染症法以外にもあって、ちょっとややこしいんです・・・。
感染症法に追加された病原体に関する規定は、おもにバイオテロ対策のためでした。そのため、感染すると重篤になるなど、医学的な観点だけでレベルを決めたわけではなく、バイオテロに使われる可能性が高く、実際に使われたときに影響が大きい(であろう)順番に並べられています。ただ、同じ法律で感染症の類型を「第○類」とすでに呼んでましたので、病原体の方は「○種」と呼ぶことになりました。実際には「一種病原体等」から「四種病原体等」まであります(表4)。

一種はエボラウイルスや痘そうウイルスなど6種類が規定されていて、原則所持等は「禁止」されており、例外的に国が定める施設のみが所持・輸入・譲渡・譲受ができるとされています。こちら、BSL-4(あとで説明します)実験施設を持っている機関のみとされており、今までは旧国立感染症研究所(現国立健康危機管理研究機構)だけだったのですが、2025年1月に長崎大学高度感染症研究センターが指定され1)、現状わが国では2施設となりました。
セキュリティの関係で、うちの研究室がどんな病原体を持っているのかというのはここではお話しできませんが(当局にちゃんと届出はしております)、四種病原体等であれば基準を遵守すれば適切に所持することができます。三種病原体等には多剤耐性結核菌やSFTSウイルスなどが含まれていて、こちらは厚生労働大臣への届出が必要ですし、施設内での取り扱い方について「病原体管理規程」として明文化するとともに、運搬するときは公安委員会への届出が必要です。
第19回で多剤耐性結核菌の話をしましたが、病院の細菌検査室で結核菌が分離されることがありまして、その感受性試験をしたら多剤耐性結核菌であることが判明した、ということはあります。そうしたら、厚生労働大臣に届け出て自施設で所持するか、それともオートクレーブで滅菌して捨ててしまうか、あるいはすでに同じ病原体を所持していて大臣に届出をしている研究機関へ運搬するか、の3択をすみやかに決定しないといけません。この決定をぐずぐずしていて7日を超えると違法状態での所持になってしまいますから・・・。よし、届出済の機関(都道府県や政令市の衛生研究所などが想定されます)に運搬しよう、ということになれば、公安委員会へ届出が必要なので、まずは所轄の警察署に相談です。よもや段ボールに詰めて宅配便で、というわけにはいきませんので、これはこれでなかなかたいへんです。
公衆衛生学的観点も含むBSLの分類
この病原体の分類、一種から四種というのはあくまでも国内法が根拠になっていますが、世界的には「バイオセーフティレベル(BSL)」というものが一般的です。これはヒト(や動物)に疾患を起こすリスク、さらに起こしたときに重篤になるか、予防法や治療法があるか、伝播する力はどうか、公衆衛生学的なインパクトはどうか、というような観点で、そのリスクをもとに1から4に分けています(表5)。

BSL-1はヒトに病気を起こす可能性がないもので、ヨーグルトの乳酸菌とか納豆を作る枯草菌などが含まれます。こちらを扱うときは一般的な実験室でいいわけです。BSL-2となりますと、ヒトに病気を起こしますが、有効な予防法や治療法があり、実験室から散逸しても地域社会へのリスクが低いものです。ヒトの病原体の多くはこちらに含まれます。この病原体を扱う実験室には原則、安全キャビネットとオートクレーブの設置が必要ですし、実験中は扉を閉める、関係者以外を立ち入らせない、入口に決められた表示を行うなど、ルールが決まっています。
BSL-3はBSL-2より感染したときのリスクが高いものです。わが国には常在しない狂犬病ウイルスや、空気感染しうる結核菌などが含まれています。この病原体を扱うには、常時安全キャビネットの中で行うのはもちろん、実験室全体を陰圧にして、HEPAフィルターを通して排気する必要があります。陰圧の実験室ですので、入口は二重扉になりますし、床や天井、壁などは消毒しやすい材質にするとか、細かい施設基準が決まっています。さらにBSL-4には、感染すると重篤となり治療法や予防法がないもの、そして実験室外に散逸すると地域社会へのリスクが高いもので、エボラウイルスなどが含まれます。BSL-4実験室となると、原則独立した建物で、出入りするときはシャワーを浴びる必要があり(よって衣服はすべて着替える)、陽圧空気を常に送り込まれている宇宙服のような密閉された予防衣(図1)を着用する陽圧防護服(スーツ型)の実験室と、完全に封鎖されたグローブボックスの中にゴム手袋を突っ込んで操作するグローブボックス型(図2)の実験室の2つの形態があります。長崎大学に新しく作られたのは前者、旧国立感染症研究所にあるのが後者のタイプです。


バイオセキュリティ,p.12,〔https://www.ccpid.nagasaki-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/07/siryou3.pdf〕(最終確認:2025年7月16日)より引用]
BSLの分類には「公衆衛生学的なインパクト」の大小という観点が含まれていることも重要ですね。たとえば、わが国ではHIVをBSL-3として扱っていますが、米国では昔からBSL-2です。これは研究を活発にする必要があったという国情のためと聞いたことがあります。あるいはサハラ砂漠以南のアフリカ諸国のような場合は、HIV陽性率が高いので、わざわざ二重扉の中であるBSL-3実験室で取り扱う必要はないかと思います。
典型的な例として、2009年に新型インフルエンザウイルス(H1N1pdm2009株)がアウトブレイクを起こしましたが、このウイルスは発見当初、BSL-3に分類されていました。国内に常在しないウイルスだからです。結果的に、実験研究ができる施設が限られてしまったのですが、1年も経てば市中のインフルエンザのほとんどはこのウイルスが原因となってしまったため、わざわざ二重扉の中に閉じ込めて実験する必要もなく、BSL-2にレベルダウンされました。病原体のバイオセーフティレベルは国や地域によっても違うというのはお話ししたとおりで、たとえばわが国には狂犬病は常在しませんので、どうしてもレベルが高くなるのはやむを得ないかと思います。
そうなんです、つまり、感染症法の病原体の分類とBSL分類はまったく観点が異なっていますよね。感染症法は「バイオテロに使われる可能性」で決めていますが、BSL分類は正攻法としてその病原体が起こす感染症の性質で決めています。それとともに、数字の順番が完全に逆になっていることにも注意が必要です。数字の1から4というのは一緒なんですが、重要なものを1にもってくるのが日本式、逆に1が一番軽くて、4がもっともインパクトの高いものとしてレベル分類するのが欧米のやり方のようです。こういう、日本と諸外国で順番が逆になる分類というのは、他にもありそうですね。今回は一種、一類、A類、レベル1と、いろいろある微生物・感染症の分類についてお話ししましたが、呼び方だけでなく順番まで違うものもある、というのが「オチ」でございました。
1)長崎大学高度感染症研究センター:長崎大学高度感染症研究センターとは,〔https://www.ccpid.nagasaki-u.ac.jp/about/〕(最終確認:2025年7月16日)



_1685342416837.png)
_1695266438714.png)