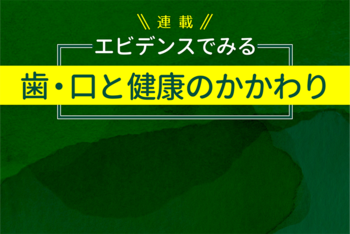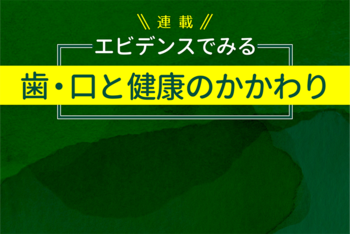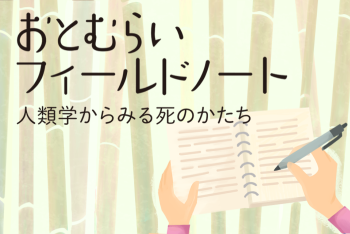正義論は、イントロダクションだけでも大変に長いものだが、今回でようやく正義概念の見取り図については最終回である。今回取り上げるのは、実質的正義の下位概念としての、分配的正義と矯正的正義である。それぞれが、どんな問題であるのかを見てみよう。
社会的な利益や負担を公平に分かち合う~分配的正義~
分配的正義は、人々が社会的に協働する際に生まれる利益や負担を、どのように分かち合うのが公平か、を問題にする。私の世代の、関西の大学に限定的な文化かもしれないが、ゼミ生が教授宅に具材を持ち寄ってお好み焼きを作るホームパーティがあった。出来上がったお好み焼きをどのように分配するのが公平なのかが、分配的正義の問題なのだが、当然ながらゼミ生の中には具材の持ち寄りや調理作業で貢献の大きい者やサボっている者、空腹の者や少食の者がいる。努力や貢献に応じて分配すべきだとか、空腹具合に応じて分配すべきだとか、それらの事情を無視して平等に分配すべきだとか、様々な答えがありうるが、これらの答えはどれも、各人が何に値するかの判断基準についての主張をしていることになる。たとえば、空腹具合に応じて分配すべきという主張は、必要性・ニーズを、各人が何に値するかを決定する基準として採用している。
平等主義・功利主義など、次々回以降紹介する多様な正義の構想の間での論争は、どのような基準をどのような時に採用すべきかをめぐる争いであると言える。ただ、どのような基準を採用し、どの主義の立場を採ろうと、それらは分配的正義の問いの内部で、その答えを探そうとしている点で、同じ土俵に上がっているのである。
このような分配的正義の問題が発生するには、いくつかの前提条件がある。第一に、社会的な協力の存在である。独力の作業で生み出した付加価値に、分配の問題は生じない。たとえば、一人で描き上げたマンガの著作権に由来する利益は、全て作者に帰属する。遠い銀河の果ての宇宙人が飢餓に苦しんでいるとしても、その救助は(たとえ技術的に可能としても)分配的正義の要求とは考えにくい。宇宙の果てと我々の間には、何の社会的な関りもないからである。正義は、対他的な徳なのだから、分配的正義も社会的な関係性を前提にしているのは、当たり前のことであろう。
第二に、分配される物の、排他的な支配可能性、つまり特定の者だけで専有できる性質が必要である。逆に、このような性質のない公共財、たとえば平和・治安・自然環境などは、個々人に配ることができないものであるから、社会全体で公共財の価値をどのように高めていくかについては、今後紹介していく分配的正義の議論が当てはまらないことが多い。
第三は、分配される物の希少性である。生命倫理の教科書等で著名な「神の委員会」の例は、シアトルの病院で腎臓透析が導入されたとき、誰の命を助け、誰を見殺しにするのかを委員会によって決めた、命の分配的正義とも言うべき悲劇的なケースである。この新技術が存在しなかった時には、同じくらい重篤な疾患の者は、平等に死んでいた。それが安価に普及したときには、皆が平等に助かる。これら、財がゼロ、あるいは需要を十分に満たす供給があるときには、分配的正義の問題は問われない。それが問われるのは、財が希少で、一部の需要にしか応えられない場合である。大規模災害時や戦場でのトリアージが典型例だが、コロナ禍初期のワクチンの分配でも、その公平性が問題となった。
問題となる財が希少である状態が解消されれば、分配的正義の問題も自然に消滅する。移植用の臓器は、今のところ絶望的に希少な財であるが、iPS細胞の臨床研究が進めば、臓器が希少ではなくなり、臓器の分配に関する悲劇的かつ厳しい判断は、必要なくなるかもしれない。それならば、答えが有るのか無いのかよく分からない正義の問題を考えるよりも、財のパイを拡大し・社会全体を経済成長させる、たとえばiPS細胞の研究推進に、社会の貴重な知的資源を費やすほうがスマートではないか、と思われるかもしれない。しかし、社会的に需要のあるすべての財が完全に希少でなくなる状況が実現されることは考えにくいので、社会が豊かになり分配的正義の問題が徐々に消滅することを期待しながらも、残念ながら正義の問題が残った場合に、それに向き合う準備もしておいた方がよい。
ちなみに、分配的正義は財(goods=善い物)の分配を例に挙げることが多いが、もちろん同じ議論は費用や危険の負担にも当てはまる。軍事基地・原子力発電所・墓地の立地や、税・社会保険料をめぐる論争を考えて欲しい。
過去になされた不正な加害行為に真剣に向き合う~矯正的正義~
続いて、矯正的正義について考えよう。これは、不正な行為によって損害を被った者に、賠償等によって正当な原状を回復することを要求するものである。盗んだ物は返す、傷つけた物は直すという素朴な問題から、奴隷貿易や戦争犯罪の補償のように歴史的・政治的な大問題までが、その範疇に入る。
この原状回復というアイデアであるが、一見したほど単純ではない。「原状」の厳密な定義の1つとして、「もし過去の加害行為が無かったら、被害者が、現在そうあったであろう状態 」1というものがある。実際には、被害者は害を被っているわけだから、現実世界における被害者の状態と、上記の仮想シナリオにおける(害を被らなかった場合の)被害者の状態との差額が、加害者が被害者に払わなければならない補償ということになる。
しかし、この額や内容の実際の算定は、極めて複雑になる。架空の世界を正確に想像するのは、そもそも不可能であるし、仮に概算的に推測するにしても問題は残る。たとえば、被害・損害のうち、被害者自身の選択の結果など、被害者本人が責任を負うべき部分をどのように認定するのかという問題や、加害時点と補償時点に隔たりがある場合、失われた時間について払うべき利率をどれくらいに設定すべきかという問題など、考えるべきことは多い。
結局は、正確な意味での原状回復は、理屈的にも、実践・技術的にも、ほとんど不可能と思われる。では、矯正的正義の主張は、存在意義を失ってしまうのかというと、それは言い過ぎであって、たとえ正確な原状回復は無理であっても、加害者が自らの不正行為を真摯に反省し、補償に誠実な態度を示すことで、被害者と加害者の関係を回復するという象徴的な意義は残ると考えるべきだろう。
* * *
さて、これで正義論のイントロダクションはひとまず終わり、以降は正義論の本論である、正義を掲げる様々な主義主張の内容の紹介に入る。しかし、多様な主義主張の具体的な内容を紹介する前に、それらとは少し異なって抽象的なのだが重要な問いとして、そもそも正義の主張は、どれくらいの確からしさ・確固たる根拠を持っているのか、それは単に個人的な好みの問題であって、数学の証明のような客観性や厳密さを期待できないのではないか、という問題に取り組みたい。すなわち、価値相対主義とメタ正義論が、次回のテーマである。
1Nozick R:Anarchy, State and Utopia,p.57,Basic Books,1974/ 嶋津格訳:アナーキー・国家・ユートピア,木鐸社,p.90,2004