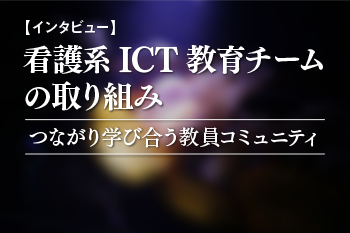「死人にものをいいかけるとは、なんという悲しい人間の習わしでありましょう。(中略)フランスのような遠い国の、名知らぬ山の、見知らぬ花に、あなたが生れかわっていらっしゃると思って、その花にものをいいかけるにしてもおなじなのです。それほどまでに今もやはり私はあなたを愛しております1 。」
川端康成『抒情歌』より
前回は、自らの死にどう立ち向かうかという問題を取り上げたが、今回は、他者の死とどう向き合うかについて考えてみたい。
死者を尊重する社会制度としての法と、それを疑う哲学
人間は太古の昔から、埋葬に多大な労力と感情を注いできた。考古学や歴史学の業績は、その思いの強さがいつの時代も変わらないことを示している。死者を思いやり悼む気持ちは、私たちの宗教・道徳・法律の多くの規範の起源となっているが、ここでは私の専門の法律の例を挙げてみよう。日本の現行の民法の最後に当たる第5編は、相続について定めている。ここには、死者との約束を守り、死者がこの世に望んだことを、できるだけ叶えようとする意図のにじんだ多くのルール2が決められている。また刑法には、礼拝所及び墳墓に関する罪の規定3がある。ここにも、死者と、その人生を象徴する物に対する、畏敬と禁忌の念が見て取れる。
これらは、至極自然な死者への尊重を制度化したものであるが、ここで再び、空気を読まない不遜な哲学者が登場する。曰く、死者は何も経験することができないのだから、約束を破られても、名誉を棄損されても、墓を暴かれても、文字通り痛くも痒くもない。いかなる害も死者に帰属することはできず、我々が死者を害するということは、定義上ありえない。だから 、死者を尊重する態度は、非合理なオカルトであり、人間の精神の弱さの現れである、と。
ただ、哲学者も、死者が害を被りうることを説明する理屈が、本当にありえないのか、いちおう探究してはいる。たとえば、死者は死後も害を帰属されうる何らかの地位を残しているという説(死者が草葉の陰で泣いている式の議論)や、死者に対する危害を生前に遡及させて帰属する(死者が、生きていた時に、害を被っていたことにする)説などが、検討されたりする。しかし、これらはいずれも、ほとんど詭弁とも言える、相当に無理のある理屈4であり、厳格と明晰を旨とする哲学者にとっては、受け入れることが難しいものである。結局、哲学者にとって、死者が害されうることを説明することは、不可能に近い。
哲学者が何を言おうと、私たちの実際の感じ方のほうが重要である
しかし、だからと言って、死者を尊重する私たちの営みを放棄すべきだと主張するのは、乱暴すぎる。哲学的・根本的な基礎や根拠がなくても、既存の社会制度や慣習を維持するための説明は、どのようにして可能になるだろうか。
たとえば、刑法学は、礼拝所及び墳墓に関する罪の規定の保護法益(法律によって保護される利益)を、個人法益ではなく、社会法益としている。つまり、たとえば死体を損壊することは、そのご遺体に宿っていた死者本人という個人に対してではなく、死者をないがしろにするような社会では生きたくないと考えている私たち、つまり生きている我々の社会全体に対して迷惑をかける行為であると考えるのである。そうすると、死者の存在や死者への危害可能性という哲学的問題はすべて回避して、既存の社会制度を維持することができる。
また、哲学的な観点から言っても、下線を引いた「だから」のつながりを断ち切る主張ができないか、検討してみる価値がある。つまり、たとえ死者を害することが哲学的に不可能であっても、だからと言って直ちに、死者を尊重する態度を社会的に非合理と断じることは早計だと言えないだろうか。
私たちが死者について語るときのレトリックには、1つの特徴がある。たとえば、死者に対する評価の変化を、「ゴッホは、死後、その名を高めた」と表現することがある。ここでの主語は、ゴッホであり、これは死者である。しかし、死者は定義上、主体性を不可逆的に喪失しているので、主語になる資格はない。厳密に表現するなら、「私たちは、ゴッホの死後、その評価を高めた」と言うのが正確である。ゴッホの評価について、私たちは真正に変化しているのに対し、ゴッホ自身は死んでいるので変化しようがないにもかかわらず、あたかも変化しているように表現される。これは真正な変化ではなく、ケンブリッジ変化という、いわば偽物の変化だと指摘されることがある。
しかし、ここで立ち止まって考えたいのは、なぜ私たちが、かくも頻繁に、偽物のレトリックを使ってまで、死者を主語に据え、あたかも死者がまだ生きているかのように語るのかである。それはひとえに、死がそれほど私たちにとって、やるせないものだからである。ゴッホに生きて、その評価の変化を経験してほしかったという、私たちの思いの強さゆえである。死者の尊重は、哲学的に非合理だろうが、不整合だろうが、そんなことは関係ない。それは、私たちにとって重要なのである。いのちの問題は、いつでも理性の範疇外である。社会の現実を重視する保守主義者としては、その感情を尊重したい。
さらに言えば、死者の尊重は、もはや死者の問題ではなく、むしろ生きている私たちの問題であるとも言える。たとえば葬儀や慰霊の丁重さは、死者本人のためというより、残された者たちの、精神の統合のためでもある。また、民法の相続法の最後は、遺留分にかかわる規定に割かれており、それによれば、配偶者や子などの遺族の生活の維持のために、被相続人の遺言の意思に反してでも留保される財産が存在する。
これらの意味で、まさに、死者と向き合うことは、私たちが自分自身に対して向き合うことに他ならない。死者との対話の儀礼は、それなしでは社会そのものが成り立たないほどに、人間の本質に深く根差した、私たちの心の叫びのようなものなのである。
***
さて次回は、各論の最後の主題として、責任の問題を取り上げたい。これは、抽象的なテーマのように聞こえるかもしれないが、私たちが生きていくうえで、誰のために、何のために、どのように行動せねばならないかを教えてくれる、大変重要な概念である。哲学的思考の鍛錬のラストスパートに向けて、一段とギアを上げていきたい。
2遺言に関する規定(第7章)のほか、特別縁故者(被相続人と特別の縁故があった者)に関する定め(第958条の2)などが、興味深い。
3礼拝所不敬罪(第188条1項:神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、~)、墳墓発掘罪(第189条:墳墓を発掘した者は、~)、死体損壊等罪(第190条:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、~)などが挙げられる。
4死者の地位が残存している説を採用すると、前回述べた主体的存在の不可逆的消滅という死者の定義と矛盾するし、遡及効説を採用すると、原因が結果よりも時間的に後に来てしまう。