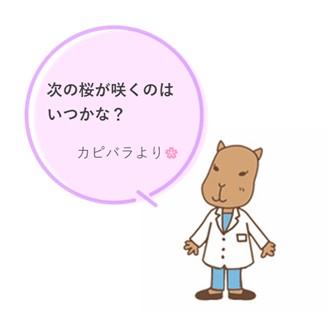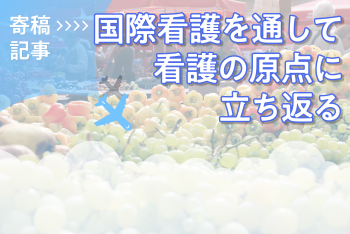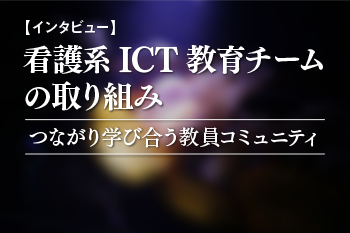毎年のことではありますが、教員の皆さまは年度末に近づき、次の年度のシラバス作成やら、学位論文審査やら、今年度を終わらせつつ、次年度を始める準備がそれにかぶさってきて、忙しくされていることと存じます。日本って年末と年度末と2つあるので、12月から3月までいろんな意味で佳境になりますね。そんななかですが、本年もよろしくお願いします。
さて、この連載の干支シリーズも3回目となりました。2023年のうさぎ、2024年の龍に引き続き、今年は編集の S さんに言われたわけではないけど、2025年の干支である「蛇」について、一年が始まる1月のテーマにして書いてみようと思います。
十二支と干支はなぜあるの?
暦は陽や月の動きから季節の変化を予測するための道具であるといえます。予測することにより、社会活動の調整をしたり、お祭りの時期が決まったりしてきました。人類が月や火星で暮らすようになったら、月の暦や火星の暦が生まれるんでしょうね。人工衛星の暦は地球時間で区切られているのでしょうけど。
年度という一年の暦により、学期が決まり、教員の仕事はやることの大筋が決まります。なので、来年の今頃もたぶん、院生の指導やシラバスの作成などで全力疾走をしていることでしょう。毎年反省するんですが、なぜこうなることがわかっているのに、前もって準備しておかないのか、なぜ毎年毎年同じような修羅場になってしまうのか、それはひとえにカピバラの時間管理のまずさもあるんですけど、もう一つの要因として、教員からすると毎年繰り返すこれらのイベント(学位論文審査、成績評価、修了判定などなど)が、大部分の学生さんにとっては初体験である、というのもありますよね。教員のほうは繰り返す季節の風物詩、でも学生にとっては初めての論文提出、などなど。
十二支は、古くから季節の移り変わりや農耕活動の目安を定める暦の作成のために発達してきました。24時間で1日となる、12ヵ月で1年となる。1年が12回で一回り。そんなふうに時間を区切っていくことで活動の目安にしてきました。
十二支が動物と結びつけられ干支という概念が生まれたのは、それぞれの動物がもつ特徴が自然現象や生活と結びつけられたから、と言われています。たとえばカピバラの干支はねずみですけど、ねずみは冬に活発に活動することから、始まりを象徴する動物とされ十二支の最初に位置づけられた、みたいなことです。12年ごとに繰り返す時間を表現しているといえると思います。12年後の蛇年に、カピバラはどんな暮らしをしているのでしょうか。いやまず、この世にいるんでしょうか、あの世にいるんでしょうか。60歳を過ぎるとこんな発想も生まれてきます。
蛇の脱皮
そんな十二支の中で、蛇は知恵と変化と洞察力を象徴すると言われています。それは蛇が脱皮を繰り返して大きくなるからです。古い皮を脱ぎ捨てて一回り大きく生まれ変わる蛇は、再生と変容の象徴。蛇年に込められたメッセージは「変化を恐れない」ということなのかなと思います。
脱皮という現象は、まず、古い皮膚の下で新しい皮膚が形成され、新しい皮膚が十分に作られると古い皮膚との間に隙間ができ、この隙間に体液がたまり、古い皮膚が新しい皮膚からはがれやすくなります。鼻先などの硬い部分をどこかにこすりつけて裂け目ができ、この裂け目からゆっくりと頭を出して、古い皮膚を裏返すようにして「脱ぎ」続けてしっぽまで脱いだら、脱皮は終わりです。健康的に脱皮するためには適度な湿度と温度、十分な栄養、静かで安全で清潔な場所が必要です。これらの条件がそろわないと脱皮不全となるそうです、と、生成AIが教えてくれました。
カピバラ的にぐっときたポイントは、古い皮膚の下に、新しい皮膚が作られる、というところです。脱皮するには新しい皮膚が作られていることが条件。脱皮のずいぶん前から、内面で静かに変化が起きているんです。その変化が続いて時が満ちると自分から古い皮膚を脱ぎ捨てる、これは誰に言われたからというわけではなく、自分の中の何かのサインを感じ取るから。脱皮は自らの内的欲求に従って進むものなんです。無理やり脱皮させることはできません。まだ脱皮を途中で止めることもできません。
脱皮して大きくなるのが蛇ですが、ちょうちょやトンボなどは、幼虫から成虫に「脱皮」すると、まったく違う形態となります。これを変態といいますね。蛇は脱皮を繰り返して成長しますが、ちょうちょやトンボは脱皮したら変態していて、完成形。成虫の姿になったら残された時間は短く、変態を繰り返すことはまずありません。蛇が干支に組み込まれたのは、脱皮を繰り返し、成長を続けるというありように、人間が何か共感したからなのかもしれません。
時間の循環性に気づく
カピバラの巣がある大学の看護学部は来年度で50周年を迎えます。開学の時にキャンパス内に植えられたソメイヨシノは幹の内部が朽ちてきて危険だということで、先日伐採され、50年の寿命を終えました。でも大きな切り株のわきにはほそっこい枝が伸びてきています。50年という時間は、後戻りはしない。でも死から再生に向かう次のターンに入ったようです。
時間は「過去→現在→未来」みたいに直線的に進むものではあるのですが、自然を観察していると、「時間って実は循環しているのでは?」と思うことってありますよね。春が来て夏が来て、秋と冬がやってくる。そしてまた春。こんな四季のリズムや、月の満ち欠け、昼と夜のサイクルは私たちの生活を方向づけています。
循環する時間の概念は、人間が自然界の観察を通じて形成したものです。古代の人々は四季の移り変わりや日夜の繰り返し、月の満ち欠けといった自然現象の観察を通して、時間が単なる直線的な進行ではなく、一定のパターンを繰り返す性質をもつことを理解しました。
生活は地球の自転と月の満ち欠けによって規定されています。朝が来て夜になって、夜になったら夜明けはもうすぐ。そして1ヵ月が12回繰り返されると1年となる。生活リズムは短期的には1日のものですけど、この一日一日の繰り返しが人生になっていくんですね。ヒンドゥー教の宇宙論では、時間は周期的に生まれ変わりを繰り返すとされ、仏教でも輪廻転生の概念が存在します。同様に、古代ギリシャの哲学者たちは、時間の循環を宇宙全体の調和や秩序と結びつけて考えました。こうして循環的な時間の概念が生まれてきたのでした。繰り返しているように見えるけど、後戻りはなくらせん状に進化しているとも言えますし、後戻りはしないけど、直線的に進むのではなく、何度でもめぐってくる時間、とも言えます。
洞察と癒しのマスタークラス
蛇の脱皮は、癒しや再生の象徴としても広く知られています。傷が回復する過程は直線的ではありませんし、局所的なものでもありません。年末にカピバラ、思いっきり転倒し、右肩を地面に強打しました。これは骨折か! と思うほどの激痛でござった。野生のカピバラ自慢じゃありませんが、骨密度は103%でござる。幸いにも骨折はありませんでした。しかし、2日くらいは体全体が右肩の痛みに支配され生活動作もままならない状態。痛みがあることですべての動作に影響が及び、イライラしたでござるよ。そして、現代医療ではどうにもならない、すなわち、鎖骨から肩の周辺って基本的に保存療法で、そっとしておく以外に何もできないってことのつらさを十分に味わったのでした。でもそのあと、1週間、2週間と時間が過ぎるにつれて軽くなっていく痛み、そして調子に乗って動かし、痛みが戻るの繰り返しをしつつ、傷ついたいろんな細胞が1個ずつ再生していき、痛みが軽くなっていき、全体的に癒えていったのでした。今はほぼ痛みはありません。この回復過程で、夜が来たら朝が来る、一日過ぎれば今日より明日は良くなっている、と希望を感じたり、痛みがぶり返すと、自分の行動を振り返って、何が影響してたかなと考えたりして、ここ2週間くらいは、「痛み」が出る動作やタイミングを察知できるようになってきました。痛みを受け入れたといってもよいかもしれません。苦痛の緩和とは、苦痛を受け入れるところから始まるのか? と思ったしだいです。
これまでのカピバラ生を振り返ると、何度も転倒してそのたびにこんなプロセスを繰り返してきました。いやこれは隠喩ではなく、マジの転倒が多いんです。「転倒する」、繰り返すこのテーマ。今回、なぜ転倒するのか? を真剣に振り返りました。そして気づきました。それはカピバラがいつも浮き足立って暮らしているからでござる。坂の上の雲ばかり見て足元を見てない、いつも違うことをいくつも考えながら移動している、注意集中機能に若干の弱点があるからなんですよね。でもこの特性により、カピバラいろんなところで、いろんなことを考えていて、教育や研究につながることもままあります。それがカピバラという存在です(ここ、リフレクションののちのカピバラという存在の受け入れと洞察ね)。入院したら転倒リスクアセスメントでレッドマークがつき、離床センサーが装着されるかもしれないし、一方、転びながらでもいつも考えていることがいろんな意味で実現するかもしれない(人生の成り行きの予測)。こう思えた時、転倒するのはカピバラの特性であって、もうこれはしかたないので、被害を最小限にするために、体重減らして筋力つけようと心に誓ったのでした。なんか普通の着地ですみません。転ばないように自立型しっぽ1)を入手しようとか、常に注意を払ってエスコートしてくれる、猫型ロボットならぬ犬型ロボットを導入しようとかっていうのもよきですけどね。
蛇年の初めに、カピバラ生に繰り返し現れる「転倒」についてリフレクションし洞察を得たことで(大げさ!)、今回の転倒が自分にとっての特別なレッスンの場すなわちマスタークラスとなり、自己改革(本気でダイエットして筋トレしよう!)という内的動機につながったといえます。そして以上の気づきのプロセスは隠喩としての「脱皮」ということになるかもしれません。
全人的癒し~序章
WHO(世界保健機関)のロゴには、蛇が巻き付いた杖が描かれています。この杖は「アスクレピオスの杖」と呼ばれます。蛇は古今東西、再生と癒しの象徴であり、アスクレピオスは古代ギリシャ神話では、医の神でした。現代のように医療が進化していない時代もそして今も、全人的癒しは、人が本来有する自然治癒力、回復の力を高め、包括的に心身をケアし、ケアされることで、癒しが完了する時がやってきます。全人的癒しに一点突破はありません。局所の治癒だけを焦点にするのではなく、傷つき病んだ人が、その人として望むような生活に向かっていけるように、死と再生の循環を受け入れ、そうして循環的な時間の中で調和と洞察が得られたら、全人的癒し、ということが起きているのかもしれません。
全人的癒しについてはまたの機会にさらに深堀りしたいなと思っている宿題です。
1) ほとんど0円大学:世界が注目する“しっぽ”ロボット?慶應義塾大学で聞いてきた!着けてきた! ,〔https://hotozero.com/knowledge/keiouniv_robottail/〕(最終確認:2025年1月29日)