『看護学テキストNiCE緩和ケア』(株式会社南江堂刊)は、このたび改訂第3版が刊行となりました。2011年の初版、2018年の改訂第2版と、これまで積み重ねてきた編集方針を引き継ぎ、今回の改訂から新たに編集を担われた林ゑり子先生(横浜市立大学医学部看護学科 がん看護専門看護師)、酒井禎子先生(新潟薬科大学看護学部 准教授)に、改訂に込めた考えや思いをうかがいました。
※本インタビューは2024年12月に行ったものです。
(NurSHARE編集部)
-本書序文にもあるように、がん対策基本法の成立から約20年が経過し、「緩和ケア」という言葉は広く浸透してきているような印象を受けます。おふたりがお感じになっていることをお聞かせください。
酒井:保健医療を提供する側の専門職においては、「がん患者だけではなく、がん以外の疾患(以下、非がん疾患)を有する人にも緩和ケアが必要である」という認識が高まっているように思います。また、老いによる脆弱さや認知症を有する人たちなども、全人的苦痛を体験しています。どのような対象であっても、その人が体験している全人的苦痛を理解し、その人のQOLに視点を置いた援助を追求していくことが、これからさらに重要になると思います。
林:一方で、保健医療の専門職ではない身内や知人などを見ていると、緩和ケアがいわゆる終末期ケアと混同されているように感じることもまだまだあります。緩和ケアは「ケガが治った」「検査の数値が改善した」といった客観的情報をもとに評価するものではなく、対象者の主観に働きかけるものであり、「その人の苦痛が軽減されていること」こそが結果です。その結果にたどり着くために常に試行錯誤する、実に幅広く奥深い分野だと感じています。
だからこそ、世間に対して簡潔かつ正確に「緩和ケアとはどのようなものか」を説明することが難しいのですよね。しかし苦痛緩和のためのケアは、だれもが享受できるものであるはずです。言葉だけでなく、実際のところを世間によりよく知っていただくこと。緩和ケアの担い手としては、これも現在の課題なのではないかと考えています。
-これからの時代、看護師が緩和ケアを行うにあたり、何が求められているとお考えですか。
林:求められる基本的なことはこれからも変わらないと思います。まごころをもって患者を思いやることだったり、あたたかな声かけだったり、目で見て、手で触れることだったり。ただ、それだけでは苦痛は緩和できない。患者の気持ちや心を大切にしつつ、知識や技術を身に付けるために日々学ぶ姿勢が、緩和ケアの実践には不可欠だと思います。
酒井:そうですね。医療が日々進歩する中で、緩和ケアのエビデンスや新しい薬剤に関する知識をアップデートする力を継続的に磨いていくことが大事ですよね。また、地域包括ケアシステムが推進され、緩和ケアを実践する場の多様化や多職種連携もいっそう求められていますから、看護師にはコミュニケーション能力や調整力、実行力、リーダーシップの発揮なども期待されるでしょう。他にも、その人にとって最善の意思決定ができるよう擁護者として支援する態度や、医療・ケアの場における倫理的課題に遭遇したときに解決に向けて真摯に取り組む態度を身に付けていくことも、重要であろうと考えています。
-これまでのご質問へのご回答もふまえて、今回の改訂で力を入れた点、意識された点を教えてください。
林:前版(改訂第2版)が刊行された2018年から、多死の時代が到来し、緩和ケアを取り巻く社会状況もさまざまに変化してきました。酒井先生のお話にもあったように、緩和ケアの実践の場の拡大・多様化への対応として、第Ⅱ章「緩和ケアの基盤となる考え方」において「緩和ケアにおけるコミュニケーション」の節を新設し、「多職種チームアプローチ」の節は全面的に見直しました。また、「家族ケア」の節では、AYA世代の患者の家族ケアやヤングケアラーについてのコラムを新しく追加しました。
酒井:冒頭でお話ししたように、非がん疾患についての記述を厚くすることは必須と考えました。事例を通して緩和ケアで求められる全人的苦痛のアセスメントを学ぶ第Ⅵ章「さまざまな事例で学ぶ緩和ケアの実際」には、誤嚥性肺炎を繰り返す高齢者や、ALSにより全身の機能障害が進行した患者の事例を追加しました。
林:療養の場が広がったことで、看取りの場も病院ばかりではなくなってきました。老衰や誤嚥性肺炎の患者は、今後ますます出会う機会が増えることと思います。またALSはご存じのように経過が非常に長い疾患で、意識があるけれど動けない、というところでつらい思いをされてきた患者も多かったと想像されます。そういう対象者の苦痛や苦悩、尊厳を守ることへの理解を深めてほしいと考え取り上げました。
酒井:また、非がん疾患における緩和ケアの考え方や症状マネジメントを学ぶ第Ⅳ章「さまざまな対象への緩和ケア」に、「救急・集中治療領域における緩和ケア」の節を新しく追加しました。救急・集中治療においても、緩和ケアの技や心が重要であることを意識してもらえると思います。そして、がん患者への緩和ケアの実際を学ぶ第Ⅲ章「がん患者の全人的苦痛に対する緩和ケアの実際」では、「社会的苦痛へのケア」の節を新設し、「身体的苦痛」「精神的苦痛」「社会的苦痛」「スピリチュアルペイン」の4つの痛みとそのケアの実際を系統的に学べるような構成としたことで、より全人的なケアが理解しやすくなったのではないでしょうか。
林:緩和ケアの知識や技術を得るための情報が増えてきたことで、看護師が提供できる技も多くなっていますよね。身体的苦痛の緩和を目的とした治療法や薬剤の選択肢が広がりましたし、精神的苦痛へのケアも専門家がガイドラインを出してくれて、よりエビデンスに基づいたケアができるようになりました。社会的苦痛へも傾聴だけではなく、メディカルソーシャルワーカーとの連携など何かしらの形で介入ができるようになりましたし、スピリチュアルケアの勉強も活発に行われています。本書では、こういった “全人的苦痛の緩和”に関して、最新の情報に基づき系統的に学んでもらえるような構成を意識しましたね。
-最後に、緩和ケアを学ぶ看護学生に向けたメッセージや、今後への期待についてお聞かせください。
酒井:日本ではこれから、高齢化率のさらなる上昇とともに、慢性的な病を抱えながら生活する人がますます増えると考えられます。そのような中、人々が病いや老いにより体験する苦痛や苦悩を予防・緩和し、その人らしく、質の高い生活を送れるように援助する看護師の役割はとても大きいはずです。
看護学生のみなさんには、緩和ケアの基本的な知識を系統的に学習するためにぜひ本書を役立てていただきたいです。そして今後、看護師として多くの医療やケアの場で活躍される際、本書での学びが緩和ケアの実践に寄与できればうれしいです。緩和ケアの実践は、看護の本質と向き合うことにも通じるのではないかと思っています。緩和ケアを専門的に学びたい、極めたいと思ってくれる学生が育ってくれることを期待しています。
林:学生のみなさんは、ゆくゆくは看護師として臨床に羽ばたいていくことでしょう。初めのうちは目の前の業務に必死で、患者が苦しみや悲しみを抱いているということ、ひいてはそれらと向き合っているという自分の状況が想像できないかもしれません。しかし、看護の現場で長く働いていると、看護師にしかできないケアやかかわりがあるのだと気付くことがあると思います。病気を治すことはできなくても、看護ケアによって患者が少しでも楽になったり、笑顔になったりすることがあるのだと知るはずです。そういったかかわりから信頼が生まれることによって、患者の苦痛がフッと楽になる瞬間に立ち会える。それは、私たち看護師にとってすごく幸せなことです。その幸せを、緩和ケアを学ぶこと、そしてその実践を通して体感してもらえるといいなと思います。
(おわり)
林 ゑり子(はやし・えりこ)
横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻・藤沢湘南台病院看護部/がん看護専門看護師
横浜市立市民病院外科病棟で5年間、がん患者の看護を行う。聖路加看護大学(現 聖路加国際大学)大学院博士前期課程に進学し、がん看護CNSコースを修了。2005年にがん看護専門看護師の認定資格を取得以降、約20年にわたり臨床での緩和ケア・がん看護の実践や、がん患者の地域での療養支援・調整を行ってきた。この間、聖路加看護大学臨床助教、旭川医科大学大学院客員講師も務め、2020年9月に横浜市立大学に着任。現在も臨床での実践と相談、研究活動を続けながら、がん看護専門看護師の育成に携わっている。
酒井 禎子(さかい・よしこ)
新潟薬科大学看護学部老年看護学 准教授
聖路加看護大学(現 聖路加国際大学)卒業後、新潟市民病院内科・放射線科病棟に5年間勤務。その後、聖路加看護大学大学院看護学研究科博士前期課程を修了し、同大学成人看護学助手として看護基礎教育に携わる。2001年、新潟県福祉保健部福祉保健課県立看護大学設立準備室での勤務を経て、2002年4月に開学した新潟県立看護大学に着任し成人看護学を担当。慢性期看護、緩和ケア、エンドオブライフケアなどの科目を担当した。2024年4月より現職。一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院において、2015年の開院時より看護部特任教育コーディネーターとして新人教育等を支援している。

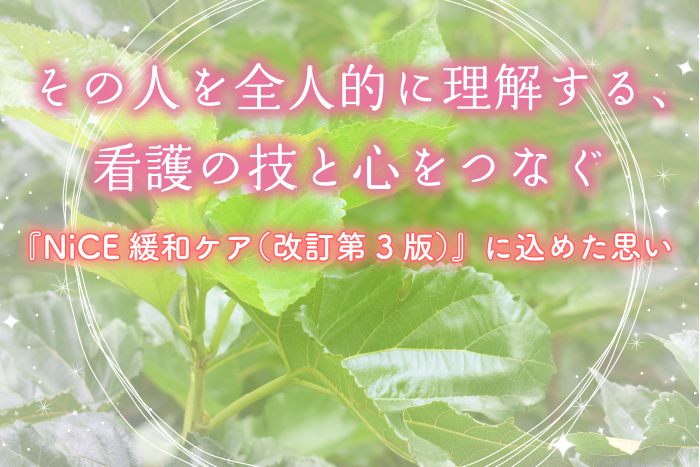


」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)
