現代社会を象徴するキーワードの一つとして、ダイバーシティが挙げられ、その推進への取り組みが求められています。しかし、多様な課題を抱える現代の学生に対して、教員としてどのように導き、支えることができるか、対応の難しさに悩まれる先生方も少なくないのではないでしょうか。新年度を迎えて新たな学生と出会うこの時期に、今一度、学生支援について考えてみませんか。本企画では全8回をとおし、看護教員、教育学者、コミュニケーション・キャリアの専門家、それぞれの視点から学生支援について見つめ直し、互いに課題を共有しながら、今何が求められるのかを掘り下げていきます。
今回は、“看護師になっていく”学生への支援について考えていきます。
企画:三森寧子(千葉大学教育学部 准教授)
今回、このような素敵な企画に参加させていただき、教育実践を振り返る機会を頂いたことに感謝している。看護教員になって20年が経ち、つくづく看護と教育は似ていると感じている。看護は、病気を看るのではなく病いとともに生きる“人”を看る。教育もその人の学習状況を見るのではなく、学ぶ“学生”を見ている。「教員は学生が個々にもつ学習への意欲を育み、人間的な成長とともに看護職としての資質を身につけ発展していくことを保証する役割を負う」1)とされ、学生が看護師になっていくことを支援する役割を担っている。
では、看護師になるとは、どういうことを指すのだろうか。看護師になるという形成は「一定の時間をかけて、よい意図をもった一般人から、弱者や苦しんでいる人に敬意とスキルで対応する看護師へと変身するときに起こる」2)とされ、そのためには「古い習慣や概念を捨て去らなければならない」2)。ここでは、看護師になっていく学生への支援について、4つの視点から考えてみたいと思う。
視点①:現代の学生像から看護教育現場の支援を考える
現代の学生像:一般的な捉え方
はじめに、現代の学生像について考えてみることとする。学生それぞれに個別の生活背景があるので、学生像としてひとくくりにしてしまうことで見えにくくなってしまうこともあるが、現代の学生は一般的に、生まれた時からインターネットが発達した社会において生活し、友人関係もSNSをとおして育んできたという特徴がある。
そして彼らには、未来に希望をもちづらい時代背景の中で、叱られる機会や承認される機会が少なかったことで、傷つくことを恐れ「同質の仲間とだけつながる」という傾向がある一方、「真面目」「協調性」「素直で優しい」という強みがある3)。このような学生にとって、病いに罹り自律した生活を送れなくなってしまった患者の苦悩や生活を想像したり、親よりも年上の世代の患者と援助的関係を築いていくことは、決してたやすいことではない。
現代の看護学生像を踏まえた支援
かねてより、セカンドキャリアとして看護師資格の取得を目指す社会人経験がある学生が増加しており、彼らは高校を卒業したばかりの学生たちといい意味で刺激し合って学んでいる。筆者が以前勤務していた看護専門学校においても、年齢も生活背景も異なる仲間の存在は、お互いの価値観を問い直すよい機会となっていたように思う。彼らは育児や仕事との両立という学習時間確保の課題や、経済的な問題を抱えていることも多く、クラス担任が奨学金制度などの情報提供を行い支援していた。
教育の場にかかわらず、発達障害のように強い個性をもつ学生もいる。その場合には、個人面談を繰り返し行いながら、得意なことを伸ばし、不得意なことを乗り越えていくためにどうしたらよいかを一緒に考えていくようにしている。学校は看護学を学ぶ場なので、学生は伸び伸びと学んでいければよいのだが、臨地実習では患者理解が促されるよう患者との関係構築を教員が支援する必要がある。また看護師として働く場所の選定については、学生の希望と適性を見極めながら具体的なアドバイスを慎重に行っている。このような支援は、一人の教員が個人的に行うのではなく、学生の尊厳を守りながら情報を共有し、組織的に取り組むことも必要である。
そして、大学でも専門学校でもクラス担任制度によって、学習や学生生活が円滑に送れるように学生を支援しているところが多いことと思う。また上級生が下級生の学生生活上のアドバイザーになるスチューデント・アシスタント制度を導入している学校もある。
コロナ禍においては、臨地実習が困難になり、シミュレーションや模擬患者等を活用した代替実習が行われたが、一定の学習成果を得るには整備が不十分であるとの報告もある4)。コロナ禍がもたらした課題については、彼らが看護師になってからの現任教育においても継続的に、看護界全体で取り組むことになるのだろう。
視点②:看護師としての態度を培う実習環境を整える
臨地実習は、看護師としての実践力や態度を養うためにとても貴重な学びの機会である反面、強いストレスが生じる場でもあり、看護師になる学生を支援するためにはこの実習環境を整えることが重要となる。
目黒は、看護基礎教育が行っているのは、学生の視線がスッと患者に向かうように導くことだと言う5)。これは看護の核となる患者への関心がもたらす態度6)のことである。では、どうしたら学生の視線が自然に患者に向かうようになるのだろうか。普段私たちは視線の先の対象に関心を向けているため、視線の向かい方を意識してはいない。教員や臨床指導者が「できた」「できない」と評価すればするほど、学生の関心は実践する自分に向かってしまうのである。
そのため、学生の関心が目の前の患者に向くように支援するためには、萎縮せず伸びやかに自分の考えを言えるような安心できる環境を整える必要がある。居心地が悪いと学生は緊張してしまい、どう振る舞えばよいかと自分の行動や感情が気になり、教員や臨床指導者の顔色をうかがうようになる。そうならないためには、学生がなりたい看護師像に向かって失敗を恐れずに行動できるように環境を整える必要がある。臨床指導者にロールモデルになってもらうようにお願いをし、厳しい指導が必要な場合は教員が行うなどと役割を分担し、病棟で学生の居場所をつくるようにする。それでも青年期の学生には、臨床現場という非日常の場は強いストレスになる場合がある。眠れない、食べられないといった身体への影響が出た場合には看護ができる状態ではないので、スクールカウンセラーの力を借りることもある。その場合には、学生の思いを尊重しながら、必要に応じて保護者とも相談し、一緒に方向性を検討していくことになる。
次に、このような一般的な学生支援とは異なる側面から、実習での学生支援について考えてみたい。
視点③:自己の概念が揺らいだ学生を支える
学生には、育ってきた中で培われた習慣や価値観、他者との関係性のつくり方、物事を捉える固有の枠組みがある。しかし看護師になっていくプロセスにおいて、それが障壁となり、病いと共に生活する患者を捉えきれない、関係性を構築できない場合がある。実習では学生の枠組みに患者を当てはめるのではなく、看護師としての新しい枠組みで患者を捉えられるように既存の枠組みを問い直していくことになる。これは冒頭で述べた古い習慣や概念を捨て去ることにつながるのだが、学生にとってはそれまで培ってきた固有の概念が揺らぐことになる。
この学生の概念が揺らいだときの支援が、看護基礎教育においてとても大切だと考えている。培ってきた概念が揺らぐと強い不安を生じ、学生の自己肯定感が低下する。そのようなときに教員が評価のみをフィードバックすると、さらに看護師になれるかどうかと不安をあおり、自己効力感を低下させてしまうことになる。そのため、そのようなときは学生の不安な思いを傾聴し、「物事を新しい見方で捉えるために今までの概念を変えていくことは、あなた自身を否定することではなく、看護師になる大きな一歩である」と伝えて支える必要がある。この看護師としての新しい概念で物事を捉えられるようになるまでの時間には個人差があり、その間、学生のもつ力を信じて待てるかどうか、教員としての力量が試されるときでもある。我々教員が、たとえ祈るような思いでいたとしても、大丈夫だと揺るがない態度で臨んでいるうちに、いつしか学生は患者との関係性において看護師らしい表情で前を向くように変化していく。それは学生のもつ強さに感動させられる瞬間でもあり、教員としての醍醐味を感じる瞬間でもある。
最後に、組織的な視点からの学習者支援について考えてみたい。
視点④ 学び合う“しかけ”をつくる
組織的なしかけとして、ラーニング・アシスタント(LA)制度も学習者支援に効果的である。筆者はピアエデュケーションを促進する目的で、教育改革事業としてLA制度の導入に取り組んだ経験がある7)。LA制度はその名のとおり、学びを支援する制度であり、LAはボランティアではなく正式に大学が雇用し、教員と打ち合わせをしながら、既習科目を学ぶ下級生の学びをサポートする役割を担う。
実習を終えた上級生が下級生に看護過程のコツや看護技術を教えることで、より学習者の視点に近づいた支援が可能になり、実習に対する漠然とした不安の軽減にもつながる。実際にこの制度が機能すると、LAを務める先輩が身近なロールモデルとなる。先輩のように自分もなれるかもしれないという代理体験になり、学習者の自己効力感を向上させるしかけとなる。
また教える上級生にとっても、実習をとおして学習したことを言語化して下級生に伝えることで、専門職者の資質である教育力を培うことができる。LA役割を体験した学生からは、学習者が自ら答えを探せるような学習意欲を向上させるかかわりが難しかったが、やりがいがあったという声が聞かれた。
学年を越えた縦のつながりや学び合う雰囲気が生まれると、学生たちは自然とお互いを支え合うようになる。
* * *
以上、4つの視点から、看護基礎教育における学生支援について考えてきた。看護師になっていく学生の力を信じて支援することは、将来患者や仲間に尊厳をもってかかわることのできる看護師を育てることにつながる。そして、学生が看護師になっていくプロセスに伴走させてもらえる教員は、学生からたくさんのことを教えられ、共に成長させてもらえる存在なのだと思う。
1)日本看護系大学協議会 平成20年度看護学教育研究倫理検討委員会:看護学教育における倫理指針(2008年12月),p.4,https://www.janpu.or.jp/umin/kenkai/rinrishishin08.pdf,アクセス日:2022年4月4日
2)パトリシア・ベナー,モリー・サットフェン,ヴィクトリア・レオナードほか,早野ZITO真佐子 訳:ベナー ナースを育てる,医学書院,2011
3)玉木敦子:今どきの看護学生をどう育てるか,神戸女子大学看護学部紀要2巻,p.1-10, 2017
4)日本看護系大学協議会:2021年度看護系大学生の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチン接種状況等に関する緊急調査結果報告書(2021年7月14日),https://www.janpu.or.jp/wp/wp-ontent/uploads/2021/07/2021JANPU kinkyuchosa-houkoku.pdf,アクセス日:2022年3月11日
5)目黒悟:教えることの基本となるもの;「看護」と「教育」の同形性,メヂカルフレンド社,2016
6)パトリシア・ベナー,ジュディス・ルーベル,難波卓志 訳:ベナー/ルーベル 現象学的人間論と看護,医学書院,1999
7)池口佳子,五十嵐ゆかり,三浦友理子ほか:聖路加国際大学看護学部におけるLA(Learning Assistant)システムの創設,看護教育,59(4):302-306,医学書院,2018


_1649815027631.jpg)
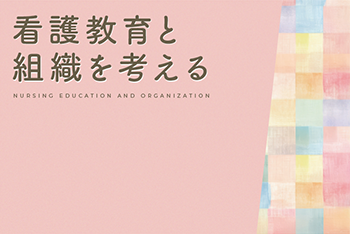

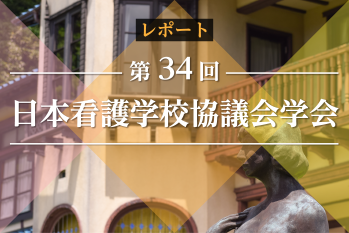
」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)