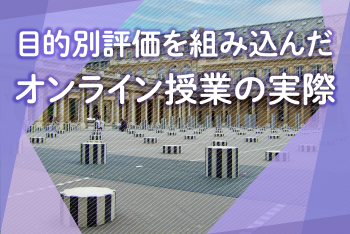看護教育を志したきっかけはオリエンテーション後の学生の“表情”
幼少期に遭遇した新潟地震の際、赤十字のマークの入ったキャップ姿の看護師(当時は看護婦)が、怪我を負われた方たちの手当てをしている姿が脳裏から離れず、いつしか看護師は憧れの職業になった。看護師になって4年目頃から学生指導に携わり、“教える”ことがこんなにも楽しいと知った。何よりも一生懸命に患者とかかわる学生が眩しくて仕方がなかった。学生の姿は私を看護師としての原点に戻してくれるものでもあった。しかし、ある時の学生指導初日に考えさせられることがあり、後々考えるとこれが看護教員の道へ進むきっかけとなった出来事であったように思う。
その日、看護短大1校から3年生、看護師養成所1校から2年生と3年生の、計3つの学年の実習がスタートした。実習指導体制は恵まれており、実習期間を通して、各校それぞれに1人ずつ、私を含め3人の実習指導者が立てられた。また、実習指導者は卒業校の学生を指導するという体制で勤務表が組まれていた。ほぼ同時刻に3校の学生へのオリエンテーションが開始した。オリエンテーションの内容はマニュアル化されており、3人の指導者は同じマニュアルを持ってオリエンテーションに臨んだ。同時刻に開始したオリエンテーションであったが、私が最初に終了し、他の指導者が終了したのはそれから30分程後であった。同じマニュアルなのに、他の人は何を話しているの? と疑問に感じたのも束の間、オリエンテーションを終えたそれぞれの学生の表情の違いに愕然とした。私がオリエンテーションを担当した学生から意欲を感じない訳ではなかったが、それ以上に他の指導者がオリエンテーションを担当した学生は、その表情が生き生きとしていた。“さあ実習頑張るぞ”という意気込みが伝わってきた。その差は受けた学生の差ではなく、オリエンテーションを担当した指導者側の力量の違いであることが歴然としていた。
「自分には言葉にする看護観がない」
その後は、自分と他の指導者の違いを探るのに必死であった。同僚には、オリエンテーションで話す内容やどんな点に心掛けているのかを聞いたり、先輩には夜勤で一緒になった時に話を聞いたりした。最も心掛けたのは他の指導者のオリエンテーションの様子や指導の実際、学生の反応をつぶさに観察することだ。
その結果、自分に足りないものがいくつも分かった。私に不足していた点は、根拠を明確にしながら伝えることやその根拠を学生自身に考えるように導く方法、学生の反応を確認してから説明を進める事、そして、ちょっとしたエピソードを盛り込み、学生に笑顔をもたらす方法などである。しかし、最も大きな違いは、学生指導に携わっていた同僚や先輩方は学生に自分の看護に対する考えや気持ちを伝えていたという事であった。その違いにショックを受けた私は、自分には言葉にする看護観がないことに気付いてさらにショックを受けた。看護学生にとって慣れない環境下でスタートする実習開始時のオリエンテーションがいかに重要であるかは言うまでもない。指導者から教授された患者や看護に対する思いであったり、それを受けて目の前で繰り広げられる看護の実際は、これからの実習だけではなくその学生の今後の看護師としての道のりに大きな影響を与える。
それからの私は“看護って何だろう”と問い続けた。そしてほどなくして、私がその答えを手にする時がやってきた。ある日、直腸がんの壮年期の患者で翌日に直腸全摘手術を控えた方の全剃毛を終え、いつものように「ひげはご自分で剃っておいてくださいね」と伝えたところ、患者から「いやだ。ひげは剃らない」と言われた。ひげを剃る理由を術前オリエンテーションで聞いているはずなのにと思いながら、「理由はお聞きだと思いますが、麻酔をかける時に、管をテープで固定するのですが、ひげがあると安全に管の固定ができないのです。ひげを剃っておいてくださいね」と繰り返した。しかし、返事は同じで「ひげは剃らない」であった。その後も押し問答をした記憶が残っている。結局、患者は医師に直談判をして、ひげを剃らずに無事に手術を終了した。
「三重の関心」が看護師、看護教員としての自身の基準に
手術が終わってしばらくしても、私の中には「私は間違ったことを言っていない」という思いが渦巻いていた。そんなモヤモヤした気持ちを聴いてほしくて、看護学生時代の恩師を訪ねた。恩師は静かに私の話に耳を傾けてくれた。そして、1冊の本を持ってきてくれた。それを読んで今回のケースを考えることが恩師からの私への宿題であった。
その本には「看護婦は自分の仕事に三重の関心をもたなければならない。ひとつはその症例に対する理性的な関心、そして病人に対する(もっと強い)心のこもった関心、もうひとつは病人の世話と治療についての技術的(実践的)な関心である」1)とあった。これを目にして、私は何と一人よがりだったかと、本当に自分が恥ずかしいと感じた。私は疾患や手術について理解していたが、それは知識としての理解にとどまり、患者のための理解にはほど遠かった。まして、患者の「ひげは剃りたくない」という思いに心と耳を傾けず、通り一遍の返答に終始した。患者は手品師であった。私にとってはただのひげであったが、手品師であるこの方にとってのひげは自身の職業のシンボルであり、生へのエネルギーだったに違いない。私にはこの方の思いを理解しようとする心のこもった関心を寄せることができていなかった。もし、この方の思いを、ひげの意味を理解しようとしていたら、「ひげを残しつつ安全に管を固定するにはどうすればよいか」と技術的な関心を寄せることができ、それを形にすることもできたはずである。
恩師から出されたこの宿題によって、自分に決定的に欠けていた事がわかり、「看護とは何か」を少し言葉で表現することができるようになった。それ以降は、この三重の関心が患者に必要な看護を考える時の基準になった。そればかりか、看護教員として学生への対応を考えるとき、自分が判断しようとしていることは真に学生の利益のための判断かどうかの基準になっている。
教員の役割は、学生の学びの土壌を整えること
7年間の臨床経験の後、看護を教えたいという私の気持ちを後押してくれたのが、「看護とは何か」を言葉にするきっかけをくれた恩師であった。いつしか看護教員としての経験年数は長くなったが、看護教員になった当初は「なんでわかってくれないの」「こんなに一生懸命教えているのに・・・」と思い通りに行かないことを嘆くばかりであった。そもそも看護を教えるとは何なのか、またしても大きな壁に行く手を塞がれてしまったが、学生と一緒に患者の援助をする中で、看護を教えるのではなく、学生が看護を学ぶ土壌を整えることが看護教員の役割であることに気づかされた。そのためには、その学生に合った土壌づくりが必要である。学生の話によく心と耳を傾け、学生はこの患者をどう捉え、何をしようと考えているのか、学生の思いはどこにあるのか、看護教員が患者と学生の思いに近づけば土壌も整うのではないだろうか。そうなれば学生はおのずと看護を学んでいくのである。そして、看護教員には、行きつ戻りつする学生の学びの過程を見守る我慢強さも必要である。
専門職を育てるとは、自らが姿勢を示すこと
私たちは学生に患者の言葉の意味や思っていることを理解してほしいと願っている。これは看護基礎教育の課程で身に付けてほしい能力の1つでもある。学生に身に付けてほしいのであれば、看護教員がそれを示すことが大切である。
このように、専門職を育てるには、教員自らが専門職としての姿勢を示すことが必要である。他者から学ぶ姿勢を持ち続けることであると思う。ライバル(好敵手)を大切にし、お互いに切磋琢磨し、自分自身を振り返りながら今以上を目指すこと、そして自分の思いを表現する術を持ち、それを惜しみなく使う様を教員は自ら示すのである。
1)F.ナイチンゲール:病人の看護と健康を守る看護. ナイチンゲール著作集第2巻第1版(湯槇ます 監,薄井坦子ほか編訳),p.140, 現代社, 1979
★ご案内
筆者が運営委員長を務める「第36回一般社団法人日本看護学校協議会学会」が、2024年8月1日(木)~2日(金)より、愛知県名古屋市のウインクあいち(愛知県産業労働センター)にて実施されます(オンラインとのハイブリッド開催)。詳細はこちらからご覧ください。