<前編はこちら>
看護技術
看護において人間関係と共に重要な要素は、看護技術です。看護技術の刺激は小さいので、その効果を測定し、より効果のある技術を開発していく研究が盛んになされています。看護技術が伝播可能になるには、①その技術を用いる目的が明確、②簡便かつ確実な手技、③安全性、④看護技術に対する生体反応、⑤効果を引き起こす作用機序、⑥臨床効果(目的達成に有効か、その確率)、 ⑦気持ちよさが得られることが言語化されている必要があります1)。
実験室で行う基礎研究でも、被験者と技術を使う術者の人間関係はデータに影響するのですが、たとえば温罨法で皮膚温が何度上がるのかは、数値を明示することが求められます。なるべく人間関係が影響しない実験設定をし、一般的な反応を捉えることが必要です。
排便・排ガスを促す目的で腰背部に行う温罨法を例にすると、皮膚温が上がる、皮膚血流が上がる、腹鳴が増えるのは、温熱刺激に対する生体反応です。熱は高いほうから冷たいほうへ移動する、副交感神経系が賦活化して相対的あるいは絶対的に交感神経系の活動が低下し、皮膚血管が開き、血流が増えるというのは、皮膚温が上がる作用機序です。排便・排ガスが促される作用機序は、副交感神経系の賦活化が消化管を動かすからと説明できます。バイタルサインの変化はない、皮膚温の上昇は火傷を起こさない範囲であるなどが、安全性の証明になります。臨床研究において、どれくらいの人に効果があったか、気持ちよさをもたらすことができたかを示せば、この技術を使うかどうかの判断材料になります。温罨法の詳細は、日本看護技術学会が発行している「便秘症状の緩和のための温罨法Q&A」2)にまとめてありますので、ご参照ください。
看護技術の基礎研究で、生体反応や作用機序の解明を行うことは、看護技術について説得力のある説明ができる第一歩だと思います。作用機序や生体反応がわかれば、方法の変更も開発も可能ですし、その技術を適用する目的が広がる可能性も見えてきます。反応を起こすのに必要な刺激量がわかれば、刺激の与え方、つまり方法を開発することも可能です。ただ現場で使うためには、方法はなるべく簡便で確実なものが必要です。
1990 年代にEvidence-Based Nursing (EBN)という考え方が看護界に入ってきました。エビデンス(根拠)には、看護技術の作用機序を指す場合と、臨床効果の有効性を指している場合がありますが、EBNは後者の意味で使われます。臨床研究により、その技術の有用性が証明されているかどうか、その研究結果に基づいて看護をすべきという意味です。同じ状況で、その看護技術を使った場合と使わなかった場合で、意図した目的の達成度に有意な差があって有用性が確認できれば、その技術を取り入れる価値があります。 ただ、有効性が確認されていても、10人中2人に有効という場合と、6人に有効という場合では、実際に使うかどうかの判断は違ってきます。いろいろな看護技術を試みて、最後に試しにやってみましょうという段階であれば、20%の確率のものも使うでしょうが、最初に選ぶ技術にはならないでしょう。6割の確率なら、やってみましょうかと提案しやすいです。有効だというだけでなく、 効果が得られる確率がわかっていると、選択するかしないかを決める材料になります。
ケアとしての看護によって患者に現れる効果
気持ちよさが効果になるのは、看護技術の特徴です。看護職は看護技術も医療技術も駆使していますが、医療技術の効果に気持ちよさは含まれないと思います。看護技術の適用目的は、日常生活行動またはそれに代わる行動の遂行、痛みの除去・予防、症状悪化の予防であり、治療下にあっても、その一瞬でも気持ちよさをもたらすことができるのが看護技術なのです。
そしてさらに、気持ちよさの先に来る、技術の効果が「看護はケアである」という観点からは最も大切なものではないかと考えます3)4)。
患者は痛みやだるさ、不安などに、意識を集中せざるを得ない状況に置かれています。疾患・治療にまつわるさまざまな制約を受けています。凝り固まった気持ちと体は、外界とのかかわりを閉じていきます。そういう時に看護技術の刺激が体を揺り動かすと気持ちよく、凝り固まった状態から解放される時間になるのです。そうすると、体と心が少しほどけて、食べてみよう、歩いてみよう、退院を考えよう、あるいはこれでいい、やっていけそうなどと、その人の日常性や力が回復してくるのだと考えています。
排便を促す目的で温罨法を実施して、お通じは出なかったけれど、気持ちがよくて寝てしまったということがありました。この場合、温罨法を適用した目的は達成できなかったので、その意味の効果はゼロですが、「気持ちいい」という効果はあったと言えるでしょう。直接の効果に続く日常性の回復や、たとえ重篤な状況であっても本人が「これでいい」と思えることは、看護の大きな力です。
看護職に必要な力とケアによって得られること
人間は、何かをしようという意思を持つところから、意図的な活動が始まります。看護職が看護をしようという意思を遂げるのは、知力、コミュニケーション力、技術力、体力が必要です。どれが欠けても、うまくできないでしょう。コミュニケーション力は相手との意思疎通に必須です。疾病や病態、状況の理解と、どの技術を使うかの判断、適切な方法で間違いなく実施すること、その土台には知識と体力がいります。
もう一点、相手もまたその人の意思、知力、コミュニケーション力、技術力、体力を持っていることを忘れないでください。たとえば 自己注射を教える時には、患者が自分で注射をやろうという意思があるのか、自己注射に関してどんな知識を持っているのか、看護職とのコミュニケーションは取れているか、自己注射の技術をどこまでできるようになっているか、練習する体力があるかを確認しながら行います。相手の知力や技術力をアセスメントしない、あるいは相手がどうしたいのかの意思を確認せずに行うことは、失敗につながります。
ケアとしての看護が成立した場合、看護職はやってよかった、もっとやりたい、患者の回復を願うという、物質的でない見返りを受け取ることができます。これが看護職の喜びであり、やりがいなのです。看護もどきで、最低限のことをして、早く患者のそばから離れたいというのとは、雲泥の差です。看護から得る満足ややりがいが、看護職が看護を続ける力になっているのではないでしょうか。ただし、やりがいがあるから安い賃金でよいということではありません。ケアを担う職種には働きがいがある金銭的な報酬も必要です。
とはいえ、いつでもケアとしての看護ができるとは限りません。看護もどきになったとき、なぜかを考えることも看護職としての成長に資するでしょう。学生時代にケアとしての看護を体験すべきです。その体験は、看護とは何かを語るときの中身になり、看護を主張していく原動力になるに違いありません。
引用文献
1)菱沼典子:研究による経験知の実証―筋が通った看護技術を確立するために.日本看護技術学会誌8(3):4-9,2009
2)日本看護技術学会技術研究成果検討委員会温罨法班:便秘症状の緩和のための温罨法Q&A Ver.4.0,日本看護技術学会,2021,〔https://jsnas.jp/system/data/20160613221133_ybd1i.pdf〕(最終確認:2024年11月25日)
3)島田多佳子:いかにして患者の「気持ちいい」は生まれるのか,日本看護協会出版会, 2017
4)大橋久美子,縄秀志,佐居由美ほか:国内における「気持ちよさ」をもたらす看護ケアに関する統合的文献レビュー.日本看護技術学会誌16:41-51,2017



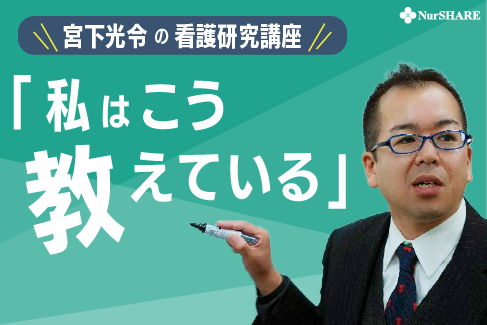

_1729484624408.png)
」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)