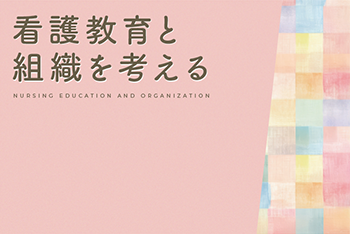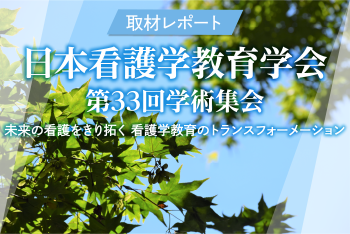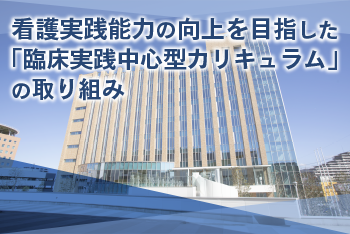<前編はこちら>
ベナーによる看護師の技能習得過程
初めて就職したところに話を戻しましょう。現在、学生時代の実習ではごく限られた範囲の経験しか積めませんから、就職がスタートです。実践の繰り返しと、そこからの学びによって、看護職として成長するのです。やりっぱなしは力になりません。振り返って学びを蓄積していくことが成長につながります。実践の場でコミュニケーションをとり、知識を使いこなし、判断をし、技術を使える、そして自分の看護を評価しながら、日々成長していくのです。
1984年に、ベナー(Benner P)が「From Novice to Expert」1)という本を出しました。これに先立ちドレイファス(Dreyfus H)らが、パイロットやチェスのプレーヤー、ドライバー、外国語を学ぶ成人の技能獲得の過程を分析して、共通してビギナー、中級者、上級者、プロ、エキスパートの5段階があることを示しました2)。状況に対応する時の、課題の理解の仕方や意思決定の方法が順々に変化していくというのです。この技能獲得の段階が妥当かどうかを、看護師で研究したのがベナーです。その結果、看護師の技能獲得プロセスにも、ドレイファスモデルが当てはまり、5段階は妥当であると発表しました。ベナーの訳本では、5段階を「初心者(novice)」→「新人(advanced beginner)」→「一人前(competent)」→「中堅(proficient)」→「達人(expert)」と訳していますので、以後この用語を使いたいと思います(1992年に日本語訳が出され、2005年に新訳版が出版されています。ここでは新訳版を元にしています)。
課題の理解の仕方や意思決定の方法が段階で異なるということですが、ベナーは状況をどう判断するか、何をするか(どういう技術を用いるか)の判断、そして技術の実施の熟練度に違いがあることを見出しています。学生が初心者、卒業して就職したてを新人としていますが、ベナーはたとえば老人看護の達人でも、新生児のICUでは初心者になる3)と述べており、状況が異なれば対応力は異なることを前提としています。初心者はその状況の注目する場面だけを取って、その前後の流れに気がつかず、技術の選択も含めてマニュアル通りに行う段階です。新人はその状況について、背景や類似の状況との比較を含めて理解できますが、用いる技術はマニュアルに従う段階です。一人前はその状況について自分で分析して判断し、その判断に基づいて計画を立てて実行することができる段階です。中堅はその状況を全体像とともに捉える事ができ、何が重要かを識別できる、その状況判断は直観的な段階です。達人は状況判断が直観的ですぐさま対応を決め、すぐ実行しています。気がついた時にはもう対応していて、その状況に没入できる段階です。
マニュアルは初心者、新人には必要ですが、マニュアルを超えた様々な状況があるわけで、それに対応できるようになったら一人前ということになるでしょう。看護師が自分の経験の中で自分の中にさまざまな規範例を積み上げ、状況判断、すべきことの選択、その行為のスピードが、より相手の状況の改善に結びつくようになる過程は、経験年数で区切られるものではありません。経験年数が長ければ達人だとはならないのです。また、一足飛びに新人から中堅になれるのではなく、誰もが段階を踏んで成長していきます。ただ看護師個々人によって、段階が上がるスピードは違うでしょう。経験を流してしまうのではなく、この時はこうだった、あの時はこうだったという事例を、自分の中に記録し引き出せるように努力して、看護師としての成長を遂げていってほしいです。
相性が悪くても看護ができる
看護職は病者であれ、その家族であれ、共に働く看護職であれ、他職種であれ、その人との人間関係を結ぶことが大事です。病者への看護場面において看護技術を実施する際に、人間関係はその行為の過程に影響し、その結果、効果にも影響します(第5回参照)。出会ったときに感じる相性から人間関係は始まりますが4)、その相性が悪いと人間関係を結ぶことが困難になります。看護職も相手も互いに人間ですから、相性の良し悪しがなくなることはないでしょう。
相性が悪くてコミュニケーションが取れず、看護技術の提供過程でつまずき、良い効果に至らないことは第5回で説明しました。この時の研究5)6)から、ある段階を超えると相性が悪くても看護をできるようになることが、導かれました。
これにも、新人からの成長プロセスがありました。研究の中で実施した看護師への面接調査からは、下記のような内容が読み取れました。新人の時は相性が悪いのは私のせいで、全ての患者に平等にすべきなのにできないと思い「私が悪い」と自分を責めていたと言います。いろいろなことができるようになると、私がこんなに一生懸命やっているのに、患者が分かってくれないと、自分はできているのだから「患者が悪い」と思ったと言います。しかしさらに経験を積むと、相手との相性が悪いことを認め、見通しがつくようになって技術提供がスムーズにできる、必要時には他の看護師に依頼するし、患者にも「私でないほうがいい時は言って欲しい」と頼める、相性は悪くても嫌いという気持ちはなくなっていて「相性が悪くても看護ができる」ようになったというのです。
その変化に影響したこととして、臨床経験の積み重ね、思い通りにはならないことが一番よくわかった看護職自身の子育て、患者の気持ちがわかった看護職自身の病気体験が挙げられました。これらの経験によって、さまざまな価値観があることがわかる、いつも思い通りにはいかないと知る、相性が悪いことが倫理的に悪いことではないとわかったことが、変化をもたらしたと解釈できました(図)。
臨床での判断能力と人間関係構築力
ベナーは臨床での状況判断能力の差を成長過程の要素としていますが、もう一つ、看護師の成長過程には人間関係の構築能力が要素になると考えられます。
ベナーは一人前と中堅の間には飛躍があると述べており、相性が悪くても看護ができるのは中堅以上に該当するのではないかと考えます6)。新人は「私が悪い」、一人前は「わかってくれないのはあなた」と思ってしまいますが、中堅になると相性が悪くてもできるようになるというのは、とても納得がいくように思います。看護職の皆さんが、ベナーの視点からと人間関係構築の視点から、自分は今どの段階にいるかを考えてみると面白いと思います。
看護学は紙と鉛筆があればできる机上の学問ではなく、実践に根差しています。実際に相手をケアしその安寧や回復を支援し、ケアによる双方の成長があって意味があるのです。もともと学問と職業は直に結びつくものではありません。看護の研究は看護職でなければできないかという議論がありますが、看護職でなくとも看護の現象を見る事ができる人ならば、看護学の研究は可能だと私は考えています。ドレイファスモデルは、コンピュータサイエンスの研究者と哲学者の兄弟が見出したものですが、ベナーはドレイファスモデルによって看護師の成長過程を言語化し、看護学以外の人にも理解できるものにしています。学問分野が協働、または融合することで、さらなる研究が開かれていくことでしょう。
教員にも当てはまる
長い間大学で仕事をしていた私自身を振り返ると、学生を支援することはケアであり、教員の成長段階もドレイファスモデルに当てはまると思います。教員の新人からベテランまでを3段階で説明した、ある話です。講義ノートを作り、教科書を何冊も持って教室に行く、講義ノートだけを持っていく、チョーク(今は消えた黒板に書く道具です)だけを持っていく、まさに新人から一人前、達人への過程を表していると思います。
こんな段階説もあります。解いて教える師、自ら楽しむ師、響きを楽しむ師です。計画通りに教えたいことを一生懸命伝えようとする新人、自分が講義するのが楽しくて語る一人前、学生の反応を楽しむ中堅以上で、こちらも3段階です。知っていることを100%使わないと間に合わない新人、80%で授業ができる、50%でできる、30%でできるというのも、教員の成長段階を言い得ています。
こんな指標で自らを見てみると、教師としての自分の成長段階がわかりますね。新人教員の時、直前まで調べて作ったノートと、本を何冊も持って教室に行っていたなあ、ノートにある知識が100%だったなあ、自分の予定した授業をして、学生の反応は見ていなかったなあ、と思い出します。何事も始めから一人前や中堅段階でできるわけはありません。分析的にみる訓練を重ねた上に、直観が働くようになるのですから、経験を宝にして、達人の域に達したいものですね。
引用文献
1)ベナー著,井部俊子監訳:ベナー看護論―初心者から達人へ,新訳版,医学書院,2021
2)ドレイファス HL,ドレイファス SE著,椋田直子訳:純粋人工知能批判,アスキー,1987
3)前掲1), p.253
4)小代聖香:看護婦の認知する共感の構造と過程.日本看護科学会誌9(2): 1-13,1989
5)Hishinuma M,Katogi M:Nurses' Relationships with Patients and It’s Impact on Effectiveness of Nursing Skills.聖路加看護学会誌26:1-10,2022
6)菱沼典子:看護技術と看護職と患者の人間関係からみた看護実践のプロセス―看護職の視点から.日本看護技術学会誌23:1-7,2024