前回(第7回)では、社会性の背景に「心の理論」の獲得による思いやりが関係することを触れてきました。さて、学齢期は、未成熟な存在どうしである「子どもどうし」で“学習”が促進されるシステムですが、このシステムも完璧ではありません。予測力があるために「理想」と「実際」の乖離や「成功への期待」と「失敗による落胆」も生み出します。
これらを繰り返すと私たちは理想や期待をもつことにおそれをもつようになります。さて、私たちはどのようにしてこの葛藤を乗り越えていくのでしょう。
知性を支える分類力と整理力
ヒトの知性を支えていることはとても多くあるのですが、感覚刺激を通じて獲得した感覚に名前をつけることができたり、関連を記憶することで抽象的な事象を扱うことができるようになっていきます。
まず、感覚刺激を通じた感覚に名前がつくという例は、第3回で紹介した感情の発達や、第4回で紹介した意味への注目にも関係します。「りんご」はりんごという物体がありますが、「おいしい」は「おいしい」という物体があるわけではありません。味覚を通じて自分が経験することで初めて「おいしい」という感覚を知ることができ、そこに「おいしい」という言葉があてはめられると「おいしい」感覚と言葉が一緒に記憶されることになります。
さらに、語彙が増えるとともに抽象化や具体化ができるようになり、同じ「おいしい」が「コクがあっておいしい」「さわやかでおいしい」などに分類されていったり、逆に「ミニカー」「積み木」などを「おもちゃ」と統合することもできるようになります。
このように、分類や統合ができることでヒトは多くの情報を効率よく記憶することができていきます。たとえば、何種類かのケーキを食べたことがあって、どれも「甘さとほどよい柔らかさがおいしい」としたら、ケーキに関する味の情報をまとめて覚えて効率的に記憶します。効率的に記憶すると、その後はそれまで食べたことのあるケーキとの比較で「とてもおいしい」「甘さがいい」「硬い」などの感覚によって、その時起きている出来事を理解しやすくなっていきます。
こうして、感覚記憶や言語記憶とともに過去の記憶と比較することによって、私たちは物事の理解を素早く行うことができるようになるのです。

連動性を支える小脳
さて、前の項目で述べたような分類と整理を支えているのは、脳の小脳です。小脳は小脳という名前のためにあまり目立った機能がないように想像するかもしれませんが、実は神経伝達による活動が活発な部位で、大脳皮質のニューロン数がおよそ140億といわれている一方で、小脳には1000億ものニューロンがあると推定されています。つまり、前回紹介した大脳皮質の一部である前頭前野に比べて、ニューロンによる情報の送受信の量がとても多いのです。
小脳が行っているのは、脳内のさまざまな指令や情報を分類したり整理したりすることです。たとえば、身体を動かすときには動きの指令そのものは前頭葉後部から出されるのですが、その指令を分析して実際に個々の筋肉の動きの程度や順序やタイミングを調節するのは小脳です。さらにこれらの手続き記憶も小脳が行います。これまでに紹介した例では、跳び箱を跳ぶことや靴紐を結ぶ例をイラストで表してきましたので、これらを例にしてみましょう。
跳び箱を跳ぶという行為の際には、体のさまざまな部位をタイミングよく連動的に使う必要があります。跳び箱を跳ぶ際の身体の動きは、
①両足を交互に前に出す(走る)
②踏切板で両足をそろえて両腕を前方に出す
③跳び箱の上部に手を置いて胴体を引き付けて両足を左右に開く
④体が跳び箱の真上にやってきそうなタイミングで両手を離す
⑤胴体が跳び箱の上部を通過したら両足を閉じていく
⑥両足をやや屈伸して着地時の衝撃を吸収しながら両手を開いて左右のバランスをとる
という順序で行われます。実際に跳び箱を跳ぶときには、これを言葉で一言一言言葉を発しながら行っていると間に合いませんので、素早くこれらの動きを順序よく行っていく必要があります。
また、靴ひもを結ぶ時には、視覚によって細やかに靴紐がどのような形状になっているかを見定めて、靴紐を通す場所に合わせた指先の動きの調整が必要です。これらの「順序よく体のいろいろな部位に指令を出す」「視覚刺激に合わせて運動を調整する」などの調整を瞬時に行うことは、小脳でそれぞれの脳領域と連携することで可能になります。
言語についても、小脳が大脳皮質からの指令を受けて、発声(調音)の際の声帯、喉、舌や唇などの動きの細かな指示を個々の筋肉に送っています。小脳の発達により、学童期には言葉の言い間違いが減って発音も流暢になりますし、同様のことは手の指の細やかな筋肉の使い分けにも活かされますので、漢字などの細かく複雑な字も書くことができるようになっていきます。また、鍵盤や楽譜を見ながら楽器を演奏することがしやすくなっていきます。

感情の共時性と観察学習
小脳の発達は、細やかな運動や連動性のある運動を実現していきます。そのため、流暢な発話や連動性のある動きなどができ、言語の発達と理解の連携もよくできるようになります。このことで、自分の気分(快や不快)を口調や表情、動作などで表現することができるようになっていきます。
これまでの連載で述べた通り、幼児期のヒトは多くの発見を快体験として蓄積します。幼児期には発見の喜びが不快を伴わない喜びとして経験されていきますが、幼児期から学童期には自分以外の誰かの快感情を感じ取ることで、共時性による快体験も多く経験するようになります。共時性による快体験は自分が快の感情を表現できることや自分以外の人の快の感情を読み取ることによって生じます。
跳び箱を順番に飛ぶという行為は同時には行えませんが、快の体験は共有することができます。つまり、経験は同時ではないけれども、快の感情や快の気分が自分と他者に同時に起きる(共時性)ことによって効果的に学習をすることができるのです。
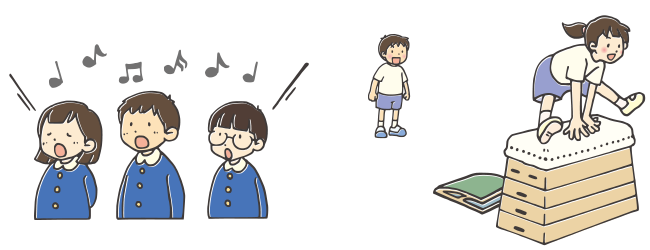
観察学習と自己効力感
人間は観察による学習ができる生き物です。観察学習ができるのは、誰かが快体験をしていることを発見することで自分にも快体験が起きる(または、もう起きている)と思うことで他者の様子を記憶することになるのです。この観察学習は共同注視などのような共時性をもたなくても学習が促進できるため、学校でクラスメイトや教師から学ぶ時にも効果的に機能します。
また、観察学習のポイントは快体験が伴うことで学習効果が高まるということです。つまり、子どもたちは自分自身ができないことがあっても、仲のいい子どもができるのを見るだけで嬉しくなり、その嬉しさを伴って学習していくことができるのです。

このような観察学習が効果的に機能すると、自分がすぐに達成できない物事に出くわしても「自分はできるようになるはずだ」などと前向きに考え続けることができます。こうした感覚のことを第6回で自己効力感と紹介しましたが、自己効力感が生まれていく背景には、同時性のある経験だけでなく、他者の感情や考えを推察できることによる学習があるのです。
周囲の不快による葛藤と対処
ここまで快体験に伴う学習を扱ってきましたが、残念ながら人間を取り巻く経験はすべてが快体験というわけではありません。周囲の人たちが不快な気持ちをもっていると思えるような表情や声の調子や行為をしていると、仮に言葉そのものでは不快な情報が入ってこなくても受け取る側の人は「なんだか相手はいい気持ちではないぞ」ということに気づきます。
たとえば、自分のクラスメイトが跳び箱を跳べなくて表情が暗いとしたら、仮にその子どもが「だいじょうぶ」と抑揚のない声で話していたとしても「ああ、この子は嬉しくない経験をしているんだな」と思うことになります。つまり、相手の不快な気持ちを受け取るため、快体験に伴う学習はここでは進められません。このように、周囲の状況にある不快によって自分が考えなければならない場面は、小さな「葛藤」といえます。ではこの場面では、その様子を見ていた子どもたちはどうやって「対処する」のでしょうか?
1つ目の選択は、「自分は元気があるし、きっと自分の元気を相手に与えればこの子も元気になる!」と考えて「きっと次はうまくいくよ!」という声をかけたり励ましたりすることです。この方法の場合は、跳び箱を跳ぶことへの快体験を受け取ることをいったん保留して、相手の快体験から自分が嬉しくなることではなく、自分の気持ちを相手に分け与えることで相手に快の感情をもってもらおうという作戦です。この方法は、自分が相手に自己効力感を分け与える方法ともいえるでしょう。
2つ目の選択は、「自分が跳べれば、まあいっか」と考えて、自分の快の感情のおおもとを「別な子どもができること」から「自分ができること」に切り替えて、自分が跳び箱を跳ぶためのイメージをつくるようにすることです。学童期頃の子どもは、心の理論の形成ができていることが多いため、「○○という方法でうまくいかなかったから、××という方法でやってみるといいはずだ」という推察もできるようになります。この方法は、自分が達成することで快体験を発生させて、自分と周囲の人たちに快の感情をもたらそうという方法です。
3つ目の選択は、「この場面ではできないものと思ってあきらめよう」として、学習することをやめることです。これまでの連載で扱ってきたとおり、人間はそもそも不快なことは学習したくありません。「○○すると嬉しい」「名前を覚えたい」「やり方を覚えたい」などの快の感情をもてる場面で学習を進めます。よって、もしもこの場面で快の感情をもつことが難しいだろうな、と思ったら、「あ、この場面は学習しないほうがいい場面だ」と思って学習意識を切り離すことで、余計なことを覚えなくてすむようになります。
こうして、人は自分や周囲の人々の様子から「快か不快か」を判断してその場面での学習を促進するかどうかを判定していきます。チームスポーツでピンチの時には、おそらく1番目か2番目の方法を使って自分と周囲の集中度を高めて対処していき、そのチームスポーツでうまくいかなくても(試合で負けたとしても)「一緒にやれたから楽しかった」「今度は○○をすればうまくいくはずだ」などの別な快の感情の持ち方をすることができます。
さらに、人は自分や他人に生じている不快な体験を前向きに乗り越える方法を見つけることができるようになります。小学校の中学年くらいからはチームスポーツや学級内のグループ活動でも葛藤の克服ができるようになっていきます。その背景には、他者の存在から不快を感じ取ることと、自己効力感を分け与えるという発想が生まれることが影響します。人が幼児期に獲得し始めた社会性をさらに強化して、精神保健の面で助け合うことはこのように成熟していきます。
補足:自分で自分を励ますこと
今回は、人の社会性に注目して“自己効力感を他者に分け与える”という過程を紹介しました。ところで、この自己効力感を分け与えるという考えが生まれると、個人のストレス対処能力も向上していきます。たとえ目の前の出来事に失敗したり落ち込むことがあっても、自分の過去の経験の中に、達成経験や自己効力感を高める経験が十分にあると、過去の記憶をもとに自分で自分に自己効力感を分け与えることができます。
このような自分の自己効力感を失わないようにする力は、ストレスに対する余力のように働きます。近年ではこのような力をレジリエンス(困難や脅威に直面している時の「うまく対処していく能力や過程」)とよぶことがあります。レジリエンスについては、この連載の後半で扱っていきたいと思います。






