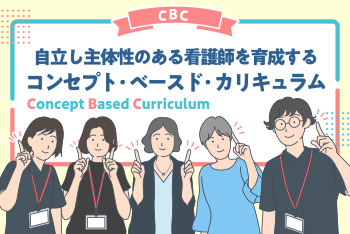はじめに
6回目の講義は観察研究です。最初の導入は、以前に話した「飲酒は肺がんの発症要因になるか」という研究です。このように患者にとって不利益があるエンドポイントを調べる研究は、ランダム化比較試験をすることができません。では、そのような場合にどのような研究デザインを考えればいいか、ということから入ります。
追跡型の研究―集団を“追って”調査する
エビデンスの信頼度のピラミッドに沿って、まずは図1のように曝露とアウトカムの因果関係の推測を目的とした前向きコホート研究、後ろ向きコホート研究、ケースコントロール研究から話します。

この図では、矢印はデータ収集の向きを示しています。これらの追跡型の研究では、曝露がアウトカムより前に取られており、Hillの因果性の判断基準のうち時間的先行性が満たされていることが強みです。
前向きコホート研究について
ご存知のようにコホートとは古代ローマの歩兵隊に由来する集団のことです。前向きコホート研究は研究開始時に曝露情報を収集し、集団の追跡により死亡や罹患などのアウトカムを測定します。この研究の例はフラミンガム研究を簡単に説明しています(図2)1)。

フラミンガム研究はとても有名な研究なので名前くらい知っておいたほうがいいでしょう。日本で行われているコホート研究についても一覧を出して少し話しますが、東北大学では震災後に東北メディカルメガバンクという事業が始まり、宮城県と岩手県で地域住民コホート調査(8万人)と三世代コホート調査(7万人)というプロジェクトが動いているのでそれもほんの少し触れます。

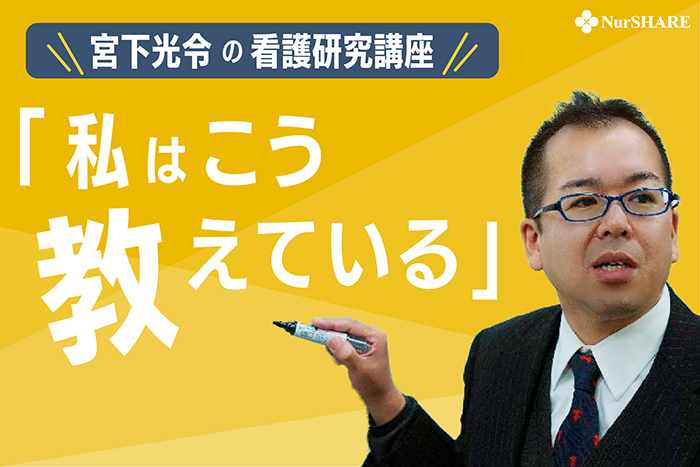


_1647410109603.png)