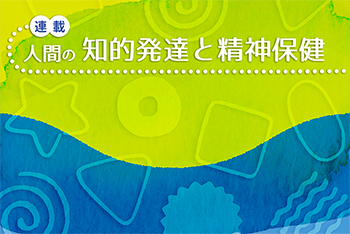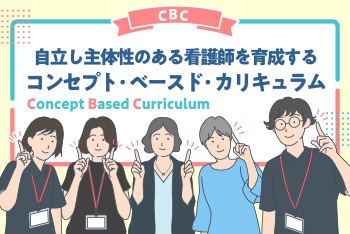今回のテーマは研究倫理です。本学の学生は1年次に生命倫理学の講義を受け、また、この講義の前に一般社団法人公正研究推進協会(APRIN)によるe-learningであるeAPRINを受講しています。eAPRINの受講は医学部学生は指定された20コマが必須となっており、看護学専攻の学生はこの看護研究の講義のなかで9月から今回の講義までに受けることになっています。本講義は前半がeAPRINの復習的な研究倫理の基本的な考え方の講義で、後半は「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の内容に関する講義で構成しています。
今回の研究倫理の講義では最初に生命倫理学の講義で学んだ「倫理4原則」について復習したのちに、STAP細胞事件を取り上げて、そこで出ていた研究倫理の問題について話しています。STAP細胞事件は2008年ですので、もう17年前になりました。現在の学生は小学校に入る前のことですのでリアルタイムに知っている人はいないと思います。そろそろ例を変えたほうがいいのかもしれません。
研究倫理の基本的な考え方
この講義では、まず研究者の責任ある行動とは何か(図1)というところから入って、研究活動における不正行為(特定不正行為)について話します(図2)。そして、公的研究費の使用ルールとして預け金、カラ出張、カラ給与・謝金などは絶対してはならないこと、もし他の教員・研究者からこれらの疑いがあるようなことに誘われた場合には、必ず誰かに相談するように話しています。幸いにして本学ではこのような事例は聞いたことがありませんが、世の中ではたびたび報道されているのも事実だと思います。



次は個人情報とデータの扱い、利益相反について復習します。そして、オーサーシップについて、ICMJEによる定義(図3)やギフトオーサーシップ、ゴーストオーサーシップなどについて話します。余談ではありますが、ICMJEのオーサーシップの定義で「論文のあらゆる側面について、論文の正確性・真正性に疑義が寄せられた時に適切に説明することができる」というのは厳しいなあといつも思います。

次は重複出版、重複の度合いと自己剽窃、サラミ出版、盗用について話しています。盗用についてはコピペは絶対にダメ、引用する時にはその引用元をきちんと明記するように話していますが、最近は生成AIなどの出現で線引きが難しくなってきたと感じています。このあとにメンターとの関係の在り方についてもアカハラ・パワハラの防止の観点から話しています(図4)。本来ここで話す内容ではないのかもしれませんが、どこかでちゃんと話しておきたくて、ここに入れています。このあたりまでの話が、eAPRINの復習的講義です。


人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
ここから「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に関する講義です。倫理指針およびガイダンスについて、以下の要点に沿って話しています(図5)。

まずは「人を対象とする生命科学・医学系研究とは」として、この指針の適用範囲=倫理申請が必要な範囲について話した後に、侵襲・軽微な侵襲(図6)と介入(図7)について例を挙げて説明します。この侵襲と介入の理解が指針の肝だと思います。



次に挙げた図は侵襲の程度と介入・観察研究によって指針をどのように解釈すればいいかをまとめたものです(図8)。こちらはICRwebという臨床研究に関するe-learningサイトで現東北大学大学院文学系研究科の田代志門先生が作成されたものですが、とてもコンパクトにまとまっていて素晴らしいと思っています。

その後に、倫理指針に沿って研究計画書に記載するべき事項、東北大学における倫理審査の区分などについて説明します。東北大学では倫理委員会のポータルサイトでプロトコルのテンプレートが提示され、看護研究向けのテンプレートも収載されています(https://www.rinri.med.tohoku.ac.jp/portal/tmpl.html)。こちらは、東北大学の書式ではありますが、誰でもアクセス可能になっておりますので、看護研究を行う際にどのように計画書を書いてよいか悩んだときには参考にすることができます。
その次に、具体的な審査の方法として迅速審査や症例報告(原則として倫理審査不要ですが、必要であれば東北大学は審査してくれます)、インフォームドコンセントと説明書・同意書に記載する内容について説明します(図9)。侵襲を伴わない研究では書面による同意が必要ないケースがありますので、それについても説明しています。


ここまでで臨床倫理に関する講義は終了です。冒頭申しましたが、東北大学では1年次に生命倫理学の講義があり、また、eAPRINを指定された20コマ受講することも必須ですので、大学全体としては充実した倫理教育がなされていると思います。研究倫理には面倒でわかりにくい点もありますが、学生には「とにかく倫理はきっちりやらないといけない」「ガイドラインをしっかり読んで遵守しなくてはならない」と印象づけることが大事だと思っています。